物理学?の質問です。
http://q.hatena.ne.jp/1412510338
↑この質問のHarlockさんの回答で
>この穴が仮に真空でないとしたら、地球の表面を覆う大気が地球の両側の穴から
>落ちていくことになりますよね。このとき単純に穴の体積分の空気が移動して
>終わりということではなく、地球の中心に行くほど大気の密度が濃くなるような
>形でどんどん空気が穴に落ちて行ってしまうのではないでしょうか?
>このとき、地表の酸素は維持できるのでしょうか?
とあります。
地表上にある大気層が1万kmだとすると、トンネルの中心までがおよそ6000kmですから単純計算でせいぜい1.6気圧程度、トンネル内の重力が小さいことを考慮すると1.3気圧程度になると考えました。
これで合ってますでしょうか?
- 回答の条件
-
- 1人5回まで
- 登録:
- 終了:2014/10/13 09:11:00
その他の回答(6件)
POGPI 428
428 59
59
 5pt
5pt
大気の層は、もっと薄いです。中はマグマだから、そもそも貫通が無理です。
勘弁して下さいよ、仮想の話に決まってるじゃないですか……
誰も本気で地球に穴開けようとか思わないですって。
椶櫚 338
338 120
120
 15pt
15pt
こちらを参照
http://news.mynavi.jp/c_career/level1/yoko/2013/01/36_1.html
この中で出てくる「1,000km」の上空を気圧0だと仮定すると、あなたの話では
100kmが気圧0.9
200kmが気圧0.8
300kmが気圧0.7
:
:
とならないとおかしいわけですが、実際には3776m(=3.78km)の富士山が0.6気圧、8848m(=8.85km)エベレストが0.3気圧だそうです。これらの事実を単純に考えても、もっと放物線を描くような気圧変化がないとおかしいわけで、地球の中心は1.6気圧より遥かに高い数値であると考えられるようですけれども。
ありがとうございます。
具体的にはどのぐらいの気圧になりますか?
crazycrescent 48
48 6
6
 20pt
20pt
同じネタと使った本に書いてあったと思います
>具体的にはどのぐらいの気圧になりますか?
具体的に計算はできませんが記憶だと

- 作者: 内山安二
- 出版社/メーカー: 学習研究社
- 発売日: 1976/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
に数万気圧と書いてあったような気が
何気圧か忘れましたけどその圧力の空気は
鉄より固いという話
どうなんすかね学研まんがだからそうめちゃくちゃは書かないと思うんだけど
あんまりあてにならない情報ですんません
ありがとうございます。液化するレベルですねえ。
質問者から
Lhankor_Mhy気圧変化がリニアではないというのは、その気圧によって大気密度が変わりそれが下層への圧力になるから、ということかな。地表面より下になるとたぶん単純な放物線を描かないだろうけれど。
つまり、各高度において大気層上端からの距離と重力の強さによってその気圧が決まるから、それを積分すればいいってことですかね? 違うかな?
椶櫚 338
338 120
120
 15pt
15pt
うーん、あなたの想定している気圧っていうのは単純に大気の重さなわけだけど、この大気っていうのが曲者で、惑星質量が大きいと自身の回りに多くの物質を引き止める事ができ、質量が小さいと軽い物質は宇宙空間へと逃げていってしまいます。木星や太陽の大気の素成分が水素なのは、水素という軽い物体を引き止める事ができるほど大きな質量を持っていたからに他ならず、地球の大気に水素が無いのは地球の質量が小さいためです(惑星生成時に水素も発生したはずなのですが、水素など軽い気体は宇宙空間に逃げていってしまったと考えられています)。さらに質量の小さい月などでは大気そのものがありません(全ての気体が宇宙空間に逃げていってしまったと考えられています)。だから大気の組成は惑星の質量によって異なるし、高度によっても異なるわけです(例えばオゾン層は地球上でも上空にしかありません)。
さらにいうならば、実際には地球の表面も、○○の層、△△の層、のように下から順に重い気体から順に積み上がっていてもおかしくはないわけですが、大気の流れ(主に水の循環作用による)がこの形成を阻んでいるわけですね。しかし地下トンネルが作られるとなると話は別です。そこには空気の入れ替えが起こる原理が働きませんので、トンネル内は重い気体から順に積み重なる事でしょう。地表付近の大気組成(窒素78%、酸素20%、アルゴン1%)を元にした計算式はそのまま成り立つはずもなく、狭いて長いトンネル内は重い気体で埋め尽くされているでしょうから、自然、1.6気圧より大きくなるであろう事は容易に想像できます。実際に何気圧になるのかまではわかりませんが。
数値一部修正
ありがとうございます。
なぽりん 4907
4907 910
910
 20pt
20pt
孔の太さと向きに依るんでは。
数千気圧になるのはストローくらいの細さのトンネルですかね。
半径が数千キロにもなる巨大なトンネルを掘って地球を貫通させると(その際に失う質量分は、海水や地殻をタングステンにでもかえて補填するものとする)、
大気はその孔に薄く偏在し、かつ孔の壁面に多少濃く存在するようになる。
半径および場所によって1気圧にならない場合があるとおもいますよ。その場所での周辺質量の積分値ですねえ。地球の重心では無重力ですから意外と大気が薄いんじゃないでしょうか。台風の目みたいに。また、周りの地熱があるとすると、分子の拡散速度が早いので、孔内部にわりあい均一に存在するバランスにもなり得るでしょう(ブランコのように行ったり来たりする気流のぶつかる乱流かも)。
この運動エネルギーをうしなって地熱の補給がなければ
霜になりますね。重心周辺では閉塞することもあるかも。
彗星や小惑星には事実そういうトンネルつきの形のものもあるでしょうね。
子午線というか北極=南極方向に孔をあけると、孔に流入した大気は自転で壁面にもっとおしつけられるでしょう。
そうでない場合はもっと面白いことになるでしょう。適当なところで液体窒素の潮汐がおこるかもしれません。
ってことで定性分析とさせていただきます。めんどくさいから計算してなくてごめんなさいね。
あ、表面に「酸素が」残るかどうかですが、今地表の岩石などはおよそ酸化されていますが、内部は還元されているので、酸素を欲しています。剥き出しのマントルは流動しながら酸素をすべて吸収するでしょう。トンネルにシェルがあれば吸収はされない可能性があるでしょう。どんな素材のシェルか?知りませんw
御嶽山みてるかぎり意外と地殻ってモロくてすきまだらけっぽいですよね…
内部に気泡のある岩石や地殻とマントル層の境界の不連続面とか密度の変化があるのは確かです。
マントル層までだけでも掘り進んだら色々な事が分かると思う。
たけじん 1543
1543 203
203
 20pt
20pt
結構真面目に解いてる人がいた。
http://okwave.jp/qa/q93834.html
やたらすごい圧力になってます。
中心は無重力になるんだけど、周りの気体の圧力が凝縮されていて、もう液体だか個体だかわからん感じですね。しかも高温って。
どうやら、一時的にそういうパイプを作っても、圧力が高くなるから、途中で固体化したスラッジが急速に溜まって詰まってしまうようですね。
内部気圧を低くしたままだと、たぶん潰れるな。
パイプを構成できる物質が、とりあえず地球上にありません。
ita 204
204 48
48 ここでベストアンサー
ここでベストアンサー
うわ、すごいですね。
まさかこんなきちんとした回答が返ってくるとは思っていなかったので、多少狼狽していますw
-
 Lhankor_Mhy
2014/10/07 13:29:02
ああ、そうか、単位間違ってるじゃん。。。
Lhankor_Mhy
2014/10/07 13:29:02
ああ、そうか、単位間違ってるじゃん。。。
単純計算でも6000気圧かあ。 -
実際には地下深くでは高温になっているので
シャルルの法則により体積当たりの重量は地表の1/10~1/20程度になるはずです。
6000気圧だとしても地上の600気圧相当の分量しか穴には吸い込まれないですね。 -
さて他人のふんどしで相撲をとると
地球内部の重力加速度の計算図が
http://www3.atwiki.jp/space/pages/15.html
にあります。
これを基にすると地表から3000kmの深さ(マントルと外核の境界付近)までは
1Gの重力加速度を保ち、それ以上では直線状に0まで減少すると考えればよいかと。
地球内部の温度については
http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/publications/scientific_results/structural_materials/fig/topic0_fig3.jpg
で考えると3000kmの深さまでは2000℃、それ以上は4000℃で近似できそう。
4000℃以上では酸素分子や窒素分子が熱分解して酸素原子、窒素原子の気体として存在すると考えるほうが妥当なため、平均分子量は15程度と重さが半分になるでしょう。
あとは積分すればよいだけですが、それはポイント回答の人にお願い。 -
この質問の発端となった Harlock です。
何気なく人力はてなのサイトをペラペラ閲覧していたら、自分の回答から派生
して新たな質問がされているのを知ってビックリしました。
自分が相乗り質問を書いた時は、まさかこんなに沢山の頭のいい方々が真剣に
考えて下さるとは思ってもいませんでした。
正直、私は皆さんほど頭が良くないので、半分くらいしかついて行けませんが
面白く読ませて頂きました。
これだけ関心を持っていただける はてな を提供できたことを嬉しく思います。
質問を上げて頂いた Lhankor_Mhy さんと回答を寄せて下さった皆さんに感謝
します。ありがとうございます。
まだ、回答は終了していないようですので、引き続き、皆さんの回答を楽しく
拝見させて頂きます☆
-
>計算してみました。
おーっ液体になると重い気体元素から下に詰まるというのはすばらしい視点ですね。
ラドンは崩壊性だから抜いてあるのかな?
CO2が熱分解してどんどんダイアモンドが詰まっていくというのは考えたけど
Xeとは恐れ入りました。
Hgとかも常温で蒸気圧が無視できない量大気に混じってるみたいなので
http://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f31332d326a706e/save/0/0/13_2-09.pdf
最終的にはHgに置き換わったりして。
-
おお、なるほど水銀ですか。大気中濃度は変動してるようで、火山などからの放出と気流による拡散、場所により地表への
吸着や化学反応による吸収があって非平衡状態なんでしょうね。ラドンも同様に地表から出るようで、評価が難しいです。
穴に達する前に他所の地表にいっちゃうかもしれません。
後で気がついたんですが、分子量1の違いが顕在化するのに絶対温度*1km程度の深さが必要です。
Xeは安定同位体が5種類あるので、場合によっては重いものがさらに地下で精製される可能性が
ありますが、温度が3000度とかあるので分離するまえに固化して分離できないことも考えられます。 -
ラドンは最長寿命の同位体半減期が3.8日なので
ラドン自体は無視できるんですが崩壊して最終的には鉛あたりの重元素になるので
Xeより重い元素になって貯まるという結果が生じるのかも知れません。
まあ量的に見れば極僅かですがね。
実際には核の近くなんて凄い放射線量でしょうから鉄やニッケル以外の物質が改変せずに
安定存在できるのかどうかもあやしいところなんですよねえ。
圧力融点の線で出来る固相については、
温度からしてあまり常温付近の固体のように固定化して考えないほうがいいかなあ。
半導体でも不純物拡散のように内部での原子移動は起こりますし
特にXeのような不活性気体元素固体内を原子がドリフトする速度は
かなりの速度になるはずです。 -
できるできないの秘密は、
十万気圧と書いてました
トラックバック
-
地球に穴をあけたらどうなる? この質問。http://q.hatena.ne.jp/1412645084 たかだか標高8kmの山に登った程度で命に関わるくらい空気が薄くなるわけで、じゃあ反対に6000kmくらい下にいったら超は



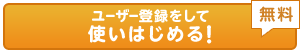

うわ、すごいですね。
2014/10/11 14:06:47まさかこんなきちんとした回答が返ってくるとは思っていなかったので、多少狼狽していますw