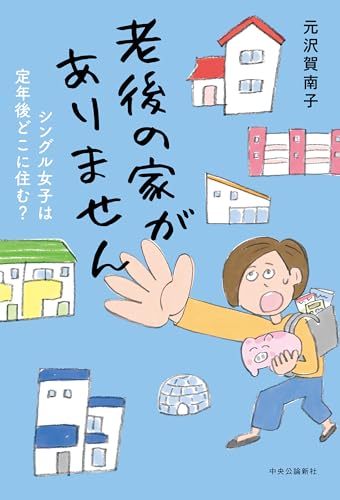本文抜粋
『モンスーン経済―水と気候からみたインド史―』(名古屋大学出版会)
インド出身、経済史の分野では世界的に知られるティルタンカル・ロイの著書『モンスーン経済』の日本語版がこのたび刊行されました。経済発展の歴史を読み解く鍵として、ロイは「化石燃料」ではなく「水」に着目しています。なぜ「水」が重要となるのでしょうか。もっぱら西洋の経験にもとづくこれまでの議論とは一線を画し、新たな発展モデルを示すこの著作の読みどころを、「第1章 なぜ気候が重要なのか」を手がかりにご紹介いたします。
インドが自らをとりまく環境との間で結ぶ関係の変化について、昨今のメディアが映し出す二つのイメージは、本書にとって格好の出発点である。過去に干ばつや飢饉の影響を受けやすいことで知られた地域は、「干ばつ防止」に成功した(「タイムズ・オブ・インディア」)。上に引用した1947年の報告が示している飢饉への懸念は、20世紀の第三四半期まで大きな影響力をもっていた。その後、その懸念は薄らいでいった。だが、干ばつ、熱波、そして弱いモンスーンを生み出す条件が消えたわけではなかった。それどころか、地球温暖化は、「致命的な熱波をインドでは普通のこと」にしてしまった(「BBCニュース」)。にもかかわらず、乾燥に悩まされる度合いは、百年以上にわたって低下した。水の供給と分配におけるたぐいまれな達成は、奇跡を起こしたのである。その一方で、2017年にはひそかに、そして2020年には大々的に、インドと中国の間で衝突が生じ、全面的な国境紛争になりかけた。ブラフマプトラ河(チベットではヤルンツァンポ河、バングラデシュではジョムナ河と呼ばれる)における水資源の管理は、南アジアでは絶えることのない不安の元である。河川水への需要は供給量をはるかに超えており、「この有限な資源をめぐって世界の二大人口大国の間で紛争が起きる可能性は、誰もが認めるところである」(M・クリストファー『Water Wars』)。

これらの報告は、地理的条件が経済成長、厚生、そして南アジアの政治にいかに深く影響を及ぼしているのかを示している。また、この影響が長期に及び、インドの近代史を形成し、さらに大きな試練を作り出してきたことも指摘している。その記述の一部は楽観的なメッセージを伝えているが、別の部分は憂慮すべきものである。
私は、1880年ごろ以降のインドにおける環境変化と経済変化の相互作用を検討することで、自然にうまく対処するためにかかるコストの要因を解明したい。熱帯モンスーン気候は、貧困や水へのアクセスの不平等、そして極端な雇用の季節変動が遍在する状況を作り出した。1880年ごろから、これらの状況を克服するための措置が先例のない規模で成功を収めるようになった。その措置は、死亡率の低下や人口増加につながり、集約農業や都市部の工業化を促した。化石燃料〔石炭――訳者注、以下同〕の採掘が西ヨーロッパの経済的台頭の鍵となったように、取水および水へのより広範なアクセスは、インド経済史において重要な役割を果たしたのである。しかしながら、その非凡な達成は、環境負荷(ストレス)および政治的対立といった代償をともなった。
本書は、三つのタイプの読者の興味を引くだろう。一番目のタイプは、経済成長や不平等を説明するという課題に関心のある読者である。経済史家は、国家間の比較によって、近代世界における経済成長の根源を発見しようとしている。彼らが用いる理論のほとんどは、西ヨーロッパの経験にもとづいている。その理論では、19世紀のヨーロッパにおいて経済上の大転換をもたらした諸要素が、なぜ世界の他地域では見られなかったのかが問われる。しかし、世界各地の地理的条件が不均衡なものであれば、この方法はあてにならない。熱帯モンスーン地域の初期条件はヨーロッパや北米と異なっていたため、ヨーロッパ人やアメリカ人にとって解決の必要があった問題とは異なる問題を解決することで、経済成長に到達できたのである。その問題とは、清潔な水への安定したアクセスの確保、そしてモンスーンの季節性への対処である。
本書がアピールしたい二番目のグループは、経済発展の持続可能性を議論することに関心のある読者である。経済発展の径路はストレスを生み出す。そのストレスを抱えたままでも、経済発展の径路は持続可能なのだろうか。どのように介入すれば、持続可能になるのだろうか。これらの問いに対する答えは、気候変動や地下水のストックなど、どの種類のストレスに悩まされているかによって変化する。
三番目のターゲットは、近代インドの興隆に関心のある読者である。イギリスの植民地帝国は、およそ1765年から1947年までインドの広範囲を支配した。帝国主義者は、1947年以後に出現した国家〔インドおよびパキスタン〕にさまざまな遺産を残していった。現在の南アジアの政治地図は、その遺産の一つである。この地域を扱う近代史研究の多くは、これらの遺産を研究対象として、ナショナリズムにもとづく開発政策による遺産の再変容のありようを説明している。その過程で歴史家は、英領インド時代の植民地国家であれ、独立後の国民国家であれ、国家権力に目を奪われ、その役割を過大視している。本書では、非ヨーロッパ世界の近代史を説明する際にみられる、こうした植民地主義とナショナリズムに対する執着を修正したい。私の論述では、地理的条件がどのように物質生活に影響を及ぼしていたのかを示していく。権力は重要な問題であるが、それはひとえに、基本的なプロセスにおいて間接的な役割を演じたからである。その基本的なプロセスは、環境と経済の相互作用から構成されているのだ。
[書き手]ティルタンカル・ロイ(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)教授。専門は経済史。)
[翻訳]小林和夫(早稲田大学政治経済学術院准教授)
「水」から読み解くインド経済:経済成長、不平等、サステナビリティ(持続可能性)
洪水と飢饉は、国家による水資源の開発という一つの問題における、二つの側面である。 ――国家計画委員会(インド)、1947年
インドが自らをとりまく環境との間で結ぶ関係の変化について、昨今のメディアが映し出す二つのイメージは、本書にとって格好の出発点である。過去に干ばつや飢饉の影響を受けやすいことで知られた地域は、「干ばつ防止」に成功した(「タイムズ・オブ・インディア」)。上に引用した1947年の報告が示している飢饉への懸念は、20世紀の第三四半期まで大きな影響力をもっていた。その後、その懸念は薄らいでいった。だが、干ばつ、熱波、そして弱いモンスーンを生み出す条件が消えたわけではなかった。それどころか、地球温暖化は、「致命的な熱波をインドでは普通のこと」にしてしまった(「BBCニュース」)。にもかかわらず、乾燥に悩まされる度合いは、百年以上にわたって低下した。水の供給と分配におけるたぐいまれな達成は、奇跡を起こしたのである。その一方で、2017年にはひそかに、そして2020年には大々的に、インドと中国の間で衝突が生じ、全面的な国境紛争になりかけた。ブラフマプトラ河(チベットではヤルンツァンポ河、バングラデシュではジョムナ河と呼ばれる)における水資源の管理は、南アジアでは絶えることのない不安の元である。河川水への需要は供給量をはるかに超えており、「この有限な資源をめぐって世界の二大人口大国の間で紛争が起きる可能性は、誰もが認めるところである」(M・クリストファー『Water Wars』)。

これらの報告は、地理的条件が経済成長、厚生、そして南アジアの政治にいかに深く影響を及ぼしているのかを示している。また、この影響が長期に及び、インドの近代史を形成し、さらに大きな試練を作り出してきたことも指摘している。その記述の一部は楽観的なメッセージを伝えているが、別の部分は憂慮すべきものである。
私は、1880年ごろ以降のインドにおける環境変化と経済変化の相互作用を検討することで、自然にうまく対処するためにかかるコストの要因を解明したい。熱帯モンスーン気候は、貧困や水へのアクセスの不平等、そして極端な雇用の季節変動が遍在する状況を作り出した。1880年ごろから、これらの状況を克服するための措置が先例のない規模で成功を収めるようになった。その措置は、死亡率の低下や人口増加につながり、集約農業や都市部の工業化を促した。化石燃料〔石炭――訳者注、以下同〕の採掘が西ヨーロッパの経済的台頭の鍵となったように、取水および水へのより広範なアクセスは、インド経済史において重要な役割を果たしたのである。しかしながら、その非凡な達成は、環境負荷(ストレス)および政治的対立といった代償をともなった。
経済成長、不平等と「水」
本書は、三つのタイプの読者の興味を引くだろう。一番目のタイプは、経済成長や不平等を説明するという課題に関心のある読者である。経済史家は、国家間の比較によって、近代世界における経済成長の根源を発見しようとしている。彼らが用いる理論のほとんどは、西ヨーロッパの経験にもとづいている。その理論では、19世紀のヨーロッパにおいて経済上の大転換をもたらした諸要素が、なぜ世界の他地域では見られなかったのかが問われる。しかし、世界各地の地理的条件が不均衡なものであれば、この方法はあてにならない。熱帯モンスーン地域の初期条件はヨーロッパや北米と異なっていたため、ヨーロッパ人やアメリカ人にとって解決の必要があった問題とは異なる問題を解決することで、経済成長に到達できたのである。その問題とは、清潔な水への安定したアクセスの確保、そしてモンスーンの季節性への対処である。
持続可能性と「水」
本書がアピールしたい二番目のグループは、経済発展の持続可能性を議論することに関心のある読者である。経済発展の径路はストレスを生み出す。そのストレスを抱えたままでも、経済発展の径路は持続可能なのだろうか。どのように介入すれば、持続可能になるのだろうか。これらの問いに対する答えは、気候変動や地下水のストックなど、どの種類のストレスに悩まされているかによって変化する。
インドの歴史と「水」
三番目のターゲットは、近代インドの興隆に関心のある読者である。イギリスの植民地帝国は、およそ1765年から1947年までインドの広範囲を支配した。帝国主義者は、1947年以後に出現した国家〔インドおよびパキスタン〕にさまざまな遺産を残していった。現在の南アジアの政治地図は、その遺産の一つである。この地域を扱う近代史研究の多くは、これらの遺産を研究対象として、ナショナリズムにもとづく開発政策による遺産の再変容のありようを説明している。その過程で歴史家は、英領インド時代の植民地国家であれ、独立後の国民国家であれ、国家権力に目を奪われ、その役割を過大視している。本書では、非ヨーロッパ世界の近代史を説明する際にみられる、こうした植民地主義とナショナリズムに対する執着を修正したい。私の論述では、地理的条件がどのように物質生活に影響を及ぼしていたのかを示していく。権力は重要な問題であるが、それはひとえに、基本的なプロセスにおいて間接的な役割を演じたからである。その基本的なプロセスは、環境と経済の相互作用から構成されているのだ。[書き手]ティルタンカル・ロイ(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)教授。専門は経済史。)
[翻訳]小林和夫(早稲田大学政治経済学術院准教授)