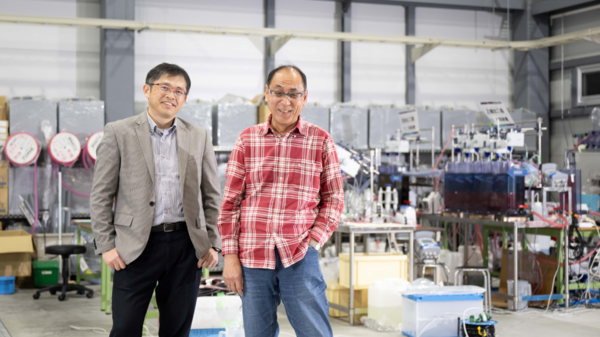次世代の量子計算機を日本発で。100万量子ビット実装へ加速するOptQC
間近となる2025年度の光量子コンピューター商用実機完成
「光量子分野は日本がリードしていきたい。そのためにも、2025年度には実機を完成させる」と意気込むのは、OptQC株式会社 代表取締役CEOの高瀬寛氏。2024年9月に誕生した同社は、20年以上にわたり光量子コンピューターを研究してきた東京大学の古澤明教授を取締役に、教え子である高瀬氏が代表に就任したディープテック・スタートアップだ。「研究に留まらず起業したのは、将来の量子コンピューター市場に入り込む隙がなくなる前に実機を出してアピールするため」だと高瀬氏は語る。光量子コンピューターとはどういうものか、どんな世界を実現していこうとしているのか、話を聞いた。
市場での存在感を示すため、2025年度に実機開発へ
「製品を出して得られるインパクトはとても大きい。研究だけではなく、製品を世に出すことで、光量子コンピューターの存在を多くの人に知らしめたい」――東大の研究室から飛び出し、OptQCを起業した理由を高瀬氏は端的にこう説明する。
量子コンピューターは、従来のコンピューター(古典コンピューター)とは異なる原理に基づいて動作する次世代演算技術であり、世界中の企業や研究機関、スタートアップで開発が進められている。多くの人が「量子コンピューター」と聞いて頭に浮かべるのは、IBMのQ(IBM Quantum)ではないかと高瀬氏は指摘する。
「実際の運用でいえば、(量子コンピューターでは)まだまだすごいことができるほどではない。ただし、やはり実機を見せてアピールしたインパクトは相当に強い」(高瀬氏)
OptQCが開発を進める光量子コンピューターは、現在の主流となっている量子コンピューターとは異なる技術特性を持ったものだ。超伝導体の物質を「量子ビット」として利用するのではなく、光パルスを用いて同様の機能を実現する。
「2025年度、茨城県つくば市の産業技術総合研究所の中に新たにできる施設『産総研G-QuAT(量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター)』の中で1号機を作ることが、我々にとって本当のスタートということになる」
産総研G-QuATには、OptQCの光量子コンピューターだけでなく、富士通の超伝導量子コンピューター、米QuEra Computingの中性原子量子コンピューターが入る予定で、日本における量子コンピューターの拠点となる。「創業間もない我々がこの施設に入ることができるのは光栄なこと」だと高瀬氏。
2024年11月、理化学研究所の量子コンピュータ研究センター(古澤チーム)は光量子コンピューターの開発に成功したと発表しているが、これはあくまで研究用途の試作機であり、外部の関係者は利用できない。OptQCの取り組みとは異なる文脈に置かれている。
「2026年4月に披露する予定のOptQCとしての1号機は、外部の人にも使ってもらえるものを目指している。競合は世界に存在するが、光量子の方式で実機まで完成しているところはない。一足早く光量子コンピューターの実機を完成できれば、久しぶりに日本が世界をリードするコンピューターとなる」とスピーディーなロードマップを描いている。
100万量子ビットの実装をたった1フロア未満に
そもそも、光量子コンピューターとはどんなものなのか。
現在、我々が利用している古典コンピューターは、ムーアの法則に代表される半導体の進化によって演算性能を上げてきた。しかし量子コンピューターは、「量子もつれ」や「量子テレポーテーション」などの量子操作によって演算を行う。量子的な重ね合わせにより「0」と「1」の状態を同時に取る量子ビット(キュービット)や、無数の計算結果の可能性から正解を取り出す量子干渉を巧みに利用することで、複雑な最適化問題をはじめとする古典コンピューターでは解決が難しい分野での活躍が期待されている。
光量子コンピューターも同様に量子操作を活用するが、「時間領域における光多重化技術」によって、コンパクトなセットアップで大規模計算が可能となり、一つの演算装置で大量の量子ビットを処理できる。この光多重化技術は、複数の量子的な光パルスを、光通信のように1つの伝送路上で時系列的に送信する技術だ。

光量子コンピューターの実機がコンパクトである理由は、量子操作と読み出しを行う1つのプロセッサーを反復的に使うことで、光軸上にある多数の量子ビットを扱えるため。このようなブレイクスルーは2019年に古澤研が世界で初めて実現し、2020年からのムーンショット型研究開発制度で大きく飛躍したという(画像提供:OptQC)
主な特徴としては、計算のクロック周波数(動作周波数)を数百テラヘルツという光の周波数まで原理的には高められる点や、室温での動作が可能な点が挙げられる。また光通信との親和性が高く、ネットワークの構築が容易になるとも考えられている。だが一番大きな特徴は、上述した光多重化技術によるコンパクトな設置が可能な点だ。
従来の量子コンピューターは、この先、量子ビット数の増加が求められることに伴って、巨大かつ複雑なシステムになることが予想されている。空間的に並列化された量子ビットそのものはコンパクトであっても、現在主流となっている超電導方式では、それらを個別に冷却・制御したり信号を読み出したりする周辺系の設備は大規模となる。
この点において、光量子コンピューターは現状で量子ビット数の大規模化を実現する目途が立っている唯一の方式と言えるという。量子ビット数を増やしてもハードとしてはコンパクトかつシンプルなままで、しかも常温常圧で動作できる。
通常の量子ビットは空間的に並列化するしかないが、光量子ビットは光通信のように時間軸や周波数軸にも並列化が可能だ。そのため1量子ビットを制御・読み出しするシンプルなプロセッサがあれば、実際は無数の量子ビットを扱うことができる。
実用的な計算を行うのに必要とされる100万量子ビットを実現するには、既存の量子コンピューターの場合はビル一棟レベルが必要ではないかという一方で、光量子コンピューターは1フロア未満で済む可能性もあると高瀬氏は強調する。
日本発で光量子コンピューターへの実装が加速した背景
光量子コンピューターを実現したのは、OptQCの取締役であり、東京大学大学院工学系研究科教授である古澤明氏の20年以上の研究だ。1998年カリフォルニア工科大にて決定論的量子テレポーテーションに世界で初めて成功。失敗する可能性がなく、量子情報を確実に送れる量子テレポーテーションの可能性を開いた。
「古澤先生が東大で研究を進める中でも、いくつかのトピックがあった。そのひとつがプロセッサー技術の確立。従来は、量子ビットが1個入ってきて、1回計算が出てくるという仕組みだったため、小規模な演算しかできない。コンピューターとして利用するためには、マルチステップでマルチビットにしないといけない。実は5年くらい前にそれを実現することに成功した」(高瀬氏)
プロセッサー技術を確立できたことで光量子コンピューターの実機を作る道ができた。そして、「(プロセッサーが)評価をあげた要因のひとつとなり、古澤先生の『誤り耐性型大規模汎用光量子コンピューターの研究開発』が、2020年度のムーンショット型研究開発制度に採択された。これは研究にとって大きなプラスとなるもので、予算規模は従来の10倍になり、大企業との研究連携といった成果が生まれることになった」という。
ちなみに、高瀬氏が古澤教授の研究室のメンバーとなったのは2016年。「学部で学ぶ中でやはり量子力学が面白かった。量子力学でいい研究室はないかと探している時に出会ったのが古澤研だった。かつての古典物理学では、『もう人類は物理を理解しきった』と思われた時期が一瞬あった。ところが、20世紀になってからもっと深遠な世界が広がり、相対論、量子物理学が現れてきた。両方とも面白かったが、相対論はエクストリームな環境で発現する物理。一方の量子力学は、これからエンジニアリングの場面で重要になってくることがはっきりとわかっていた。工学部だったのでかなり興味深いと考え選択した」
古澤研に入り、東京大学大学院工学研究科物理工学専攻博士課程にて博士号を取得後、同専攻で助教となったが、その後OptQCを起業する話が持ち上がる。設立前に助教を辞し、同社の代表取締役 CEOに就任した。光量子コンピューターの実装に向け、その存在を広くアピールしていくこともCEOとしての役割の一つとしている。
パートナーやアプリなどエコシステム作りが課題に
現在東京大学の研究室にある光量子コンピューターのデモ機は、これまで見たどのコンピューターとも似ていない、多数のレンズやミラーが並ぶ独特の筐体である。
「ここにあるものは実装からは遠い。これを現実的なハードウェアに仕上げていくことがこれからの課題となる」(高瀬氏)
そのために必要となるのが新たなスタッフだ。研究段階を超えて、電子デバイス、レンズ、メカトロニクスなど、関連するノウハウや技術を持っているスタッフや企業など、これまでなかった力が必要な段階となってきている。
「起業したのは、まさにそうした外部の力が明らかに必要だったため。研究だけでは、接点がなかった技術やノウハウを集めるのは容易ではない。我々が必要としているものをアピールすることで、新たな協力者を募りたい」
実際に設立発表後、協力者として名乗りをあげた企業なども出ているそうで、「起業したことは間違いではなかったという手応えを感じている。パートナーとなる企業が参加することができるエコシステムを作りたい」と話す。

2024年11月に理化学研究所で発表された古澤チームによる光量子コンピューター実機。上部にあるのは各種測定器であり、プロセッサーも含めた核となる部分は、写真下段の振動をコントロールする台の中に収められた増幅器やスプリッター、各種レンズ群や光ファイバーとなる(画像引用元:理化学研究所)
https://www.riken.jp/pr/news/2024/20241108_2/index.html
将来の実装に向けては、このようなハードウェア開発とともに、光量子コンピューターにはどんなアプリケーションが最適となるのかという模索も必要となる。現段階では、「ニューラルネットワークに最適という声は出ている」と高瀬氏。その理由も光量子コンピューターの特性を理解する手がかりとなる。
「ニューラルネットワークは、人間の脳を模して作られている。が、実際には人間のフィジカルな脳内ではアナログ的に情報処理がされている。世の中にある情報はほぼアナログで、それが脳内で処理され、判断されている。
同じことをデジタルデータしか処理できないコンピューターでやろうとすると、アナログ情報を全部デジタルに変換し、さらにすべてをデジタル処理し、その結果をもう一度アナログに戻す必要がある。このアナログからデジタルへ、デジタルからまたアナログに戻すという工程が非常に効率が悪いのではないかとも考えられている。すべてデジタルに変換せず、あくまでアナログのまま処理できれば効率がよくなる。
光量子コンピューターは、アナログ的な(量子の)重ね合わせを使い計算ができるので、ニューラルネットワークをより効率的に処理できるのではないかといわれている」
光量子コンピューターの特性を活かしたアプリケーションについては、実機完成後、多くの検証作業が進む中で本当に適したアプリケーションが見つかるのだろう。実機完成後には研究者や開発者向けのSDKを公開し、AWS経由で光量子コンピューターを試用し、扱える仕組みを作る計画だ。これもエコシステム作りの一環となる。
上述した理化学研究所で実装された光量子コンピューターについても、あくまで研究用途にとどまっている。「現段階では、量子コンピューターを理解している人の中でも、光量子の仕組みを理解しているごく一部のプロだけが扱える状態。これを広げ、例えばニューラルネットワークの専門家にSDKを使ってもらうなど、利用者を増やしていく仕組みを考えていかなければならない」と課題解消を狙う。
実機を作り続ける中で新たな課題が生まれる可能性も
現在、2028年ごろに2号機、2029年ごろに3号機というOptQCとしてのおおまかなロードマップが決定している。しかし、「5年先はどうなっているのかわからない」と高瀬氏は話す。「真剣にハードウェア作りに取り組んでいく中で、1台を作る中でもいろいろな発見がある。その中で、いま言っていたこととは全然違うことになる可能性も十分にあり得る」という実感からだ。
「今のところ、大きな方針はぶれてないが、小さいことは頻繁に事情が変わり、変わっていくことになる。ハードウェア作りという点では5年では時間が足りないが、とにかく良いものにしていく必要がある」(高瀬氏)
こうした変化を受け入れつつ、高瀬氏自身は、「まず光量子コンピューターをなくさないこと。20年以上研究が続いてきたこの技術を絶対に実用化させたい」と強い決意を持っている。
「もともとの私自身の研究テーマは、GKP量子ビット※であり、いわゆる量子誤り耐性ビット。『こう作れば、もっと効率的にできるのでは』といった論文を書いてきたが、実際にGKPを作り、目の当たりにしたい。研究者として、社長として光量子コンピューター実機でのGKPを絶対に目にするということがモチベーションとなっている。そのため、もしかしたら研究者に戻るという可能性もあるが、実機を作り続けていくことが一番の近道になるのではないかと考えている」
※量子ビットへの外部環境からの物理的エラーの情報を取り出し、情報を復元することで情報を保持する特性を持つ光パルスを用いた量子ビット。1つの量子ビットのみで、誤り耐性を持つ論理量子ビットを実現できる。
OptQCの試みは、2040年には100兆円超ともいわれる光量子コンピューターによる経済価値以上に、「日本発で世界をリードする新たなコンピューター」であることに、わくわくする人も多いのではないか。先端研究分野での高い実績があるにもかかわらず、ビジネス化という点で成功例が少ない日本のイメージを覆す、大学発スタートアップとして成功することができるのか。OptQCには、期待を圧倒的に超える実機開発スピードと、業界のリードを期待したい。