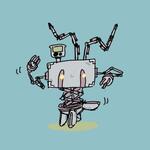ASCII Power Review 第272回
操作性も連写も高感度画質も最先端でした
クラシックカメラなデザインの最新鋭ミラーレスカメラ「OM-3」実機レビュー
2025年02月11日 10時00分更新
OMシステムのマイクローサーズの新製品「OM-3」が発表された。昨年発売したフラックシップモデル「OM-1 MarkⅡ」と同等の機能を、銀塩時代の名機「OM-1」を彷彿させるデザインのボディーに搭載、昔からのカメラマニアには気になるところだ。
実機を借りたので、写りはもちろん、使い勝手をチェックしていこう。
まさにフィルム一眼のデザイン
ダイヤルも増えて操作性も◎
ボディーはグリップレスのフラットなデザイン。カラーはシルバーのみとなる。上面や背面のボタン類は下位モデル「OM-5」に似た配置になっている。
グリップレスということでホールド感が気になるところだが、実際に手にして見ると軽量化や背面のサムレストのおかげで思いのほか構えやすく、キットのような小柄なレンズとの組み合わせなら苦になることはなかった。
前面には色調などの画像仕上げを調整できる「クリエイティブダイヤル」を搭載。こちらも2016年発売の「PEN-F」に初搭載された機能だが、OMシリーズでは初となる。調整項目は彩度や階調など多岐にわたり、自分好みの絵作りを追求したい人には楽しい機能だ。

プリセット3(彩度とハイライト&シャドウを強調)にシェーディング+3で撮影した作例。使用レンズ「12-45mm F4」・焦点距離14mm・絞りF8・シャッタースピード1/640秒・ISO200・ホワイトバランスオート。

プリセット2(ハイライト&シャドウを強調し粒状感を追加)にシェーディング-3で撮影した作例。使用レンズ「12-45mm F4」・焦点距離17mm・絞りF5.6・シャッタースピード1/250秒・ISO200・ホワイトバランスオート。

主なアートフィルターの作例。ノーマル、ポップアートⅠ、ファンタジックフォーカス、ラフモノクロームⅠ、トイフォトⅠ、クロスプロセスⅠ、ドラマチックトーンⅠ、リーニュクレールⅠ、ウォーターカラーⅠ、ヴィンテージⅠ、ブリーチバイパスⅠ、ネオノスタルジー。
上面左肩には静止画/動画/S&Qの切換ダイヤルが新設された。従来機まで動画撮影はモードダイヤルにあったので、露出モードは別途メニュー画面から変更しなければならなかったが、独立したおかげで操作性は向上している。
「S&Q」(スローモーション&クイックモーション)もメニュー画面に個別の項目が追加。クイックモーションではフレームレート1fpsも可能になり最大60倍速の動画が撮れる。
なお初期設定では動画撮影は上面右端のボタンでおこなうが、配置が窮屈で少々押しにくい。なのでボタンの設定項目からシャッターボタンで動画撮影をオンにしておくのをオススメする。
「OM-5」では「AEL/AFL」だった背面のボタンはCP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンに変更。高画素撮影をする「ハイレゾショット」やスローシャッター効果が得られる「ライブND」などの機能の切換やオンオフが設定できる。
なおこのボタンもFnボタンを兼ねているので他の機能に変更したり、逆に他のボタンに「CP」を割り当てることも可能だ。
EVFは236万ドットで倍率最大1.37倍。「OM-1 MarkⅡ」の576万ドット・1.65倍よりはスペックダウンしている。ただ確かに倍率は低めだがクリアな光学系のおかげか精細感には十分満足できた。
背面液晶のスペックやバリアングル式は変わらず。メニュー画面では上部の左右タブのみタッチ操作という謎の仕様も同様だ。
バッテリーは「OM-1 MarkⅡ」と共通の「BLX-1」で公称撮影可能枚数は590枚。スリムボディーでも大型のバッテリーを搭載しれたのは嬉しいが、バッテリーグリップは用意されていない。
メディアはUHS-II対応のSDでスロットはシングルになっている。側面ではUSB-CがPDに対応し充電にくわえ給電も可能となった。
ただレリーズ端子は排除され、さらに従来のワイヤレスリモコン「RM-WR1」も使用不可。レリーズには新しいリコモン「RM-WR2」(実売1万120円)か、スマホアプリからおこなうことになる。
撮像素子はフラッグシップと同じ
高感度画質も優秀だ
撮像素子も「OM-1 MarkⅡ」と同じ2037万画素の積層型。そのおかげで電子シャッターならAF/AE固定で秒120枚、AF/AE追従で秒25枚、一部対応レンズなら秒50枚の高速連写が可能だ。
プリキャプチャー機能も搭載し、被写体認識などのAFも同等だ。メカシャッターでの連写速度や連続撮影枚数が少ないものの、高速性能は「OM-1 MarkⅡ」に匹敵する。

飛び立つ鳥を撮影。被写体認識のおかげでしっかりピントが合っている。使用レンズ「100-400mm F5.0-6.3 Ⅱ」・焦点距離123mm・絞りF6.3・シャッタースピード1/5000秒・ISO1600・ホワイトバランスオート。

水面と駆け抜ける鳥。とっさにカメラを向けたが、しっかり追従してくれた。使用レンズ「100-400mm F5.0-6.3 Ⅱ」・焦点距離218mm・絞りF6.3・シャッタースピード1/5000秒・ISO1600・ホワイトバランスオート。

捕食した瞬間の1枚。こんな写真が撮れるのもプリキャプチャーおかげ。使用レンズ「100-400mm F5.0-6.3 Ⅱ」・焦点距離400mm・絞りF6.3・シャッタースピード1/8000秒・ISO800・ホワイトバランスオート。
ただボディーが小型かつグリップレスなぶん、超望遠レンズで長時間撮影していると少し手首が疲れてくる。やはり本格的は動体撮影なら「OM-1 MarkⅡ」のほうが向いているかもしれない。
また個人的感覚ではシャッターボタンがやや重めで、メカシャッターでは動作時に多少バタつく。このあたりは上位機との差といったところだろうか。
高感度も同じく常用最高ISO 2万5600、拡張で10万2400まで設定可能。ノイズ処理のバランスが良く6400程度までは安心して実用でき、ある程度の光量があるシーンなら2万5600でも許容範囲だ。

感度別に撮影した写真の一部を拡大して比較。左上からISO3200・ISO6400・ISO12800・ISO25600・ISO51200・ISO102400。使用レンズ「12-45mm F4」・絞りF6.3・ノイズ処理標準。
ボディー内手ブレ補正は中央6.5段、周辺5.5段。「OM-1 MarkⅡ」の8.5段を下回るが、実際にキットレンズ「12-45mm F4」で試してみると、遠景なら2秒程度までブレを防止してくれた。近景では流石にブレやすくなるが、慎重に撮影すれば1/2秒でもブレがなく撮れることがあった。
「OM-1 MarkⅡ」との価格差がわずかなことは気になるものの、小型ボディーでの軽快な撮影スタイルは思いのほか楽しかった。気合の入った撮影ならフラックシップのほうがいいだろう。だが普段から生活を共にするカメラとして選ぶなら「OM-3」は丁度良いかもしれない。
3本の新レンズは防塵防滴
17mmでお散歩がグッド
「OM-3」と一緒に3本のレンズが発表された。いずれも光学系に変更はないが、せっかくなので試しに撮らせてもらった。

この連載の記事
- 第271回 自動認識AFも連写も画質も最強だった=ソニー「α1Ⅱ」実機レビュー
- 第270回 インテルの最新AI CPU「CoreUltra2」搭載モバイルノートPC「Swift 14 AI」実機レビュー
- 第269回 14万円で買えるニコンの最新ミラーレスカメラ「Z50Ⅱ」実写レビュー
- 第268回 インテル最新AI CPU「CoreUltra2」搭載で超軽量なのにバッテリーは15時間持ち=「MousePro G4」実機レビュー
- 第267回 18インチになる世界初の2階建て2画面ノートPC「GPD DUO」実機レビュー
- 第266回 ついに発売!! キヤノンの最上位ミラーレスカメラ「EOS R1」徹底実写レビュー
- 第265回 未来デザインのPCが「CoreUltra2」で「Copilot+PC」になった!! 新「XPS13」実機レビュー
- 第264回 Copilot+PCはペンで使いたい=14型2in1ノート「HP OmniBook Ultra Flip14 AI PC」実機レビュー
- 第263回 「アポ・ズミクロン」の描写力に圧倒された!!フルサイズコンパクトカメラ「ライカQ3 43」実機レビュー
- この連載の一覧へ