新年明けましておめでとうございます。 昨年は天中殺に入ったとたんいろいろとありましたが、人生最悪に近いどん底から上昇中であります。 さて、今年最初の記事は、ジャーナリストとブロガーの違いについて述べ、私自身はあくまでもウェブ上においてジャーナリスト志向ではなくブロガー志向で書いていくことを、新年の抱負の代わりにまとめてみたいと思います。 ■これまでの新年コメント 2004年「ことのは」は……新年の抱負 [絵文録ことのは]2004/01/01 新年明けましておめでとうございます [絵文録ことのは]2005/01/01 「豆乳組」(www.tonyu.net)、満を持して登場 [絵文録ことのは]2006/01/01 ■ブロガーとジャーナリスト ブログというのは、あくまでも表現手段の一つとしてのツールにすぎない。表現のためのプラットフォームであって、その上で何をやるかは自由である。したがって、ブ
タグ
- すべて
- #|ω`)<笑った (2)
- *社会 (1)
- 2ch (4)
- 2ちゃんねる (8)
- 9・11 (1)
- AR (1)
- AV (2)
- Apple (24)
- Augmented Reality (2)
- A級戦犯 (2)
- BLOGGER (1)
- Benz (1)
- CGM (3)
- CMS (8)
- CNET Japan (26)
- Conference (1)
- Dell (1)
- Edward Tufte (1)
- Facebook (6)
- Flickr (1)
- GMO (1)
- GS (1)
- Gmail (1)
- Google (22)
- Google Docs (2)
- Googlezon (2)
- GripBlog (25)
- HUD (1)
- IPA (2)
- IPアドレス (1)
- ISMS (1)
- IT (2)
- ITmedia (2)
- J-CAST (1)
- JASRAC (6)
- JunJun (1)
- Linux (6)
- MSN Spaces (1)
- Microsoft (16)
- Movable Life (1)
- Myspace (2)
- NEC (2)
- NGN (1)
- NHK (1)
- NTT (1)
- Netscape (2)
- OpenPNE (2)
- OpenSIM (1)
- PDF (1)
- PuTTY (1)
- R30 (10)
- RDBMS (1)
- RSS (4)
- RedHat (1)
- Rimo (1)
- SBI (1)
- SEO (2)
- SL (1)
- SNS (8)
- SONY (1)
- SQL (1)
- Second Life (62)
- StarSuite (1)
- Steve Jobs (2)
- TBS (1)
- Ubuntu (1)
- VirtualWorld (9)
- Vista (12)
- ajax (2)
- apache (1)
- bill gates (4)
- blog (4)
- book (1)
- bot (1)
- burninglife (1)
- dankogai (1)
- docomo (1)
- ekken (2)
- eコマース (1)
- eラーニング (1)
- finalvent (31)
- firefox (1)
- friendfeed (1)
- gadget (1)
- google adsense (1)
- google earth (2)
- greasemonkey (1)
- iKnow (1)
- iNTERNET magazine (1)
- iPhone (5)
- iPod (5)
- javascript (1)
- leopard (1)
- life (1)
- lovecraft (1)
- lunarr (2)
- mac os x (1)
- mixi (4)
- naoya (1)
- network (1)
- oracle (4)
- pagerank (1)
- photoshop (2)
- rsync (1)
- ruby (2)
- ruby on rails (6)
- secondlife (1)
- software (1)
- spam (2)
- ssh (1)
- tool (1)
- twitter (1)
- unicode (1)
- web (9)
- web2.0 (10)
- webアプリ (1)
- webサービス (3)
- webデザイン (1)
- wikipedia (12)
- windos (1)
- xoops (3)
- yahoo (5)
- youtube (2)
- あとで考える (6)
- あとで読む (9)
- いじめ (2)
- おもしろ (1)
- おもしろい (3)
- がんだるふ (1)
- きっこ (3)
- きっこの日記 (28)
- こうさぎ (1)
- ことかん(仮) (1)
- ことのは (9)
- ことのは告白 (79)
- これはすごい (5)
- これはひどい (3)
- しょこたん (2)
- そのまんま東 (1)
- はてな (2)
- はてな匿名ダイアリー (1)
- はてブ (1)
- ひろしまドッグぱーく (1)
- ひろゆき (1)
- まとめ (1)
- アイコン (1)
- アイデンティティ (1)
- アイピーモバイル (13)
- アジア (1)
- アフィリエイト (1)
- アメリカ (3)
- アルファブロガー (3)
- アーレフ (6)
- イザヤ・ベンダサン (2)
- イラク人質事件 (1)
- インサイダー取引 (1)
- インターネット (5)
- インターネットマガジ (1)
- インターン (1)
- インフルエンザ (1)
- インプレス (1)
- イーホームズ (2)
- ウェブサービス (1)
- ウェブ時代をゆく (1)
- ウェブ進化論 (1)
- エイプリルフール (2)
- エクステンション (1)
- エルビス (1)
- オウム (7)
- オウム信者 (1)
- オウム真理教 (16)
- オタク (1)
- オブジェクト指向言語 (1)
- オヤジ (1)
- オリコン (2)
- オリックス (2)
- オープンキャンパス (1)
- オープンソース (3)
- オーマイ (1)
- オーマイニュース (35)
- カウンセリング (1)
- カンヌ (1)
- ガ島通信 (5)
- キリスト教 (1)
- ギャルサー (1)
- クジラ (1)
- クチコミ (12)
- クローズアップ現代 (1)
- グループウェア (1)
- ケイタイ (1)
- ケータイ (1)
- ゲーム (4)
- コミュニティ乗っ取り (1)
- コメント欄 (1)
- コンテンツシンジケー (1)
- コンテンツ政策 (1)
- コンプライアンス (1)
- サイゾー (1)
- サイトキャッチャー (1)
- サイバッチ (2)
- サイバー (1)
- サイバーファーム (6)
- サイボウズ (1)
- サイモン・ウィーゼン (1)
- サブプライム (1)
- サヨク (1)
- システム (4)
- システム工学 (1)
- シンクタンク (1)
- ジェノサイド (1)
- ジャーナリスト (1)
- ジャーナリズム (8)
- スクリプト (2)
- スターウォーズ (1)
- スティーブ・ジョブズ (5)
- ストックオプション (1)
- スパム (1)
- スラッシュドット (1)
- スラッシュドット ジャ (1)
- セカイカメラ (1)
- セキュリティ (3)
- セキュリティポリシー (1)
- セクハラ (3)
- セゾン (1)
- セルフブクマ (54)
- セレゴ (1)
- ソフトバンク (5)
- ソフトバンクモバイル (1)
- ソラマメ (1)
- ソーシャルネットワー (1)
- ソーシャル・ネットワ (1)
- タグ乱造反対 (1)
- タミフル (1)
- ダイナミック転送 (1)
- ダカール (1)
- ダライラマ (1)
- ダルフール (2)
- ダンス (1)
- チベット (2)
- ツンデレ (1)
- ツール (4)
- テレビ (1)
- デジハリ (2)
- トーラ (1)
- ドラゴンクエスト (1)
- ニホンザル (1)
- ニューディール (2)
- ニート (3)
- ネオコン (1)
- ネタ (5)
- ネットジャーナリズム (3)
- ネット右翼 (4)
- ネット広告 (1)
- ネット議論 (1)
- ハッカー (1)
- ハーレム (1)
- バベル (1)
- パソコン市場 (1)
- パフォーマンス (1)
- ヒロシマ (1)
- ビジネス (2)
- ビデオニュースドット (1)
- ビラ配布 (1)
- ビルゲイツ (1)
- ビルマ (4)
- ビル・ゲイツ (3)
- ビートルズ (1)
- ピクサー (1)
- フィナンシャル・タイ (1)
- フェミニズム (1)
- ブロガー (3)
- ブログ (15)
- ブログの女王 (1)
- ブログマーケティング (1)
- ブロゴスフィア (1)
- プラネタリウム (1)
- プリンタ (1)
- プルート (1)
- プレゼン (1)
- プログラミング (3)
- プロフ (7)
- ベンチャー (2)
- ペコちゃん焼 (2)
- ページランク (1)
- ホテル・ルワンダ (12)
- ホテル・ルワンダ (2)
- ホリエモン (2)
- ボランティア (1)
- マイクロソフト (5)
- マスコミ (2)
- マスメディア (1)
- マッシュアップ (2)
- マニュアル (1)
- マリオ (1)
- マルコポーロ (1)
- マンガ (1)
- マーケティング (4)
- ミサイル (3)
- ミス・ユニバース (1)
- ミトニック (2)
- ミャンマー (9)
- メタバース (1)
- メディア (6)
- メール (1)
- メール偽装 (2)
- モバイル (12)
- ユーザーカルマ (2)
- ユーロスペース (1)
- ライブドア (31)
- ライブドアニュース (2)
- ライブドアマーケティ (1)
- ライブドア事件 (2)
- リキッドオーディオ (6)
- リスクヘッジ (1)
- リスト (1)
- リテラシー (1)
- リモートホスト (1)
- リンデンラボ (1)
- ルーカス (1)
- ロシア語 (1)
- ロス疑惑 (3)
- ロッキンオン (1)
- ロングテール (2)
- 三島由紀夫 (3)
- 三浦和義 (3)
- 三鷹市 (1)
- 上祐史浩 (1)
- 不二家 (3)
- 世界史未履修問題 (1)
- 中原中也 (1)
- 中国 (5)
- 中国当局 (1)
- 中沢新一 (2)
- 中谷巌 (1)
- 亀田興毅 (2)
- 事件 (2)
- 事件・事故 (1)
- 事業計画 (1)
- 人力検索はてな (1)
- 人材募集 (1)
- 人生 (1)
- 人間 (2)
- 仏教 (1)
- 仮想世界 (3)
- 仮想化 (1)
- 仮想空間 (1)
- 任天堂 (1)
- 企業業績 (1)
- 伊東 乾 (2)
- 伊集院静 (1)
- 佐々木俊尚 (13)
- 佐藤優 (1)
- 便利 (2)
- 保坂展人 (1)
- 倫理 (1)
- 偽メール事件 (1)
- 備忘録 (2)
- 全共闘 (2)
- 公安調査庁 (9)
- 公正取引委員会 (1)
- 公益通報 (5)
- 内定者 (1)
- 内田樹 (1)
- 再考 (1)
- 冥王星 (1)
- 冷笑マン (5)
- 処女懐胎 (1)
- 分祀 (1)
- 切込隊長 (5)
- 初音ミク (1)
- 労働 (1)
- 動物 (1)
- 動物虐待 (1)
- 動画 (1)
- 動画共有 (1)
- 北尾吉孝 (1)
- 北朝鮮 (5)
- 医療 (1)
- 半角英数 (1)
- 南泉斬猫 (1)
- 博報堂 (1)
- 原爆 (1)
- 原発 (2)
- 司法 (1)
- 吉良上野介 (1)
- 名文 (1)
- 国会TV (3)
- 国賠 (1)
- 在日外国人 (1)
- 地下鉄サリン事件 (1)
- 地球温暖化 (1)
- 堀江貴文 (3)
- 報道 (3)
- 売文日誌 (17)
- 大前研一 (2)
- 天文 (1)
- 天皇 (3)
- 天皇制 (2)
- 太陽系 (1)
- 女 (1)
- 嫌韓流 (1)
- 学校裏サイト (1)
- 学歴 (2)
- 学習指導要領 (1)
- 孫正義 (1)
- 宇宙 (2)
- 宇宙のような慈愛 (1)
- 安田好弘 (1)
- 実名と匿名 (1)
- 宮内義彦 (1)
- 家畜人ヤプー (1)
- 家計簿 (1)
- 富樫義博 (1)
- 富田メモ (3)
- 専業主婦 (1)
- 小沢一郎 (3)
- 小泉純一郎 (2)
- 小泉総理 (1)
- 小飼弾 (12)
- 山口洋 (1)
- 山本七平 (3)
- 島尾ミホ (1)
- 島田 裕巳 (1)
- 島田裕巳 (1)
- 差別問題 (1)
- 市場 (1)
- 年金 (14)
- 広告 (4)
- 強制捜査 (1)
- 後で読む (3)
- 忠臣蔵 (1)
- 情報 (1)
- 情報セキュリティアド (1)
- 惑星 (1)
- 愛国心 (1)
- 戦争責任 (1)
- 戦後 (1)
- 技術 (1)
- 投資事業有限責任組合 (1)
- 押し紙 (2)
- 拉致問題 (2)
- 揉め事 (1)
- 携帯 (3)
- 政治学 (1)
- 教育 (1)
- 教育委員会 (1)
- 新型インフル (1)
- 新自由主義 (2)
- 新風舎 (1)
- 日本の広告費 (1)
- 日本ブログ協会 (1)
- 日本人とユダヤ人 (3)
- 日経新聞 (1)
- 早稲田大学 (2)
- 映画 (2)
- 昭和天皇 (4)
- 時事通信社 (1)
- 書評 (2)
- 朝日新聞 (5)
- 朝鮮人大虐殺 (8)
- 朝鮮総連 (8)
- 本当にありがとうござ (1)
- 村上ファンド (5)
- 村上春樹 (2)
- 松永英明 (24)
- 検索連動型広告 (3)
- 検閲 (2)
- 楽天 (2)
- 権威主義 (2)
- 歌田明弘 (2)
- 毎日新聞 (3)
- 民主党 (36)
- 沖縄 (2)
- 派遣 (2)
- 渡邉恒雄 (2)
- 町山智浩 (5)
- 疑問 (2)
- 皇室典範 (2)
- 真性引き篭もり (2)
- 社会 (2)
- 神保哲生 (2)
- 福田康夫 (2)
- 絵文録ことのは (2)
- 興味深い (2)
- 著作権 (5)
- 藤原新也 (2)
- 裁判 (3)
- 西武 (2)
- 読み物 (2)
- 週刊アスキー (9)
- 関東大震災 (9)
- 集合知 (2)
- 電通 (7)
- 靖国問題 (5)
- 靖国神社 (3)
- 韓国 (2)
- SEO (2)
- ことのは告白 (79)
- Second Life (62)
- セルフブクマ (54)
- 民主党 (36)
- オーマイニュース (35)
- finalvent (31)
- ライブドア (31)
- きっこの日記 (28)
- CNET Japan (26)
- GripBlog (25)
ジャーナリズムに関するBigBangのブックマーク (8)
-
 BigBang 2007/01/01"ジャーナリストは正義を追及するがブロガーは事実を淡々と書く” →ジャーナリストの定義が少々ラフな気がする。正義を叫ぶジャーナリズムという、「旧来型マスメディア」批判との領域認識が問題となるか。
BigBang 2007/01/01"ジャーナリストは正義を追及するがブロガーは事実を淡々と書く” →ジャーナリストの定義が少々ラフな気がする。正義を叫ぶジャーナリズムという、「旧来型マスメディア」批判との領域認識が問題となるか。- ジャーナリズム
- ブロガー
- あとで考える
リンク -
オーマイニュース(韓国):Web2.0の先駆け - ビジネススタイル - nikkei BPnet
オーマイニュース(韓国):Web2.0の先駆け (小屋 知幸=日本総合研究所 企業革新クラスター 主席研究員) 「オーマイニュースは読者が参画する仕組みをつくることにより、メディアのあり方を変えました」. オーマイニュース(韓国)のオ・ヨンホ代表の語り口は、その紳士的な風貌に反してきわめて情熱的である。 「市民みんなが記者」を理念に掲げるオーマイニュースが、世界初のインターネット新聞を立ち上げたのは2000年のことだ。オーマイニュースは、新聞の既成概念に真っ向から挑戦した。読者参画の仕組みは、その核心に位置づけられる。オーマイニュースでは市民記者として登録すれば、誰もが記事を書くことができる。さらに記事に対する読者のコメントを掲載する。読者は記事とともにその反響を読むことができる。 オーマイニュースは読者に開かれたプラットフォームであり、読者がコンテンツづくりに参画する。つまりオ
-
2006-06-25
歌田明弘の『地球村の事件簿』: 日本のネットはなぜかくも匿名志向が強いのか さて、事情を知っている人なら「相変らず」という感想しかでてこないのだが。 歌田氏の今までの「ことのは」関連のエントリ。 歌田明弘の『地球村の事件簿』:われわれはみな「隠れオウム」の容疑者 歌田明弘の『地球村の事件簿』: われわれがオウム事件で忘れていること 歌田明弘の『地球村の事件簿』: (今ふう)ジャーナリズムとは何か これらのエントリは、途中からコメント・トラックバックの受付を締め切り、しかも一部を除いて殆ど削除してある(最初からコメントを受け付けていない例もあった)。更に今回は、最初から両方受け付けていない。ご覧になれば判るが、他のエントリはそのような処理はしていない。 今回歌田氏はこのような事を書かれているが、 実際のところ、実名ブログを書いて炎上すると実生活で困る人は、どれぐらいいるのだろうか。 炎上の仕

-
本が出ます | ネットは新聞を殺すのかblog
けろやんブログを通じて、自分の本の予約販売が始まったことを知る。 6月24日発売だそうです。本のタイトルは「ブログがジャーナリズムを変える」です。ブログ「は」ジャーナリズムを変える、だと思っていた。NTT出版の社長の鶴の一声で決まったそうです。まあ僕の提案だった「メディアの融合と参加型ジャーナリズム」というインパクトのないタイトルよりはましか。 ただ自分としては、ブログがジャーナリズムを変える完璧なツールだとは思っていない。個人の情報発信、消費者発信メディア(CGM)がジャーナリズムを変えることは間違いない。CGMの歴史の中では、ブログはあくまでも過渡期的なツールだと思う。というのは、まだまだネット上の言論空間は未成熟だし、ブログを通じた議論は健全なものばかりではないからだ。 それでもブログというツールには非常にお世話になったという思いが強い。ブログを通じて多くのことを得た。 僕は幼いころ
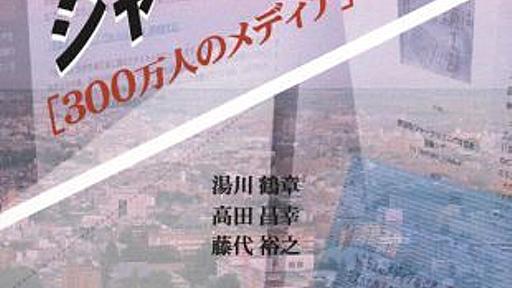
-
-
言論の自由と宅配制度をリンクさせるな | ニュースの現場で考えること
公正取引委員会が新聞の特殊指定見直しを検討している。宅配制度が維持できるか、はたまた崩壊するかの分岐点だとみて、新聞各社は与党・政府などにここぞとばかりの猛アタックを繰り返している。共同通信の特集を見ていると、新聞労連もその輪に加わり、いわば労使一体の運動になったようだ。 規制に守られていた業界にとって、その規制存続は死活問題だ。1960年代の繊維業界から始まって、日本では(もちろん諸外国も一緒)過去、各業種・各企業が「規制を存続させてください運動」「業界を守ってください運動」を繰り広げてきた。誤解を恐れずに言えば、新聞業界が「規制を続けてください、宅配制度を続けさせてください」と言い続けるのは、企業のリクツからすれば、当然のことだ。 むろん、賢い経営者は、「規制で守ってください」と嘆願する一方で、自社の経営体質改善を図り、来るべき自由化時代への備えを着々と進める。で、その備えが整った段階

-
中間報告 | ネットは新聞を殺すのかblog
まだ中間かよ、と怒られそうだが、この本をブログにする計画はまだ進行中です。現在GW中ながら再校のゲラをチェック中。6月くらいには本として完成する見込みです。 タイトルは「メディアの融合と参加型ジャーナリズム」とわたしから提案したのですが、編集者はあまり感心しなかったもよう。その後、「ブログの読者からは『ネットにやられてたまるか』というタイトルを提案してもらったんだけど」と話したら「それでいきましょう。編集会議でそのタイトルを強く推します」と言っていた。いいのか、そんな刺激的なタイトルで。 実はこのタイトルを提案したのは、スポンタさんなんです。 ほかにいいタイトルがないか考えているんだけど、まったく思いつかない・・・。困った。 出版されれば、このブログも閉めようかなあ。1つのくぎりとしてね。でもまたすぐに別のところでブログを始めるかもしれないけど。
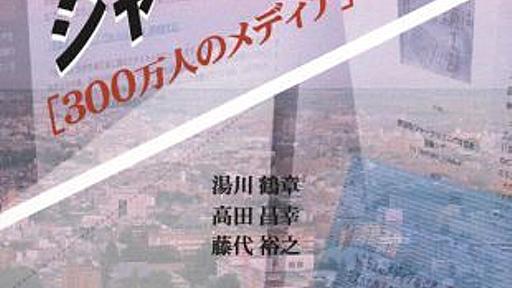
-
-
 1
1
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く





