
タグ
- すべて
- .Net (253)
- 3D (179)
- 3Dプリンタ (37)
- AKB48 (30)
- AMD (28)
- API (25)
- AR (26)
- ARM (26)
- ATOK (270)
- AWS (64)
- ActionScript (77)
- ActiveX (24)
- Adobe AIR (241)
- Aira Mitsuki (29)
- Amazon EC2 (26)
- Android (386)
- AphexTwin (26)
- Arduino (33)
- BD (63)
- BI (23)
- Beatles (28)
- C (50)
- C# (201)
- C++ (472)
- C++11 (30)
- CASIO (51)
- CD (26)
- CG (98)
- CI (188)
- CM (89)
- COM (62)
- CORNELIUS (55)
- CPU (136)
- CSS (44)
- Chrome (38)
- ConceptBase (29)
- DAC (88)
- DAW (45)
- DB (99)
- DRM (62)
- DS (52)
- DS-10 (28)
- DSD (44)
- DTM (187)
- DVD (58)
- ETF (70)
- Erlang (49)
- Excel (629)
- F# (62)
- FIAT (248)
- FIAT 500 (23)
- FIAT Panda (45)
- FIAT500 (136)
- FLEX (90)
- Flash (216)
- GDI (26)
- GDI+ (31)
- GPU (62)
- Git (43)
- GitHub (36)
- HASYMO (23)
- HDD (48)
- HP (56)
- HTML (58)
- HTML5 (178)
- Hadoop (40)
- IBM (99)
- ICT (25)
- IDE (37)
- IE (30)
- IME (76)
- IPA (68)
- IoT (25)
- JFL (100)
- Java (227)
- JavaScript (441)
- Jenkins (271)
- KDDI (54)
- KINGSOFT (36)
- KORG (104)
- KRAFTWERK (39)
- Kindle (47)
- LED (59)
- LibreOffice (62)
- Linux (116)
- MFC (80)
- MIDI (50)
- NEC (71)
- NHK (137)
- NTT (39)
- ODF (23)
- OLE (26)
- OS (109)
- OSS (72)
- OSX (59)
- Objective-C (28)
- Office365 (24)
- Ooo (60)
- OpenCV (39)
- OpenGL (30)
- OpenXML (39)
- P2P (29)
- PC (428)
- PDF (95)
- PHP (37)
- PKI (305)
- POLYSICS (52)
- POP (31)
- Panasonic (26)
- Python (99)
- REST (23)
- RIA (110)
- RSA (42)
- RaspberryPi (37)
- Roland (56)
- SAKEROCK (38)
- SDP (54)
- SHARP (40)
- SNS (42)
- SONY (206)
- SQLite (25)
- SSD (96)
- SSL (39)
- STL (27)
- Scala (50)
- TOKYO SONATA (151)
- TV (288)
- ThinkPad (164)
- TypeScript (24)
- UI (146)
- UMPC (55)
- USB (132)
- USBメモリ (23)
- UX (31)
- VAIO (56)
- VBA (93)
- Vista (37)
- VisualStudio (281)
- VisualStudio 2010 (32)
- WPF (33)
- Windows (584)
- Windows 7 (144)
- Windows10 (46)
- Windows8 (121)
- Windows8.1 (40)
- WindowsPhone (24)
- WindowsRT (26)
- W杯 (25)
- XML (100)
- YAMAHA (48)
- YMO (206)
- YouTube (42)
- ad (30)
- adobe (109)
- amazon (132)
- app (225)
- apple (249)
- artist (25)
- au (84)
- audio (442)
- blade runner (25)
- blog (115)
- bug (89)
- chiptune (32)
- debug (56)
- dev (1209)
- dpz (132)
- eclipse (23)
- facebook (84)
- firefox (37)
- football (1517)
- free (73)
- game (499)
- google (506)
- graphic (301)
- hacking (32)
- hash (54)
- iMac (24)
- iOS (234)
- iPad (255)
- iPhone (375)
- iPod touch (50)
- iTunes (56)
- instagram (37)
- intel (121)
- internet (80)
- ipod (36)
- isai (24)
- justsystems (455)
- kaspersky (38)
- keyence (44)
- lenovo (198)
- mac (93)
- memory (65)
- metamoji (31)
- microsoft (714)
- mindmap (26)
- mixi (40)
- mobile (106)
- money (1290)
- ms office (126)
- music (26)
- netbook (97)
- network (23)
- node.js (33)
- note (128)
- office (500)
- office2013 (37)
- ototoy (31)
- perfume (344)
- perl (35)
- programming (537)
- rails (39)
- recorder (30)
- ruby (163)
- saas (73)
- salesforce (36)
- samsung (25)
- secuirty (38)
- security (1010)
- server (55)
- silverlight (70)
- social (139)
- software (170)
- storage (218)
- subversion (29)
- surface (32)
- synth (142)
- tablet (224)
- tech (518)
- techno (37)
- test (163)
- thumbnail (31)
- tips (226)
- tool (45)
- tools (106)
- toshiba (31)
- twitter (441)
- unicode (26)
- ustream (37)
- verisign (34)
- vocaloid (55)
- web (656)
- webAPI (30)
- webサービス (135)
- windowsAzure (93)
- xfy (45)
- xmas (314)
- yahoo (62)
- うどん (53)
- はてな (57)
- べつやくれい (30)
- まつもとゆきひろ (24)
- まとめ (660)
- みずほ銀行 (37)
- ゆらゆら帝国 (29)
- アジャイル (30)
- アニメ (286)
- アメリカ (175)
- アルゴリズム (55)
- イベント (158)
- イーバンク (36)
- エディタ (42)
- エネルギー (35)
- オイシックス (28)
- オバマ (24)
- オープンソース (42)
- カメラ (87)
- カーネーション (90)
- ガイナーレ鳥取 (31)
- ガスタンク (31)
- ガンダム (37)
- キングジム (24)
- キーボード (40)
- クックパッド (34)
- クラウド (461)
- クリーピー (43)
- グラフ (196)
- グルメ (160)
- ケータイ (178)
- コミック (272)
- コンサドーレ札幌 (48)
- コンパイラ (47)
- コーヒー (122)
- サイボウズ (66)
- サザエさん (26)
- ザスパ草津 (28)
- ジブリ (39)
- スケジューラ (49)
- スピーカー (46)
- スマホ (280)
- セレッソ大阪 (51)
- ソース管理 (30)
- チャットモンチー (94)
- デザイン (811)
- デジカメ (34)
- データ分析 (27)
- ニコ動 (82)
- ネタ (260)
- ネットバンク (30)
- ハイレゾ (69)
- バックアップ (40)
- バニラビーンズ (26)
- ビットコイン (29)
- ビューア (35)
- ピアノ (94)
- ファイル管理 (66)
- ファジアーノ岡山 (67)
- ファッション (95)
- フィッシュマンズ (42)
- フォトブック (112)
- フォント (72)
- ブラウザ (137)
- プレゼン (63)
- プロジェクト管理 (131)
- ポメラ (32)
- マーケティング (24)
- ムーンライダーズ (32)
- メディア (144)
- メモ (28)
- モバイル (111)
- ユーザビリティ (34)
- ラーメン (57)
- リリース情報 (1480)
- レシピ (143)
- ワープロ (38)
- ヴァンフォーレ甲府 (43)
- 一太郎 (94)
- 並列処理 (65)
- 中国 (79)
- 中田ヤスタカ (29)
- 事件 (461)
- 人工知能 (54)
- 人類史 (46)
- 仕事 (126)
- 仮想化 (77)
- 任天堂 (39)
- 企業 (38)
- 企画 (50)
- 会計 (27)
- 住宅ローン (40)
- 佐古 (24)
- 佐野元春 (29)
- 債券 (24)
- 共有 (69)
- 写真 (453)
- 出版 (76)
- 初音ミク (185)
- 労働 (71)
- 動画 (288)
- 北海道 (54)
- 印刷 (42)
- 原発 (93)
- 古書 (32)
- 可視化 (75)
- 地名 (28)
- 地図 (113)
- 地理 (35)
- 地震 (73)
- 坂本龍一 (258)
- 大阪 (78)
- 天皇杯 (50)
- 宅配 (67)
- 宇宙 (60)
- 宮崎駿 (49)
- 宮沢賢治 (75)
- 家電 (179)
- 富士通 (62)
- 将棋 (27)
- 小西康陽 (54)
- 小説 (31)
- 山下達郎 (45)
- 岡山 (354)
- 広告 (64)
- 建築 (100)
- 徳島 (903)
- 徳島ヴォルティス (909)
- 忌野清志郎 (235)
- 愛媛FC (44)
- 戦争 (176)
- 手書き (78)
- 技術 (345)
- 投資 (223)
- 投資信託 (134)
- 押井守 (28)
- 政治 (170)
- 教育 (165)
- 数学 (345)
- 文化 (35)
- 文学 (76)
- 文書作成 (33)
- 新聞 (36)
- 日本 (663)
- 日本代表 (42)
- 日本語 (268)
- 日本酒 (24)
- 映画 (1297)
- 暗号 (285)
- 書店 (37)
- 書籍 (3024)
- 東京 (27)
- 東日本大震災 (113)
- 柿谷曜一朗 (37)
- 栃木SC (27)
- 株式 (107)
- 植物工場 (135)
- 検索 (189)
- 業界 (443)
- 楽器 (477)
- 楽天 (45)
- 機械学習 (56)
- 正規表現 (24)
- 歴史 (1057)
- 死刑 (28)
- 民主党 (57)
- 水耕栽培 (58)
- 池田亮司 (31)
- 沖縄 (105)
- 津波 (43)
- 深層学習 (35)
- 漢字 (105)
- 災害 (29)
- 環境 (119)
- 生物学 (27)
- 画像処理 (147)
- 登山 (24)
- 矢野顕子 (31)
- 石野卓球 (31)
- 秋田 (27)
- 科学 (196)
- 納豆 (126)
- 細野晴臣 (110)
- 経営 (498)
- 翻訳 (53)
- 考古学 (28)
- 脆弱性 (66)
- 自動車 (335)
- 芸能 (132)
- 英語 (65)
- 萌え (50)
- 落合博満 (40)
- 著作権 (94)
- 行政 (48)
- 表計算 (116)
- 言語 (808)
- 訃報 (489)
- 計算機 (182)
- 認証 (58)
- 語源 (25)
- 讃岐うどん (55)
- 資源 (41)
- 起業 (49)
- 農業 (254)
- 通販 (72)
- 配信 (228)
- 酒 (59)
- 野球 (27)
- 野菜 (91)
- 鉄道 (157)
- 銀行 (140)
- 開発 (337)
- 開発環境 (39)
- 開発者 (34)
- 雑誌 (133)
- 電子工作 (46)
- 電子政府 (39)
- 電子書籍 (193)
- 電子署名 (31)
- 電気グルーヴ (74)
- 音声合成 (29)
- 音楽 (6271)
- 食 (887)
- 香川 (92)
- 高橋幸宏 (72)
- 鳥取 (24)
- 鶴見俊輔 (51)
- 黒沢清 (479)
- 音楽 (6271)
- 書籍 (3024)
- football (1517)
- リリース情報 (1480)
- 映画 (1297)
- money (1290)
- dev (1209)
- 歴史 (1057)
- security (1010)
- 徳島ヴォルティス (909)
関連タグで絞り込む (130)
- Aipo
- Android
- App-V
- ART
- ascii
- AUFS
- BlueOnyx
- CAD
- CentOS
- chef
- Chromebook
- ChromeOS
- citrix
- CoreOS
- CPU
- ctrix
- DaaS
- dev
- DevOps
- DOcker
- docker
- Docker
- DTI
- Ericom
- ESXi
- Excel
- ExpEther
- FlexSystem
- free
- GCP
- Go
- HTML5
- Hyper-V
- IBM
- iPad
- KitKat
- KVM
- Linux
- linux
- lmctfy
- MDOP
- microsoft
- minishowcase
- MirageOS
- mobile
- MountainLion
- NAS
- NEC
- network
- office
- Office
- Office2013
- openflow
- Oracle
- OS
- OSX
- PaaS
- Parrot
- PaulMaritz
- PC
- Python
- QNAP
- Ruby
- ruby
- SecureRDP
- security
- server
- ServersMan
- ServersMan@VPS
- SnowLeopard
- solaris
- SR-IOV
- storage
- Sun
- tech
- Tintri
- tips
- Ubuntu
- UI
- UnionFS
- UNIX
- UX
- Vagrant
- vagrant
- VDI
- VERDE
- Virtual PC
- VirtualBox
- virtualbox
- VirtualTop
- VMware
- VMWare
- VMWarePalyer
- vSphere
- vThrill
- windows
- Windows
- windows 7
- Windows 7
- Windows XP
- Windows10
- Windows8
- windows8
- WindowsServer
- WindowsXP
- Wine
- WMWAre
- WMWare
- Wnidows
- Xen
- XenServer
- XPMode
- ぷらら
- まえだこうへい
- イスラエル
- イーゲル
- クラウド
- コンテナ
- サーバー
- シンクライアント
- ストラトスフィア
- バックアップ
- リリース情報
- ワークステーション
- 仮想ドライブ
- 平初著
- 書籍
- 森若和雄
- 鶴野龍一郎
仮想化に関するakakitのブックマーク (79)
-
 akakit 2016/10/12
akakit 2016/10/12- バックアップ
- 仮想化
- NAS
- virtualbox
リンク -
-
インストール不要で複数OSが高速起動する東大の変態Mac (1/5)
東京大学では、学生や教職員が利用するPCや各種サービス一式を教育用計算機システム(ECCS)と呼んでおり、これを4年一度リプレースしています。2016年度はその更新時期にあたり、今回も入札の結果、クライアントマシンにはMacが選ばれました。東大では、2004年以来3期12年に渡ってMacが導入されてきましたが、、今回(ECCS2016)もこれが継承されたことで4年後の2020年3月(2019年度)までは引き続きMacが使われることになります。このあたりは、前回の取材記事で詳しく紹介しているので、文末に張ったリンクから関連記事をチェックしてください。 東大での取材で個人的にかなり気になったのが、もう変態といっていいほど特殊なMac。電源ボタンを押してもすんなりとOS Xが起動するわけではありません。Macハードウェア上で、UEFI(Unified Extensible Firmware In

-
米VMwareが踏み出した「脱vSphere」、狙いは「DevOps」
米VMwareがついに、「vSphere」の名前を冠さないサーバー向けの仮想化製品を発表した。コンテナベースの仮想化製品である「Photon Platform」だ。同社は「クラウドネイティブ」と呼ぶ新しいタイプのアプリケーションの開発者を取り込むと説明している。 Photon Platformは、同社が2015年8月30日から9月3日まで米サンフランシスコで開催した「VMworld 2015 US」で発表した。コンテナベースの仮想化とは仮想的なOS環境である「コンテナ」単位でサーバーを論理分割する手法だ。VMwareの既存のサーバー仮想化製品である「vSphere」は、「仮想マシン」によってサーバーを論理分割する。 今回の発表によってVMwareはコンテナベースの仮想化製品を2種類持つことになった。一つは既存のvSphereをコンテナに対応させた「vSphere Integrated Co

-
-
vSphere5.5 お試し環境構築 ~ESXiホスト~
仮想環境の基盤となる ESXi 5.5 を構築しました。 物理マシンを何台も用意できないので、Windows 7 上の VMware Player 6.0 の 仮想マシンで、ESXi 5.5 ホストを作成しました。 《物理環境》 ・CPU: Intel Xeon L3426 (1.87GHz, 4C/8T) ・メモリ: 16GB ・ネットワーク アダプター: Intel 82574L Gigabit Network Connection (ASUSTeK P7F-M WS オンボード NIC) ・OS: Windows 7 Professional 64-bit Service Pack 1 ・仮想化ソフトウェア: VMware Player 6.0.1 《ESXi 5.5 仮想マシンの作成》 ESXi 5.5 をインストールする仮想マシンを作成します。 ESXi 5.5 のシステム要件は

-
HugeDomains.com
Captcha security check virtxpert.com is for sale Please prove you're not a robot View Price Processing

-
Nested Virtualization - VirtualBox inside ESXi | Stuff I've Figured Out
This process describes how to configure an ESXi Linux guest so that the guest can then run VirtualBox and create a nested, 64 bit guest within the ESXi guest – Nested Virtualization. There is nothing special about the use of Linux as either the ESXi guest, or the nested guest. Any supported operating system should work at either nesting level. This includes nesting ESXi inside of ESXi, which appea
-
日本初「4K映像配信」のNTTぷららが“Solaris好き”な理由
日本初「4K映像配信」のNTTぷららが“Solaris好き”な理由:Solarisでの仮想化を進める配信プラットフォームの裏側(1/3 ページ) NTTぷららは2012年から同社の事業基盤である「配信プラットフォーム」をSolarisによる仮想化で取り組んでいる。社内はそもそもSolarisファンが多いようだが、破たん寸前の現場を救い、社内説得の材料にもなった“決め手”とは。 ISP事業者として1996年に設立されたNTTぷららは、インターネットの普及を背景にプロバイダ/ネットワーク事業を軸に、「IP電話」や「ひかりTV」など事業を相次ぎ立ち上げてきた日本の大手ISPの1つだ。2015年2月末現在、約300万の会員を抱える。 そんな同社が2012年から、事業の基盤である各種コンテンツの「配信プラットフォーム」でSolarisによる仮想化移行を継続的に進めている。日本オラクルが開催したイベン

-
一口で喉が渇くほど大量の粉が付いた「ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ」試食レビュー
2024年7月22日(月)、亀田製菓から「ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ」が登場しました。通常品から体積比で約40%まで小型化し、粉を存分に味わえるようにした品とのことで、どれほどの違いが生まれたのか確かめるべく通常品と食べ比べてみました。 ハッピーターン史上最小※1!? 『ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ』 7月22日(月)発売 約40%※2サイズなのに“あの粉”がたっぷりツイてる | 亀田製菓株式会社 https://www.kamedaseika.co.jp/news/20240719_21912/ 左が「ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ」です。右が通常の「96g ハッピーターン」。どちらも亀田製菓に提供してもらいました。 「ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ」の原材料(左)と「96g ハッピーターン」の原材料(右)は以下の通り。「ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ

-
-
ChromebookでExcelが使える、Ericom“HTML5レシーバー”の実力とは?
関連キーワード Chromebook | HTML5 | Windows | Citrix XenDesktop | Excel | iOS | VDI(Virtual Desktop Infrastructure) | Android | デスクトップ仮想化 | アプリケーション仮想化 イスラエルのEricom Softwareが開発するデスクトップ仮想化製品が勢いを増している。2012年2月に日本で販売を開始し、TechTargetジャパンが同年8月に取材した当時、導入実績はまだ5社だった。ところが2014年8月現在、国内での導入実績は120社を超えたという。この勢いの背景には、商品戦略のユニークさや、価格の安さ(参考:費用は従来の2分の1以下、イスラエル発のハイブリッド型デスクトップ仮想化製品)、導入の容易さなどがある。 関連記事 費用は従来の2分の1以下、イスラエル発のハイブリッド

-
Vagrant で Windows もゲストOSに - Qiita
基本的に Vagrant で作ったり壊したりできる Windows 環境を手に入れるまでの手順 - てっく煮ブログ の情報通りにやれば構築できます。 ただ、いくつか追加で手順が必要です。 試してみた環境は以下の通り。 ホストOS:Windows 8.1 Pro(x64) ゲストOS:Windows 7 Professional with SP1(x86) ゲストOS:Windows 8.1 Pro(x86) 構築したときの作業ログは こちら 環境構築 せっかくなので必要なソフトは Chocolatey でインストールしてみましょう。 chocolatey のインストールは管理者権限でコマンドプロンプトを起動して以下のコマンドを実行するだけ。 インストール完了後続けて cinst するとエラーになることがあるので、コマンドプロンプトは一旦終了させておきましょう。 @powershell -N

-
-
今からでも間に合うDockerの基礎。コンテナとは何か、Dockerfileとは何か。Docker Meetup Tokyo #2
今からでも間に合うDockerの基礎。コンテナとは何か、Dockerfileとは何か。Docker Meetup Tokyo #2 コンテナ型仮想化の技術として注目されているDockerの勉強会「Docker Meetup Tokyo #2」が4月11日にグーグル東京オフィスで開催されました。 この勉強会には定員100名のところへ400名を超える申し込みがあり、参加できなかった方も多かったと思います。本記事では、最初のセッションとして行われた森和之氏による「今からでも間に合うDocker基礎+Docker 0.9概要」をダイジェストで紹介しましょう。 参考記事 2013年のDocker登場から現在(2018年)までを振り返り、その次の段階を展望した記事もご参照ください。 Dockerコンテナ時代の第一章の終わり、そして第二章の展望など 今からでも間に合うDocker基礎 株式会社トップゲー

-
すでにGoogleは全部のソフトウェアをコンテナに乗せており、毎週20億個ものコンテナを起動している
Google Cloud Platform担当のシニアスタッフソフトウェアエンジニア Joe Beda氏が先週公開したスライド「Containers At Scale」は、「Everything at Google runs in a container」(Googleでは全部をコンテナで実行している)と説明するページがあります。Everythingがわざわざ太字で強調されています。 つまり私たちが利用するGoogleのすべてのサービスも、Googleの社内で使われているツールもすべて、すでにGoogleではDockerのようなコンテナ型仮想化技術の上で実行されているということのようです。 「We start over 2billion containers per week.」(私たちは毎週20億個以上のコンテナを起動している)とも書いてあり、Google内部ではすさまじい数のコンテナが

-
ついに1.0がリリース! Dockerのインストールと主なコマンドの使い方
連載目次 本日、Docker 1.0がリリースされました。開発元であるDocker社は公式ブログで、「エンタープライズでの活用に耐え得るものになった」と述べています。また、これと同時に企業向けサポートやトレーニング、コンサルティングも開始すると発表(参考:公式ブログ)。今後、企業での活用も増えることが予想されます。 1.0のリリースに合わせて、Dockerの名称変更がアナウンスされました。前回の「アプリ開発者もインフラ管理者も知っておきたいDockerの基礎知識」で概要、特徴や動作環境を説明したDockerの本体となるソフトウェアは、今後「Docker Engine」と呼ばれることになります。これにDocker社が提供するWebサービスである「Docker Hub」、APIを介して連携するサードパーティのソフトウェア/サービスによるエコシステムを含めたDockerによるプラットフォーム全体
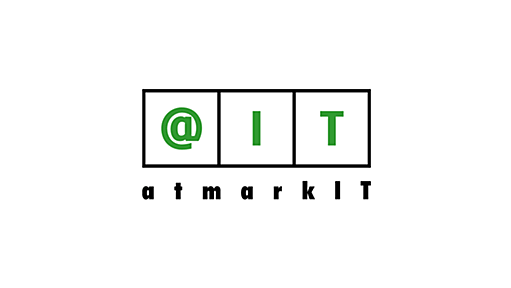
-
vagrant ユーザよ、その VM は安全なのか? (veewee のすゝめ) - Hack like a rolling stone
タイトルは単なる煽りなので、気にせず先に進みましょう。 最近 chef や puppet、fabric などの自動化ツールの流行を受けて、 その実験環境として vagrant もかなり使われているようです。 vagrant は virtualbox の CLI ラッパーとして非常に良くできており、実験環境を構築するのに非常に便利なツールです*1。 そして、多くの vagrant 紹介記事が書かれているのですが、そこで気になったことがひとつあります。 それは vagrant を利用する際に vagrantbox.es に用意されている VM を利用しようと紹介されていることです。 vagrantbox.es は各々が作った VM イメージ(通称 box)を持ち寄って共有しあうサイトです。 新しくリリースされた distro. のイメージや、ツール(chef, puppet, guest ad
-
5分で分かるDockerのキホン
アジャイル開発に取り組むチーム向けのコーチングや、技術顧問、認定スクラムマスター研修などの各種トレーニングを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください(初回相談無料) 全国100万人のImmutable Infrastructure職人のみなさんこんにちは。 もう誰も彼もがDockerなので、あんまりブログに書こうという気にもならなかったのですが、知り合いからリクエストを貰ったので、5分くらいで分かるようにかいつまんで概略を説明します。 Dockerとは詳しくは本家サイト見ればだいたい分かる。仮想化技術コンテナ単位でパッケージングVirtualBoxとかと違って高速、オーバーヘッドが少ない。chrootに近い。LXCには依存しなくなっているコンテナごとにIDが振られるコンテナは差分保存なのでロールバックも簡単一回作ればどこでも動く。JavaっぽいDockerfileでコンテナを作成するDo

-
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く








