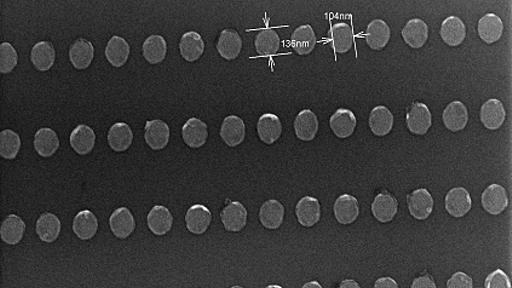東日本大震災は地方の医療過疎の深刻さを浮き彫りにした。寝たきり患者や、病院が被災して治療を受けられない患者をケアするには、医師自らが患者の元に向かうことが必要。また、津波で多くの医療情報が流されたことは、情報保存のあり方を見直すきっかけとなった。 震災で浮き彫りになった 訪問診療体制の不備 世界でもいち早く高齢化が進み、医療・介護ニーズが高まり続けている日本。しかし一方で、医師や看護師などの人材は慢性的に不足し、地方財政のひっ迫による公立病院の閉鎖など、医療サービスの質と量の低下が大きな社会問題となっている。 寝たきりや慢性疾患に苦しむ患者は増え続けているのに、「近くに病院がない」「満足な診断や治療が受けられない」という状況が年々深刻化しているのだ。 2011年3月11日に起きた東日本大震災は、そうした日本の医療の問題点をあらためて浮き彫りにした。 甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の沿岸