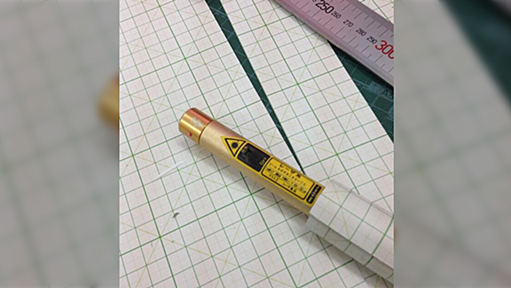タグ
- すべて
- .NET (8)
- 2ch (15)
- 2chまとめ (10)
- 4Gamer (13)
- A.I (12)
- AMAZON (34)
- AMD (13)
- API (34)
- AR (8)
- ARM (18)
- ASCII (8)
- AWS (14)
- Advent Calendar (12)
- Agile (85)
- Android (149)
- Android App (18)
- Android Tablet (15)
- Apple (40)
- Architecture (14)
- BDD (12)
- BI (9)
- BSDライセンス (12)
- BitCoin (8)
- Blog (53)
- Bluetooth (11)
- Bug (11)
- C++ (17)
- CI (20)
- CMS (8)
- CPU (13)
- CSS (29)
- CUI (8)
- Chef (12)
- Civilization (10)
- Cloud (11)
- CodeIQ (8)
- Coding (15)
- Copyright (8)
- CryptCurrency (8)
- C言語 (16)
- DB (19)
- DIY (10)
- DRM (23)
- DevOps (35)
- Docker (29)
- Dropbox (14)
- Editor (11)
- English (28)
- FSF (13)
- Facebook (28)
- Firefox (20)
- Firefox OS (10)
- FizzBuzz (17)
- Framework (13)
- GIGAZINE (13)
- GPL (23)
- GPU (13)
- GTD (11)
- GUI (9)
- Gadget (60)
- Geek (76)
- Git (94)
- GitHub (133)
- Google (91)
- HP (8)
- HTML (12)
- HTML5 (27)
- Hacker (26)
- Hardware (8)
- Huffington Post (8)
- IT (52)
- ITMedia (22)
- ITPro (9)
- ITエンジニア (60)
- IT企業 (8)
- IT技術 (9)
- IT業界 (25)
- IaC (8)
- Incident (13)
- InfoQ (41)
- Intel (13)
- IoT (21)
- JAXA (9)
- Java (54)
- JavaScipt (14)
- JavaScript (104)
- JavaScript library (8)
- KickStarter (9)
- Kindle (12)
- Kindle Fire (9)
- LLVM (15)
- LifeHack (89)
- Linux (115)
- MAKE (47)
- MAKERS (10)
- MAKERムーブメント (8)
- MIT (9)
- MIT License (12)
- MITライセンス (18)
- Mac (16)
- Management (13)
- Mercurial (8)
- Microsoft (15)
- Mozilla (14)
- MySQL (18)
- NAS (10)
- NHK (59)
- News (65)
- Node.JS (23)
- OAuth (18)
- OOP (40)
- OSS (144)
- Online Strage Service (9)
- OpenID (19)
- Opensource (9)
- P2P (16)
- PC (28)
- PC Watch (9)
- PCWatch (11)
- PDF (26)
- PHP (79)
- PM (8)
- POSTD (23)
- PR (11)
- Palm (9)
- Perl (13)
- Press Enter■ (12)
- Progarmming (20)
- Programing (26)
- Programming (258)
- ProjectManagement (45)
- PublicKey (25)
- Python (30)
- Qiita (34)
- REST (15)
- RSS (9)
- Rails (11)
- Raspberry Pi (16)
- Ruby (45)
- R不動産 (64)
- SCM (49)
- SCRUM (13)
- SE (10)
- SEO (9)
- SF (45)
- SF小説 (8)
- SIer (125)
- SNS (15)
- SONY (26)
- SQL (16)
- Scala (8)
- Science (23)
- Security (72)
- Slide (38)
- SlideShare (40)
- Smartphone (29)
- Sourceforge (12)
- Startup (116)
- Steam (11)
- Subversion (19)
- TDD (59)
- TED (11)
- TRPG (9)
- TechBlog (10)
- TechCrunch (27)
- Techcrunch Japan (11)
- Technology (8)
- Testing (15)
- TiDD (8)
- Togetter (199)
- Twiiter (12)
- Twitter (256)
- UI (35)
- UNIX (12)
- UX (14)
- UnitTest (34)
- VPS (10)
- Vagrant (14)
- WAF (16)
- Web (40)
- Web API (9)
- WebAPI (11)
- WebOS (8)
- WebService (21)
- Webアプリケーション (19)
- Webサイト (11)
- Webサーバ (10)
- Webサービス (245)
- Webデザイン (47)
- Web開発 (46)
- Wi-Fi (17)
- Windows (83)
- WordPress (8)
- XP (32)
- Y Combinator (15)
- Youtube (12)
- amazon ec2 (8)
- bash (24)
- book (12)
- bookscan (11)
- cli (10)
- coworking (8)
- debug (8)
- design (78)
- diff (10)
- ebook (36)
- economics (8)
- education (10)
- epub (19)
- event (15)
- font (13)
- fonts (9)
- free (8)
- game (8)
- go (9)
- hash (8)
- iOS (20)
- iPad (14)
- iPhone (52)
- license (8)
- lifehacker (12)
- lifehacks (9)
- note (12)
- privacy (10)
- programmer (63)
- programming Language (56)
- rust (9)
- scheme (12)
- sharehouse (11)
- shell (10)
- shell script (9)
- textbook (9)
- tips (32)
- tool (12)
- webdesign (11)
- zenn (18)
- あとで読む (78)
- うつ (12)
- はてな (16)
- はてなブックマーク (30)
- はてなブログ (10)
- はてブ (92)
- まとめ (81)
- アイデア (26)
- アジャイル (73)
- アニメ (32)
- アフィリエイト (13)
- アベノミクス (14)
- アメリカ (20)
- アメリカ社会 (11)
- アルゴリズム (23)
- イノベーション (46)
- イノベーションのジレ (10)
- イベント (17)
- イラスト (15)
- インタビュー (24)
- インターネット (21)
- インフラ (13)
- エッセイ (9)
- エロゲ (16)
- エンジニア (29)
- オタク (22)
- オブジェクト指向 (39)
- オープンソース (94)
- カスタマイズ (15)
- ガジェット (44)
- キャリア (17)
- ギークハウス (13)
- クラウド (17)
- クリエイター (10)
- ゲーマー (9)
- ゲーム (37)
- ゲームデザイン (17)
- ゲーム業界 (9)
- コミュニケーション (35)
- コミュニティ (12)
- コメント (19)
- コメント欄 (9)
- コンテンツ (10)
- コーディング規約 (12)
- サイエンス (13)
- サーバ管理 (20)
- サービス (10)
- シェアオフィス (9)
- シェアハウス (14)
- システム開発 (53)
- シリコンバレイ (9)
- シリコンバレー (11)
- ジェンダー (12)
- スキルアップ (15)
- スタートアップ (66)
- スマフォ (12)
- スマホ (11)
- スマートフォン (51)
- セキュリティ (64)
- ソシャゲ (13)
- ソフトウェア (13)
- ソフトウェア工学 (27)
- ソフトウェア構成管理 (9)
- ソフトウェア開発 (123)
- ソーシャルゲーム (36)
- ソーシャルメディア (11)
- ダイエット (14)
- チュートリアル (9)
- ツール (48)
- テスト (11)
- テンプレート (15)
- デザイン (56)
- デザインパターン (17)
- デスマーチ (15)
- データベース (15)
- トランプ (12)
- ドキュメント (10)
- ニコニコ動画 (26)
- ニコニコ技術部 (15)
- ニュース (27)
- ネタ (123)
- ネトウヨ (31)
- ノマド (19)
- ハッカー (9)
- バイアス (9)
- バージョン管理 (19)
- パスワード (10)
- パフォーマンス (10)
- ビジネス (58)
- ビジネスモデル (16)
- ファンタジー (10)
- フォント (11)
- フリーウェア (20)
- フリーランス (25)
- フレームワーク (24)
- ブラック企業 (19)
- プライバシー (13)
- プレゼン (12)
- プログラマ (22)
- プログラマー (24)
- プログラミング (140)
- プログラミング言語 (17)
- プロジェクトマネジメ (10)
- プロジェクトマネジメント (16)
- ヘイトスピーチ (14)
- ベンチャー (34)
- ボードゲーム (13)
- マスコミ (9)
- マネジメント (29)
- マネタイズ (14)
- マネー (10)
- マーケティング (25)
- メディア (21)
- メディアリテラシー (9)
- メモ (12)
- メンタルヘルス (13)
- モバイル (10)
- ユーザビリティ (33)
- ライセンス (9)
- ライトノベル (13)
- ライフハック (17)
- ライブラリ (14)
- ラノベ (19)
- リテラシー (28)
- リファクタリング (22)
- リーダーシップ (9)
- レシピ (14)
- ロボット (14)
- 不動産 (25)
- 不況 (21)
- 世界経済 (13)
- 中国 (21)
- 仕事 (37)
- 仕事術 (20)
- 仮想マシン (11)
- 仮想化 (12)
- 企画 (10)
- 会社 (9)
- 会計 (11)
- 位置情報 (15)
- 個人情報 (10)
- 健康 (19)
- 公衆無線LAN (14)
- 写経 (10)
- 出版 (14)
- 出版業界 (13)
- 労働問題 (13)
- 勉強 (18)
- 勉強会 (31)
- 原発 (22)
- 同人誌 (9)
- 図書館 (9)
- 国会 (16)
- 増田 (62)
- 外交 (29)
- 契約 (10)
- 学習 (13)
- 安倍政権 (22)
- 安倍晋三 (10)
- 安部政権 (70)
- 就職 (16)
- 山形浩生 (9)
- 差別 (23)
- 心理学 (11)
- 戦略 (36)
- 技術 (24)
- 技術書 (21)
- 技術的負債 (12)
- 投資 (23)
- 携帯電話 (9)
- 政治 (111)
- 政策 (9)
- 教科書 (19)
- 教育 (25)
- 数学 (25)
- 文具 (17)
- 文化 (12)
- 新型肺炎 (10)
- 新技術 (24)
- 日本 (18)
- 日本政治 (15)
- 日本社会 (303)
- 日本経済 (104)
- 日本語 (10)
- 書店 (12)
- 本 (22)
- 東京R (30)
- 格差社会 (16)
- 検索エンジン (10)
- 楽天 (9)
- 横浜 (13)
- 歴史 (33)
- 民主主義 (16)
- 炎上 (20)
- 無線LAN (10)
- 特許 (13)
- 生活保護 (20)
- 発達障害 (9)
- 発音 (11)
- 知的財産 (9)
- 社会 (24)
- 社会保障 (15)
- 社会学 (10)
- 科学 (19)
- 科学技術 (11)
- 移民 (10)
- 素材 (13)
- 経営 (31)
- 経済 (52)
- 経済学 (93)
- 経済政策 (9)
- 統計 (12)
- 考え方 (20)
- 考具 (11)
- 考察 (10)
- 脆弱性 (12)
- 自民党 (29)
- 自炊 (19)
- 艦これ (35)
- 英会話 (13)
- 英語 (79)
- 萌え (12)
- 著作権 (45)
- 行政 (10)
- 表現の自由 (20)
- 規制 (15)
- 訃報 (10)
- 設計 (15)
- 読み物 (13)
- 読書 (16)
- 論考 (12)
- 議論 (10)
- 貧困 (11)
- 賃貸 (36)
- 起業 (71)
- 転職 (20)
- 選挙 (13)
- 開発 (11)
- 開発プロセス (12)
- 開発環境 (13)
- 関数型言語 (9)
- 障害者 (21)
- 雇用問題 (11)
- 電子書籍 (120)
- 電子書籍ストア (12)
- 高速化 (12)
- 日本社会 (303)
- Programming (258)
- Twitter (256)
- Webサービス (245)
- Togetter (199)
- Android (149)
- OSS (144)
- プログラミング (140)
- GitHub (133)
- SIer (125)
関連タグで絞り込む (68)
- AgTiO2
- DeathValley
- ES細胞
- FAQ
- ITMedia
- JST
- LED
- Math
- science
- SF
- SHARP
- Space
- STAP細胞
- Technology
- technology
- Togetter
- Twiiter
- さまよう石
- アジモフ
- インタビュー
- オカルト
- グラフェン
- コミュニケーション
- ソーラーパネル
- ダイエット
- ナノテク
- ノーベル賞
- リセット細胞
- レーザー
- レーザーポインタ
- ロボット三原則
- ロボット工学
- 中村修二
- 伊豆大島
- 充電池
- 光合成
- 光触媒
- 化学
- 可視光
- 可視光通信
- 地球型惑星
- 地質学
- 太陽光
- 実験
- 技術
- 捏造問題
- 摩擦
- 数学
- 方法論
- 日本社会
- 植物シグナリング
- 植物型知能
- 死の谷
- 気象学
- 火山
- 物性
- 物理
- 環境
- 生命
- 生態模倣技術
- 確率・統計
- 科学
- 科学技術振興機構
- 統計学
- 考察
- 自然科学
- 触媒
- 読み物
Scienceに関するatsushifxのブックマーク (23)
-
 atsushifx 2024/03/03ざっと見だけど、都市サイズの大きさのソーラー発電所があれば、砂漠に雨を降らせられるらしい。ソーラー発電所は周囲より暑くなるため、上昇気流を起こすらしい。日本の首都圏のゲリラ豪雨みたいなもの?
atsushifx 2024/03/03ざっと見だけど、都市サイズの大きさのソーラー発電所があれば、砂漠に雨を降らせられるらしい。ソーラー発電所は周囲より暑くなるため、上昇気流を起こすらしい。日本の首都圏のゲリラ豪雨みたいなもの?- Science
- ソーラーパネル
- 気象学
リンク -
政府 ムーンショット型の研究を支援へ | NHKニュース
科学の分野での日本の国際競争力を高めるため、政府は、実現すれば社会に与える影響が大きいプロジェクトを、ことしから集中的に支援する方針です。 テーマとしては、研究が長期間にわたり、少子高齢化や地球温暖化、それに、大規模災害など社会問題の解決につながるものが想定されています。 そして、文部科学省が所管する科学技術振興機構と、経済産業省が所管するNEDO=新エネルギー・産業技術総合開発機構に基金を創設し、2つの機構が、大学や民間企業などからプロジェクトを公募する方針です。 今年度の第2次補正予算案と新年度予算案には、必要な経費として、合わせて1000億円余りが計上されています。 政府は、ことし秋には制度を始めたい考えで、今後、有識者会議を設けて具体的なテーマを決める方針です。

 atsushifx 2019/01/20DARPAは植物学にも目を向けている https://twitter.com/keikoutorii/status/1079843814221574144 ので、比較する方が失礼って感じがする
atsushifx 2019/01/20DARPAは植物学にも目を向けている https://twitter.com/keikoutorii/status/1079843814221574144 ので、比較する方が失礼って感じがする -
火星に「液体の水」初確認=地下湖存在、欧州探査機が探知-米誌:時事ドットコム
火星に「液体の水」初確認=地下湖存在、欧州探査機が探知-米誌 人工衛星 米航空宇宙局(NASA)の無人探査車「キュリオシティ」が撮影した火星表面の画像=2013年12月(AFP時事) 【ワシントン時事】米科学誌サイエンス(電子版)は25日、火星の地下深くに「湖」があることが分かったと報じた。火星で液体の水の存在が確認されたのは初めてという。 〔写真特集〕「超常」現象ショー~地獄の門、UFO、聖骸布~ 欧州宇宙機関(ESA)が打ち上げた探査機「マーズ・エクスプレス」が、火星周回軌道上からレーダーを使って探知した。湖は火星南極の地下にあるが、低温で塩分が多いとみられ、生命が存在する可能性は低いとされる。 火星は今より大気が濃く、暖かかった数十億年前、地表に液体の水が流れていたと考えられている。しかし、現在は大気が薄くなって気圧が下がったため、地表の水は蒸発し、極地などに氷の状態で存在しているだ

-
「花粉を水に変えるマスク」根拠論文を批判したら医学部教授から集団訴訟と脅された「騒動」 - 左巻健男&理科の探検’s blog
ぼくはスラップ訴訟に敏感だ。なぜならジャーナリストで大学客員教授という人(DND出口俊一氏)から仕掛けられて闘った経験があるからだ。当初、なぜ出口氏がEM菌への批判者に異常とも見える攻撃をするのかは謎だった。後で出口氏が「EM研究機構顧問」だったことがわかった。 この裁判はぼくの完全勝利で終わったが、経緯は、『ドキュメント スラップ名誉毀損裁判 EM菌擁護者と批判者の闘い』 左巻健男著 にまとめておいた。 A5 表紙込20ページ 200円(税抜) http://ankokudan.org/d/d.htm?detail099-detailread-j.html さて、そんなぼくのところに、五本木クリニック院長桑満おさむさんから、ハイドロ銀チタンのマスクを「研究中と称する信州大学の医学部の教授に「ブログを削除しろ、じゃないと次のステージに行くよ」とメッセージが来ています。」と連絡があった。
-
炭水化物は体に悪い?脂質をたくさん摂るほど健康に良い?:2017年世界一に選ばれた科学論文を解説 - Unboundedly
久しぶりのブログ更新です。今回は、「炭水化物を摂取すると死亡率があがる」「脂肪はたくさん摂っても死亡率に影響がない」ことを示したとして2017年世界中で話題になった以下の論文について、論文自体の問題点やメディアで取り上げられている内容の誤りについてまとめます。 Dehghan, Mahshid, et al. "Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study." The Lancet 390.10107 (2017): 2050-2062. http://www.thelancet.com/journals/lancet/a

-
機構報 第1168号:グラフェンによる超潤滑現象の観察とメカニズム解明に成功
ポイント 物質間の摩擦が非常に低い“超潤滑現象”を炭素薄膜(グラフェン)と金を用いて世界で初めて観察し、そのメカニズムを解明した。 グラフェンを表面にコーティングすることにより、機械部品同士の摩擦を低く抑えられる技術の実現が期待できる。 ナノ領域で部品間の摩擦力が極端に増すナノマシーンへの応用が期待される。 JST 戦略的創造研究推進事業において、バーゼル大学 物理学科の川井 茂樹 シニアサイエンティストは、炭素原子一層の薄膜であるグラフェンナノリボン(帯状構造)と金の表面間に生ずる超潤滑現象の観察ならびにそのメカニズム解明に世界で初めて成功しました。 通常、材料間の接触面ではそれぞれの材料を構成する原子が互いに吸着する方向に動いて位置合わせを行い、それが摩擦力の増加となります。しかし、炭素薄膜は構成している炭素原子間の結合力が非常に高く、原子は殆ど動きません。このため接触面での原子の位置
-
青色LEDノーベル賞受賞をお祝いして、中村修二さんの95年の記事を再掲します(その1) くねくね科学探検日記
昨日発表された、今年のノーベル物理学賞は、青色LEDの発明に対してで、名城大学の赤崎勇教授、名古屋大学の天野浩教授、およびカリフォルニア大学の中村修二教授の三名に贈られることとなった。 個人的には青色LED は応用的な発明で、ノーベル賞の対象にはならないと思っていたので、結構意外だったんだけど(取るとしても赤崎さんだけかなあと)、オレの予想を覆してお三方が受賞されたことは本当に喜ばしい。 どうも、高輝度の青色LEDの発明で作れるようになった白色LEDが、アフリカなど電力網のまだ行き届いていない場所でも使える明か理として普及してきたことが、今回の受賞の一つの理由になっているらしい。その波及効果の大きさはやっぱり凄いものなんだね。 で、まあ、オレは95年の夏前に、中村修二さんの取材をして当時連載していたログインに記事を書いたんだよね。日経産業新聞かなんかで青色LEDがはできたってのを読ん
-
-
ES細胞やiPS細胞以上のヒト多能性幹細胞「リセット細胞」 高島康弘研究員らが作製に成功
ヒト幹細胞研究で新しい突破口が開けた。胚性幹細胞(ES細胞)や人工多能性幹細胞(iPS細胞)など既存のヒト多能性幹細胞に2 つの遺伝子を発現させて、より発生初期に近いナイーブ型多能性幹細胞を作製するのに、英ケンブリッジ大学の高島康弘研究員とオースチン・スミス教授らが初めて成功した。ヒトの生命の発生初期に迫る発見である。安定して培養できるため、再生医療の有用なツールにもなりそうだ。欧州バイオインフォマティクス研究所のポール・ベルトーネ博士、英ベイブラハム研究所のウルフ・レイク教授との共同研究で、9月11日の米科学誌セルに発表した。 多能性幹細胞は私たちの体を構成するあらゆる細胞や組織になる能力を持つが、ナイーブ型とプライム型に大別される。より未分化な状態のナイーブ型は、マウスでキメラ(同一個体内に遺伝的に異なる細胞が混ざること)を作ることもでき、遺伝子改変マウス作製に用いられている。これに対

-
「死の谷」で人知れず移動する「さまよう岩」現象の謎がついに解明される
By Trey Ratcliff アメリカ・カリフォルニア州のデスバレー国立公園では、100kg以上もある巨大な岩が人知れずずるずると移動するという不可思議な現象が起こっています。これまで岩が動く瞬間を目撃した人はいなかったのですが、2年間かけてこの「さまよう岩」を研究したチームによって、岩が動くメカニズムが解明されました。 PLOS ONE: Sliding Rocks on Racetrack Playa, Death Valley National Park: First Observation of Rocks in Motion http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0105948 岩が動く瞬間をカメラで捉えた映像や、岩が動く理由を説明しているムービーは以下から見ることができます。 H

-
可視光でアンモニア人工光合成に、北大研究グループが成功
空気中の窒素を固定して、アンモニアを可視光で合成する新しい人工光合成に、北海道大学電子科学研究所の三澤弘明教授と上野貢生(こうせい)准教授、押切友也助教らの研究グループが成功した。可視光を含む幅広い波長域の光エネルギーを電気エネルギーに変換できる酸化物半導体基板に金ナノ微粒子を配置した光電極で、この新しい人工光合成を実現した。 アンモニアは水素よりエネルギー密度が高く、将来のエネルギーキャリアとして注目されており、アンモニアの人工光合成には大きな可能性がある。7月 17 日付のドイツ化学会誌Angewandte Chemie International Edition のオンライン版に発表した。同じ研究グループは金微粒子などで水の光分解、水素と酸素の発生にも成功し、7月2日付の同誌に発表した。いずれも、可視光による人工光合成に道を開く重要な成果として注目されている。 半導体の光触媒として現

-
超高速光ケーブルの素材はなんと「空気」
夢が広がります。 データを光速に転送したければ光が一番。光より速いものはないので当然ですよね。けれど環境によっては従来の光ファイバーケーブルが敷設できない場所もあります。そこで科学者たちが考えた新しいアイデアとは、強力なレーザーを使用して空気の密度を変えることで「空気の筒」を作り出しその筒を通して光の信号を伝達するというもの。まさにエア光ケーブル! メリーランド大学のHoward Milchberg博士とそのチームは、強力なレーザーを空気中に瞬間的に発するとフィラメントと呼ばれる細いビームが生成されることを発見しました。このフィラメントは通過する際に周囲の空気の温度を上昇させます。温められた空気は膨張するので、これにより低密度の空気の「管」が作られます。この空気の管は影響を受けていない周囲の空気に比べ屈折率が低くなります。鏡張りのチューブをイメージしてもらえると分かりやすいかもしれません(
-
「ゴジラ級」の地球型惑星、560光年先に発見 (AFP=時事) - Yahoo!ニュース
【AFP=時事】これまでに確認された地球型惑星の中でも「ゴジラ級」の大きさを持つ惑星が新たに見つかった。560光年離れた恒星の周りを公転する巨大な岩石惑星で、宇宙の起源についての理解が変わる可能性もあるという。 生命の可能性「スーパーアース」、銀河系に数百億個か ESO推定 米ボストン(Boston)で開かれた米国天文学会(American Astronomical Society、AAS)の会議で発表を行った専門家らによると、米航空宇宙局(NASA)のケプラー(Kepler)宇宙望遠鏡で発見されたこの「メガアース」は、質量が地球の17倍、直径は約2万9000キロで地球の2.3倍。「ケプラー10c(Kepler-10c)」と名付けられた。 これまでは、岩石惑星がここまで大きくなることは不可能とされてきた。サイズが大きくなると、引き寄せられる水素ガスの量も増え、木星のような巨大ガス惑星に

-
サルでもわかる小保方博士の論文FAQ「小保方論文の真贋について」 - 科学記事解説用
【この文章の目的と想定される読者の対象】 こんにちは。私は医学分野の博士課程の院生です。毎日小保方博士ネタがホッテントリにちらちら見えます。普段はあまり科学分野あるいは再生医療に携わってるわけではないけど気になって読んでる方も結構いる様子、とブコメを読んで思いました。せっかく科学に興味を持って頂く良い機会ですから、そういう方向けに、たぶんこういう疑問を抱いているのじゃないかな・・・というのを推測して、FAQを書いてみました。院生が勉強をも兼ねて書いていますので、詳しい方も容赦なく突っ込んでくださるとありがたいです。 想定されるFAQはいくつもあるのですが、とりあえず今一番ホットなポイントである「小保方論文の真贋について」のFAQを書いてみました。 【この文章の限界】 勿論タイトルの「サル」は釣りですが、それでもなるべく表現を簡単にしてあります。そのため用語が不正確になっているところがありま
-
家電が驚くべき進化を遂げる! シャープの「生物模倣技術」とは?
家電が驚くべき進化を遂げる! シャープの「生物模倣技術」とは?:滝田勝紀の「白物家電、スゴイ技術」(1/3 ページ) 「生物模倣技術」という言葉をご存知だろうか? 自然界に生息する生き物の機能や仕組みを参考にして、新たな技術の開発や性能向上に結びつける技術のことだ。そしてここ数年、「生物模倣技術」を家電分野に積極的に取り入れているのがシャープである。 シャープは、「イルカ」「アホウドリ」「トンボ」「ネコ」「アサギマダラ(蝶)」といった動物や昆虫を参考にした製品を送り出している。今回は、そのキーパーソンであるシャープ、ネイチャーテクノロジー推進プロジェクトチームのチーフ、大塚雅生氏に「生物模倣技術」を取り入れるきっかけから成果まで詳しく聞いた。 シャープの研究員である大塚雅生氏は、元々専門分野であった「航空工学」を使って、エアコンのファンの送風効率をそれまでの倍以上に引き上げた人物として、シ

-
植物に知能はあるか ―― そもそも知能ってなに? - HONZ
『ニューヨーカー』誌の2013年12月23日&30日合併号に、マイケル・ポーランが「植物に知能はあるか」というテーマで力作レポートを寄せていました。ポーランは、カリフォルニア大学バークレー校でジャーナリズムのジェームズ・ナイト教授職にあり、本を書けば毎度ニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト入りを果たすという売れっ子ノンフィクション作家でもあります。それに加えて、彼はアマチュアの料理人でもあるんですよね。最新作”Cooked”については、本稿の最後でさらっとご紹介いたしますが、なにせ売れっ子なので、タイトルよりも著者の名前の方が目立つカバーとなっております(^^ゞ さて「植物に知能はあるか?」と聞いて、「それってトンデモ?」と思った方もいらっしゃることでしょう。そう思われるのも無理はありません。なにしろ、「植物には感情がある」とか「植物は人間と心を通わせることができる」といった話には、

-
-
-
-
理系の議論と文系の議論 - 脱社畜ブログ
理系と文系の本当の違い http://anond.hatelabo.jp/20130308230002 そういえば、僕は文系学問と理系学問について、両方ともそれなりに勉強したことがある。そこで今日は、双方を勉強して僕が感じた「理系と文系の違い」について書いてみようと思う。 まず、自分のバックグラウンドの話からすると、僕は工学部出身で、今の仕事もざっくり言えば「エンジニア」というやつなので、これだけ見るとコテコテの理系人間に思える。 ただ、僕は昔から理系、理系と言われるのがものすごく嫌で、その反骨心が大学入学後抑えきれない大きさまで膨れ上がったため、2年半ほど司法試験の勉強をしていたことがある。当時はよく工学部の講義をサボって図書館で法律の基本書や予備校本を読んだりしていた。法学部の講義や自主ゼミのようなものにも出た。予備校にも通った。当時は本気で受かろうとして真剣に勉強していたので、勉強を

公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く