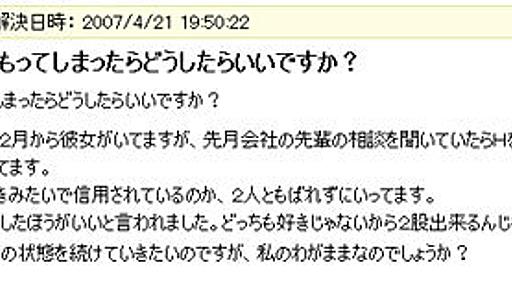店員に「ありがとう」と言う人が大嫌い。おかしいのでしょうか。。。 さっき別の方が、店員に「ご馳走様」「ありがとう」と言う人を見ると惚れそうになる、と書いていて、 あまりにびっくりしたので質問してしまいました。 私の周りにも何人かそういう人がいて、料理が運ばれてくるたびに「ありがとう」と言ったり、 買い物してお釣りをもらうときに「ありがとう」と言ったりしてました。 見ててイラッとします。会釈ならいいんです。私もするし、感じいいです。でもなんで声に出す? 知り合いでも何でもないのに、馴れ馴れしくない?と思います。 そういう人に限って、何かあったときにねちねちクレームつけたりする。 私自身、コンビニでバイトしてたときに、「ありがとう」と言われたことあります(関西の発音の人が多かったような。。。) 正直、内心で「友達でもないのに何様?」と思ってました。別にお礼言われるようなことしてないし、と。 あ