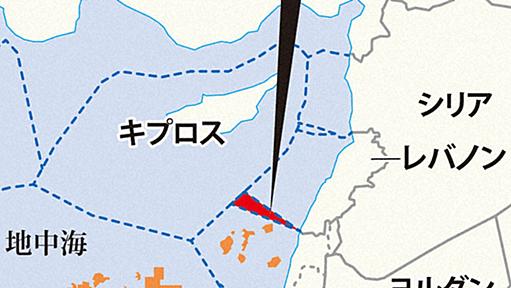京都では、大通りから入った路地の曲がり角の隅に大きな石がよく置かれている。地元では「いけず石」とも呼ばれる。なぜ置かれるようになったのか、そもそもどうしてここにあるのか? そんな素朴な疑問を解き明かそうと、大学と民間企業による共同研究が始まった。 研究は京都大大学院文学研究科の埴淵知哉(はにぶちともや)准教授(都市地理学)のチームが、2024年10月中旬にスタートさせた。埴淵准教授は元々、歩きやすいまちづくりと健康との関係などをさまざまなデータを基に研究している。日常にある物事を数値化し、地図に落とし込んで表現することで、捉えにくい「地域らしさ」を可視化している。 そんな中、京都で日常の風景ともなっている「いけず石」に目を付けた。いけずとは「意地悪」を意味する関西の方言だ。 大阪府などでもいけず石は見られるが、碁盤の目のような街路で形成された京都市内は特に多いとされる。大きさや形はさまざま