■@ブリュッセル なぜこうなっているのか、ずっと気になっていることがある。500ミリリットルのペットボトルのふたが本体から外せないようになっていることだ。 ふたが付いたままだと、何とも飲みづらい。ふた…

■@ブリュッセル なぜこうなっているのか、ずっと気になっていることがある。500ミリリットルのペットボトルのふたが本体から外せないようになっていることだ。 ふたが付いたままだと、何とも飲みづらい。ふた…


久下正史 @26rvx2K0j9nMkwG この記事を書いた人とは残念ながらお友達にはなれそうにない。 「仮に積読が年間6冊あったとしましょう。全体平均額を基にすると「1268円×6冊」で7608円無駄にしています」 news.yahoo.co.jp/articles/6ed17… 2024-07-14 22:02:34 リンク Yahoo!ニュース 6冊以上を「積読」にしている人も!?本を読まずにそのまま放置すると年間何円無駄になる?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース せっかく本を買ったなら、読まないと宝の持ち腐れになってしまいます。また、読書は自分の世界を広げる手段としてもおすすめです。 積読を少しでも有効活用するためにも、まずは積読化している本をリストアッ 27 users 546
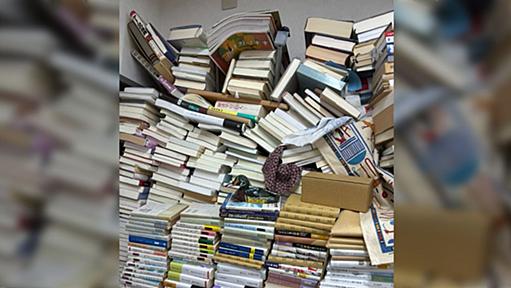
30~40代の若い人が多い青ヶ島 ――加絵さんは、YouTube以外にもいろんなお仕事をされているそうですね。 佐々木加絵さん(以下、加絵) はい。配達業、コワーキングスペースの運営、デザイナー、青ヶ島の観光ガイド、あとは実家が「かいゆう丸」という民宿を営んでいるので、その手伝いもしています。青ヶ島は人口156人(2024年1月1日時点)の島だから、1つの仕事だけでまとまった収入を得るのが難しく、私のように複数の仕事を掛け持ちしている人が多いんですよ。例えば私の弟は、建設業と漁業をしながら、村会議員としても活動しています。 ――たくさんの仕事を掛け持ちしていると、みなさんかなり忙しいのでは? 加絵 そうですね。青ヶ島出身と言うと、「のんびりした人が多そう」という印象を持たれることが多いのですが、実際にはせっかちな人が多いかもしれません。村の飲み会などがあると、集合時間の30分前には来て、準

前にもここにぽちぽちと書いたりしたけれど、1年とすこし前。こどもたちが大きくなって手狭になったのをきっかけにマンションからいまの家に住み替えたのです。で、住み替えたのはいいけれど、あたらしい家はともかく広く、そして築古の家だったので、断熱性能も高くない。つまり、マンション時代とくらべて、光熱費がドカンと上がったんですね。おりしも世界はエネルギー価格高騰の時代。出てきた電気代にほんと目ん玉飛び出るかとおもったんですよ…。 冷暖房効率がもともと悪いうえに、暖房としてエアコンをつかっていたのでなおさらです。毎月これではやってられん、なんとかせんといかん、ということで、あわてて家庭用太陽光発電の導入を決めました。せっかくじぶんで持ってる建物だし、ね。 家庭用太陽光発電。まあ賛否両論というかえらく嫌われているというか、人によっては本当にボロクソ言われていて。でもまあそんななかいろいろ調べてみると、少
あなたのご家庭では誰が家計を管理していますか? 夫婦どちらかが一括で管理しているケースもあれば、共同で家計管理するご家庭や、別々で管理しているご家庭もあります。 「共同で管理したいけど難しそう」と考えている方もいるかもしれませんね。 今回は既婚者500人にアンケートを実施し、「誰がお金の管理をしているか」や「管理方法ごとのメリット・デメリット」を聞きました。 【調査概要】 調査対象:既婚男女 調査期間:2023年10月24日~26日 調査機関:自社調査 調査方法:インターネットによる任意回答 有効回答数:500人(女性347人/男性153人) 回答者の年代:20代 12.6%/30代 42.0%/40代 28.0%/50代 13.2%/60代以上 4.2%

わたしが一緒に住んでいる女は恋人ではない。 妻でもない。妻であればラクだとは思う。お互いのオフィシャルな緊急連絡先になって、どちらかが入院したらもう片方も病室に入れて、先に死んだほうの遺産が残ったほうに自動で行く。いいなあ、めちゃくちゃラクそう。 でもわたしたちは結婚することはできない。わたしたちはどちらも女である。 わたしたちは互いの稼ぎを持ち寄り、住居の確保から家事の分担まで二人で意思決定し、生活をともにしている。相手がいなくなったら生活を立て直さなくてはいけない。そういう相手を何と呼ぶのかと、同居人でない別の友人に訊いたら、パートナーじゃん、との回答が返ってきた。 わたしは反論する。いやそれは籍を入れてないカップルの呼び方でしょ。わたしたち恋愛してないから。する予定もないから。 そもそも恋愛や性愛がパートナーシップにくっついてくるのが、変だと思うんだよねえ。友人はそのように言う。相互

大ヒット子育てエッセイ漫画『毎日かあさん』(毎日新聞出版)。作中に「ぴよ美」として登場していた、作者である漫画家・西原理恵子さんの娘による告白が波紋を呼びました。 おそらく、日本の子育てエッセイ漫画の唯一にして無二の巨星であり、2010年代を代表する国民的大ヒットを遂げた『毎日かあさん』(毎日新聞出版)。毎日新聞紙上での15年の長期連載は子育て真っ只中にあった日本中の母たちから涙ながらの共感をさらい、「卒母」という印象的な言葉とともに終了したのは、今からちょうど5年前の2017年6月26日のことだった。 作者である漫画家の西原理恵子さんは、連載終了を前に、当時こんなコメントを残している。「娘が16歳になり、経済的支援以外、お母さんとしての役割は終わった」「子育て終わり、お母さん卒業、各自解散(笑)」。だが、そのモデルとなった家庭の実像は、漫画通りの面白おかしく切なくのどかな姿などしていなか

最近、私の知っている人が一人の女優さんにより告発されました。 私も過去に性的・精神的被害を受けたことがある人でした。 当時は私なりの考えのもと沈黙を選びましたが、彼女の記事を読み、何時間もの間涙と震えが止まりませんでした。 彼女への罪悪感と共に、その文章にとても救われた自分がいました。 当時の苦しんでいた自分が、「おかしいのは貴女じゃないよ」「苦しく感じてたのはおかしくな事じゃないよ」と肯定してもらえたような気がしました。 そして、その人の行いが表沙汰になる事で、当時沈黙を選んだ自分があれから感じ続けていた罪悪感から解放されたような気がしました。 彼女の記事に対する感謝のメッセージを送ると、沈黙により更に酷い被害を招いてしまった私に対して、とても優しく親身で丁寧なお言葉を返してくださりました。 彼女の為に何かできないかと私なりに考えまして、複数の人間からの証言があれば彼女の記事の信憑性が高

今年は長くて11連休と、日々忙しく過ごす人にとって、さまざまな意味で影響の大きい期間になりました。大型連休をエンジョイしている人がいれば、僕のようにGW真っ最中にこの原稿をしたためているような、休みだからこそ仕事が多いみなさんもいたりするでしょう。 そんな、GWの代表的な使い方といえば旅行ですよね。 せっかくの長期休みですから、山や海、さらには海外……は、ご時世的に難しいかもしれないですが、ふだんは行くことのできない場所へ足を運ぶいい機会。なかなか会うことのできない友人や家族に会いに行くといった過ごし方もいいでしょう。 一方で、誰かと会ったり旅行をしたりするのはどうしてもリスクがつきまとうご時世でもあります。 「あぁ……自宅で手軽にお出かけ気分を味わえたり、いろいろな人と飲んで騒いで、みんなと遊べるような、夢みたいな話あるわけないよなぁ」 と、思ったそこの貴方!! よくぞこの記事に辿りつい

産まれた時から「ぜんっぜん俺に似てねぇなぁ」と思ってた それからも事あるごとに似てねぇなぁと思ってた 気がつけばもう年長さんだ 来年からは小学校になる 私的利用のDNA鑑定なら1.5マンで可能な時代だ 綿棒でほっぺの内側をグリグリして提出するだけだ 今日、その結果が届いた 俺と娘は間違いなく親子だった 親子だったのだ <2021.11.3 追記> 久しぶりに覗いたら、思っていたよりコメントが付いていました。 俺のタネじゃあなかったけれど、種明かしをするつもりもなく このまま平々凡々な人生を進んでいきます

先日タイムラインで、こんなツイートを見かけた。 1万に迫るいいねがついているあたり、いかに多くの人が共感したのかがわかる。 かくいうわたしも、そのひとりだ。 昔は不機嫌な人にあたると、「え?何かした?ごめんなさい!」と思ってたけど、最近は「え、その態度やと全然不満ポイントわからんから、進めますね〜」って感じになってきてしまった…わからないことを勝手に察しようとしない、先回りすることが逆にウザかったりもするからね… — りょかち (@ryokachii) 2021年7月6日 けんすうさんが指摘しているように、「まわりが察することで面倒な人が増長してさらに扱いづらくなる」というのは、結構あるあるだ。 「面倒な人とうまく付き合っていこう」とその人に合わせてしまうのは、長期的に見ると、実は『悪手』だったりする。 マネージャーに無視されるようになった理由 昔働いていた家具屋で、いままであまり関わりが

今週のお題「おうち時間2021」 まあそんなことしなくても普通の生鮮食料品店で1週間の予算をちゃんと決め、献立を考えて買い物し、冷凍庫をうまく使えば安くあがるのは間違いない。ただし、そんなことができる人間はそんなに多くはないに違いない。人類の大半はもっと場当たり的で計画能力がない。 この指摘自体はそうだと思うのだけど、もっと重要な観点として「毎回ちゃんとした食事をしたいか?」という概念の有無が大きいのではないかとも思う。自分自身は自炊になってかなりの食費節約や健康志向ができているけれど、生鮮食材を使い切ろうとしながら毎日異なる複数品目を作るのはすごく難しいし、できるわけもない。 「料理できる系男子です」って言ってくる人の知識と舌を確かめるには「お味噌汁どうやって作ってるんですか?」って聞くのが1番いい。出汁とったり顆粒だし入れずにペーストの味噌だけで作ってる人の"料理出来るレベル"と"それ
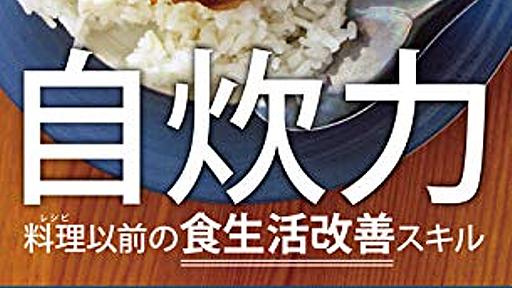
広い倉庫に白い箱がずらりと並ぶ様子をニュースで見た。今月中にも接種が始まるとされる、新型コロナウイルスワクチン用の冷凍庫。マイナス75度での保管が必要とあって、政府は1万台を確保し自治体に配るという▲冷凍庫や冷蔵庫の仕組みは単純だ。張り巡らしたパイプの中の冷媒に圧力をかけて液体にする。それが気体に戻る際、周囲から大量の熱を奪う。手に吹きかけた消毒用アルコールが蒸発するときに冷たく感じるのと同じだ▲約100年前に冷蔵庫が発明された当時は、体に有毒な冷媒が漏れ出して死者を出す事故も起きた。それを知り改良に挑んだのが、天才アインシュタインだった。物理学者仲間のシラードとともに3種類を考案し、連名で特許も取得した▲技術に目をつけた企業もあったが、日の目を見なかった。1929年の世界大恐慌に加え、30年代に入るとナチスが台頭した。ユダヤ系の彼らは冷蔵庫どころではなくなり、米国に逃れた▲その亡命先で2

日本のコロナ対策は失敗だったのか。医師の大和田潔氏は「海外では厳しい規制をかけても大きな被害が出た。日本の対応はメディアに否定的に報道されているが、緩やかな規制と人々の協力で被害は小さく、最適解だったといえる」という――。 日本人の気質 私たち日本人は、謙遜と謙譲を美徳としてきました。つらくても努力し続け、その上で評価を待つ。自らを鍛え、成果をあげて人から評価されることを受動的に待つことを教えられて育ちます。 目的と手段が本末転倒になり、最短で目的が達成するよりも努力し続ける非効率さが美徳とされることもよくあります。細かいところまで気を配り、「石橋をたたいて渡る」ことが日常茶飯事です。さらに武士道の文化もあわさり、自己研鑽けんさんの美徳と統合されています。 たとえうまくいっても「それほどでも」と謙遜し、決して「うまくいったでしょ! スゴイでしょ」なんて自慢しません。みんなで一緒に行動するこ

テナントに退去通知が出されたキャデラック会館(14日、札幌市豊平区で) 札幌市豊平区の不動産仲介店「アパマンショップ平岸駅前店」で起きた爆発事故は16日で、発生から半年を迎える。爆発の影響で傾斜した向かいのビルでは、アパマン側は修復を前提にビル所有者と賠償交渉を進めているが、ビル所有者はテナントに立ち退きを迫っており、営業を再開したテナントは困惑している。被害を受けた周辺のマンションなどでは修復工事が始まっているが、一部の住民たちは今も仮住まいを強いられている。(橋爪新拓) ■取り壊しか修復か 問題のビルは、事故があった平岸駅前店跡地の向かいの雑居ビル「キャデラック会館」と、同会館に隣接するビル「平岸3条マンション」の計2棟で、不動産仲介業者「ビッグ」(札幌市中央区)が所有し、居酒屋、美容室など計8店舗が入居している。 ビル関係者によると、ビッグは4月中旬、各テナントに対し、「建物各所に傾

1956年群馬県生まれ。放送記者を経て、1992年にフリージャーナリストに。地方自治体の取材で全国を歩き回る。97年から『週刊ダイヤモンド』記者となり、99年からテレビの報道番組『サンデープロジェクト』の特集担当レポーター。主な著書に『長野オリンピック騒動記』など。 相川俊英の地方自治“腰砕け”通信記 国政の混乱が極まるなか、事態打開の切り札として期待される「地方分権」。だが、肝心の地方自治の最前線は、ボイコット市長や勘違い知事の暴走、貴族化する議員など、お寒いエピソードのオンパレードだ。これでは地方発日本再生も夢のまた夢。ベテラン・ジャーナリストが警鐘を鳴らす! バックナンバー一覧 大震災以降、日本社会は未曾有の難局に直面している。地震、津波に原発事故、さらには政治の機能不全が加速して危機的な状況が続いている。日常生活を根底から揺さぶる重大な出来事が連日のように発生し、社会全体が心休まる
3・11から3ヶ月が過ぎようとしている。 もう何年も生きてきたような気持ちだ。 最初の数週間は、不安を押し殺しながら、夢中で過ごしたように思う。 水がない。 電気がない。 ガスもこない。 ガソリンもない。 食料も少なくなった。 生活物資も滞ってきた。 でも、被災した方々に比べたらはるかにましだ。 わたしたちがおろおろして、ここでの生活を投げ出したらどうなる。 患者さんは、妊婦さんは、お母さんは、赤ちゃんは、どうなる。 毎日、そんな思いで過ごした。 日々、刻々と変わる放射線レベルに、不安になる親御さんがたくさんいた。 わたしたちなりに、必死に情報を集め、その時に正しいと思う情報を伝えてきた。 今もその考えは、同じだ。 4月になって、県内のほとんどの学校が再開した。 遅れて卒業式をやった学校もあった。 ・・・・・ここまでは、よかった。 4月中旬、文科省の「年間20mSv」という基準が発表されて

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く