かとうひろし @mangakato COMでデビューし、コロコロコミックで再デビューしたマンガ家です。「マンガ表現」に関して、いろいろツイートしています。つくばビジネスカレッジ専門学校非常勤講師 。noteで「マンガCOMマガジン」を展開しています。 note.mu/mangakato


学問を好み、伝統を愛してその歴史を紡いできたまち、金沢。 工芸が今も生活のなかに息づくこの地は、ものづくりのまちでもあります。 金沢美術工芸大学は、戦後の困難な時代のなか、 人のつくる力を信じる金沢の市民が、その心でつくった大学です。 この大学には、「手で考え、心でつくる」ということばがあります。 ここで教鞭をとったある教員が残したこのことばは、ものをつくることが 「つくりながら、試み、考える」ことであること、 「心をこめて」行うことであることを教えてくれます。 この大学で、たくさんの先輩たちが 「つくりながら、試み、考える」ことを繰り返し、 「心をこめて」作品をつくりあげ、世界へ飛び立っていきました。 「手で考え、心でつくる」。 今日も金沢美術工芸大学では、このことばのもとで、 学生たちが学び、鍛錬を重ねています。 ものをつくること、そして ものをつくることについて真剣に考えること。 そ

・・・・のレジュメを公開・・・・と思ったんですが、準備不足のままアドリブでやっているので、全然まとまらず、抄録にします。学生たちにとっても、ちょっとわかりにくい感じだった印象です。う~ん。 1) 視線誘導とは? わかりやすい具体例 (青年マンガ A) 佐藤秀峰『ブラックジャックによろしく』9 講談社 04年 #86「スイッチオン」 138~147p 視線=顔~(めくり)~セリフと奥行き→セリフ→顔 +コマ構成による圧縮効果 B)浦沢直樹×手塚治虫『PLUTO』1 小学館 04年 ○7~9p ニュース音声と会話の並行(文字情報の多層化 物語内の「ロボットが不明確な感情のようなものを自らに発見する切なさ」 →読者が明確な感情を読めない「ロボットの顔」に感情を読もうとする詐術 →人が、目鼻を連想させる図柄に「何か」人間的なものを見てしまう「本能(?)」 以上は、場面を具体的に分析し、コマ構成や

知人に夏目房之介さんの『マンガはなぜ面白いのか』を読ませたところ、もっとも腑に落ちたところが「コマの圧縮と開放」であったという(第十章、文庫版P139から)。「今まで読んでいて気持ちの良いコマ割りと、そうでないコマ割りには、こんな違いがあったのかと気づかされたのだ」と。その興奮具合が面白かったので、手近にあるマンガの中から「圧縮と開放」を読み取ってもらった。 例:福島聡『機動旅団八福神』2巻P59_P60 図1 麻草「開放感あるねえ(図1)」 知人「しかもこれ、メクリなんだよ。ページをめくると北極の真っ白な空、そしてセリフ『北極は寒い』」 麻草「ミもフタもない。直前のコマで砕氷船を左斜め上に進ませてるのもポイント高いね」 知人「効果音や、セリフ、そして描いてあるものを辿るだけで、視線の誘導も計算されつくしてるんだってことがわかる(図2)」 同トレース図上、視線誘導ライン 図2 麻草「これは

「どうすれば、読みやすいマンガが作れるのだろうか?」『マンガ表現論』『視線誘導論』の夏目房之介 掲載日:2007.09.21 夏目先生に『マンガ表現論』を聞いちゃいました 『視線誘導論』についてじっくり教えていただきました。 「どうすれば、読みやすいマンガが作れるのだろうか?」 これは、マンガソーシャルメディア編集部のマンガ編集者であるジェダイ峯村が、約10年のマンガ編集業においてずっと悩んでいたテーマです。 そこで今回のウェブ編集部特別企画インタビューとして、日本のマンガ評論の第一人者である夏目房之介さんに、マンガ表現論の中でも読みやすさと大きく関わってくる『視線誘導論』についてじっくり教えていただきました。 作品解説 ストーリーの面白さはもちろんのこと、描線、吹き出し、コマの構成や動きなど、マンガ家が考えだすアイディアの数々を紹介し、実は複雑な構造をもつマンガ表現を明快に解き明かす。
漫画ではセリフを入れる際にフキダシを使いますが なんとなく空いたスペースに入れる、というわけではなく 読者に伝わりやすくするための沢山の工夫があるようです。 今回ご紹介するイヅルさんの「漫画のコマとフキダシ」では、そういった フキダシやコマの使い方の具体例が分かりやすく説明されています。 (以下ダイジェスト 1.セリフは内ワクに収める 2.浮かしのフキダシは見せ場に使う 3.視線誘導を意識する 4.フキダシの無いコマの役割 5.フキダシで位置関係を演出する 6.対話している際の方向など 7.斜めの構図はここぞというときに 8.フキダシはパースに合わせるとよい 9.縦長のコマは上下が抜けるコマの演出につかうと有効 10.必要な情報は隠さない 11.無駄なコマは思い切って削る 12.絵や情報は必要なものに絞る 13.しゃべっているのが誰か分かるフキダシ フキダシ一つとってもこれだけの表現がある

「マンガを読んできてよかった」 つい先日、富沢ひとしの『ミルククローゼット』第4話(月刊アフタヌーン連載中・講談社)を読んで、僕はこう思った。 作品そのものに衝撃を受けたのはいうまでもない。作者の才能に触れて恍惚を覚えたのも確かだ。非物質的に変形する身体描写、極限まで抑えられたセリフ、「カワイイ」とも「気持ち悪い」ともつかない奇妙で魅力的なデザイン、ソリッドな美しさをたたえたヴィジュアル。しかし、それ以上に、そこに「マンガ」という表現の持つ力、可能性を感じた。もっと言えば「マンガ」というジャンルの持つ底力を見た気がしたのだ。ああ、6歳のときからずっとマンガを読み続けてきてよかった、マンガを愛してきてほんとうによかった。そう感じられたことが、体が震えるほど嬉しかった。 『ミルククローゼット』は、先行する作品『エイリアン9』(全3巻・秋田書店)とほぼ同じスタイルで描かれている。もちろん、僕は『
答えをずばり→「動き」が楽しい。 物語の盛り上がり具合と、コマを行き来する目の動き、キャラの挙動が重なるとき、わたしは喜ぶ。「コミPo!」でマンガを描く(というか構成する?)ようになって、能動的にマンガを「見る」ようになり、さらに本書を読んで、ようやっと気づいたのだ。「マンガはなぜ面白いのか」は、自分がいかに複雑な手続きを経て、マンガ文法を読みこなしているか、改めて自覚させてくれる。 (自分で)マンガを構成うえで、かなり役に立ったのは、「コマの変化による圧縮と開放の効果」だ。コマの大きさとコマ内の人物の比で緊迫感を表し、コマの広がる方向と、人物の動線を合わせること(合わせないこと)で、開放感と示す。指摘されれば、ああ成程かもしれないが、石ノ森章太郎の作成でもって腑に落ちる。わたしが「意識して」つくると、こうなる。 この「運動」をキーワードに、小説の快楽を追求した評論がある。「小説のストラテ

※2014/03/17追記:巻末にオマケを追加 先日、Twitterで漫画のイマジナリーラインについて話題になった。 【イマジナリーライン】を超えたマンガは最悪なのか http://togetter.com/li/641095 その中で、自分もドラゴンボールのワンシーンを画像としてTwitterに投稿し、その画像を起点に色々な議論が交わされていくのを非常に興味深く読んだ。そこで思い出したんだけど、自分もドラゴンボールの左と右に関する記事を書いてる途中だった。 というわけで、話題がホットなうちに公開しようと思い急遽書き上げたのでお読みください。(書くこと多すぎて旬を過ぎた感は否めないけど、イマジナリーラインとは直接関係ない話だし、ね!) キャラ位置が頻繁に入れ替わるのに読みやすい まずはこの画像を見ていただきたい。自分がTwitterに投稿して議論になったドラゴンボールのワンシーン。 2コマ

考えるんじゃない!感じるんだ!! あけましておめでとうございます。J君です。相変わらず始動の遅い当サイトですが今年もよろしくお願い申し上げます。一年の中で最も数の子を食べまくるイベント「SHOGATSU」も無事滞り無く終わりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?数の子だけじゃなく黒豆やチョロギを食べた人も多いと思いますが、チョロギってあれなんなんですかね?あんなに立派にトグロを巻いてるブツって巷ではチョロギかウ●コぐらいだと思うんですけど・・・まあ美味いからいいんですけど。 と、新年早々どうでもいいチョロギトークはこれぐらいにしまして、新年一発目のレビューはインパクト重視!マンガでありながらマンガの枠を完全に飛び越え、アートの領域に入ってしまっている凄まじい作品をご紹介します。その名も「ガバメントを持った少年」です。 「ガバメントを持った少年」は風忍先生の短編集になります。当サイトでは過
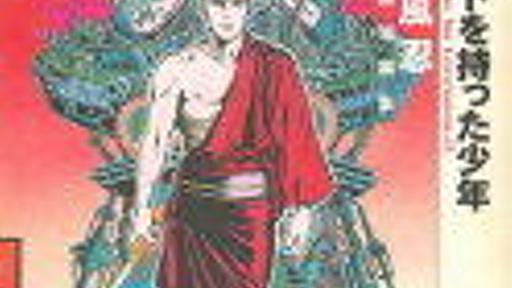
学問を好み、伝統を愛してその歴史を紡いできたまち、金沢。 工芸が今も生活のなかに息づくこの地は、ものづくりのまちでもあります。 金沢美術工芸大学は、戦後の困難な時代のなか、 人のつくる力を信じる金沢の市民が、その心でつくった大学です。 この大学には、「手で考え、心でつくる」ということばがあります。 ここで教鞭をとったある教員が残したこのことばは、ものをつくることが 「つくりながら、試み、考える」ことであること、 「心をこめて」行うことであることを教えてくれます。 この大学で、たくさんの先輩たちが 「つくりながら、試み、考える」ことを繰り返し、 「心をこめて」作品をつくりあげ、世界へ飛び立っていきました。 「手で考え、心でつくる」。 今日も金沢美術工芸大学では、このことばのもとで、 学生たちが学び、鍛錬を重ねています。 ものをつくること、そして ものをつくることについて真剣に考えること。 そ

■京都精華大学連続講義レジュメ 第四回「マンガ版『ナウシカ』はなぜ読みづらいのか?」(1) 講師 竹熊健太郎 【A】手塚治虫と宮崎駿の複雑な関係 ●手塚の死去(1989年)に際して、様々な雑誌で追悼特集が組まれ、多くの識者が追悼文を寄せていたが、ひとり宮崎駿は、手塚のマンガ家としての功績を十分に認めながらもアニメ分野における手塚の活動を痛烈に批判して世間を唖然とさせた。 →「だけどアニメーションに関しては───これだけはぼくが言う権利と幾ばくかの義務があると思うのでいいますが───これまで手塚さんが喋ってきたこととか主張してきたことというのは、みんな間違いです」(手塚治虫に「神の手」をみた時、ぼくは彼と訣別した」宮崎駿 comicbox 1989.5月号) →宮崎は、手塚がアニメ作家としては「素人芸」であり「下手の横好き」であって、にもかかわらずマンガ家としての名声をバックにアニメ会社を作
学習院身体表象の担当ゼミ(批評研究)で、以下のようなレジュメの発表を行いました。 2013.10.2-9 マンガ・アニメーション芸術批評研究(3限) 宮崎駿『風の谷のナウシカ』マンガ版と「読みにくさ」 夏目房之介 ※以下のメモは、今秋提出の当専攻博士課程後期・砂澤雄一の『風の谷のナウシカ』についての博士論文に触発されたものである。 1)『ナウシカ』マンガ版は読みにくいのか? 阿部幸広「究極の、そして最も幸福なアマチュア-マンガ家としての宮崎駿」(「ユリイカ 臨時増刊 宮崎駿の世界」青土社 1997年)をはじめ、『ナウシカ』マンガ版を「読みにくい」とする意見が複数ある。夏目自身は、違和感は多少あるが、それほど読みにくいとは感じていなかったので、少し意外であった。直観的には、宮崎のマンガ観が50年代の読書体験によって形成され、古典的な表現形式を踏襲しているために、現在のマンガ形式になじんだ読

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く