マネードクターのFPパートナー、「生保業界のビッグモーター」呼ばわりに法的措置を検討するも結局本当に金融庁が立ち入り検査に動く
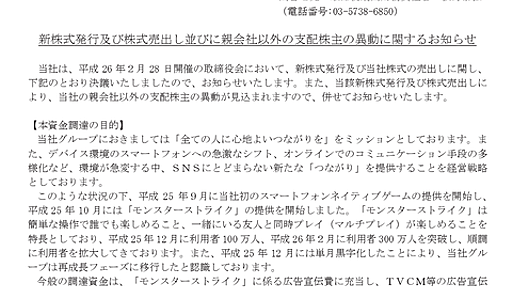
マネードクターのFPパートナー、「生保業界のビッグモーター」呼ばわりに法的措置を検討するも結局本当に金融庁が立ち入り検査に動く
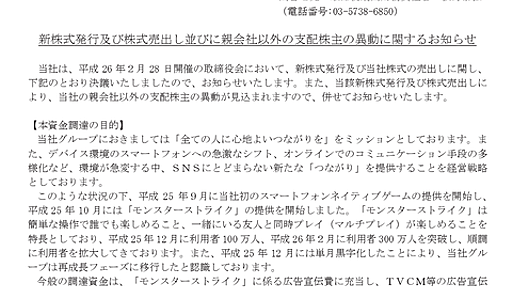

ミクシィが11月2日に発表した2012年4~9月期(上期)連結決算は、純利益が12億500万円と前年同期比3.5倍に伸びた。ソーシャルゲームの課金収入と、スマートフォンの広告収入が成長。「1年前とはビジネスモデルが変わってきた」と、荻野泰弘取締役は話す。 上期の売上高は前年同期比12.1%増の68億17800万円、営業利益は89.7%増の16億1200万円、経常利益は2.3倍の15億8300万円。前年上期まではフィーチャーフォン・PC向け広告収入が大半だったが、同下期の「mixiゲーム」リニューアルを機に課金収入が急伸。今期は課金が広告を上回った。フィーチャーフォン向け広告は急減しているが、スマートフォン向け広告が順調に拡大している。 7~9月期の課金収入は、6月に導入したソーシャルゲームの新ガイドラインの影響で前四半期より微減したが、「10月から徐々に回復の傾向が出ている」(荻野取締役)

mixi に関しては当初、特に何の感想も持っていなかったのですが、ここ最近「mixi 衰退論」的な記事が大きな反響を生んでいる事例をぽつぽつ見かけて感化されてしまったので何か書いてみます。今回は、衰退論と言うか「ソーシャルメディアの一生」と言うテーマで書いてみようと思います。言いたい事は大体上図の通りで、「キャズム」等で言われる「企業や製品のライフサイクル」をベースにちょっとだけソーシャルメディア用に書き換えたものとなります(具体的には、衰退期の次に滅亡期と言うものを追加)。尚、mixi と ラグナロクオンライン*1 を思い浮かべながら書いた図なので、どの程度まで一般化できているかは不明です。 黎明期〜成長期 新し物好きが飛びつき、ブログ等で言及する事によって広まっていく(口コミ効果)、一方で、目にする機会が多くなったので取りあえずやってみたが要領を得ず「○○の何が面白いのかさっぱり分から

【書評】『必ず結果が出るブログ運営テクニック100 プロ・ブロガーが教える“俺メディア”の極意』(コグレマサト&するぷ・著) 最近読み直して、改めて書評を書こうと思い立ちまして。 本書では、プロフェッショナルのブロガーをおおまかに二つに分けて”本職がほかにある人がブログを書いて本業の助けにしている人”と”ブログを書くことで直接収入があることを期待する人”と定義して、結構ノウハウの中でも「あー。そういうことだったのか」というのを記述しています。 で、自分もブログをささやかながらやっておりますので、どれをどうすればいいのか参考にしようと思ったりするわけなんですけれども、これがねえ、面倒臭いんですよ。いろいろと、ああしようこうしようというのはありますけれども、アフィリエイトも書籍をお奨めするときぐらいですし、あとはほかのソーシャルからの誘引といっても別に何もしません。ああ、twitterには一応

今回はアブラハム・プライベートバンク(「いつかはゆかし」等)がおかしいという話ではないのですが、これ関連の金融商品をがさごそと漁っておりましたところ、ハンサードやフレンズプロビデントの金融商品をマルチ式に売っている業者の名簿が出てきました。これがまた外=外で運用しているので大脱税大会になっており、震撼しております。どうやって日本に持ち込んで所得になっているのか分からんのですが、まあ分かっちゃった以上は細大漏らさず当局に対してご報告の段取りを取りたいと思います。アブラハム以外の面白カンパニーについてはここでうっかり書いて逃げ散られてもしょっぱいですから、当局が首根っこ掴まえるまでは触れない方向で頑張って参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 ところで、アブラハムの法務担当取締役の(自粛: 2015年2月9日)に、さくじつ再びメールで質問状をお送りしておいたのですが、前回のメールで

ソーシャルメディアマーケティング支援を手がけるトライバルメディアハウスは、社員のブログに不適切な表現があったとし、謝罪文書(PDF)を7月12日付けで公開した。 同日正午ごろ、同社の社員が所属を明かしたブログで、「LINEのソーシャルネットワーク化の先にあるもの? SNS難民は救われ、mixiは死ぬ」と題した記事を公開。LINEのSNS化戦略と、Facebook、Twitter、mixiなどの位置付けについて考察した記事で、ネットで賛否両論が飛び交い、話題になっていた。 午後7時過ぎ、「記事タイトル・内容に関して行き過ぎた表現があった」とし、タイトルを「LINEのソーシャルネットワーク化の先にあるもの」に、本文内の「SNS難民は救われ、mixiは死ぬ」という表現を、「SNS難民は救われ、mixiは新しい方向性を求められる」に変更。「mixiやmixiユーザーに対して誹謗中傷に等しい表現をし

要するにSNSの本質である、 「ユーザー活動のコンテンツ化」を忘れると、力を失う。 ということ。 mixiはあくまでも元々は純粋なSNSをやりたかったんだと思う。 純粋なSNSをやりたいならユーザー活動にフォーカスしなければダメだ。 mixiはたしか2006年ごろニュース機能を導入した。 Facebookはその何倍の規模になってもユーザー活動にフォーカスしている。 あのブレない姿勢はえらい。 2006年に書いた記事。 mixiの変化 mixiがSNSの中で一番成功した理由は 「ユーザーの些細な動きも増幅して、それを別のユーザーへのコンテンツとして提供する」 事に徹底的に注目した所にあると思います。 「独特の9面レイアウト」「プロフィール写真」「日記」「コミュニティ」「あしあと」 等が特徴的ですが、「あしあと」なんかは最高の例だと思います。 発言をしないユーザーが他のページにアクセスしたとい

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く