タグ
- すべて
- 311 (29)
- @nifty (4)
- AR (1)
- BPM (2)
- Chef (3)
- GTD (120)
- Gmail (110)
- Google (358)
- Google App Engine (4)
- Google Base (16)
- Google Calendar (44)
- Google Co-op (4)
- Google Desktop Search (7)
- Google Docs (4)
- Google Earth (22)
- Google Maps (35)
- Google Notebook (10)
- Google Reader (5)
- Google Talk (6)
- Heroku (1)
- IT (45)
- IoT (1)
- Lightroom (26)
- Markdown (5)
- Music (16)
- Photos (3)
- Picasa (10)
- Pocket (5)
- Raspberry Pi (23)
- Ruby on Rails (17)
- Second Life (11)
- TV (7)
- UI (11)
- UML (4)
- VirtualBox (2)
- WYSIWYG (10)
- Webサービス (2)
- YouTube (53)
- acrobat (1)
- adobe (4)
- adsense (20)
- affiliate (2)
- ai (6)
- ajax (56)
- amazon (95)
- ambient (2)
- analysis (1)
- android (4)
- anime (3)
- apache (4)
- aperture (2)
- app (66)
- apple (39)
- architecture (26)
- art (1)
- atom (15)
- attention (1)
- attention economy (14)
- aws (11)
- bitbucket (2)
- bitcoin (6)
- blockchain (1)
- blog (209)
- bloglines (10)
- book (17)
- bookmarklet (36)
- branding (1)
- business (5)
- camera (4)
- chasm (8)
- cheap revolution (11)
- chrome (3)
- ci (1)
- civilization (2)
- cli (2)
- cloud (34)
- cms (5)
- colinux (16)
- comic (1)
- computer (1)
- coreserver (9)
- cpu (2)
- creative commons (26)
- crowdsourcing (7)
- css (78)
- cui (3)
- culture (1)
- db (13)
- del.icio.us (19)
- design (9)
- development (2)
- devops (9)
- disaster (1)
- docomo (2)
- dropbox (2)
- economics (2)
- electronica (2)
- emacs (29)
- emergency (1)
- emmulator (1)
- essay (4)
- evernote (51)
- extension (39)
- facebook (98)
- fashion (13)
- filter (1)
- filter_bubble (1)
- finance (16)
- firefox (95)
- flickr (39)
- foaf (7)
- folksonomy (26)
- food (1)
- framework (1)
- free (3)
- future (2)
- gadjet (6)
- game (4)
- git (28)
- github (10)
- godzilla (3)
- goods (1)
- google chrome (2)
- greasemonkey (14)
- hardware (80)
- hawaii (7)
- health (1)
- history (9)
- hobby (1)
- homebrew (4)
- hosting (6)
- htaccess (1)
- html (64)
- http (1)
- iGoogle (3)
- icloud (6)
- ide (1)
- idea (2)
- ie (17)
- ifttt (2)
- image (2)
- instagram (1)
- interface (3)
- internet (4)
- ios (38)
- ipad (40)
- iphone (208)
- ipod (24)
- irc (1)
- itunes (56)
- java (23)
- javascript (98)
- jazz (2)
- joke (37)
- joost (5)
- jupyter (1)
- kindle (4)
- knoppix (2)
- life (1)
- lifehack (2)
- lifehacks (364)
- lifestyle (1)
- line (3)
- linux (50)
- literature (1)
- live (1)
- long tail (30)
- mac (371)
- management (1)
- manga (1)
- map (4)
- marketing (1)
- meadow (1)
- media (12)
- medium (9)
- memory (3)
- mental (1)
- microformats (30)
- microsoft (47)
- military (4)
- mind hack (17)
- mindmap (30)
- mixi (11)
- mobile (1)
- moleskine (80)
- money (7)
- mountain (1)
- movabletype (317)
- movie (11)
- mp3 (3)
- mycomment (1)
- mysql (18)
- nas (2)
- nature (10)
- negicco (8)
- net (2)
- ning (11)
- objective-c (1)
- open (4)
- open source (67)
- openid (69)
- os (11)
- oss (3)
- outliner (1)
- p2p (13)
- paas (1)
- pda (7)
- pdf (24)
- perfume (21)
- perl (60)
- philosophy (1)
- photo (29)
- photoshop (3)
- php (24)
- pim (12)
- plagger (9)
- planner (9)
- platform (4)
- plugin (139)
- podcast (53)
- politics (9)
- polytics (1)
- pr (1)
- preset (4)
- privacy (33)
- productivitiy (8)
- productivity (15)
- programing (8)
- programming (33)
- pukiwiki (5)
- python (21)
- qemu (1)
- radiko (1)
- radio (1)
- religion (1)
- remember the milk (36)
- review (2)
- ria (6)
- rimo (5)
- robot (1)
- rss (93)
- ruby (56)
- saas (22)
- sbm (72)
- scalability (3)
- science (5)
- search (1)
- search engine (50)
- security (35)
- semantic web (50)
- seo (8)
- service (103)
- sf (6)
- shop (3)
- siri (2)
- sixapart (8)
- skype (34)
- sns (120)
- soa (18)
- social (7)
- society (8)
- sociology (2)
- software (236)
- sony (2)
- sports (10)
- squeak (10)
- startup (4)
- stationary (175)
- stevejobs (7)
- study (1)
- subversion (23)
- survival (1)
- tag (60)
- technology (4)
- technorati (3)
- theme (8)
- tips (473)
- travel (4)
- tumblr (5)
- twitter (135)
- typekey (7)
- ubuntu (4)
- unix (10)
- ustream (6)
- vagrant (4)
- video (6)
- vm (16)
- vox (6)
- vr (1)
- watch (2)
- web (10)
- web service (38)
- web2.0 (236)
- widget (1)
- wiki (16)
- wikipedia (5)
- windows (136)
- windows vista (14)
- wisdom of crowds (27)
- wordpress (139)
- words (2)
- workflowy (10)
- world (1)
- writing (2)
- xml (15)
- xrea (26)
- xslt (6)
- yahoo! (13)
- yokohama (1)
- あちら側 (15)
- あとで読む (90)
- ことば (42)
- はてな (115)
- はてなRSS (3)
- はてなスター (2)
- はてなブックマーク (94)
- アウトドア (14)
- アフィリエイト (17)
- アフォーダンス (2)
- アート (7)
- イノベーション (24)
- インテリア (1)
- ウェブ人間論 (12)
- ウェブ時代をゆく (20)
- ウェブ進化論 (47)
- ウクレレ (1)
- オープンにする (39)
- カメラ (9)
- カレンダー (1)
- グルメ (45)
- コミュニケーション (61)
- コミュニケーション" (1)
- コモディティ化 (5)
- コンサルタント (1)
- ゴジラ (3)
- サービス (40)
- シン・ゴジラ (6)
- ストレス (8)
- スピーチ (6)
- スポーツ (1)
- セキュリティ (15)
- デザイン (226)
- デザインパターン (1)
- ドロップシッピング (1)
- ハウツー (2)
- ビジネス (1)
- ビジネス・モデル (5)
- ファッション (1)
- ブラウザ (4)
- プレゼンテーション (17)
- プログラミング (25)
- プロジェクト管理 (18)
- マネジメント (33)
- マーケティング (38)
- モバイル (106)
- レシピ (15)
- ロジカルシンキング (2)
- 仮想化 (7)
- 住宅 (1)
- 健康 (31)
- 写真 (105)
- 創造性 (5)
- 勉強能力 (7)
- 和歌山 (11)
- 哲学 (1)
- 問題解決 (2)
- 地理 (1)
- 宇宙 (9)
- 家計 (2)
- 家電 (9)
- 宿 (32)
- 山 (7)
- 心理学 (12)
- 思考法 (9)
- 情報共有 (15)
- 情報収集 (28)
- 情報環境 (61)
- 戦略 (2)
- 政治 (11)
- 教育 (34)
- 散歩 (1)
- 文章 (75)
- 旅 (7)
- 旅行 (66)
- 日米 (3)
- 映画 (54)
- 未来 (26)
- 本 (246)
- 横浜 (5)
- 次の10年 (100)
- 歴史 (73)
- 沖縄 (3)
- 法律 (1)
- 無料 (82)
- 生活 (2)
- 生産性 (22)
- 社会 (149)
- 科学 (5)
- 組織 (10)
- 経営 (51)
- 経済 (60)
- 総表現社会 (9)
- 脳 (8)
- 自然 (68)
- 英語 (62)
- 落語 (2)
- 著作権 (2)
- 表現 (1)
- 記憶 (6)
- 軍事 (1)
- 開発手法 (44)
- 防災 (14)
- 電子書籍 (6)
- 音楽 (152)
- tips (473)
- mac (371)
- lifehacks (364)
- Google (358)
- movabletype (317)
- 本 (246)
- software (236)
- web2.0 (236)
- デザイン (226)
- blog (209)
historyに関するkasedacのブックマーク (9)
-
 kasedac 2018/12/18"「18世紀における経済の「飛躍」を導いたのは、「長く続いた停滞そのものであった」…(国内における)遺伝的多様性は、高過ぎても低過ぎても経済成長と負の関連があり、最適な状態がある"
kasedac 2018/12/18"「18世紀における経済の「飛躍」を導いたのは、「長く続いた停滞そのものであった」…(国内における)遺伝的多様性は、高過ぎても低過ぎても経済成長と負の関連があり、最適な状態がある"- economics
- history
- science
リンク -
『石油と日本』石油を持たない国の試行錯誤 - HONZ
これまで歴史本や評伝にて部分的に語られるものの、日本の石油外交や資源開発の歴史について網羅的にまとめた書籍は、ほとんど存在しない。日本軍が石油を求めて東南アジアに武力進出していったことは歴史年表に記されてはいるが、誰がどういう経緯で進軍を決めたかや当時の資源開発現場を紹介する本はあまりない。太平洋戦争は石油の戦争といわれるわりに、私たちは事の顛末をきちんと理解していないのかもしれない。 そんな中、明治から現在までの日本の油田開発と資源外交に焦点をあてる本書は希有な一冊といえよう。これまで歴史に埋もれてきた数多くの物語を紡ぎだす良書である。しかも、歴史の表舞台に登場するプレイヤーの動向を紹介するだけでなく、そんな彼らを支えた人、場合によっては彼らにすら認知されていない現場の人たちにまでスポットライトをあて、日本のこれまでの資源外交と油田開発の歴史を振り返っている。 本書を読むと日本の石油政策

-
『暴力の人類史』 人類史上もっとも平和な時代 - HONZ
テロ、紛争、無差別殺人。世界は悲劇的なニュースで溢れている。人類は自らの手でその未来を閉ざしてしまうのではないか、と不安になる。ところが、著者スティーブン・ピンカーは大胆にもこう主張する。 長い歳月のあいだに人間の暴力は減少し、今日、私たちは人類が地上に出現して以来、最も平和な時代に暮らしているかもしれない にわかに信じがたいこの説を検証し、読者に確信させるためにピンカーは、人類の暴力の歴史を大量の統計データとともに振り返る。本書が上下で1,300ページ超という並外れたボリュームで膨大な文献を引用しているのは、並外れた説の主張にはそれに見合った証拠を提出する必要があるからだ。しかし、ピンカーが「統計のない物語が盲目であるとするならば、物語のない統計は空疎である」と語るように、本書はデータばかりが延々と続く退屈なものではない。持続的な暴力減少を示す圧倒的な事実の積み重ねとそのメカニズムに対す
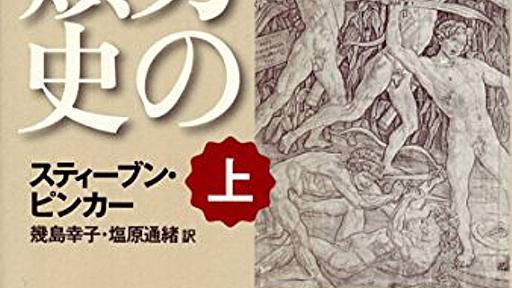
-
米中戦争勃発の可能性は「16分の12」だ! 500年間のケース分析は警告する | 「トゥキュディデスの罠」が現代の国際政治でも発動する
古典的名著『決定の本質』で、いかにしてキューバ危機が起き、いかにして核戦争が回避されたかを解明したハーバード大学の碩学、グレアム・アリソン。 500年間の「支配勢力」と「新興勢力」の争いを分析したアリソンは、紀元前5世紀に大戦争でギリシャを崩壊させた「トゥキュディデスの罠」が現代の国際政治でも発動する、と主張。目前に迫った「米中戦争」のリスクを警告する。 「戦争なんて起きない」と考えることが戦争のリスクを増やす 2015年9月、米国のバラク・オバマ大統領が、訪米した中国の習近平・国家主席と会談した。 この会談の席で、ほぼ確実に話題にならなかったことが1つある。 その話題とは、「10年以内に米中戦争が勃発する可能性がある」というものだ。 両国の首脳陣にとって、米中の武力衝突など起こりえない話なのだろう。また、米中の指導者たちには、「戦争を起こすほど自分たちは愚かではない」と考えている節がある

-
『伊四〇〇型潜水艦 最後の航跡 (上、下巻)』 忘れさられた兵器と人間ドラマを再び浮上させる! - HONZ
1945年8月28日、米潜水艦セグンドは、日本の降伏文書調印式典に、米海軍の潜水艦の代表として列席するため、日本本州から約1000マイル離れた洋上を航海中であった。そのときレーダーが何かを捉えた。レーダーのスクリーンに現れたブリップの大きさに乗員は目をみはる。これほどの大きさの物体ならば距離1万5000ヤード先からでもレーダーが確実にとらえるはずだ。しかし「それ」がレーダーに捕捉されたのは、なぜか距離5500ヤードまで近付いた地点であった。セグンドの乗員たちはわが目を疑い、次の瞬間には緊張が艦内を支配する。 実はセグンドの新任艦長であるジョンソンは部下たちからあまり信頼されていなかった。悪態をつき、せっかちで、どこかバランスを欠いたように見える人格が、部下たちを不安にさせていた。潜水艦の乗務員は水上艦の乗務員よりも死亡率が高い。完全に逃げ場の無い密閉された空間で、ひとたび事が起きれば全将兵

-
-
ブライアン・イーノが選ぶ、文明の維持を考える上で欠かせない20冊の読書リスト - YAMDAS現更新履歴
Brian Eno’s Reading List: 20 Essential Books for Sustaining Civilization | Brain Pickings ブライアン・イーノ先生の読書リストという点が興味をひくわけだが、文明の維持とは大きなテーマを選んだものだ。そういえばイーノ先生は Long Now 財団の関係者でもあるんだよな。 ジェームズ・C・スコット『Seeing Like a State』(asin:0300078153) デヴィッド・ルイス=ウィリアムズ『洞窟のなかの心』(asin:4062176130) エリアス・カネッティ『群衆と権力』(asin:4588099248、asin:4588099256) フェルナン・ブローデル『交換のはたらき (物質文明・経済・資本主義15‐18世紀)』(asin:4622020548) ウィリアム・ハーディー・マクニ
-
-
-
 1
1
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く





