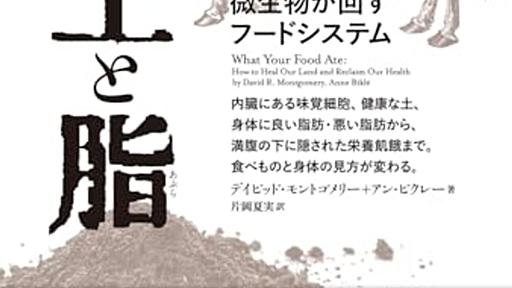酒を主食とする人々 作者:高野秀行本の雑誌社Amazonこの『酒を主食とする人々』は、数々の冒険・探検ノンフィクション(だけじゃないが)を世に送り出してきた高野秀行の最新刊だ。今回のテーマは、エチオピア南部に存在す、朝・昼・晩酒を飲んで──というか「食べて」暮らし、それ以外のものはほとんど食べないし飲まないという、酒を主食とする人々についての調査・探検である。 この酒を主食とする人々については、砂野唯による『酒を食べる』という先行書がある。砂野氏は10年以上この土地に通って調査を行っており、京都大学大学院で学び、博士号を取得した本職の生態人類学者である。その本によれば、エチオピア南部のデラシャという民族は栄養の大部分をパルショータと呼ばれる酒から得ていて、アルコール度数にして3〜4%くらいのこの酒を一日5リットルも飲むのだという。 それを読んだ高野さんは、実際に自分もデラシャの酒飲み生活を