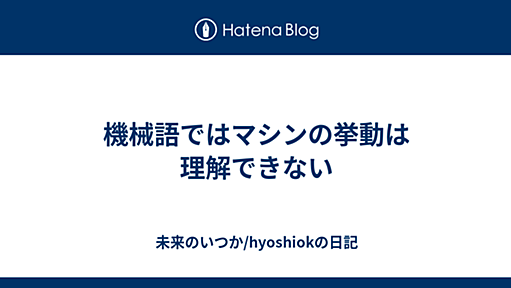今年のCPU実験では、有志からなる我らがX班が、おそらくCPU実験史上初である自作CPUへのOS (xv6) 移植に成功しました。コア係とコンパイラ係の面々がそれぞれまとめ記事を書いていたので、OS係から見たOS移植のまとめも書こうかなと思います。こんなことしてましたってことが伝わればいいなと思います。 この記事を読む後輩やらなんやらがいたら、ぜひ僕らがやったようなことはさっさとクリアしちゃって、さらにさらに面白いことをする踏み台にしていってほしいですね。 どなたが読んでもある程度概要が伝わるよう、まずCPU実験とは何かということをさらっと書いた後、実際にxv6を移植するにあたってやったことをまとめたいと思います。 CPU実験とは CPU実験は僕の学科(理学部情報科学科)で3年冬に行われる、半年間にわたる学科名物演習です。 最初の週で4~5人程度の班に分けられた後、それぞれの班でオリジナル