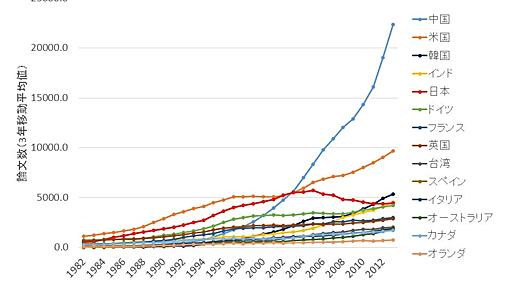近年の研究では、自然の中で過ごすことは脳卒中での生存率が上がったり糖尿病のリスクが下がったりといった健康面でのメリットや、幸福度を向上させる効果があると判明しています。ドイツのライプツィヒに住む約9800人を対象とした調査によって、街路樹に「うつ病の抑止効果」がある可能性が新たに示唆されました。 Urban street tree biodiversity and antidepressant prescriptions | Scientific Reports https://www.nature.com/articles/s41598-020-79924-5 Street trees close to home may reduce the risk of depression | The Independent https://www.independent.co.uk/news/s