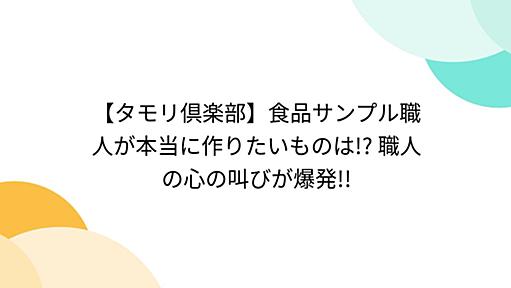タグ
- すべて
- 2ch (57)
- 2chまとめ (45)
- 2ちゃんねる (11)
- 3D (15)
- 3DCG (6)
- 3Dプリンタ (7)
- 4Gamer (13)
- AC (7)
- AI (25)
- AR (6)
- AV (48)
- AbemaTV (107)
- Adobe (22)
- Android (22)
- Animal (71)
- Apple (44)
- Application (6)
- Art (70)
- B-CAS (7)
- Blender (34)
- CM (25)
- CSS (32)
- CarAudio (18)
- Chrome (8)
- CodeZine (5)
- DAW (11)
- DAZN (5)
- DIY (21)
- DJ (6)
- DNS (9)
- DPZ (10)
- DTP (7)
- DeNA (8)
- DisplayPort (8)
- Engadget Japanese (8)
- Eテレ (8)
- FireFox (5)
- Flash (18)
- Gizmodo Japan (36)
- Googleマップ (5)
- HDMI (24)
- HTML (15)
- HTML5 (11)
- IT (17)
- ITMedia (183)
- ITunes (20)
- Ingress (14)
- JASRAC (7)
- JR (11)
- LAN (13)
- LED (7)
- LGBT (8)
- LINE (23)
- LifeHacker (14)
- Mac (163)
- MakeUp (6)
- Marketing (78)
- Mathematics (12)
- Mobile (69)
- My 3D Printer (6)
- NAS (10)
- NHK (113)
- PCパーツ (13)
- PHP (18)
- PT3 (14)
- Perfume (7)
- PhpStorm (5)
- Q&A (5)
- REGZA (10)
- SEO (9)
- SNS (57)
- Safari (6)
- Space (7)
- Suica (6)
- Swift (5)
- TPP (8)
- TV (231)
- TVTest (5)
- Tips (69)
- Togetter (310)
- Twitpic (23)
- UI (13)
- USB (32)
- USBメモリ (5)
- Unity (52)
- VOCALOID (49)
- VR (65)
- VRChat (169)
- VTuber (18)
- WELQ (5)
- WebDesign (7)
- Wi-Fi (29)
- Windows (151)
- Windows 10 (5)
- Windows10 (9)
- Windows7 (11)
- Windows8 (8)
- abematimes (23)
- amazon (55)
- anime (160)
- asahi.com (5)
- ascii (5)
- au (9)
- audio (47)
- backup (10)
- beauty (20)
- blog (11)
- bluetooth (12)
- book (32)
- business (417)
- buzzfeed (6)
- camera (52)
- car (43)
- cat (20)
- character (21)
- color (11)
- comic (51)
- communication (149)
- cooking (43)
- copyright (84)
- culture (61)
- design (250)
- development (30)
- docomo (9)
- dtm (93)
- earthquake (5)
- economy (11)
- education (138)
- eneloop (11)
- english (62)
- evernote (11)
- excel (15)
- facebook (20)
- fashion (43)
- font (30)
- food (115)
- gadget (58)
- game (235)
- gender (49)
- gigazine (119)
- goods (15)
- google (59)
- government (20)
- hardware (28)
- health (125)
- history (19)
- iCloud (5)
- iOS (26)
- iPad (46)
- iPadアプリ (13)
- iPod (16)
- iPod touch (8)
- iPodアクセサリー (5)
- illustration (41)
- illustrator (18)
- image (26)
- internet (47)
- interview (89)
- iphone (200)
- iphoneアクセサリー (9)
- iphoneアプリ (62)
- japanese (27)
- javascript (20)
- language (23)
- law (52)
- librahack (9)
- life (398)
- lifehack (222)
- linux (7)
- logo (7)
- macApp (7)
- macbook (9)
- macbook pro (6)
- management (10)
- map (13)
- math (8)
- media (147)
- medical (64)
- mental (13)
- microsoft (9)
- mixi (8)
- money (28)
- movie (37)
- music (173)
- nature (11)
- naverまとめ (80)
- net (14)
- network (33)
- news (584)
- office (10)
- osx (5)
- pc (232)
- pdf (6)
- photo (120)
- photoshop (61)
- politics (15)
- privacy (20)
- programming (65)
- python (8)
- recipe (30)
- review (6)
- school (9)
- science (97)
- security (104)
- server (15)
- sex (15)
- shopping (20)
- skype (11)
- slack (6)
- social (14)
- social game (7)
- social media (8)
- society (363)
- software (113)
- sound (12)
- spam (5)
- sports (11)
- stationery (5)
- study (32)
- tax (16)
- technology (37)
- tool (76)
- tools (7)
- travel (61)
- tweetbot (8)
- twitter (216)
- twitter 関連サービス (9)
- video (17)
- voice (11)
- weather (5)
- web (38)
- webゲーム (7)
- webサービス (255)
- webデザイン (131)
- webプログラミング (25)
- web制作 (125)
- work (24)
- yahoo (6)
- youtube (105)
- あとで読む (26)
- いい話 (15)
- いじめ (12)
- お役立ち (102)
- お笑い (5)
- お絵描き (5)
- お菓子 (10)
- かわいい (43)
- けものフレンズ (116)
- これはかわいい (9)
- これはきれい (12)
- これはこわい (7)
- これはすごい (357)
- これはすてき (10)
- これはひどい (230)
- これはステキ (10)
- これは便利 (136)
- これは大事 (26)
- これは大切 (78)
- これは欲しい (22)
- これは気になる (19)
- これは綺麗 (5)
- ちょいネタ (5)
- どうしてこうなった (8)
- ぬこ (24)
- ねこ (34)
- ねとらぼ (178)
- ねほりんはほりん (7)
- ねほりんぱほりん (23)
- はじまりの応援 (234)
- はてな (58)
- はてな匿名ダイアリー (49)
- はてブ (11)
- はるかぜちゃん (5)
- まとめ (496)
- まどか☆マギカ (26)
- ゆるキャラ (8)
- らばQ (17)
- アニメ (6)
- アメリカ (26)
- イラスト (7)
- インタビュー (12)
- インテリア (9)
- エイプリルフール (13)
- オタク (7)
- カラオケ (8)
- キャンペーン (6)
- クレジットカード (18)
- ケータイ (20)
- コスプレ (11)
- コミケ (10)
- コンビニ (9)
- スイーツ (6)
- スマホ (12)
- スマートフォン (40)
- ソーシャルゲーム (15)
- ソーシャルメディア (9)
- ダイエット (13)
- チュートリアル (20)
- ディスプレイ (8)
- デイリーポータルZ (14)
- デジカメ (11)
- デマ (6)
- トラブル (11)
- トリビア (26)
- ドメイン (6)
- ニコニコ動画 (40)
- ネコ (9)
- ネタ (86)
- ネット (16)
- バッテリー (9)
- バリバラ (6)
- バーチャルYouTuber (8)
- フジテレビ (7)
- フリーソフト (42)
- フリー素材 (14)
- ブラック企業 (19)
- プラグイン (6)
- ヘッドホン (10)
- ホテル (6)
- ホルモン (8)
- ボイストレーニング (7)
- ポケモンGO (35)
- ポメラ (6)
- マスコミ (45)
- マンガ (11)
- ラブライブ! (12)
- レシピ (12)
- レンタル (6)
- 一人暮らし (7)
- 不動産 (25)
- 中国 (14)
- 事件 (11)
- 事故 (14)
- 交通 (9)
- 人権 (13)
- 人生 (23)
- 人間関係 (7)
- 仕事 (59)
- 仕事術 (36)
- 企業 (24)
- 会社 (24)
- 使い方 (13)
- 便利 (21)
- 健康 (17)
- 児童ポルノ (7)
- 児童ポルノ法 (6)
- 写真 (46)
- 出版 (7)
- 初音ミク (48)
- 労働 (14)
- 勉強 (28)
- 動画 (29)
- 医療 (22)
- 原発 (94)
- 参考 (7)
- 同人 (15)
- 国際 (16)
- 地デジ (22)
- 地理 (7)
- 地震 (144)
- 壁紙 (6)
- 声優 (18)
- 夜更かし用 (14)
- 天文 (8)
- 始まりの応援 (23)
- 子供 (8)
- 子育て (52)
- 学校 (6)
- 学習 (22)
- 宇宙 (18)
- 家具 (6)
- 家電 (36)
- 小説 (7)
- 就活 (30)
- 就職 (10)
- 就職活動 (14)
- 広告 (27)
- 建築 (16)
- 引越し (8)
- 心理 (44)
- 思考 (13)
- 情報 (17)
- 批判 (6)
- 技術 (26)
- 掃除 (7)
- 放射線 (9)
- 放射能 (14)
- 政治 (42)
- 文化 (19)
- 文章 (16)
- 新しい地図 (37)
- 新聞 (9)
- 旅行 (25)
- 旅行用ネタ (15)
- 日本 (37)
- 日本語 (20)
- 東京 (37)
- 東京電力 (31)
- 東日本大震災 (214)
- 検索 (19)
- 検索エンジン (7)
- 横浜 (6)
- 歴史 (11)
- 水冷 (6)
- 法律 (23)
- 津波 (8)
- 流行 (7)
- 海外 (30)
- 災害 (114)
- 炎上 (18)
- 無料 (21)
- 無線LAN (22)
- 爆発 (6)
- 犯罪 (7)
- 生物 (13)
- 産経 (8)
- 男女 (13)
- 画像 (38)
- 知識 (9)
- 福島原発 (12)
- 科学 (19)
- 税金 (8)
- 素材 (22)
- 経済 (29)
- 結婚 (8)
- 統計 (9)
- 美容 (9)
- 考え方 (118)
- 考察 (38)
- 育児 (23)
- 自作PC (91)
- 自然 (11)
- 芸能 (27)
- 英会話 (6)
- 英語 (16)
- 英語学習 (20)
- 萌え (6)
- 虚構新聞 (18)
- 行政 (18)
- 表現の自由 (12)
- 表現規制 (28)
- 要はてブコメ確認 (8)
- 観光 (9)
- 解説 (8)
- 言葉 (17)
- 言語 (17)
- 設定 (8)
- 話題 (11)
- 話題ネタ (1013)
- 話題用→ブレイク (129)
- 話題用→結(オチ) (21)
- 話題用まとめ (80)
- 話題用まとめサイト (10)
- 話題用ニュース (276)
- 語学 (10)
- 読み物 (65)
- 調査 (8)
- 警察 (10)
- 資料 (37)
- 軍事 (6)
- 転職 (15)
- 選挙 (13)
- 配色 (9)
- 鉄道 (9)
- 障害 (15)
- 雑学 (112)
- 非実在青少年 (6)
- 音楽制作 (8)
- 風景 (9)
- 食 (11)
- 鹿児島 (6)
- 話題ネタ (1013)
- news (584)
- まとめ (496)
- business (417)
- life (398)
- society (363)
- これはすごい (357)
- Togetter (310)
- 話題用ニュース (276)
- webサービス (255)
関連タグで絞り込む (136)
- amazon
- Android
- anime
- art
- Art
- brain
- business
- buzzfeed
- B級グルメ
- cooking
- design
- DPZ
- drink
- fo
- Food
- gadget
- game
- GIGAZINE
- gigazine
- Gizmodo Japan
- health
- image
- ITMedia
- Life
- life
- lifehack
- Lifehack
- LifeHacker
- Marketing
- medical
- movie
- naverまとめ
- news
- NHK
- photo
- R25
- recipe
- science
- shopping
- society
- sweets
- Togetter
- togetter
- travel
- webサービス
- wikipedia
- work
- うどん
- おやつ
- お土産
- お役立ち
- お菓子
- これはすごい
- これはひどい
- これはほしい
- これはめずらしい
- これはステキ
- これは便利
- これは大切
- これは欲しい
- ねとらぼ
- はじまりの応援
- はてな
- まとめ
- らき☆すた
- らばQ
- アイス
- アメリカ
- インスタント食品
- エイプリルフール
- オフ用プレゼント候補
- カップ麺
- キャンペーン
- グルーポン
- コンビニ
- コーヒー
- スイーツ
- スターバックス
- ダイエット
- ツンデレ
- デイリーポータルZ
- デザート
- ドミノ・ピザ
- ニコニコ動画
- ネタ
- ファーストフード
- フレンチトースト
- プレゼント
- ポン・デ・リング
- マクドナルド
- マナー
- マンガ
- レシピ
- レンジ
- 一人暮らし
- 事件
- 原発
- 地方
- 外国人
- 家事
- 家電
- 掃除
- 文化
- 料理
- 旅行
- 旅行用ネタ
- 日本
- 日本語
- 東京
- 横浜
- 歴史
- 生物
- 画像
- 社会
- 科学
- 育児
- 菓子
- 衣食住
- 話題になるプレゼント
- 話題ネタ
- 話題用→ブレイク
- 話題用まとめ
- 話題用まとめサイト
- 話題用ニュース
- 買い物
- 資料
- 酒
- 雑学
- 静岡
- 食
- 食べてみたい
- 食べ物
- 食べ物メーカー
- 食事
- 飲み物
- 飲料
foodに関するkulurelのブックマーク (117)
-
 kulurel 2019/06/05
kulurel 2019/06/05- 社会
- これはひどい
- food
リンク -
ハンバーガーの絵文字は正しい? フレッシュネスに聞いた - 週刊アスキー
ハンバーガー絵文字問題、まさかの進展 絵文字専門サイトの「Emojipedia」は11月28日(現地時間)、公式ブログに「Google Fixes Burger Emoji」(グーグルがハンバーガーの絵文字を修正)なる記事を公開しました。 Emojipediaによれば、Android 8.1の開発者プレビュー版にて、「ハンバーガー」の絵文字が“修正”されていたことが確認できたそうです(関連記事)。 そもそも「ハンバーガーの絵文字はチーズの位置がおかしい」という問題は、しばしばネット上で議論(?)されてきたようですが、10月28日にフリーライターのトーマス・ベークダル氏が投稿したツイートがきっかけとなり、Twitterではちょっとした論争が巻き起こりました。 ベークダル氏は「われわれはグーグルのハンバーガーの絵文字がどうしてチーズをパティの下にしているのか、議論すべきだと思う。アップルはパテ

-
「唐揚げ万能説」を大手が実践 香港KFC、爆発シーンをチキンで表現する広告を展開
香港のKFCが、チキンを爆発に見立てた広告を展開しています。スペースシャトル発射時の煙も、ヒーロー登場シーンの爆煙も、全部チキン。 広告会社Ogilvy Hong Kongが制作した「Hot&Spicy」キャンペーンの広告。チキンの配列とライティングの工夫で、見事に爆発シーンを表現しています。ゴツゴツした衣が、実に爆煙のよう。 チキンを放出しながら飛び上がるスペースシャトル めっちゃ速そう ヒーローの登場シーンといえば、やっぱり爆発。チキンですけど 日本でも「唐揚げが爆発に見える」として、しばしば話題になるこの現象(関連記事)。広告を紹介したFacebook投稿には各国から「天才だ!」「マジで好き」「いい仕事」といったコメントが寄せられており、普遍的な話なのだと感心させられます。 画像はOgilvy Hong KongのFacebookより (沓澤真二) advertisement 関連記

-
イチゴを断面図で見せるカタログがどれもおいしそう 切り口が品種ごとにさまざまで目にも楽しい
1月15日「いちごの日」に臨み、築地市場ドットコムの公式アカウントが「イチゴの断面図カタログ Ver.04」を公開しました。イチゴの品種は外見こそ似通っていますが、断面で見ると1つ1つが全く違うんですね……! 約40の品種を「シュッとしてる/まるっこい」と「硬め/柔らかめ」の2軸でまとめたチャート。何度も更新を重ねており、今バージョンではペチカ・はるみ・恋みのり・なつあかり・寒紅いちごの5種類が追加されています。図には「ヘタのほうから食べるとより甘く感じられる」「傷みにくく輸送性に優れるイチゴが増えている」「近年は大粒な品種が人気」といった豆知識も。 切り口は外見以上に個性的(公式Twitterより) 同アカウントは以前にもリンゴの断面図カタログや、ブドウと桃の家系図を披露(関連記事)。これらを意識して店頭を見ると、買い物が楽しくなりそうです。 蜜の入り具合がよく分かるリンゴの断面図(公式

-
みんな納豆菌を甘く見ない方がいい - クマムシ博士のむしブロ
image from Wikipedia もしあなたが、納豆菌のことを納豆作りのために必要なだけの貧弱な菌だと考えているなら、それは納豆菌のことをみくびっていると言わざるをえない。 納豆そのものや、納豆菌から産生されるナットウキナーゼが、健康増進作用を持つと代替医療団体やテレビ局によって持ち上げられることもある。だがこれは、納豆菌たちが画策した印象操作にすぎない。 栄養補助食品として販売されるナットウキナーゼ 後述する通り、彼らは本当に恐ろしい奴らなのだ。 納豆菌の学名はバチルス・サブチリス・ナットー(Bacillus subtilis var. natto)。枯草菌のグループに属している。 家庭用に販売されている粉末状の納豆菌 こいつらは、栄養不足になると芽胞を形成する。この芽胞のスペックは半端ではない。まさに不死身ともいえる、驚異的な耐性能力があるのだ。 そのスペックとは、 ・栄養源な

-
飲料の製造工場の人『ここの職員は朝食に納豆を食べてはいけないんです…納豆菌が悪さをしますからね…』→納豆菌の恐ろしさを畳み掛けてくるTLに戦慄
納豆菌の持込みが厳禁とされている食品工場がある…その理由を調べてみると納豆菌の恐ろしさがよくわかります。 ちらいむ @chilime 納豆といえば、コカコーラの工場(のコーヒー製造エリア)にお邪魔した時に「ここの職員は朝食に納豆を食べてはいけないんです…納豆菌が悪さをしますからね…」と魔物に襲われた村のことでも思い出しているかの如き表情で語られたことを思い出します。あの、納豆菌に…納豆菌に何をされたんですか…。 2017-09-04 20:31:27 リンク Wikipedia 納豆菌 納豆菌(なっとうきん、学名: Bacillus subtilis var. natto)は、枯草菌の一種である。稲の藁に多く生息し、日本産の稲の藁1本に、ほぼ1000万個の納豆菌が芽胞の状態で付着している。最初に研究を行ったのは、1894年の矢部規矩治とされ 、桿菌1種と球菌3種を発見したが納豆菌の発見まで

-
-
世界一固いアイスを削れ! あの「あずきバー」に挑んだ無謀な玩具メーカー
井村屋の「あずきバー」は、自然なおいしさで年間2億5000万本以上を販売する、まさに国民的なアイスだ。一方で、その固さは有名。一部では“世界一固いアイス”といわれている。そのあずきバーを、あえて“削る”ことに挑戦した無謀な玩具メーカーがあった。 あずきバーは、ぜんざいと同じ材料だけを使い、アイスを柔らかくする添加剤を一切使用していない。しかも食物繊維たっぷりの小豆をぎっしりと詰め込んでおり、空気の泡が少ないためにさらに固くなる。「わざと固くしたわけではなく、おいしさを追求した結果、固くなった」(井村屋) “固い”よりむしろ“硬い”と書いたほうが適切に思えるほど固いあずきバー。そのあずきバーをあえて削り、ふわふわのかき氷にすることに挑戦したのがタカラトミーアーツだった。同社は市販のお菓子に手を加えて楽しむクッキングトイ「おかしなシリーズ」を展開しており、「おかしなカキ氷 ガリガリ君」などアイ

-
「カニミソ」はカニの何なのか?
「カニミソ」をご存じでしょうか。 ご承知の通りと思います。質問を変えましょう。 「カニミソが何であるか」をご存じでしょうか。 あの濃厚なおいしさを思い出せても、その正体は知らない、という方が多いのでは。 臨時収入をカニミソ缶に変換し、いそいそとスプーンを用意したところで僕は、ふと先の疑問を思い付きました。カニミソって何だ? 脳ミソか? 僕は何を食べようとしているのだ? 早速缶の原材料表示を見ると、「ずわいがにかにみそ」と書いてあり、つまりカニミソはカニミソでした。深夜1人ぼっちで味わうには、カニミソは難しすぎました。 カニミソはカニの何なのか――。早速調べて発表になだれ込んでもいいのですが、僕には脳ミソがあるので、調査結果を楽しむべく、まず仮説を立てることにしました。 思うに、カニミソが脳ミソである可能性は低い。カニがあれほどの量の脳を持っているなら、カニはもっと知能が高いと考えられるから

-
すごいものが生まれてしまった…… かわいいクマのパンを作ろうとした結果、なにかの集合体が錬成される
かわいいクマのパンを作ろうとした結果がTwitterで話題になっています。すごいものが錬成されてしまった。 何でそうなった 目指していた理想は「仲良く隣り合って座るクマたちのパン」ですが、現実でできたのは「クマだったものが合体して膨張した何かのパン」でした。取りあえずといった感じで丸い部分に顔がいくつも描かれているその姿に、なんとも言えない気持ちになります。クマは犠牲になったのだ……。 なんともかわいい見た目のパンができるはずが…… 正体の知れない集合物体的な見た目に 投稿したのはまたじさん(@beppumataji)さんで、手作り料理のコミュニティーサイト「ペコリ」で紹介されている“クマの3Dちぎりパン”を参考に奥さんが作成。「賢者の石を作りおった」と奥さんの大錬金術師っぷりを投稿していますが、味はかなりおいしかったとのことです。 ちなみに“クマの3Dちぎりパン”の作り方は、強力粉と砂糖

-
「これ私食べれた!」数年ぶりのトーストに大感激 小麦アレルギーでも食べられる”米粉パン”に喜びの声
「小麦アレルギー用の食パン!! これ、これ私食べれた!!! 数年ぶりにトーストのパンが食べられた!!! うれしい!!!」――。 喜びいっぱいのツイートを投稿したのは、漫画家の櫻日和鮎実さん(@ayuneo)。小麦アレルギーでも食べられる、米粉100%の「新潟産コシヒカリパン」を紹介するツイートがTwitterで話題になっています。数年ぶりに食べたトーストのおいしさがこちらにまで伝わってくるような文章で、フォロワーからは「よかったね~!」「釣られて無関係な私もお礼メール送りそうだわwww」といった声も寄せられていました。 あまりにうれしそうだったので、編集部では櫻日和さんに詳しくお話をうかがいました。 話題になっていた「新潟産コシヒカリパン」(画像提供:櫻日和鮎実さん) 櫻日和さんが小麦アレルギーを発症したのは数年前。当時ニュースでも大きく取り上げられた「茶のしずく石鹸」騒動の時でした。 「

-
-
カップ麺業界の暴走が止まらない 今度はマルちゃんから「甘ーいきつねうどん」爆誕
東洋水産は1月10日、カップ入り即席麺「マルちゃん 甘ーいきつねうどん」を1月23日より、期間限定で販売すると発表しました。価格は1個180円(税別)。発表資料によれば、「バレンタインのプレゼントにもぴったりな一品として、消費者にアピールして参ります」とのこと。 パッケージもバレンタインを意識? 味は「赤いきつね」をベースにしつつ、特製の液体つゆを加え、甘い味付けに仕上げた「淡口しょうゆ仕立て」。パッケージにもリボンをあしらうなど、バレンタインをイメージさせる、かわいらしいデザインになっています。 明星の「一平ちゃん夜店の焼そば チョコソース」(関連記事)や、ペヤングの「チョコレートやきそばギリ」(関連記事)など、ここのところ妙な盛り上がりを見せている「甘いカップ麺」業界に、とうとう東洋水産まで参戦した格好。果たしてこのブームはいつまで続くのか……。 商品の特徴と詳細 関連キーワード うど

-
-
「スプーンとフォークでくるくる?」「乾燥麺のほうが太りにくい?」 日本パスタ協会、日本人にありがちな誤解を発表
日本パスタ協会が、20~50代の男女約2800人を対象に、日本人が抱いているパスタへの誤解について調査したことを発表しました。生麺より乾燥麺のほうが太りにくいなんて話あったんだ! 知らんかった…… 全体の約36%が間違えていたのは「乾燥パスタは製造直後の新しい方がおいしい」という項目。実際には時間経過とともに熟成するため、むしろ食感が良くなります。さらに、40%以上が「乾燥パスタよりも、手打ちや生パスタのほうが健康増進に有効」という認識を持っていましたが、これも誤りだそう。 そもそも乾燥麺と生麺は原料が異なり、乾燥麺には糖質のほか、タンパク質やビタミンB群、鉄分などエネルギー代謝に必要な栄養素を含むデュラムセモリナという小麦粉が使用されています。また、消化吸収がゆっくりと進み、インスリンの分泌を抑えられるため、肥満防止効果があります。 パスタが持つ健康への効果は、女性の方が誤解が多いという

-
激突!「リッツ」vs「ルヴァン」攻防戦の行方
9月12日、モンデリーズ社製のクラッカー・リッツが店頭に並び始めた――。 リッツといえば、46年間に渡って山崎製パンの子会社・ヤマザキ・ナビスコがライセンス製造・販売を行ってきたブランドである。だが、本家モンデリーズ社の日本法人が自社製造・販売に切り替える方針を打ち出したため、ヤマザキ・ナビスコは8月末でリッツの生産を終了。9月1日からは社名をヤマザキビスケットに変更し、後継商品となるルヴァンの製造・販売を開始している。 まだ流通在庫が残っているためか、小売店側もさすがに新・旧製品を並べて陳列するということはしないらしい。一部の小売店舗ではヤマザキ製のリッツが売られているが、大手の量販店やコンビニでは、ほぼモンデリーズ社製の製品に入れ替わっている。 ヤマザキ製に熱烈なファンも ライセンス契約終了の対象にはリッツのほか、プレミアムクラッカーやオレオも含まれている。ヤマザキ製には熱烈なファンも

-
なぜ人は「マグロ」を食べても「サーモン」に感じるのか 大学教授が分析
なぜ人は「マグロ」を食べても「サーモン」に感じるのか 大学教授が分析:水曜インタビュー劇場(パキッ公演)(1/7 ページ) 森永製菓のアイス「パキシエル」が売れている。2013年に発売して、3年間で売上高を約2.5倍(2013年度比=100%として)に伸ばしているのだ。とはいえ、ガリガリ君やハーゲンダッツといったビッグブランドではないので、「ん? パキシエル? 聞いたこともないし、食べたこともないなあ」という人もいるだろう。 マルチパックとして発売しているパキシエルの最大の特徴は、先端部分のチョコが分厚いので、歯ごたえを楽しむことができること。チョコでアイスを包む製法によって「厚さ7ミリ」を実現しているのだ。 前回、森永製菓の担当者(川崎翔太さん、山本愛さん)にパキシエルの開発秘話を聞いた。次に、なぜ売れているのかを聞いたところ、担当者も十分に把握できていなかったので、五感情報工学が専門の

-
食べるまでわずか2分。「水漬けパスタ」の作り方 | ライフハッカー・ジャパン
パスタ料理は自炊料理の定番と言っても過言ではないほど手軽で簡単な料理の1つです。パスタを茹でてソースと絡めるだけで出来上がるので、週に何度もパスタを作る方も多いかもしれません。 ところで、パスタを作る時間を劇的に短縮できる方法をご存知ですか? 簡単だけど茹でる工程が面倒なパスタ料理 これから気温の高い時期に入ってくると火を使うキッチンが暑くて、自炊をする気がなくなります。 またパスタを茹でるには、お湯を沸かすのにまず5〜10分かかり、さらにそこからパスタを茹でるのに5〜10分かかるので、仕事で疲れたときなどにはたったそれだけの時間でも面倒です。 茹でる工程をカット&もちもちで美味しい「水漬けパスタ」がおすすめ そこでおすすめなのが今話題になっている「水漬けパスタ」という調理法がです。その名の通り、パスタを熱湯でゆでる代わりに「水に漬ける」という手法です。 「そんな方法で食べられるものができ

-
-
食レポーターが「旨い」「甘い」「白いご飯がほしい」「やわらかい」しか言わないのは、なぜか?(佐藤達夫) - エキスパート - Yahoo!ニュース
■「しょっぱい物」と「やわらかい物」も万人がおいしいと感ずる前回の投稿では『私たち(ヒト)は、体(健康)にとって必要な栄養素を「おいしい」と感ずるように進化してきたので、本能のままに食べていれば栄養バランスを保てる』と書いた(ただし「食べすぎないこと」と「野菜不足にならないこと」を肝に銘ずれば、だが)。 http://bylines.news.yahoo.co.jp/satotatsuo/20150720-00047720/ つまり多くの人は、タンパク質と糖質と脂質の3つを含んである食べ物を「おいしい」と感ずる。実はこの3つ以外にも、多くの人が「おいしい」と感ずる物が2つある。それは「食塩」と「やわらかい食べ物」だ。 食塩(中のナトリウム)は、ヒトの体液(血液や細胞液)濃度のコントロールに欠かせない。食塩が不足すると、体液がコントロールできずにヒトは生存が敵わない。食塩を絶やしてはならない
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く