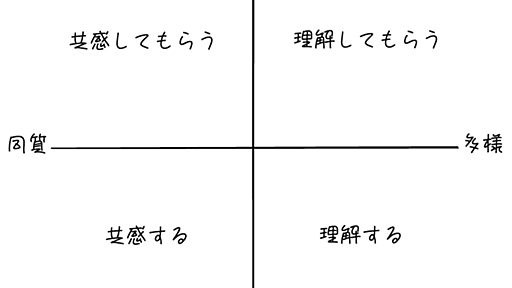ぼくはAmazonのシアトル本社でセールの機能を開発している。Amazonでお買い物をしていると「30%引き」や「20%オフ」のようなディスカウントを発見して喜んでくださっている方もいると思うけれど、あのディスカウントを提供する仕組み自体が一つの大きなプロダクト(システムと言ってもいいかな)になっている。そしてそれを支えるためにシアトル、バンクーバー、ベルリン、バンガロールにまたがるグローバルなチームによって開発・管理している。 そんなわけでぼくはPM (プロダクト・マネージャー) として日々セール機能に関するプロジェクトを回している。たくさんの刺激的で興味深いプロジェクトに恵まれてきたわけだけど、その中で一つとても記憶に残るプロジェクトがあった。 それは「定期おトク便」に関するものだ。定期おトク便というのは、平たくいうと日頃からリピートして買う商品(例えば飲料水や洗剤のような日用品)につ