私たちが見ているこの宇宙以外にも無数の宇宙が存在し、今も次々と生まれている。宇宙は単一のユニバースではなく、多数の宇宙が存在する「マルチバース」だ──。一見SFのようだが、多くの理論物理学者たちが真剣に考え、研究している理論だ。最近マルチバースについての新たな見方を提唱した米カリフォルニア大学バークレー校の野村泰紀教授に、この理論について聞いた。──マルチバースの理論はどのようにして出てきたので

私たちが見ているこの宇宙以外にも無数の宇宙が存在し、今も次々と生まれている。宇宙は単一のユニバースではなく、多数の宇宙が存在する「マルチバース」だ──。一見SFのようだが、多くの理論物理学者たちが真剣に考え、研究している理論だ。最近マルチバースについての新たな見方を提唱した米カリフォルニア大学バークレー校の野村泰紀教授に、この理論について聞いた。──マルチバースの理論はどのようにして出てきたので


将来火星を人類が居住できる環境にするため、火星と太陽の間に人工的な磁場を発生させ、太陽風を防ぐことで火星の周囲に大気層を作る――。そんな大胆な計画を、米航空宇宙局(NASA)の科学者らがこのほど提案した。 太陽風を防ぐとなぜ環境が改善するのか NASAは2月27日から3月1日にかけて、「惑星科学ビジョン2050」と題したワークショップを開催。火星の環境を改善する計画(PDF)はこのなかで提案された。 火星には現在ごく薄い大気しか存在しないが、かつて液体の海に覆われていたと考えられ、地表の一部や地下には大量の氷があることがこれまでの調査でわかっている。 太陽から放射される太陽風には高エネルギーの粒子が含まれ、強い浸食作用により火星の地表で蒸発した水蒸気を吹き飛ばしてしまう。この太陽風を人工磁場でさえぎることができれば、大気の損失が止まり、シミュレーションによると数年のうちに気圧が地球の半分ほ

天の川銀河の中心方向を近赤外線で観測したところ、29個のケフェイド変光星が見つかり、その多くが銀河中心から8000光年以上離れたところに存在していることが明らかにされた。銀河中心の領域には、誕生から3億年程度以内の若い星がほとんどない「すき間」が存在しているようだ。 【2016年8月3日 東京大学】 天の川銀河の基本的な形は、天体までの距離を測定することによって調べられている。しかしこの方法は万能ではなく、特に銀河の円盤部分では、大量に分布する星間空間の塵の影響のために多くの領域で星の分布がまだわかっていない。 東京大学理学系研究科の松永典之さんたちの国際共同研究チームは、「ケフェイド(セファイドなどとも言う)変光星」というタイプの天体を塵の影響が比較的小さい近赤外線で観測することにより、これまで塵に隠されていた銀河中心領域の星の分布を探った。このタイプの変光星は変光周期と星の真の明るさに

小さな冥王星には大きなハートマークがついている。ニューホライズンズが撮影した高解像度カラー画像(PHOTOGRAPH BY NASA/JHUAPL/SWRI) 1930年の発見以来、人類は数十億キロのかなたにある冥王星に魅せられてきた。 そして1年前の2015年7月14日、NASAの無人探査機ニューホライズンズが冥王星への接近通過に成功し、私たちはその姿を初めて間近から見ることになった。 小さな冥王星の横を探査機が通過するのに要した時間はわずか3分だったが、冥王星と、その巨大な衛星カロン、4つの小さな衛星ステュクス、ニクス、ヒドラ、ケルベロスを擁する冥王星系全体は、もっと長く、じっくりと観察することができた。(参考記事:「冥王星“接近通過”をめぐる10の疑問に答える」) その際に収集されたデータは、今でも科学者を驚かせ、当惑させているが、冥王星は巷ではすっかり人気者となり、1991年に米国

火星のゲール・クレーターで調査を続けている探査車「キュリオシティ」が鱗珪石という鉱物を発見した。火星では起こらなかったと考えられている高温の火山活動で作られるはずの鉱物が存在するということは、火星の歴史を考え直す必要があるのかもしれない。 【2016年6月27日 NASA】 NASAの火星探査車「キュリオシティ」は2012年8月に火星に着陸し、移動しながら火星の調査を行っている。 昨年7月、ゲール・クレーター内の「バックスキン」と名付けられた場所で堆積岩を掘り、採取したサンプルを分析したところ、鱗珪石(りんけいせき、トリディマイト)という鉱物が見つかった。 昨年8月に撮影されたキュリオシティのセルフィー(自分撮り)。中央下の白い部分は岩を掘ってできた粉(提供:NASA/JPL-Caltech/MSSS) 鱗珪石は珪質火山活動という爆発的なプロセスの高温環境で作られるもので、地球では鹿児島県

この赤く光る雲、綺麗だけどなんか不思議な感じですよね。この不思議の正体は雲の後ろに隠れているんです。 ヨーロッパ南天天文台が発表した1万2千光年先にある赤い雲 (RCW 106))の画像。天文学者のみなさんがこの赤い雲をよーく見てみると実はこれ、ただの雲だけじゃなかったんです。星雲の中にあるものすごい分厚い雲のうしろにだけに形成される巨大な星たちが隠れていたんです。その大きさ太陽の数倍! この星がものすごく大きくて明るいのにも関わらず、雲がとても分厚いため私たちが見えるのは、モヤから射すぼんやりした光だけです。この巨大なO型星は300万に1つのとっても珍しい星で、しかも短命。科学者たちは、こんなに大きな星がどうやって未だに持ちこたえているか不思議でたまらないそうです。今回こうしてやっと赤く輝く雲RCW 106のうしろにO型星が確認されたわけですが、研究者たちはこの巨大で不思議な星についてさ

Caltech researchers have found evidence of a giant planet tracing a bizarre, highly elongated orbit in the outer solar system. The object, which the researchers have nicknamed Planet Nine, has a mass about 10 times that of Earth and orbits about 20 times farther from the sun on average than does Neptune (which orbits the sun at an average distance of 2.8 billion miles). In fact, it would take this

惑星 水星 29日に東方最大離角となりますが、日の入り30分後の西の空での高度が10度に達しないため、観察は難しいかもしれません。下旬の明るさはマイナス0.6等~マイナス0.4等。 金星 日の出前の南東の空で明るく輝いており、たいへん目立ちます。月末に向かって、徐々に高度を下げていきます。明るさはマイナス4.2等~マイナス4.1等。 火星 おとめ座にあり、金星と木星の間に位置しています。日の出前に南東の空のやや高い位置に見えます。明るさは1.5等から1.3等。 木星 しし座にあります。夜半頃に東の地平線から昇り、日の出前には南の空に見えます。明るさはマイナス2.0等~マイナス2.2等。 土星 上旬、中旬は見かけ上太陽に近いため見ることができませんが、下旬になると日の出前の南東の空に姿を現すようになります。下旬の明るさは0.5等。 参照:暦計算室ウェブサイト 「今日のほしぞら」では、代表的な
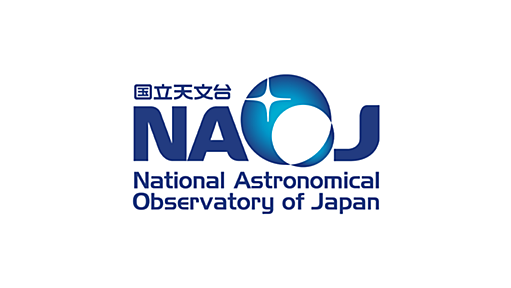
宇宙開発競争の時代にソ連で作られていた、レトロかわいいピンバッジたち2015.12.28 11:005,295 たもり その昔、ピンバッジを服につけることが流行ったときがありました。宇宙開発競走のさなかのソビエト連邦では、宇宙開発の偉業を記念したピンバッジがとても人気で、種類も幅広く、誰もがこぞって買っては誇らしげにつけていたそうですよ。 そんな宇宙開発競争時代のピンバッジの数々を米GizmodoのAttila Nagy記者が披露してくれました。ソ連の宇宙開発の歴史に残る宇宙船や衛星を描いた26個のピンバッジは渋かったり、カラフルだったりと見ていて飽きません。 USSR(ソビエト社会主義共和国連邦) コスモス(年代不明) ルナ2号 月へのミッション(1959年) ルナ1号 月へのミッション(1959年) ボストーク1号(ユーリイ・ガガーリン)(1961年) ソユーズ6号、7号、8号による合

ヨーロッパ南天天文台の望遠鏡「VISTA」による天の川銀河の観測で、これまで知られていなかった円盤状に集まる若い星が発見された。銀河中心のバルジに存在する厚い塵の雲に隠されていたのだが、赤外線で塵を見通すことによって見つかったものだ。 【2015年11月4日 ヨーロッパ南天天文台】 「VVV(Vista Variables in the Vía Láctea)」は、ヨーロッパ南天天文台(ESO)のパラナル観測所にある可視光線・赤外線望遠鏡VISTAを使って天の川銀河の中心部を赤外線で観測するサーベイで、このプロジェクトによって変光星や星団など多くの新天体が発見されている。 チリのカトリカ・デ・チリ大学のIstvan Dékányさんが率いる研究チームでは、VVVサーベイによる2010年から2014年のデータを使って、これまで知られていなかった天の川銀河の構成要素と言える若い星の集まりを発見

大マゼラン雲に存在するタランチュラ星雲中の連星VFTS 352を観測したところ、2つの若い星は互いの表面が接触していることがわかった。最終的には1つの巨大な星になるかブラックホール連星になるかもしれないという。 【2015年10月27日 ヨーロッパ南天天文台】 16万光年彼方の矮小銀河である大マゼラン雲には、タランチュラ星雲という巨大な散光星雲(星形成領域)が存在する。その中に位置する連星系VFTS 352では、2つの高温で明るい大質量星が互いの周りをたった1日ほどで回っている。2つの星は中心同士が1200万km離れているが、その表面は接近しているため、つながっている。 VFTS 352の想像図(提供:ESO/L. Calçada) VFTS 352の質量は合計で太陽の57倍もあり、表面温度は摂氏4万度だ。質量も表面温度も、VFTS 352のような「過剰接触連星」のなかで記録的なものである

この画像を大きなサイズで見る ほぼ30年間も謎だった土星の北極を取り囲む六角形の渦巻きの謎がついに解き明かされた。 土星の北極では、全幅32,187kmに広がる奇妙な六角形構造が土星の自転周期とほぼ同じ速度で回転している。これまでその原因は不明であったが、米ニューメキシコ州ソコロにあるニューメキシコ工科大学の惑星学者ラウル・モラレス=フベリアス教授の最新の研究によって、雲のある大気層で極周囲を東へと吹くジェット気流が、その下に流れる風に押されて六角形になることが判明した。 原因はジェットストリーム 研究チームは、土星北半球の高密度の大気をコンピューターでモデル化し、高度毎の風の挙動をシミュレートした。その結果、大気上層で不安定になっているジェットが曲がりくねって釣り合うことが確認された。その姿は、土星北極を覆う六角形構造の形態と位相速度をよく再現していたという。 この画像を大きなサイズで見

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く