SEO担当者のみんな!スゴいぞこれ!! キーワード提案ツール『Ubersuggest』がChrome拡張機能をリリースしたんだけど、キーワード検索するだけで欲しい情報が一気に手に入る……! 詳しくは画像を見てほしい。 SEO関… https://t.co/yyUPStKtR1


「SEO に強い HTML の書き方」というツイートがそこそこバズっていて、その内容に対して駆け出しエンジニアの方たちが「参考になった」などと称賛の声を挙げていたのを見かけて思うところがあったのでこの記事を書きました。 元ツイの概要は次の通り。 body > main > article > sectionに h1は 1 ページに 1 つ(要キーワード) 見出しタグは毎度 section で囲む ヘッダーメニューは nav で囲む 画像に適切な alt を設定する title / description を書く 階層を意識して書く div はあまり使わない 画像は p で囲む この記事は元ツイおよび元ツイの投稿者を批判する意図で書いたものではなく、あくまで挙げられている内容に対する個人的見解をまとめたものです。 正しいか正しくないかをそれぞれの項目のはじめに書いていますが、あくまで僕個人の

俺はウェブマーケをやってた。ガチガチのSEOをやっていたんだがもうそんなSEOな毎日に疲れきった。 都会から離れて実家のあるちょっと田舎でSEOとは無縁のリアルな商売をすることに決めた。 だから俺の手法を公開する。 今のグーグルならこれで簡単にだれでも検索上位をとることができる。簡単すぎる。俺が担当していた会社も今 この手法を使えば余裕なのだ。グーグルははっきりいってバカだ。 俺にはもう関係無い世界だから公開する。 まず確実にキーになるのは、中古ドメインだ。 これで9割が決まる。 いい中古ドメインを見つけるのが本当に難しい。それを探すのに力を入れろ。 良質な中古ドメインを見つけたら絶対に買え。高くても買え。 新規で参入するならもうその方法しかない。 でその良質な中古ドメインとはなんなのか。 それは年数が古く(1990~2010年ぐらいまでのがいい)被リンクがたっぷりついているドメインだ。

こんにちは、ユレオです。 数多くのブログがある中、当ブログ「魂を揺さぶるヨ!」を閲覧いただきありがとうございます。 本日この記事を読むために訪れた方はブログを始められたばかりの方か、ブログを始めてみたがGoogleアナリティクスをあまり利用されておらず、使い方を確かめたい方ではないでしょうか。 Googleアナリティクスを始めるには覚えることが多いですが、すべての機能を覚えないといけないわけではありません。 必要最低限の「これだけ覚えておけば便利に使える」という機能があり、それらを覚えた後に必要であればもっと深く勉強するというのが効率的かと思います。 そういった方のために、本日は「初心者の為のGoogleアナリティクスを図解で説明した完全マニュアル」として詳しく説明していきたいと思います。

2017年6月2日に当サイト『クレジットカードの読みもの』のサイトURLを独自ドメインに切り替えてから、約3ヶ月半が経過。 独自ドメインに切り替えた経緯と、その後の悲惨さについては下記記事で書いたとおりですが、その記事執筆から3ヶ月経過した現状について、今回は記事を書いてみたいと思います。 (この記事は6月22日に執筆)サイトURLを独自ドメインに切り替えて、地獄をみた話。はてなブログのサイト運営歴が長い方は、独自ドメインにしないほうが無難です。 その後のアクセス推移がどうなったのか気になる方は是非、参考にしてみてくださいね。 アクセス数は残念ながら戻らないまま: まず、結論から先にいってしまうと、独自ドメイン移転から3ヶ月半経過した現在でもアクセス数はほとんど戻っていません。 まぁ厳密にいうと「底」からは30~40%ほどアクセス数が回復したものの、未だにはてなブログドメインを利用していた

何度かボヤいていましたが、はてなダイアリーからはてなブログに移行し独自ドメインを割り当ててから検索流入が激減しました。日に500〜1,000近くあった検索流入が100以下といった激減っぷりです。移行したのが2014年3月前後で、下記のグラフのようにストンと落ちて地を這っていました。それが最近復活したようです。 ドメインオーソリティの低下ではなく、SEOスパム扱いのペナルティだった 検索の減少の原因について、単純にドメインオーソリティの低下と考えていました。というのは、ドメインとしての非常に評価の高いhatena.ne.jpから新設のドメインの移行、さらに今までの被リンクもリダイレクトされるということで、SEO的には不利になります。といっても6〜7割くらいに落ち込む程度だろうと高をくくってたのですが。蓋をあけると1〜2割まで落ち込むという結果でした。当然、何らかのペナルティの可能性も考えて、

当サイト『クレジットカードの読みもの』では、2017年6月2日にサイトドメインをはてなブログドメインから独自ドメイン(cardmics.com)に変更をしました。 独自ドメインに切り替えをした目的としては下記記事の通り。将来に対する投資と、更なるアクセスアップを狙ってのものとなります。 私が『クレジットカードの読みもの』のURLを、独自ドメインに移行させた3つの理由まとめ!2017年5月のアクセス数報告とともに。 独自ドメイン移行後のアクセス数がボロボロ: では、気になる独自ドメイン切り替え後のアクセス推移は下記の通り。 ちょっと長期になりすぎて見難いので、5月30日からのグラフのみを抜粋するとこんな感じになります。 まぁ、見事なまでにアクセス数は急降下。 6月21日付けのアクセス数についても3万3,688ページビューしかない状況なので、ざっくり、従来の1/3しかアクセスが稼げていない状況


こんにちは、えむしです。 この前のニンテンドースイッチの記事が久しぶりにスマートニュースに載った(えむふじんじゃなくて、僕の方が書いた記事が)ので、スマニュー覗いてたんですよ。 で、こちらの記事を見つけました。 はじめに バックリンクを否認する 対策用の.txtファイルを制作しアップロードする リンク否認のテキスト制作方法 : MacOS 著作権侵害による削除を申し立てる 今回の作業の為に参考にさせてもらったサイト 最後に はじめに www.izuremo.com うわあ、これは大変だなあ・・・。 2月の1日辺りのアクセスは確かに減ったけど、激減って言う程でもないし、なんだかんだで検索でのアクセスも少しずつ伸びてるから、こう言うのはきっと無いよねー。 とか思って記事を読んでいたんですよ。 でもブコメ見てると「うちも同じ目に遭っていた」という報告も多数。 んー・・ペナルティは受けている様子は

2016年12月6日、DeNA(ディー・エヌ・エー)のキュレーション事業を取り仕切っている、執行役員の村田マリと電話がつながった。その語り口は、強気を装っているのか、いつも通りに明るかった。 医療・ヘルスケア情報サイトの「WELQ(ウェルク)」が引き金になった問題が、オンラインサイトからの無断転用や盗用、インターネットの検索結果を強引に押し上げるSEOのやり口について、すでに多くの人々を巻き込んで「大炎上」している真っただ中のことだ。 しかし本人は、メディアも会社もなかなか手が届かない、シンガポールで暮らしている。いわゆるリモート経営のスタイルだが、さすがに日本国内で膨れ上がっている批判の波を感じたのか、話していると少しずつ声のトーンが変わってくる。

DeNA WELQ と検索技術の課題 DeNA WELQ デタラメな医療健康記事を公開していた問題と、多数のライターを使ってパクリとリライトを駆使した大量のコンテンツを生成して検索結果を占拠している問題について。 公開日時:2016年12月01日 01:28 DeNA の WELQ の件で人と会う度に見解を求められるので、ざっと述べておきます。やっぱり関心高いですよね。 デタラメの医療記事とスパム的手法によるコンテンツ量産 医学についての専門知識を持たない一般ユーザーが執筆した、正確性に疑問が残る医療系記事を大量に公開し、SEO を駆使して関連するあらゆる検索クエリで検索上位に表示させていました。病気や症状について検索するユーザーを不必要に不安にしたり、生命を危険に晒すような情報は公開すべきではないでしょう。ましてや SEO を悪用してトラフィックを稼ぎ金儲けのために使っているのであれば論

ウェルク問題で盛り上がっているので、 現状インターネットメディアを自称するほとんどの会社がやっていることは、実質メディア運営ではなく、検索エンジンを占拠するビジネスである 検索エンジン占拠ビジネスにおいては、コンテンツにお金をかける、特に一記事にコストを掛けることは経済的に不合理である と考えている理由について、気分転換がてら書いていきます。 最初に断っておくと、これから書くことはメディア運営をしている一個人の感想であると同時に、メディア運営者の一人として自分も完全にブーメラン案件であり、誰が正義とか悪いとかそういうことを話したくて書くわけではありません。 よくも悪くもインターネットというのはこういう仕組みになっているので、短期的な経済的成功だけを目指すのであれば、ウェルクを始めとする昨今のキュレーションサイトのようなやり方は合理的である というの旨の話となります。 今回のウェルク炎上で比
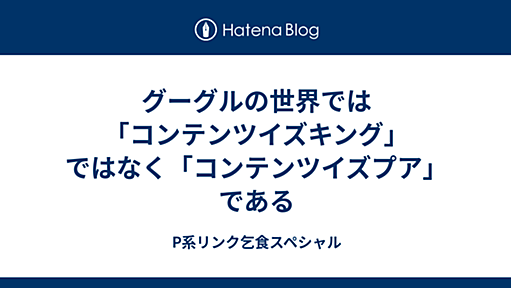
ネットに少し詳しい人ならちょっと前から「これはひどい」って評判になってるウェルク(Welq)っていう、横浜ベイスターズのオーナーであるDeNAがやってる「ココロとカラダの教科書」というキャッチフレーズの美容・健康・医療サイトのことは知ってると思います。 「死にたい」検索トップの「welq」の記事、DeNAが広告削除 「不適切」指摘受け 【DE●A】キュレーションメディアの依頼の実態を掴んだ結果マジで酷いことになってます! SEOの専門家の知識とノウハウをフル動員し、資金を投入して1日何百ページもぶっ込んで、企業モラルや順法精神を全く考えずに金儲けだけを考えれば、割と簡単に健康関係のキーワードを独占して金儲けができるというのは、SEO界隈ではみんな分かっていたことですが、それはそれ。 人の生き死にや不安につけ込んだり デマをまき散らしたり 医学の知識のない人がウソ書きまくったり パクリという
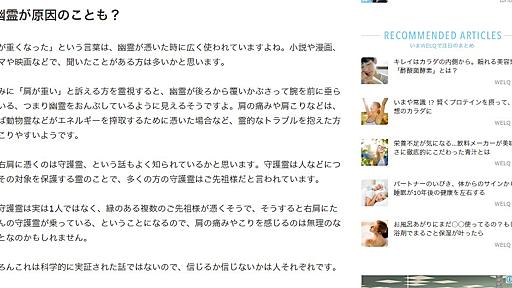

この記事には広告を含む場合があります。 記事内で紹介する商品の購入やアプリをダウンロードすることで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。 ブログをやっている皆様、amp対応していますか? ▼ ampって何?おいしいの?って人はこちらをどうぞ。 はてなブログのAMP対応に伸るか反るか ampだとアドセンスが表示されない(やる方法あるという噂もあるけど僕はできませんでした。誰か教えて)ので対応させたくないっていう人もいると思います。 僕の場合は「いろいろ問題あるけど100%やるべき」っていうのが主張なんですけど、最近アナリティクスとか見ているとなおのことやるべきだなと思っています。 今日はその辺を実例を交えつつ書いていこうかなと。 amp対応しておけばとんでもないビッグワードで上位表示できる可能性がグンと上がるよ ampをやるべきと僕が主張していた一番大きな理由は「検索結果のか

これまで、メディア企業が自社サイトやサービスにお客さんを誘導する際に、まず最初に対策することとしてSEOがありました。しかし、ここ数年で集客方法も徐々に変わってきており、分散型メディアに代表されるような、各ソーシャルメディアを主な集客メディアとして捉えるようになってきています。 そしてメディア企業の中ではその考え方がより強まり、今では”SEO”ではなく”FBO”(Face Book Optimization=Facebook最適化)を念頭にコンテンツを制作・配信するところが増えてきています。 そこで今回はFBOという考え方が出てきた経緯やすでに対応している企業の事例をご紹介します。 目次 FacebookはもはやGoogleを超えた 検索しなくなった?ユーザーの環境変化 ニュースを読むのはソーシャルメディアで Facebookのアルゴリズムに対応するメディア企業 まとめ Facebookは

[対象: 中級] サーバーにアクセスしてきたクローラが本当にGooglebotかどうかを確認したいときにはIPアドレスだけを基にして判断するべきではありません。 DNSのリバース ルックアップ(逆引き参照)を用いて、そのIPアドレスがGoogleが所有するものかどうかを併せてチェックする必要があります。 SEOに慣れている人なら当然のことなのですが、IPアドレスでクローラを制御することは誰もが行う設定ではないので知らないサイト管理者も多いのではないでしょうか。 IPアドレスでGooglebotを識別しようとしたためにトラブルが発生した事例が立て続けに2件英語版のウェブマスター向け公式ヘルプフォーラムに投稿されていたので、僕のブログ読者にも知らせておくことにしました。 Googlebotが使用するIPアドレスをGoogleは公開していません。 非常に多くのIPアドレスを使用しているのとこれら

ただ、こういったものの確認にいちいちブラウザから右クリックして「ページのソースを表示」とかして、タグなど大量の文字列の中から、上記の表記などを見つけて確認するのは一苦労です。これが1ページだけならまだしも、何ページも何ページも確認するとなると、気が遠くなります。 そんなんだったら、ブラウザでページを閲覧しているときに、noindexとnofollowの状態を確認できるツールがあれば滅茶苦茶楽ですよね。と以前探してみたら、そんなツールがありました。 こういった、noindex、nofollowの状態を手軽に確認できるブラウザツールです。 noindex、nofollow確認拡張(アドオン)noindexなどを確認するツールは、Chrome拡張とFirefoxアドオンで出ています。以下でそれぞれについて説明します。 Chrome拡張「NoFollow」NoFollowは、Chromeでページを

+1 ボタン 2 AMP 11 API 3 App Indexing 8 CAPTCHA 1 Chrome 2 First Click Free 1 Google アシスタント 1 Google ニュース 1 Google プレイス 2 Javascript 1 Lighthouse 4 Merchant Center 8 NoHacked 4 PageSpeed Insights 1 reCAPTCHA v3 1 Search Console 101 speed 1 イベント 25 ウェブマスターガイドライン 57 ウェブマスタークイズ 2 ウェブマスターツール 83 ウェブマスターフォーラム 10 オートコンプリート 1 お知らせ 69 クロールとインデックス 75 サイトクリニック 4 サイトマップ 15 しごと検索 1 スマートフォン 11 セーフブラウジング 5 セキュリティ 1

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く