1. Actor とエラーハンドリング ∼Erlang 時々 Scala∼ M.Ikuta(@cooldaemon) Sep.4,2011 1
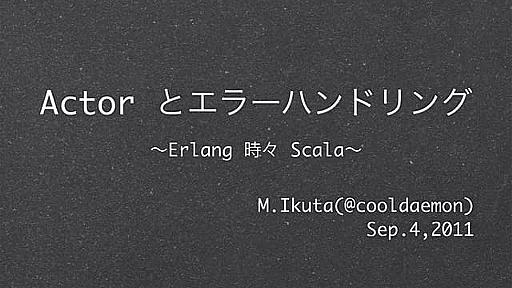

● [Scala] Webフレームワーク play scala 「play」という凄い Web フレームワークがある。何が凄いかと言うと、まずは名前だ。だって "play" だよ?検索し辛いにも程がある。この衝撃は、http load balancer の "pen" 以来だ。ググっても無駄に時間がかかるので公式サイトを載せておこう。 http://www.playframework.org/ 日常会話にも困る場合があるので、サイト名から「playframework」と呼ばれることが多い。管理者の tw 名も @playframeworkであり、hashtagも #playframework なので、play は単なるコマンド名で、こっちの方が正式名という認識でいいのかもしれない。(gem と rubygems の関係に近い) play scala で、本来 Java 用の play(fr
1階受付:インストール等 / 1階案内版:コマンド / 2階:書き方 / 3階:文と式 / 4階:関数 / 5階:オブジェクト指向 / 6階:型 / 7階:注釈等 / 屋上:言語仕様要約 / 雲:scalaパッケージ概観 / 青空:その他の付属パッケージ概観 なお、以上の解説はJavaの文法とコマンドや標準ライブラリ等を一応知っていることを前提(現行のScalaはなおJavaライブラリへの依存度が高くScalaだけで完結できる状態では無い。なお、Scalaのコンパイラ自体はJava1.4用のコードも吐けるが、標準ライブラリが多く1.5を前提としている)とし、その違いだけをとりあえずは書き留めるものである。もっぱら文法やライブラリ参照用であることを目指しているので、例や特長等は次のリンクを参照されたい(なおただし、原著者たちの配慮にもかかわらず、それらの例は関数型言語に関する事前の概要的把握
● [Scala]「Scala開眼」が凄い件 Scala の深い部分を検索すると必ずヒットするサイト 「Scala開眼」 http://www.h7.dion.ne.jp/~samwyn/Scala/scalaindex.htm が凄すぎる。この人は何者なの?文章を少し読むだけで只者じゃないことがわかる。一言にすれば天才。 Scalaへの深い理解を持ち 多方面の膨大な背景知識を武器に 圧倒的な概念の整理力と 優れたワードセンスと表現力で 体系的に形式的にScalaを説明している 特に、凡人なら10行くらいかけてグダグダ説明しそうなものを、片っ端から漢字2文字ぐらいの言葉で簡潔かつ的確に表現(説明)していくその姿には畏敬の念すら感じる。入門書だけでは「Unit型」が結局何なのか理解できずにモヤモヤとしていたのだが、このサイトには概念の理解を最優先にする姿勢が見え、誤解を恐れない直球な説明に鼻
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く