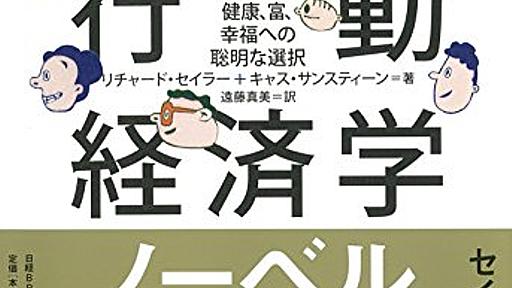きのうの松本さんの記事に関連して、私も経済学について似たような印象をもっています(経済学が科学だとすればですが)。日本の政治家も官僚も、経済学者の話を審議会や「研究会」などで聞くけど、それが政策にまったく反映されない。渡辺喜美金融担当相は「経済学の本は1冊も読んだことない」と公言していたし、3月に行なわれた「有識者会合」は見ていて寒くなりました。 これに対して欧米の経済政策を動かしているのは、バーナンキにしてもサマーズにしてもローマーにしても、超一流の経済学者です。この違いの原因は、先日の記事でも書いたように、日本の経済学者にもありますが、最大の問題は、日本の政治が政策論ではなく「政局」的な人間関係で決まるので、専門知識が役に立たないことだと思います。麻生首相の「政局より政策」という口癖が、それを逆説的に示しています。 官僚の政策立案には少しはロジックが通用しますが、彼らは学者より自分たち