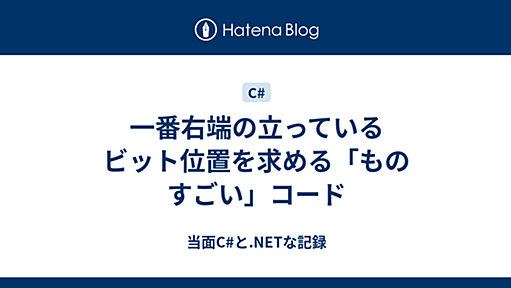タグ
- すべて
- * (454)
- .net (61)
- 1981s (3)
- 2ch (487)
- AR (2)
- AdventCalendar (1)
- COVID-19 (41)
- DIY (3)
- GAE (6)
- GTD (3)
- GitHub (4)
- PHP (3)
- SF (2)
- UI (3)
- VB (3)
- accident (17)
- accounting (25)
- actionscript (3)
- actor (2)
- addon (40)
- adult (56)
- advertising (13)
- affiliate (8)
- agile (11)
- ai (12)
- aichi (7)
- airplane (9)
- ajax (4)
- algorithm (7)
- amachang (2)
- amazon (47)
- america (11)
- an (2)
- analytics (2)
- android (8)
- animal (19)
- anime (145)
- anonymous (261)
- api (3)
- app (11)
- apple (61)
- architecture (12)
- art (66)
- auction (2)
- audio (9)
- auth (10)
- automaton (2)
- aws (3)
- bank (14)
- baseball (32)
- bath (3)
- beattakeshi (5)
- beer (2)
- bicycle (5)
- binary (3)
- birthday (2)
- blog (223)
- bluetooth (2)
- body (7)
- book (178)
- bookmark (54)
- bookmarklet (14)
- bot (3)
- bouldering (208)
- brain (22)
- bridal (3)
- browser (10)
- building (16)
- business (759)
- c# (49)
- cafe (13)
- calendar (2)
- camera (11)
- campaign (2)
- car (29)
- career (40)
- cat (3)
- chiba (2)
- child (26)
- children (3)
- china (10)
- chrome (4)
- cinema (7)
- claim (2)
- climbing (214)
- clock (2)
- cloud (11)
- cmd (6)
- code (6)
- coffee (3)
- color (6)
- column (87)
- comedy (3)
- comic (135)
- comment (2)
- commercial (18)
- communication (199)
- company (167)
- computer (19)
- convert (5)
- cooking (132)
- cookpad (5)
- copyright (18)
- cost (6)
- creative (2)
- crime (42)
- critics (10)
- css (4)
- culture (52)
- curry (7)
- cute (4)
- dance (6)
- dart (2)
- data (15)
- database (43)
- datebase (2)
- death (47)
- dental (3)
- design (84)
- desktop (6)
- development (73)
- device (4)
- dictionary (2)
- disaster (83)
- display (3)
- document (8)
- dog (4)
- download (18)
- dpz (28)
- drama (2)
- drink (7)
- dropbox (11)
- drug (5)
- dvd (3)
- dwango (4)
- earthquake (92)
- ecology (4)
- economics (61)
- economy (19)
- editor (13)
- education (127)
- electric (6)
- electronic (5)
- encode (2)
- energy (25)
- engineer (25)
- english (76)
- environment (9)
- eros (59)
- evangelion (80)
- event (131)
- evernote (23)
- exam (6)
- excel (12)
- exercise (3)
- eye (4)
- facebook (24)
- family (30)
- fashion (17)
- favorite (25)
- festival (6)
- fight (7)
- file (13)
- finance (39)
- firefox (98)
- fish (4)
- flash (14)
- font (10)
- food (254)
- football (8)
- france (2)
- freelance (5)
- freesoft (61)
- fukuoka (3)
- fukushima (2)
- future (7)
- fx (6)
- gadget (12)
- game (215)
- generator (3)
- gift (2)
- gifu (5)
- gimp (3)
- girl (6)
- glasses (6)
- godzilla (2)
- goods (11)
- google (99)
- gourmet (7)
- graph (9)
- greasemonkey (49)
- gree (9)
- grep (3)
- gym (84)
- hadoop (2)
- hair (7)
- happy (3)
- hardware (23)
- hatena (299)
- hdd (8)
- health (64)
- heartwarm (38)
- heroku (3)
- hiroshima (4)
- history (131)
- hokkaido (2)
- hold (10)
- homepage (16)
- hongkong (3)
- horror (11)
- hotel (4)
- house (64)
- html (6)
- human (7)
- hyougo (4)
- iOS (2)
- ichiro (2)
- icon (5)
- idea (27)
- idol (44)
- iis (2)
- illustration (19)
- index (6)
- india (3)
- information (3)
- instagram (5)
- install (19)
- insurance (6)
- interface (2)
- interior (12)
- international (5)
- internet (50)
- interview (249)
- investment (69)
- iot (5)
- ipad (2)
- iphone (115)
- it (232)
- japan (72)
- japanese (23)
- japanese_chess (20)
- java (8)
- javascript (72)
- jazz (2)
- jkondo (4)
- jquery (9)
- json (2)
- kagawa (5)
- kanagawa (9)
- keyboard (15)
- kochi (2)
- kumamoto (2)
- kyoto (15)
- lan (6)
- language (8)
- laugh (43)
- law (32)
- legend (2)
- license (3)
- life (560)
- lifehack (142)
- line (5)
- link (59)
- linux (13)
- list (3)
- livedoor (4)
- local (5)
- log (2)
- logic (3)
- love (31)
- lyrics (2)
- mail (30)
- malaysia (2)
- management (63)
- map (36)
- marketing (32)
- marriage (2)
- marrige (14)
- math (43)
- media (75)
- medical (67)
- memo (3)
- mental (13)
- microsoft (63)
- mind (3)
- mixi (5)
- miyagawa (3)
- mobile (32)
- money (237)
- motivation (15)
- mountain (7)
- mouse (3)
- movie (439)
- mp3 (14)
- mukaishutoku (3)
- muscle (2)
- museum (5)
- music (285)
- nagano (2)
- name (3)
- naoya (2)
- nara (31)
- nasne (2)
- nature (12)
- neta (246)
- network (19)
- news (465)
- newspaper (3)
- nhk (125)
- niconico (85)
- niigata (2)
- nintendo (19)
- note (7)
- novel (5)
- nuclear (58)
- numbergirl (8)
- oil (2)
- okayama (3)
- okinawa (13)
- olympic (6)
- oracle (6)
- os (8)
- osaka (10)
- otsune (10)
- outdoor (3)
- pairprogramming (3)
- pc (64)
- pdf (11)
- performance (18)
- perfume (15)
- perl (9)
- philosophy (5)
- phone (14)
- photo (268)
- physics (8)
- plagger (6)
- podcast (11)
- poem (2)
- police (2)
- politics (135)
- portal (4)
- present (2)
- presentation (6)
- privacy (5)
- product (3)
- programming (399)
- psychology (3)
- python (28)
- quality (2)
- question (31)
- quruli (16)
- radio (22)
- rails (5)
- rakuten (12)
- recipe (110)
- recovery (2)
- recruit (10)
- region (2)
- religion (12)
- report (31)
- research (3)
- restaurant (3)
- review (25)
- rip (26)
- robot (4)
- rock (5)
- root (2)
- rss (11)
- ruby (27)
- rule (3)
- russia (3)
- saitama (3)
- school (9)
- science (150)
- script (5)
- search (17)
- security (65)
- self (30)
- server (36)
- service (140)
- sex (12)
- shiga (2)
- shop (35)
- sier (69)
- simulation (4)
- sisha (6)
- slide (36)
- sns (14)
- soccer (31)
- social (5)
- society (194)
- softbank (18)
- software (90)
- song (23)
- space (12)
- spam (5)
- speech (23)
- sports (166)
- sql (28)
- star (3)
- station (4)
- statistics (4)
- stevejobs (3)
- storage (3)
- strategy (2)
- study (152)
- suicide (8)
- summer (3)
- sumo (2)
- system (21)
- tabacco (10)
- talent (4)
- talk (5)
- tamori (50)
- tax (13)
- technology (52)
- template (4)
- tennis (3)
- test (9)
- text (71)
- thai (2)
- thinking (44)
- tips (369)
- tochigi (2)
- togetter (94)
- toiret (3)
- tokyo (46)
- tombloo (2)
- tool (124)
- tooth (5)
- topo (2)
- train (76)
- training (16)
- translation (2)
- travel (69)
- trouble (73)
- tumblr (12)
- tv (263)
- twitter (472)
- ubuntu (10)
- udon (2)
- umedamochio (18)
- unicode (5)
- ustream (9)
- venture (18)
- vimperator (9)
- vista (3)
- vmware (2)
- vocaloid (7)
- wall (4)
- wallpaper (4)
- war (10)
- weather (6)
- web (550)
- wii (2)
- wikipedia (2)
- windows (98)
- word (38)
- work (588)
- world (10)
- xml (5)
- xpath (2)
- yahoo (38)
- yamanashi (2)
- youtube (262)
- あとで読む (5)
- business (759)
- work (588)
- life (560)
- web (550)
- 2ch (487)
- twitter (472)
- news (465)
- * (454)
- movie (439)
- programming (399)
algorithmに関するtoriaezuのブックマーク (7)
-
 toriaezu 2021/09/07
toriaezu 2021/09/07- algorithm
- ai
リンク -
一番右端の立っているビット位置を求める「ものすごい」コード - 当面C#と.NETな記録
一番右端の立っているビット位置(RightMostBit)を求めるコードで速いのないかなーと探していたら、ものっっっすごいコードに出会ってしまったのでご紹介。2ch のビット演算スレで 32bit 値のコードに出会って衝撃を受けて、その後 64bit 値版のヒントを見つけたのでコードを書いてみました。 この問題は ハッカーのたのしみ―本物のプログラマはいかにして問題を解くか (Google book search で原著 Hacker's delight が読めたのでそれで済ませた) で number of trailing zeros (ntz) として紹介されています。bit で考えたときに右側に 0 がいくつあるかを数えるもの。1 だと 0、2 だと 1、0x80 なら 7、12 なら 2 といったぐあい。0 のときに表題どおりの問題として考えるといくつを返すの?ってことになるので、
-
マルコフ連鎖による文章の自動生成 - Kentaro Kuribayashi's blog
「PEAR::Net_SmartIRC を使って、一定間隔でニュースを配信する IRC BOT を作成する」で作成したごく簡単な BOT はしかし、外部のリソースをひっぱってきて、それを単にそのまま流すことしかできません(RSS をパースする処理はあるけど、本質的には垂れ流してるだけ)。通常 IRC BOT というと、チャンネルのメンバが喋った言葉を憶え、それらをアレンジしたデータを用いて、時には当意即妙に会話に介入することもあればまるで的はずれな発言で場を微妙な雰囲気に陥れることもあるといったものですし、また、なかには日記や Blog を書くすごい BOT さんもいます。 そうなると当然、次の目標は「おしゃべりをする、あるいは日記を書く BOT を作成する」というものになるわけですが、まぁ僕の頭ではいきなりそんなことを実現することは不可能ですし、また、そのような方向で BOT を作成する
-
第 1 回 「インデックスアーキテクチャとデータアクセス方法を理解する」~ システム構築 ~
図 1-5-1 PRIMARY KEY 制約と UNIQUE KEY 制約を作成すると暗黙的にインデックスは作成される 1-6. sysindexes システムテーブルの理解 sysindexes システムテーブルはテーブルとインデックスに関する情報が格納される重要なテーブルであり、データベース内のインデックスとテーブルごとに 1 行のデータを保持します。インデックスの理解を深めるためにはsysindexesテーブルを理解することが必要です。その中でも以下の列は特に重要です。 indid 列 0 ‥ このエントリがヒープであることを示します 1 ‥ このエントリがクラスタ化インデックスであることを示します 2 ~ 250 ‥ このエントリが非クラスタ化インデックスであることを示します FirstIAM 列 indid が 0 の場合、インデックスを使わずにヒープにアクセスす

-
-
インデックスの基礎知識
■ インデックスとは データベースの世界で、インデックス(索引)とはテーブルに格納されているデータを 高速に取り出す為の仕組みを意味します。 インデックスを適切に使用することによってSQL文の応答時間が劇的に改善 される可能性があります。 インデックスにはB-Treeインデックスをはじめ、ビットマップインデックス、 関数インデックスなどの種類がありますが、ここでは最も一般的に使われ、かつ ほとんどのDBMSでサポートされているB-Treeインデックスについて解説します。 ※ CREATE INDEX文でオプションを指定しない場合は通常B-Treeインデックスが 作成されます。 ■ B-Treeインデックスのしくみ B-Tree(Balanced Tree)インデックスは次のようなツリー状の構造になっています。 ツリーの先頭はヘッダブロックと呼ばれています。ヘッダブロックでは、キー値の 範囲
-
B-Tree インデックス - オラクル・Oracleをマスターするための基本と仕組み
B-Tree インデックス (B-Tree Index) オラクルのインデックス、すなわち、デフォルト時のインデックスは B-Tree インデックス(※1) になる。 B-Tree インデックスとはバランスド・ツリーインデックスの略である(1969 年頃に既に考案されている)。プログラミングを始めたときにソートアルゴリズムやデータ構造で勉強したであろうと思う二分木 (Binary-Tree) の進化版みたいなものである。 一部のブランチが異常に成長しないように平衡を保つように再編成(バランス)する仕組みによって、常にインデックスによる検索性能を高い状態に保つことができる(※2)。 RDBMS によっては色々な種類のインデックスが存在しているが、現在においても B-Tree インデックスが多くのケースで優れたパフォーマンスを出していることには変わりないようである。 (※1) B-Tree に
-
 1
1
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く