昨日つらつらモノを考えていて、企業のM&Aを「恋」や「結婚」に例えると、いろいろ示唆があるなあ、と思いました。 昨日の日経新聞の朝刊、「広がる買収防衛策(中)」でも、「買収提案後に両社長が直接交渉したのは一回だけで、事実上の門前払いだ。」てなことが書いてあって、あたかも門前払いするほうが悪いようにも読めます。 この会社さん(買収防衛策に記載した手順を会社側が遵守しているのか?等)の個別の事例は存じませんので、一般論としてですが、 「あの、えと、僕とつきあってくれませんか。」 「・・・あなた、私のタイプじゃないから。・・・ごめんなさい。」 と言われて、 「おい、あの娘の件、どうなった?」 「オレのこと、タイプじゃないっていうから、あきらめた。」 ・・・てなことを言ってるやつがいたら、・・・おいおい、それで終わりかい!・・・とツッコミの一つも入れたくなるというもんです。 一度振られたからってそ
タグ
- すべて
- 2006 (9)
- 2ch (598)
- 3D (43)
- 801 (17)
- ArtsManagement (47)
- BI (18)
- CentralBank (119)
- DIY (11)
- Google Apps Script (17)
- PR (60)
- RTC (11)
- academy (20)
- accounting (63)
- ad (338)
- addon (22)
- administration (41)
- adobe (11)
- adsense (61)
- adwords (22)
- affiliate (106)
- africa (36)
- agri (102)
- ajax (116)
- amazon (42)
- amn (17)
- analytics (76)
- apache (27)
- api (84)
- apollo (16)
- app (91)
- apple (39)
- architecture (33)
- arimasa (18)
- art (116)
- asia (13)
- auction (14)
- baseball (27)
- biology (14)
- blog (539)
- blogパーツ (81)
- bogusnews (43)
- book (437)
- bookmarklet (15)
- bootstrap (11)
- brainstorming (12)
- branding (30)
- broadcasting (30)
- browser (30)
- business (1456)
- buzz (27)
- calendar (90)
- capitalism (13)
- career (58)
- central (10)
- cgm (117)
- chat (11)
- china (267)
- chrome (20)
- city (24)
- cm (13)
- cms (75)
- coaching (12)
- color (37)
- communication (542)
- community (44)
- company (23)
- contents (83)
- cooking (104)
- copy writing (15)
- copyright (837)
- creative (35)
- creativecommons (36)
- crime (150)
- critic (10)
- css (276)
- culture (216)
- currency (28)
- cyberspace (17)
- data (9)
- database (13)
- db (29)
- del.icio.us (14)
- design (153)
- development (119)
- dictionary (13)
- digg (15)
- diplomacy (203)
- docs (17)
- domain (28)
- download (14)
- drm (19)
- dropbox (14)
- dropshipping (25)
- drug (10)
- dtm (18)
- e-book (10)
- ec (94)
- eclipse (15)
- ecology (27)
- economics (440)
- economy (662)
- edit (11)
- editor (74)
- education (438)
- election (72)
- energy (68)
- english (101)
- environment (53)
- ero (23)
- europe (40)
- event (90)
- evernote (24)
- excel (51)
- extension (310)
- facebook (38)
- facilitation (22)
- fashion (154)
- favicon (19)
- feed (55)
- feedburner (21)
- felica (14)
- fileshare (15)
- finance (561)
- firefox (444)
- flash (74)
- flickr (52)
- fon (32)
- font (82)
- food (117)
- football (137)
- form (55)
- framework (24)
- ftp (9)
- fx (14)
- gadget (77)
- game (137)
- gamification (15)
- gender (45)
- generation (69)
- generator (103)
- geopolitics (26)
- gimp (12)
- git (12)
- github (10)
- gmail (138)
- google (478)
- google gears (10)
- google maps (39)
- google reader (27)
- google street view (19)
- google八分 (9)
- gourmet (37)
- government (397)
- graph (24)
- greasemonkey (125)
- groupon (14)
- groupware (13)
- growthhack (13)
- gtd (79)
- health (79)
- history (349)
- hosting (26)
- hr (99)
- html (82)
- icon (80)
- ide (12)
- idea (134)
- idolm@ster (23)
- ikzo (24)
- illust (32)
- illustrator (16)
- im (16)
- ime (11)
- industry (22)
- innovation (39)
- intelligence (24)
- interior (21)
- international (223)
- internet (131)
- interview (136)
- investment (166)
- ipad (25)
- iphone (148)
- it (24)
- itunes (40)
- japan (80)
- jasrac (43)
- javascript (138)
- job (99)
- jojo (37)
- joost (11)
- journalism (135)
- judgment (113)
- knowledge (26)
- korea (105)
- labor (16)
- language (15)
- last.fm (10)
- law (410)
- lawyer (12)
- ldr (19)
- library (46)
- life (514)
- lifehacks (520)
- linux (43)
- literacy (216)
- literature (51)
- livedoor (52)
- local (146)
- logo (24)
- long tail (13)
- love (19)
- lpo (19)
- m&a (13)
- mac (233)
- mad (23)
- magazine (18)
- mail (65)
- management (428)
- manner (17)
- map (33)
- market (10)
- marketing (537)
- marketplace (16)
- mashup (42)
- material (102)
- math (28)
- media (486)
- medical (232)
- medicine (53)
- meeting (40)
- miau (102)
- microfinance (13)
- microsoft (28)
- middle east (26)
- mikumikudance (27)
- military (188)
- mindmap (39)
- mixi (141)
- mobile (396)
- money (131)
- movabletype (21)
- movie (108)
- mp3 (10)
- mt (44)
- music (339)
- mysql (56)
- negotiation (13)
- network (10)
- news (115)
- newsing (23)
- newspaper (52)
- nhk (17)
- niconico (222)
- node.js (17)
- npo (12)
- nuclear (28)
- office (37)
- ohmynews (44)
- openid (35)
- opensocial (15)
- os (10)
- oss (138)
- overture (17)
- p2p (60)
- paul graham (18)
- payment (10)
- pc (34)
- pdf (27)
- pension (49)
- perl (22)
- philosophy (19)
- photo (191)
- photoshop (57)
- php (156)
- pipes (32)
- plagger (46)
- plugin (151)
- pm (44)
- podcast (23)
- police (33)
- policy (101)
- politics (1541)
- portal (12)
- presentation (82)
- profile (13)
- programming (277)
- project (29)
- promotion (12)
- psychology (74)
- publishing (49)
- ranking (21)
- realestate (84)
- recipe (82)
- regulation (169)
- religion (100)
- research (37)
- restaurant (30)
- review (24)
- rimo (14)
- robot (14)
- rss (108)
- rtm (17)
- ruby (67)
- ruby on rails (104)
- russia (55)
- saas (11)
- sbm (157)
- sbm研究会 (22)
- science (202)
- search (218)
- secondlife (60)
- security (234)
- sem (69)
- seo (656)
- server (75)
- sex (13)
- sf (22)
- shop (24)
- shopping (50)
- shortcut (21)
- skype (53)
- smo (44)
- sns (152)
- social media (44)
- socialgame (44)
- socialgraph (14)
- socialmedia (40)
- society (953)
- software (224)
- sound (14)
- space (33)
- spam (112)
- speech (16)
- sports (83)
- startup (12)
- stationery (20)
- statistics (159)
- stock (22)
- storage (54)
- story (11)
- strategy (15)
- study (193)
- tag (21)
- tax (100)
- technology (79)
- template (121)
- text (13)
- theme (16)
- thumbnail (10)
- thunderbird (18)
- tips (1133)
- todo管理 (20)
- tool (942)
- trade (29)
- translation (11)
- travel (54)
- trivia (10)
- tumblr (34)
- tutorial (74)
- tv (196)
- twitter (173)
- ui (155)
- union (19)
- usa (142)
- usability (126)
- ustream (12)
- vc (11)
- venture (103)
- video (172)
- vocaloid (237)
- w-zero3 (55)
- wallpaper (28)
- web (72)
- web2.0 (246)
- webサービス (924)
- webデザイン (743)
- welfare (17)
- widget (15)
- wiki (38)
- wikipedia (24)
- windows (64)
- winny (27)
- wisdom of crowds (24)
- wordpress (268)
- work (478)
- writing (128)
- yahoo! (92)
- youtube (299)
- あとで (356)
- いい話 (15)
- いじめ (35)
- お笑い (41)
- ことば (55)
- これはすごい (296)
- これはひどい (343)
- これは便利 (17)
- これは欲しい (69)
- すばらしい洞察 (50)
- はてな (158)
- はてなスター (18)
- はてな質問 (16)
- はてブ (211)
- まとめ (841)
- もごもご (10)
- アキバ (14)
- アクセス解析 (123)
- アニメ (131)
- アルファブロガー (16)
- アンケート (11)
- イスラム (13)
- インフラ (10)
- インフレ (37)
- エイプリルフール (12)
- エヴァ (41)
- オシム (22)
- オタク (78)
- オリコン (25)
- ガンダム (21)
- グローバル化 (14)
- コピペ (10)
- コラム (11)
- サマータイム (23)
- シブヤ (32)
- テンプレ (34)
- トピック (14)
- トレーニング (16)
- トンデモ (58)
- ドラえもん (18)
- ニコニコ動画 (152)
- ネタ (920)
- パブリックコメント (57)
- ビジネスモデル (107)
- プレスリリース (12)
- ヘルシング (13)
- マスコミ (187)
- マンガ (200)
- モバゲー (33)
- ワーキングプア (27)
- 亀田 (12)
- 交通 (38)
- 人 (81)
- 人事 (55)
- 保険 (14)
- 児童ポルノ (20)
- 共謀罪 (10)
- 出会い系 (59)
- 初音ミク (86)
- 口コミ (19)
- 名刺 (13)
- 名言 (43)
- 図書館 (17)
- 地デジ (17)
- 増田 (92)
- 失敗学 (17)
- 宋文洲 (12)
- 少子化 (22)
- 就職 (12)
- 山形浩生 (34)
- 差別 (36)
- 思想 (35)
- 憲法 (14)
- 批評 (18)
- 文章 (16)
- 日本 (86)
- 日本語 (31)
- 時々読み直したい (10)
- 暴力団 (11)
- 未来予想図 (119)
- 東京 (19)
- 格差 (43)
- 格差社会 (175)
- 梅田望夫 (18)
- 楽天 (23)
- 比較 (25)
- 法政大学 (11)
- 演劇 (86)
- 炎上 (40)
- 無断リンク (31)
- 生活 (20)
- 男女 (79)
- 画像 (19)
- 白田秀彰 (28)
- 皇室 (14)
- 真性引き篭もり (14)
- 福祉 (24)
- 移民 (10)
- 考え方 (16)
- 考察 (161)
- 自戒 (57)
- 芸能 (16)
- 表現の自由 (127)
- 西原理恵子 (10)
- 解説 (32)
- 訃報 (35)
- 記事 (11)
- 読み物 (18)
- 議論 (13)
- 財政 (35)
- 貧困 (13)
- 資料 (89)
- 起業 (107)
- 身体 (25)
- 転職 (70)
- 選挙 (32)
- 配信 (11)
- 鏡音リン・レン (15)
- 雑学 (32)
- 青空文庫 (10)
- 靖国 (39)
- politics (1541)
- business (1456)
- tips (1133)
- society (953)
- tool (942)
- webサービス (924)
- ネタ (920)
- まとめ (841)
- copyright (837)
- webデザイン (743)
m&aに関するudyのブックマーク (13)
-
 udy 2008/06/06"株価指数も上がんないし、買収防衛策を導入する企業がけしからん。(ROE低いくせに。)" = "少子化問題は、女性が結婚相手の男性に求めるハードルを上げ過ぎてるのが原因だ。(30越してるくせに。)"ww
udy 2008/06/06"株価指数も上がんないし、買収防衛策を導入する企業がけしからん。(ROE低いくせに。)" = "少子化問題は、女性が結婚相手の男性に求めるハードルを上げ過ぎてるのが原因だ。(30越してるくせに。)"ww- m&a
- ネタ
- finance
リンク -
MIT教授が緊急提言! マイクロソフトが買収すべきはヤフーではなくSAP|IT&Business|ダイヤモンド・オンライン
マイケル・クスマノが予測するMSの未来 買収交渉破談後もヤフーに秋波を送るマイクロソフト。その戦略は果たして正しいのか。『マイクロソフト・シークレット』の著者で、IT産業分析の泰斗、マイケル・クスマノMIT教授は、買収すべき相手は消費者向けビジネスを展開するヤフーではなく、企業向けソフト大手の独SAPだと言い切る。(聞き手/ジャーナリスト 瀧口範子) マイクロソフトはヤフーへの買収攻勢で多大なエネルギーをロスしたが、本来の買収対象はコンシューマ(消費者)向けビジネスを展開するヤフーではなく、企業向けソフト大手のSAP(本社・ドイツ)であるべきだった。 マイクロソフトがインターネット部門のMSNから得る収入は、全体の5~6%にすぎない。グーグルという巨大な脅威を前にし、自社の技術だけでは成長が見込めないとヤフー買収に走ったわけだが、その判断が間違っていた理由は複数ある。 第1に、買収額
-
-
買収防衛策は世間に受け入れられつつあるのではないか?(その3)
第一問:アクティビストによる敵対的買収の成功例が実質ない以上、敵対的買収が成功する可能性は非常に低いという判断は非合理的とは言えないと思います。また、買収防衛策の株価に対する影響について意見が別れている段階においては、必ずしも、買収防衛策の導入が善管注意義務を充分に果たすための絶対条件と言えないように思えます。「ま、大丈夫でしょ」と言っていたら無責任に聞こえますが、実質大丈夫な状況が続いています。 第二問:仮に「市場」がA社、B社に関する適切な情報を持っていれば、設問のTOBがあり得ると考える投資家はいると考えられます。その場合、1200億円であったとしても、1800億円まで買い進める投資家が出てきても不思議ではなく、結果として、1800億円?近く?で買わざるを得ない可能性があると思います(つまり(良くあるように)ファイナンシャルアドバイザーが間違っている)。実際そのような抵抗を投資家がし
-
ブランド価値再考 - 債券・株・為替 中年金融マン ぐっちーさんの金持ちまっしぐら
ニューヨークは相変わらずすさまじいね。日本は関係ないとかおもってちゃだめですよ。株についてはバーゲンハンティングでいいと思いますが、金融システムという観点からいうと日本も対岸の火事という訳には行きません。 ここで説明したCLOをAAAだから、AAだからという理由で大量保有して、バッファーがみんなすっ飛んでしまい裸の王様ならぬ、幻の高格付け債券になっちゃった訳ですから大変です。まともに評価したらBもないんじゃないかな。 4000億円とかがいっぺんに投資不適格・・・これって不良債権てことです・・・に落ちた訳ですから大変です。しかもノーゲイン。二度と戻りません。笑っている場合じゃないですね。 今回クライマックスは何でしょうね? まあ、10年前くしくもアジア通貨危機になった訳ですが、名のある大手金融機関が飛ぶとかいろいろ推測はできますが、多分そんなんじゃないと思います。一応アイデアはあるのですがあ

-
最高裁の決定で、結局トクをしたのは誰?――ブルドックソース VS スティールパートナーズ
最高裁の決定で、結局トクをしたのは誰?――ブルドックソース VS スティールパートナーズ:保田隆明の時事日想 大手ソースメーカー・ブルドックソース(証券コード:2804)に対してTOB(株式公開買付)を仕掛けた、米系投資ファンドのスティールパートナーズ。8月7日、最高裁は高裁、地裁の判断を支持し、ブルドックの買収防衛策を認めた。これにより、法廷でのスティールの負けが確定したことになる。 スティールが負けて一件落着――多くの人はそう思っているかもしれないが、ゲームは振り出しに戻っただけだ。今後この問題の焦点は、買収防衛策の無策ぶりと、ブルドックの株主が失った財産へと変わっていくはずだ。 スティールから見た現状:買収総額自体は変わっていない 8月8日、スティールは早速TOBの価格を1700円から425円に引き下げた。これは、ブルドックの買収防衛策が認められ、株数が約4倍になることを受けての措置

-
今後買収の対象となるウェブ企業は?:コラム - CNET Japan
この1年、M&Aの舞台ではさまざまな出来事が起こり、多くのWeb 2.0関連の有名企業が買収対象となった。際立った例をいくつか挙げると、YouTube、Photobucket、Feedburner、Last.fm、StumbleUponなどがある。 しかし、市場にはまだうまみのある魅力的な標的がいくつも残っている。これは、既存メディアにとっても一部のインターネット巨大企業にとっても、新しいウェブの世界での飛躍をもたらすものかもしれない。この記事では、まだ市場に残っている人気企業をいくつか見ていこう。 Digg:既存メディアは急速に地歩を失いつつある。ソーシャルニュースサイトとブログがこれまで以上のトラフィックと関心をひきつけつつあり、従来型メディアに代わるこうしたニュース源が人気を得ている。Diggはこの分野のパイオニアで、攻勢の先頭に立っている。Diggのよい競争相手だったRedditが

-
isologue - by 磯崎哲也事務所:ブルドックの新株予約権発行で改めて思う平和ボケ社会の恐怖
リリース、出てますね。 http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070711_IR1.pdf マスコミではおそらく、「世界初の買収防衛策発動!」というように取り上げられるのではないかと思いますが、これは「確かに、とんでもないことだ!」ともいえますし、「別に、それほど大したことないじゃん」、ともいえるかと思います。 「別に、それほど大したことないじゃん」という視点は、以前のエントリでも申しましたとおり、これが、買収防衛策とは言っても、株主に「損害を与えない」ということにかなり注意が払われたスキームであり、弾があたってもスティール側としてはあまり困らないはずだからであります。 つまり、買収防衛策とはいっても「麻酔銃」みたいなもんで、襲い掛かってくる買収者を「殺す」殺傷能力があるものではない。 会社側が本当にライフル(スティール側の株式の経済的価値が希薄化するよ
-
Economics, Technology & Media » スティール・パートナーズ
スティール・パートナーズがブルドックソースの買収防衛策の差し止めを求めていた件で、東京高裁はスティールの抗告を棄却したとのことです。 「不思議のおでん村」を地で行っているような気もしますが、これで皆さん安心して仲良く生活できるということで目出たし目出たし。 判決はどんなものか分かりませんが、毎日の報道によると、 東京高裁は、企業の経営に参加する意思がなく、株価を上昇させてから関係者に株式を高値で売りつけるような「乱用的買収者」は、「差別的取り扱いを受けてもやむを得ない」との判断を示した。その上で、スティールについて過去の投資活動を分析し、「投資ファンドという性格上、自らの利益のみを追求しようとしている存在と言わざるを得ない」とし「乱用的買収者」と認定した。 だそうです。個人的には「株価を上昇させてから・・・高値で売りつけるような」者は「株主平等の原則」の埒外にあるというのは理解できませんし
-
ビジネスリサーチの心得
3.ビジネスリサーチの報告書作成 ファクト、ファクト、ファクト〜事実に基づくこと 「What's Your Story?」という提案や提言がないレポートは意味がない、ということがよく言われますが、ビジネスリサーチの報告書は、内容の8〜9割は ファクト … 2021.01.19 2021.05.16 313 view 5.ビジネスリサーチのビジネスモデル ビジネスリサーチがアウトソースされる理由 ビジネスリサーチを社外に依頼する理由①〜信頼できる人「すべては依頼から始まる」からでも書きましたが、依頼主が社外にリサーチを委託する最大の理由は、事業環境を定点で把握… 2021.01.18 2021.05.13 147 view
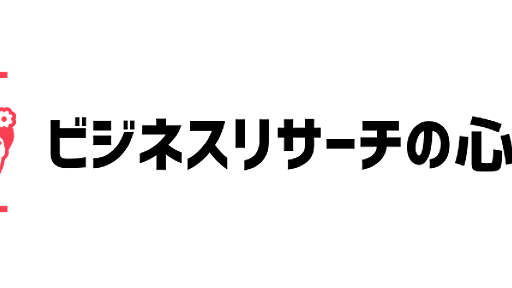
-
日本企業には買収できなかったYouTube
10月9日に発表されたGoogleによるYouTubeの買収合意ですが、プレスリリース発表後に電話会議(カンファレンスコール)形式による両社のスピーチ、および、ウォール街証券会社アナリストや各種メディア記者とのQ&Aセッションがありました。 今やYouTubeの閲覧数のうち、結構な割合が日本からのアクセスで占められていますので、日本企業が買収に興味を示す可能性もなきにしもあらずだったのでは? と思ったりもしますが、そのカンファレンスコールから明らかだったことは、日本企業にはYouTubeの買収はやりたくてもできなかったということでした。 株式交換による買収 今回の買収は、株式交換によって行われます。あるアナリストが、どうして今までのGoogleの買収では現金による買収が多かったのに今回は株式交換によるものなのか、という質問をしました。確かにGoogleの保有現金同等物から勘案するに、今回の

-
ウェブサイトM&Aサービスの実態 | ランサーズ社長日記
こんな感じである。そして利用実態は実は下記のようなものだ。 利用者層 利用者のほとんどが「買い手側」だという。そして、やはりコマースサイトなどを運営する法人の買い手が多い。またそれゆえに、人気があるのはコマースサイト関連サイトなのだという。 サイト売買メリット 買い手としては、「時間をお金で買う。」これにつきる。サイトを0から構築する手間や集客するコストを考えると、選択肢の一つとして買収というのがでてくるのもうなずける。 売り手としては、異業種ビジネスへの転換を考えていたり、本業を持っている人が、副業で営んでいたが手に負えなくなったので売却するといった例が多いようだ。 価格決定 マッチング会社を通すメリットは、価格の妥当性のノウハウを持っていることだ。しかし、残念ながらまだまだ始まったばかりの業界であり、明確な価格決定ロジックはない。 基本的には、現時点のそのサイトの利益×2・3年が目安と
-
-
 1
1
公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く




