前の記事 何でもつかめて操作できる、新発想のロボット(動画) 技術4社が支配する「メディア新時代」 2010年10月27日 経済・ビジネスメディア コメント: トラックバック (0) フィード経済・ビジネスメディア Fred Vogelstein ベルリンにて撮影。画像はWikimedia 伝説的なベンチャー・キャピタリストJohn Doerr(ジョン・ドーア)氏は、大言壮語でも有名だが、ハイテク界の転換点をつかみ、正しい企業に賭けるという点では定評がある。同氏は現在、シリコンバレーではコンピューティングの「第3の波」が起きており、それはAmazon社、Apple社、Google社、およびFacebook社の影響だと述べる。 Doerr氏と彼の投資会社である米Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB)社は、1980年代の「パソコンの時代」においては、米Co
タグ
- すべて
- *google (3)
- *lifehack (22)
- *lifehacks (19)
- *linux (2)
- *news (1)
- *tips (3)
- *あとで読む (1)
- *レビュー (1)
- *仕事 (1)
- *仕事術 (1)
- 2ch (1)
- @it (2)
- Boxing (8)
- DS (1)
- Felica (2)
- IR (2)
- IT (63)
- Internet (5)
- KING (2)
- KLab (1)
- NTT (1)
- SNS (5)
- TV (1)
- Twitter (2)
- accounting (1)
- amazon (2)
- android (4)
- apple (8)
- bank (1)
- biz (1)
- biz.id (3)
- blog (29)
- blogger (1)
- book (14)
- bookkeeping (1)
- books (1)
- business (22)
- calendar (2)
- career (1)
- chat (1)
- cnet japan (1)
- column (8)
- command (1)
- communication (3)
- computer (2)
- copyright (1)
- credit (1)
- creditcard (1)
- culture (1)
- data (1)
- data center (1)
- design (2)
- docomo (2)
- drm (1)
- e-book (1)
- economy (6)
- education (1)
- edy (1)
- energy (1)
- facebook (3)
- fighting (1)
- finance (11)
- football (1)
- freemind (1)
- fx (1)
- gmail (3)
- google (45)
- google base (1)
- googlecalendar (1)
- gphone (1)
- gtd (2)
- health (1)
- history (1)
- honda (1)
- html (2)
- i-pod (4)
- iPad (3)
- iPhone (4)
- iPhoneアプリ (1)
- ibm (1)
- igoogle (1)
- instapaper (1)
- intel (1)
- interview (11)
- investment (1)
- ipod (3)
- itmedia (23)
- itunes (1)
- itガバナンス (5)
- it業界 (9)
- j-sox (1)
- jasrac (1)
- java (1)
- javascript (1)
- job (3)
- life (13)
- life hacks (2)
- lifehack (45)
- lifehacks (39)
- linux (8)
- m&a (4)
- management (1)
- mba (1)
- media (8)
- microsoft (2)
- mileage (2)
- mobile (9)
- money (9)
- movie (1)
- ms (1)
- music (9)
- news (10)
- newspaper (3)
- nikkei (7)
- nintendo (2)
- notebook (1)
- o'reilly (2)
- official (1)
- open source (1)
- opensource (1)
- p2p (1)
- peak oil (2)
- podcast (4)
- podcasting (8)
- politics (1)
- programming (1)
- radio (1)
- reit (1)
- rss (2)
- ruby (1)
- saas (1)
- salesforce (1)
- sbi (2)
- science (1)
- search (1)
- security (1)
- server (1)
- shopping (6)
- si (1)
- sier (1)
- soccer (4)
- sony (1)
- sports (1)
- steven jobs (1)
- study (7)
- techcrunch (1)
- template (1)
- texty (1)
- travel (1)
- venture (2)
- video (2)
- warren buffett (1)
- web (21)
- web 2.0 (2)
- web2.0 (24)
- webservice (3)
- webサービス (6)
- wifi (1)
- windows (1)
- work (4)
- yahoo (1)
- youtube (3)
- あとで書く (4)
- あとで読む (101)
- あとで買う (5)
- これはすごい (1)
- これは便利 (2)
- はてな (1)
- まつもとゆきひろ (1)
- まとめ (2)
- まとめサイト (1)
- ものづくり (1)
- アイデア (2)
- アフィリエイト (16)
- アフリエイト (20)
- アメリカ (2)
- アーカイブ (1)
- インタビュー (6)
- インターネット (1)
- インターネットマガジ (1)
- インテリア (1)
- インフラ (1)
- ウェブ人間論 (1)
- ウェブ時代をゆく (5)
- ウェブ進化論 (2)
- エクセル (1)
- エコロジー (1)
- エンジニア (4)
- オプション (1)
- オープンソース (4)
- ガジェット (1)
- キャリア (11)
- ギーク (1)
- クラウド (1)
- クレジットカード (5)
- ケータイ (2)
- ゲーム (1)
- コマンド (1)
- コラム (9)
- コンサル (1)
- コンプライアンス (2)
- コンプライアンス不況 (1)
- コーポレートガバナン (2)
- サッカー (11)
- サブプライム (9)
- サーバ (1)
- サーバ管理 (1)
- システム (2)
- システム管理 (1)
- システム開発 (7)
- ショートカット (3)
- シリコンバレー (1)
- ステーショナリー (1)
- ストリーミング (1)
- スポーツ (2)
- スーツ (1)
- セキュリティ (3)
- セコム (1)
- セミナー (4)
- ソフトウェア (1)
- ソーシャルメディア (2)
- タックスアンサー (1)
- ダウンロード違法化 (1)
- ツール (5)
- ティム・オライリー (1)
- テンプレート (1)
- デザイン (1)
- ニュース (4)
- ネタ (2)
- ネットバンク (2)
- ネットビジネス (27)
- バフェット (1)
- パソコン (1)
- ビジネス (28)
- ビジネスモデル (1)
- ビットワレット (1)
- ピーター・ドラッカー (1)
- フィットネス (1)
- フラット化する世界 (1)
- フランクリン・プラン (1)
- フリーソフト (1)
- ブログ (6)
- プログラミング (2)
- プログラム (1)
- ベンチャー (2)
- ホンダ (1)
- ボクシング (1)
- ポイント (2)
- ポッドキャスティング (4)
- ポッドキャスト (6)
- ポータル (4)
- ポータルサイト (1)
- マイクロクレジット (1)
- マイル (2)
- マイレージ (3)
- マインドマップ (4)
- マスコミ (2)
- マネジメント (1)
- マネー (1)
- マーケット (1)
- メディア (5)
- メディア論 (1)
- メルマが (1)
- メルマガ (7)
- モバイル (2)
- ライフハック (1)
- リンク集 (8)
- ルール (1)
- レビュー (3)
- レポート (1)
- 不動産 (8)
- 不動産投資 (22)
- 世界情勢 (6)
- 世界遺産 (2)
- 中国 (2)
- 中国株 (4)
- 事業革新 (1)
- 人 (1)
- 人物 (1)
- 人生 (7)
- 仕事 (32)
- 仕事術 (22)
- 任天堂 (1)
- 企業 (12)
- 会社 (1)
- 便利 (1)
- 便利サイト (3)
- 保険 (12)
- 偉人 (1)
- 健康 (4)
- 内部統制 (2)
- 労働生産性 (1)
- 勉強 (5)
- 勉強法 (1)
- 動画 (8)
- 北尾吉孝 (1)
- 半導体 (4)
- 危機管理 (1)
- 原発 (1)
- 口コミ (5)
- 古川享 (1)
- 名言 (2)
- 国税庁 (1)
- 国際 (2)
- 国際会計基準 (1)
- 国際競争力 (1)
- 地上デジタル放送 (1)
- 地域コミュニティ (1)
- 地震 (2)
- 外交 (3)
- 大前研一 (11)
- 太陽電池 (1)
- 姿勢 (1)
- 学習 (1)
- 宋文洲 (1)
- 官製不況 (1)
- 対談 (1)
- 小飼弾 (6)
- 就職 (3)
- 山崎養世 (1)
- 岡ちゃん (1)
- 後で読む (4)
- 心理 (1)
- 恋愛 (1)
- 情報収集 (2)
- 情報整理 (7)
- 情報誌・情報源 (7)
- 情報起業 (2)
- 戦争 (1)
- 手帳 (2)
- 技術 (3)
- 技術情報 (1)
- 投資 (21)
- 投資信託 (9)
- 投資参考 (1)
- 携帯 (2)
- 政治 (7)
- 教育 (1)
- 文例集 (1)
- 文化 (2)
- 旅 (2)
- 日本 (5)
- 日本の内向き志向 (1)
- 日経 (3)
- 日経ビジネス (6)
- 時評 (2)
- 書評 (4)
- 有料サービス (33)
- 本 (3)
- 本田宗一郎 (1)
- 株 (32)
- 株式 (1)
- 株式投資 (39)
- 格闘技 (3)
- 梅田望夫 (14)
- 植草一秀 (1)
- 検索 (1)
- 橋本徹 (1)
- 歴史 (2)
- 江島健太郎 (11)
- 江戸 (1)
- 注目企業 (1)
- 海外 (2)
- 海外投資 (14)
- 源泉徴収 (1)
- 無線 (1)
- 爆笑問題 (1)
- 環境 (1)
- 生命保険 (4)
- 生活 (1)
- 白州次郎 (2)
- 知識 (1)
- 確定申告 (1)
- 社会 (5)
- 社長 (6)
- 税制 (2)
- 税務 (1)
- 税金 (1)
- 簿記 (2)
- 経営 (6)
- 経営者 (1)
- 経済 (22)
- 経済破綻 (1)
- 経理 (1)
- 緒川たまき (2)
- 美術館 (1)
- 耳学習 (2)
- 脳 (1)
- 自己啓発 (30)
- 英語 (7)
- 茂木健一郎 (3)
- 著作権 (3)
- 装置 (1)
- 製品情報 (1)
- 製造業 (1)
- 読み物 (13)
- 読書 (14)
- 賃貸 (1)
- 資料 (1)
- 資格 (11)
- 資産運用 (126)
- 起業 (5)
- 転職 (30)
- 週末起業 (1)
- 金融 (9)
- 雑学 (2)
- 雑誌 (1)
- 電子マネー (19)
- 電子書籍 (6)
- 電波 (3)
- 面白い意見 (1)
- 音楽 (1)
- 資産運用 (126)
- あとで読む (101)
- IT (63)
- google (45)
- lifehack (45)
- lifehacks (39)
- 株式投資 (39)
- 有料サービス (33)
- 仕事 (32)
- 株 (32)
関連タグで絞り込む (52)
- @it
- blog
- business
- career
- column
- computer
- data center
- energy
- Internet
- IT
- itmedia
- itガバナンス
- it業界
- j-sox
- life
- m&a
- microsoft
- mobile
- money
- news
- science
- server
- si
- sier
- web
- web2.0
- あとで読む
- エンジニア
- キャリア
- コンプライアンス
- コーポレートガバナン
- システム開発
- ビジネス
- フラット化する世界
- プログラミング
- ポータル
- メディア
- メルマガ
- レビュー
- 仕事
- 仕事術
- 企業
- 内部統制
- 就職
- 日本
- 江島健太郎
- 茂木健一郎
- 製品情報
- 読み物
- 資格
- 転職
itに関するy-museのブックマーク (63)
-
 y-muse 2010/10/30
y-muse 2010/10/30- IT
- メディア
リンク -
IBM、グーグル、インテルなどが続々参戦 クリーンエネルギーで世界の覇権を取れ!~(5) | JBpress (ジェイビープレス)
今回はクリーンエネルギー産業の特徴を分析します。近年、産業としてのクリーンエネルギーは、新興産業として目覚ましい成長を遂げています。 この6年間で投資額は約4倍に膨れ上がった 産業の規模を確認するに当たって、1つの指標として、2004年以降世界のクリーンエネルギー産業に投融資された金額を見てみます(図20)。 Bloomberg New Energy Finance によりますと、世界のクリーンエネルギーへの投資・融資額の総額は、2004年は460億ドル(4兆1400億円)でしたが、2009年は若干世界同時不況の影響は受けたものの、それでも2007年を上回る1620億ドル(14兆5800億円)に達しました。 この6年間で、クリーンエネルギー産業に投入された資金規模が約4倍に膨れ上がったのです。短期間に、この規模で、これだけ高い成長を遂げた産業が過去あったでしょうか?

-
IT社会で求められる経営者の能力とは(茂木健一郎):後編
──前編では、急速なIT社会の発展と脳の関係について聞きました。その最後の方で紹介してもらいましたが、現代の脳科学の世界では、人間の経験のうち計量できないものを「クオリア(感覚質)」と呼ぶそうですね。クオリアを“味わい”ながら一つひとつの作業と向き合うと、時間はかかるのですが、不思議なことに非常に豊かな気持ちになります。 茂木: いわゆる「スローライフ」「スローフード」というムーブメントはクオリアと密接な関係があります。それは、時間をかけなければできないプロセスというのが必ずある。そして、そのスローなプロセスというものが人に幸せをもたらすということなのです。 さらに重要なことは、ゆっくり時間をかけなければ出てこない発明や発見、ひらめきというものがあって、それが人類に大きな恵みをもたらしてきたこと。そして、それがなければ人類は豊かになれなかったということです。 スローなプロセスは重要ではあり
-
bpspecial ITマネジメント
●企業が経営戦略を考える上で、ITは今や必要不可欠なものとなっている。その一方で、IT社会における様々な課題も叫ばれ始めている。特にデジタル情報の流通量は加速度的に増大しており、処理し切れない量に達しているともいえる。例えば、昼夜を問わずやり取りされる電子メールの処理に追われ、疲弊してしまっているビジネスパーソンも多いのではないだろうか。 ●それに対して、脳科学者であり、ソニーコンピュータサイエンス研究所のシニアリサーチャーである茂木健一郎氏は、「ITの成長のシナリオは我々の脳の情報容量が無限であることを前提としたものであるが、実際には脳が受け取り消化できる情報には限界がある」と提言する。 ●現在のIT社会の課題を克服し、真に豊かなIT社会を築き上げていくにはどうしたらよいか。そのためには経営者やCIO(情報統括責任者)はどういったことに考慮してITマネジメントを行い、経営戦略に結び付
-
「10年以内に社内で運用されるサーバーは無くなる」,MSバルマーCEOが「破壊」を宣言
「挑発的な意見になるかもしれないが,10年後に,自社で独自に管理するサーバーで,データを保持したり,トランザクションを実行したりする企業は無くなるだろう。ほとんどのトランザクションやアプリケーション,システム管理機能が,インターネット上のコンピュータ・クラウドからもたらされるはずだ」--。米Microsoftのスティーブ・バルマーCEOは11月8日,都内で開催した「Microsoft Partner Conference」でこう断言した。 バルマーCEOの見解自体は,珍しいものではない。多くのベンダーが,ユーティリティ・コンピューティングやクラウド・コンピューティングのビジョンを示しているし,Microsoftも「ソフトウエア+サービス」というスローガンの下,ソフトウエアのパッケージ販売からサービスの提供に軸足を移しつつある。しかし,今現在,ユーザー企業に対してサーバー・ハードウエアやパッ

-
成長に舵を切るニッポン企業、求められる新たなIT基盤とは?
長くて暗いトンネルを抜けたニッポン企業の多くは、売り上げの拡大を伴う力強い成長に向け、いよいよアクセルを踏み込み始めた。情報システム部門には、経営陣の意思決定を迅速に実現する柔軟なIT基盤の構築が求められており、なおかつ、消費電力や排熱の問題も解決しなければならない。成長企業に求められる新たなIT基盤とは? 「失われた10年」とも「失われた15年」とも呼ばれる長くて暗いトンネルを抜けた日本企業の多くは、売り上げの拡大を伴う力強い成長に向け、いよいよアクセルを踏み込み始めた。生き残りを賭けた事業の見直しやコスト削減を担ってきた情報システム部門も、事業の成長に向けた貢献が求められようとしている。 調査会社のガートナーが今春に発表した「Garnter EXP 2007 CIO Agenda」でも、日本のCIOらの回答に大きな変化が見られた。最も際立ったのは、ビジネス面において「収益の増加の必要性

-
はてなブログ | 無料ブログを作成しよう
初めて梅干しを作ってみた話 今年の夏、初めて梅干しを作りました。 私梅干し大好きなんですが、自分で作るという発想がなくて…同僚が梅シロップを作っているのに影響されて去年から梅仕事を始めてみたんですが、そのときの説明書に「梅干しの作り方」というのも入っていて、えーー梅干しって自分…

-
ニッポンIT業界絶望論:江島健太郎 / Kenn's Clairvoyance - CNET Japan
日本のIT業界は救いようがない。絶望的としか言いようがない。 IT業界不人気なんて、この業界に重くのしかかる決して晴れることのない暗雲の氷山の一角に過ぎない。はてなの匿名ダイアリーにもどうせ理系出身者なんていらねえんだよ。なんて書かれていたけど、これが現実なのだよ、学生諸君。 ちょっと補足しておくけど、ここでIT業界っていうのは、SIerのことだ。お客さんの要件をヒアリングして、その要求に沿ったシステムを受託開発するっていうビジネスのことを指している。 ぼくもその昔、その世界のループに組み込まれていた。そして華麗なるコミュニケーション能力とやらをいかんなく発揮し、場の空気を読み、生意気なぐらいのチャレンジ精神で、それなりに仕事のできるよい子だったようだ。 いや、正直に言うよ。正直に言うとだね、結構楽しかった。 だって、考えてみてごらん。お客さんのところに出向いて行って、その業界のことをじっ

-
収入格差がシステム開発にもたらすもの:上流工程で生き延びろ!〜SEサバイバル - CNET Japan
巷では「勝ち組」「負け組」等、収入格差が開きつつある 現状に対する議論がなされている。 IT業界に目をむけてみると、 大手SIerや外資系に勤務しているマネージャークラス 年収 ○千万円から○億円で能力給の比率が高い の人間もいる一方 弱小ベンダー(いわゆる下請け) に勤務しているプログラマークラス 年収300万円に満たないし、やってもやらなくても 収入のアップが望めない人間もいる。 もちろん能力の差はあるのだろうが、 それ以上に「立場」によって 収入格差がつくケースが多いように思われる。 システム開発プロジェクトの場合、 上記収入格差のある人達が 各々の立場で参画し、カットオーバーを 目指す事になる。 当然、モチベーションが同じ訳がない。 あまりにも立場が違い過ぎる人達の意識の共有を 計らなければプロジェクトは破綻へと向かっていく。 どうやって? スーパープロジェクトリーダーが死にそう
-
-
FPN-ゼイヴェル・大浜史太郎社長へのインタビューを読んだ
4.インプリケーションと提言 リサーチを通じて気付いたことは?公開情報から点と点を結ぶイン… インサイダー情報はそのままでは役に立たない!?ビジネスリサーチの依頼の中で、「業界の空気感はどうなっているか?」「この技術が主流になっているというのは信憑性があるか?… 2021.01.27 2021.05.13 185 view 1.ビジネスリサーチの基本・心構え すべては「依頼」から始まる〜社内リサーチャーと社外リサーチャ… 【 リサーチャー とは 】企業で企画系の仕事をしていると、上司の依頼で調べものをして資料にまとめるという仕事が多いと思います。企画系の業務では課長クラスまではこうしたリサ… 2021.01.18 2021.05.13 340 view 2.ビジネスリサーチの情報収集 デスクトップ調査 の基本〜アニュアルレポートなど公開情報から… デスクトップ調査 とは、主にインターネット
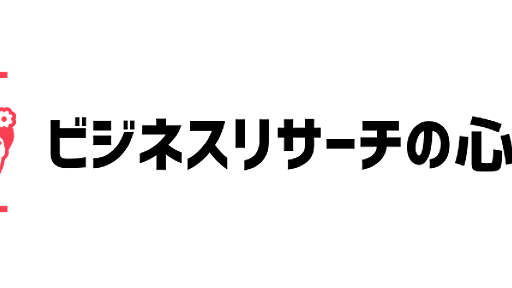
-
イメージを形にできない人は減衰する : 404 Blog Not Found
2007年11月06日03:45 カテゴリArt イメージを形にできない人は減衰する イメージを形にできないものに産業の名は値しない。IT産業はイメージの具現化がすべてである。人気を魅力と勘違いする人は減衰する。 ユメのチカラ: 若い人に人気のない産業は減衰する 未来をイメージできない産業に人は集まらない。IT産業は人がすべてである。魅力のない産業は減衰する。ユメのチカラ: 若い人に人気のない産業は減衰する参加者がすごい。業界の重鎮。岡本晋氏(TIS株式会社 代表取締役社長)、浜口友一氏(社団法人情報サービス産業協会 会長、株式会社NTTデータ 取締役相談役)、藤原武平太氏(IPA 理事長)。 大変恐縮なのだが、私はこの参加者のすごさが全く理解できなかった。なぜ業界の重鎮なのかさらに理解できなかった。「IPAフォーラム2007:プログラム(詳細)」を見たら、それがますますわからなくなった。

-
Life is beautiful: ソフトウェアの仕様書は料理のレシピに似ている
先日、経済産業省向けの仕事をしている知り合いと食事をしたのだが、彼によると経済産業省の今の悩みは、「IT産業の階層化の弊害によっておこる下流のプログラマーの収入の低下」だそうである。「プライムベンダー」と呼ばれる「上流コンサルタント」たちがインドや中国にも仕事を発注できることを理由に、激しく値切り始めたために、今やわずか一人月30万円というケースもあるという。 こんな話を聞くと本当に悲しくなる。まず第一に「プログラムを書く」という仕事は簡単な仕事ではない。数学的な頭を持っていないとかなり辛いし、基礎がしっかりと出来ていないとろくなソフトウェアは作れない。物価の安いインドや中国なら許せるが、米国よりも生活費の高い日本で一人月30万円とはあまりにも低すぎる。 「彼らは下流のエンジニアで、詳細仕様書に従った通りのプログラムを書くだけの簡単な仕事をしているから給料が安い」という説明を聞いたことがあ
-
優秀なエンジニアは「入社時のスキルを問わない会社」には就職してはいけない
ちまたで問題になっているIPAフォーラム2007に参加した学生がエントリーを書いているのだが、それが半端じゃないぐらいのエンターテイメント。 ...IT産業というよりSIerの人気がないことについて語りたいだけなんじゃないかという顔ぶれだったし... ...はてなブックマークのコメントを見ている限りでは、パネリストの方々は相当現実の見えていない発言をしているようだ。... ...ITを専攻している学生達からは、「就職時にITスキルが問われないのだとしたら、大学でやっていることには何の意味があるのか」という質問が出ていたのだけど、明確な回答はなかったと思う。その人たちは、ちょっとショックを受けていたような気がする。... ...その流れで、「入社時にITのスキルを問わないというのは、Googleのような企業の方針とは反対であるが、それですばらしいサービスを作ることができるのか」という質問が出
-
第7回 サポート「“攻め”の応対」--クレディセゾン:共通DBで後方業務を支援
2007年3月期のクレジットカード新規獲得枚数420万枚、実際に使っている会員数(稼働会員数)が1255万人(記事執筆時点の見込み)――。これらの数字がともに業界トップ・クラスといわれるクレディセゾンは、2006年1月にユーシーカードと合併し、旧ユーシーカードの会員427万人を加えるなど、急拡大を続けている。 そうした成長を支えている同社の強みの一つが、顧客からの問い合わせや要望を受け付けた際の対応力だ。見込み顧客からの問い合わせや申し込みにすぐに対応できなければ新規獲得にはつながらないし、既存顧客の満足度を上げなければ稼働会員数は増えない。 カード会社の顧客窓口の中心はコールセンターである。そこでクレディセゾンは05年4月に「Ubiquitous(ユビキタス)」と呼ぶコールセンターを新設してオペレーションを集約。組織体制も大幅に変更し、顧客対応力を高めた最前線拠点とした。その頭脳にあたる

-
-
フリーになる前に押さえておきたいポイントとは - @IT自分戦略研究所
2007年9月、東京・九段下で「フリーエンジニアカンファレンス2007」が開催された。これからフリーとして働こうと考えているITエンジニアや、すでにフリーで活躍しているITエンジニアが考えている不安や疑問に対して、専門家がそれぞれの立場から答えた。その中から「安定的に案件を受注するテクニック」というテーマで行われたセッションをレポートしよう。 @IT自分戦略研究所が2007年5月に行った読者調査では、「現在の雇用形態」としてフリーランスと回答したのは、わずか3.6%。しかし、今後フリーランスとして働きたいと考えているITエンジニアは13.6%に上る。つまり、フリーランスとして働きたいと考えているITエンジニアがいるが、なかなかフリーという立場に踏み出せないという人が多いということだ。 フリーとして働きたい人が、フリーとなるために障害になっていると考えていることはなんだろうか。読者調査結果で
-
プロセスはチャンスが訪れるたびに改善する/パート2:プロセスと基準(後編)
ソフトウェア開発は、優先事項、要件、そして場合によってはチームメンバーも頻繁に変わるダイナミックな活動だ。さらに、場合によっては相反するさまざまな問題に取り組むことになるため、ソフトウェア開発は非常に複雑だ。固有の動きや複雑性があるため、プロジェクト当初に合理的かつ詳細に今後の流れを予測することはできない。挑戦はしてみるべきだが、ソフトウェア開発を本当に効率的に進めたいのなら、進行に合わせて積極的に学習し、必要に応じて戦術を変更する必要がある。 この手法の背景にある重要なコンセプトはシンプルだ。チャンスが訪れるたびに作業方法を改善する。「毎日何か新しいことを学ぶはずだ」というのは優れた格言だ。だがこの手法では、一歩先へ進み、学んだことに対して何らかの行動を取り、全体の効率を引き上げることを推奨している。 ソフトウェアプロジェクトの進行中に、その中で潜在的に改善可能な点を特定する方法は次のよ
-
MyNewsJapan NTTデータが偽装請負 直接指示どころか下請け富士ソフト社員を奴隷扱い、指摘後も対応せず
私は今年3月まで富士ソフトの社員として、同社の請負契約先であるNTTデータのプロジェクトに常駐で参加していた。請負の場合、元請けが現場社員に直接指示を出すことは労働者派遣法に抵触するが、私は直接指示どころか、ほとんど奴隷扱いだった。作業の進捗だけでなく休日出勤の管理までNTTデータ社員によって行われ、違法性を指摘してもなお、私が辞職するまで止めなかった。SI業界で横行する偽装請負の実態について自身の体験を報告する。 【Digest】 ◇NTTデータのプロジェクトに参画 ◇逆ギレする富士ソフトA氏 ◇「てめえ何やってんだ!」10歳以上年長の私に怒鳴るデータT氏 ◇プロマネN氏まで直接指示で罵声 ◇契約違反を認めるも、泣き寝入りさせるNTTデータ ◇最後まで態度を改めなかったT氏 ◇NTTデータ総務が認めたこと、認めないこと ◇SI業界での偽装派遣の構造 ◇「下請けに発注している」というおごり

-
最新スキル習得にあえぐ技術者のストレス
常に新しいITスキルを習得するのが望ましいという点で専門家の意見は一致している。しかし、変化し続ける技術と、常にその最先端にいなければならないというプレッシャーにストレスを感じるIT技術者も多い。 ウェスタンオンタリオ大学のニコール・ハガーティ助教授によると、新技術には新しいスキルが必要なため、持続的な技術革新によってIT技術者の「能力が破壊されてしまう」ことがあるという。レガシー技術でもまだ通用するが、そうしたスキルの需要は減っていく。 ハガーティ氏のチームは10人以上のIT技術者について詳しく研究し、仕事上のストレスにどう対処しているかを調べた。 「ほかの分野の専門職は、既存の知識への積み重ねで済む。IT技術者は常に建て直しモードだ。新技術が登場すると、それまでの知識は意味がなくなる。まったく新しいスキルを1から組み直さなければならなくなる」と同氏は話す。 防衛関係業務を請け負っている

公式Twitter
- @HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
- @hatebu
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
キーボードショートカット一覧
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く



