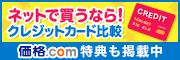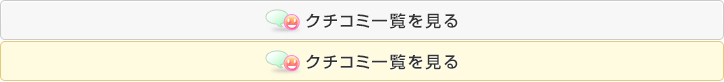マザーボード > MSI > B350M MORTAR
相変わらずニッチな題目で恐縮ですが、今回MSIのAM4マザーボードを入手しましたので、従前のものよりピン数が増加している 新JSPI1ピンヘッダー(UEFI(BIOS)ROMチップへのアクセス用端子)の結線を調べてみました。
MSI B350M MORTAR (PCB Rev 1.1)の JSPI1ピンヘッダーとROMチップ周辺の様子を(画像-1)に、ピンヘッダー <--> ROMチップ間の接続図を(画像-2)に示します。多分最近の128Mbチップ採用のMSIマザーボードではB350M-MORTAR以外でも同じピン割当だと思われます。(確証はありませんので、この接続図を他のマザーボードで利用する際には必ず接続が正しいかどうか確認してからにして下さい)
尚、(画像-1)の写真からはちょっと読み取り難いのですが、採用されているROMチップは電圧3V品の Winbond W25Q128FV シリーズではなく、1.8V品のWinbond W25Q128FW シリーズ (W25Q128FWSIQ) となっております。どうやらAM4用チップセットでは 1.8V品 が標準なのかも知れません。この1.8V品のROMチップのDC印可電圧の絶対最大許容値は 1.8 + 0.6 = 2.4 V までなので、例えば、EZP2010の様な下限3V品までしか対応していないROMライターで読み書きを行うと最大定格を越えてしまいますので、ROMチップへのダメージや破損またはチップセットへのダメージや破損のリスクも有ると思われます。(ですので、自分は 1.8V対応コンバーター を入手する迄は EZP2010 を使わないつもりです)
また、MSI新JSPI1ピンヘッダー用のハーネスも試作してみました。(画像-3、4) 尚、2.0mmピッチコネクタハウジングは手持部品の都合で必要極数12よりも2極多い14極品を使用しています。白色線(ピン9)については今の所用途は不明ですが、恐らくICP(In-Circuit Programming)時に関る制御関連ではないかと推測しておりますので、念の為に引き出して置きました。
書込番号:20819996
![]() 14点
14点
BIOSチップに直接読み書きとは、業界の方ですか?
書込番号:20820503
![]() 1点
1点
いいえ、PC業界とは一切関係はありません。単なる深追い癖がなかなか直らないただの一般人です。
書込番号:20820701
![]() 2点
2点
昨日、中国(深セン)より 1.8V Adopter (画像-1)が届きましたので、早速ROMチップの読取試験を実施してみました。(画像-2)
試験結果は良好だったのですが、一点だけ注意事項があります。それはMSIのAM4マザーボードのJSPI1ピンヘッダーを使用して1.8V ROMチップの読み書きを行う際には、CPUをソケットから外して置かないと信号エラーが発生してしまい、読込み動作すら出来なくなります。低電圧化の影響かも? 作業を行う際には必ずCPUを外した状態で行って下さい。
Intel系のマザーボードではROMチップアクセスに使われる SPI(Serial Peripheral Interface)はチップセットから出ているのだけれど、AMD系はCPUから直接出ているのかな???
ちなみに、1.8V Adopter はたったの USD 2.5 でした。AliExpress での e-EMS配送指定で発注日も含めて6日間で到着しました。商品発送まで2日間を要しているので郵便区間は4日間だけでした。さすがEMSです。実は同じ品物をebayを通しても発注しているのですが、こちらの方は Free Economy Shipping なので最短でも2週間、遅いと1ヶ月程度はみておく必要がありそうです。
書込番号:20839895
![]() 9点
9点
その後、EZP2010 + 1.8V Adaptor を介してのオンボードROMチップへの消去・書込テストも実施してみましたので結果を追記しておきます。
消去・書込・確認テストともCPUを外している限り結果は良好でした。CPUを取り付けたままの状態だと、信号が減衰してしまう為なのか、それとも反射等で波形が乱れる為なのかどうかまでは判りませんが、何れにせよエラーが多発してまともにROMライターとして機能はしませんでした。
あと、MSIのUEFI(BIOS)のROMチップへの書込用バイナリーファイルですが、MSIのWebサイトからダウンロードしたものそのもの直接書き込んでもマザーボードのUEFI(BIOS)としては問題なく動作します。但し、UUID,S/N等の情報は書き込まれていない為、OSあるいは各種アプリケーションソフト等でこれらの情報を認証・識別等に利用している場合には問題が発生する可能性もあると思われます。(画像-1)参照
ROMライターでUEFI(BIOS)を取り扱う作業を行う際にまず最初に行っておくべき事は、正常状態(マザーボード購入時の初期状態が一番望ましい)でのROMチップの内容を完全にダンプし、バックアップファイルとして保存しておく事です。後は必要な段階で適宜バックアップを作成しておきます。これらのファイルさえあれば例え通常のFlash操作に失敗したとしても、ROMライターによる書込で何度でも好みのバージョンで復旧出来ます。
書込番号:20842775
![]() 11点
11点
WebでAMDのドキュメントをチェックしていてほぼ判明したのですが、RyzenのAM4ソケット等ではROMチップのアクセスに使用されるSPIのマスター機能は、チップセット側ではなくやはりCPU側に組み込まれている様です。(AM4マザーボードではROMチップならびにピンヘッダーがCPUソケットのすぐ傍にあることからも推測出来た事なのですが…)
ですので、ROMライターでJSPI1ピンヘッダーを使用してAM4ソケットのマザーボードのROMに直接アクセスする場合には、必ずCPUを外した状態にして行って下さい。さもないと、高価なCPUを壊し兼ねません。ましてやCPUを付けたままで1.8V Adaptor等を使用せずに3.3Vや5Vの高電圧を印加するのは極めてリスクが高い行為だと思います。お気を付け下さい。
書込番号:20843252
![]() 8点
8点
MSIのソケットAM4マザーボードに関する追加情報です。
マザーボード固有ID情報であるUUID、S/N等のUEFI(BIOS)ROMチップ上の収容位置に関するものです。(画像参照)
1) UUID情報収容位置:0xD6004C からの16バイト
2) S/N等情報:0xD7C53C - 0xD7C63B の 256バイトブロック内
尚、この情報はある特定のマザーボード(B350M MORTAR)の特定のファームウェアーバージョン(Ver. 1.30)上で検証したものであり、他の製品、ファームウェアーバージョンによっては変更される可能性もあることにご留意願います。
書込番号:20887582
![]() 9点
9点
ROMライターに関する追加情報です。
安価に(2〜4千円程度)入手可能なROMライターとして、CORIGHT社製のSkyPROと言う製品を今般入手しましたので参考までに紹介致します。
最初に注意喚起しておきますが、この製品の対応ROMチップリストには1.8V SPI Flash品(Winbond W25Q128FW等)も何の注意書等もなく記載されていますが、実際には外付けの1.8Vアダプターが必要です。
1.8Vアダプターは付属していませんので、はっきり言ってインチキです。(画像‐1)参照
次に製品外観についてですが、EZP2010(2013)とそっくりの作りです。どうやら SkyPRO の方が本家本元で、EZP2010 の方がコピーキャット品の様です。外見上の違いはマーキングは別としてUSB接続コネクタがBタイプ(EZP2010)かマイクロタイプ(SkyPRO)かと言うこと位です。でも、中身については結構な違いがある様です。内部で使用されているMCU(Micro Controller Unit)が違う様です。(画像‐2)参照
EZP2010: C8051F340 (Silicon Laboratories) 8-bit MCU
SkyPRO: STM32Fシリーズ? (STMicroelectronics) 32-bit ARM Cortex-M MCU
そこで採用MCUの違いによるROMチップ(Winbond W25Q128FV)の読み書き動作速度について差違はあるのかどうかを検証してみたところ、大差はなかったもののコピーキャット品である EZP2010 の方がやや高速と言う少々意外な結果に終わりました。
(Read) (Erase) (Write) (Verify) [Total] 単位(秒)
EZP2010 51.496 48.345 74.458 51.528 225.827
SkyPRO 53.99 49.42 85.34 54.00 242.75
とは言え、SkyPROにはEZP2010等には無いメリットがあります。それはソフトウェア面での事です。
1)ドライバーソフトが Windows 10 (x64) に完全対応 (Testモードにする必要なし)
2)現在もファームウェア、ソフトウェアの更新サイトが機能しており、アップデートが受けられる
ですのでこれから新規にROMライターを購入される方には SkyPRO の方をお勧め致します。
(但しSkyPROにはソフトウェア等のCDROM等は一切同梱されていませんので、CORIGHT社のダウンロードサイトに取りに行く必要があります。)
書込番号:21013315
![]() 9点
9点
SkyPROに関する補足です。
USBドライバーソフトはダウンロードしたファイル skypro_4.0.4.606.exe の中に含まれています。インストール途中で(画像‐1)に示す様なインストールするドライバーの種類を尋ねるダイアログが出ますが、そこでは デフォルトで Virtual COM Port (VCP) にチェックマークが付いていますが、VCP機能はSkyPROでは使用しない様なのでインストール不要ですのでチェックを外して下さい。たとえチェックを付けたとしてもVCPデバイスとしては認識されません。
それとSkyPROで使用されているプロセッサ(MCU)についてですが、何とか型番が読み取れましたので記しておきます。(まぁ、どうでもいい情報ですが、気になる人には気になると思いますので)
SkyPRO MCU: STM32F103CBT6 (STMicroelectronics) 32-bit ARM Cortex-M3 MCU
書込番号:21021374
![]() 6点
6点
MSI製マザーボード UEFI(BIOS) SPI FLASH ROM アクセス(新JSPI1ピンヘッダー)用簡易ワイヤー・ハーネスの作製例です。
必要部材は以下の2点のみです。
1) ミニQIケーブル (6S-Z 311-330) 2 組 @¥124 計¥248
http://eleshop.jp/shop/g/gAA741J/ (共立エレショップ取扱い)
2) 丸ピンICソケット (DIP8) 1 個 ¥47
(例)http://eleshop.jp/shop/g/gF91316/ (共立エレショップ取扱い)
ここでは片端に2.0�oピッチ用のQI(Quick Insertion)コネクタが圧着済みの半完成品を利用して、面倒で厄介なコンタクトピンの圧着作業を省いています。このケーブルのもう一端側は自由端で半田あげだけしてあり、長さを自由に調整可能ですが、そのままの長さ(500�o)では長すぎますので、作業性が損なわれない範囲で極力短くします。(ケーブルを流れる信号は数MHz〜数十MHzオーダーの高周波信号ですので)
また、この自由端側にはDIP8の丸ピンICソケットを半田付けします。結線図はここの最初の投稿の(画像-2) (http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958574/SortID=20819996/ImageID=2741028/)に従って下さい。尚、ここでは結線はICピン8本全部を対象に行っておりますが、EZP2010等のFLASH ROM WRITERとの接続ではICピン#3 (/WP)、ICピン#7 (/HOLD)の接続は不要かも知れません。(ROM WRITERではQPIモードやQ-SPI命令等の高速モードを使用しない為)でも、念の為、今後の為にも接続しておきましょう。(画像-1)、(画像-2)参照
[その他]
UEFI(BIOS)の読み取り、書き込み等の更新作業に必要な機材としては、
1) SPI FLASH ROM WRITER (EZP2010) 1 台 ¥2,133
(例)http://amzn.asia/iH9KJlV
又は、
SkyPRO USB Programmer 1 台 ¥3,799
(例)http://amzn.asia/a8nNZOX
2) 1.8V ADAPTER(必要に応じて) 1 基 ¥999
(例)http://amzn.asia/8iOapjP
等があります。もちろんROMライターのソフトを走らせる為のUSBポートを備えたPC一式と若干の工具(ニッパー、半田鏝)も必要ですが・・・。
ほんの少しの手間を厭わなければ、総額4千円以下の金額で、マザーボードのUEFI(BIOS)の直接書き換えが可能となります。書き換えの為だけにCPUを購入する位なら、今後の事も考慮しROMライター、接続ケーブル等の機材に投資しておくことをお勧め致します。
書込番号:21567483
![]() 7点
7点
一つ前の投稿で、
> ここでは結線はICピン8本全部を対象に行っておりますが、EZP2010等のFLASH ROM WRITERとの接続ではICピン#3 (/WP)、ICピン#7 (/HOLD)の接続は不要かも知れません。
と書きましたが、"論より証拠"という訳で検証を行ってみました。尚、検証に使用したROMチップは Winbond W25Q128FVAIQ です。(画像)参照
結果としては、ROMWRITER(EZP2010、SkyPRO)での読込み/書込み動作では、ICピン#3 (/WP)並びにICピン#7 (/HOLD)の接続はやはり不要でした。
ですので、JSPI1接続用のワイヤー・ハーネスの作製に必要な最低限必要な極数のミニQIケーブルは、
1) ミニQIケーブル (2S-Z) 1 本 ¥87 (2極 JSPI1 PIN#4:DI, PIN#6:CLK 接続用)
http://eleshop.jp/shop/g/gAA741F/
2) ミニQIケーブル (4S-Z) 1 本 ¥108 (4極 JSPI1 PIN#1:Vcc, PIN#3:DO, PIN#5:/CS, PIN#7:GND 接続用)
http://eleshop.jp/shop/g/gAA741H/
となります。
書込番号:21569450
![]() 2点
2点
本スレッドの投稿の内容に関し新たな事実が判明しましたので、内容の一部を追補させて頂きます。
新事実とは In Circuit Programming (ICP) に関することで、JSPI1ヘッダーの9番ピンを地気(GND)状態に落とすことによりSPIインターフェースのCPU側が隔離され、CPUをソケットに装着したままでUEFI(BIOS) FLASH ROMチップの読み書きが可能となることです。
ここで注意が必要な点は電源供給に関することで、CPU側を隔離状態にするためにはマザーボードが通電状態(電源ON)になっている必要があるという事です。拠って、ROMチップのVCC(1.8V)はマザーボード側から供給されますので、ROMライター側から供給してはいけません。(画像-1)参照
従って、ICPにてROMライターで読み書きを行うには、
JSPI1 ROM Writer
Pin# Pin#(DIP8)
(1 or 2 ---- Vcc ---- 8) (<--- ICPの場合には接続しない)
3 ---- DO ---- 2
4 ---- DI ---- 5
5 ---- /CS ---- 1
6 ---- CLK ---- 6
7 or 8 ---- GND ---- 4
9 ---- ICP ---- GND
の接続が必要です。尚、JSPI1のPin#11並びにPin#12は、EZP2010,SkyPRO等のROMライターを使用する限りに於いては、Quadモードは使用しませんので接続は不要です。但し、ロジ・アナ等で通常動作時のSPI信号をキャプチャーしようと計画されている方はQuadモードも使用されますので、結線して置くことをお勧めします。(画像-2)参照
書込番号:21578124
![]() 2点
2点
一昨日GIGA GA-AB350N-Gaming WIFI + A10-9700Eのサブ機をRaven 対応BIOSに更新かけたら
まさかのフリーズ、復旧しようとググってたらこちらを見つけました。
EZP2010は持ってたのでAMAZONから1.8V レベル変換下駄とSOP8 クリップを速攻で取り寄せ
こちらを参考に無事復旧できました。UUID,S/N etcはこれからですが。
ちなみにSPI Flashは1.8V Macronix MX25U12873Fです。
MSIのようにJSPI1ピンヘッダがなくSOP8 クリップをつかいましたが、ちゃんとコンタクト取るのに
だいぶ苦労しました。
お陰で回り道せずに短期で修復できました。 ありがとうございます。
書込番号:21592959
![]() 2点
2点
自分のPCのBIOSの更新を失敗してしまい、にっちもさっちもいかなくなり色々とググっているうちにこちらにたどり着きました。
ここにくるまでの断片的な情報でROMライターを使ってMSIマザーのJSPI1ピンから直接BIOSを焼きこめるというのはなんとなくわかったのですが、そこから先の具体的な情報が見つからず途方に暮れていましたが、Springbokさんの実演を兼ねた情報で光が差した気がします!
電子工学知識0なのでまだまだ先は長いですが、ここの情報を頼りに頑張ってみようと思います!
素敵な情報をありがとうございました!
書込番号:21754713
![]() 0点
0点
tm1001さん、
>こちらを参考に無事復旧できました。
こんなニッチな情報でも少しでもお役に立てた様で良かったです。
>SOP8 クリップをつかいましたが、ちゃんとコンタクト取るのにだいぶ苦労しました。
そうなんですよね〜。自分もPomona社製のClipを試してみましたがうまく固定出来ませんでした。
一休さんさん
>電子工学知識0なのでまだまだ先は長いですが、ここの情報を頼りに頑張ってみようと思います!
かなりニッチな内容の上ある程度の電子工作経験者を対象に書いたので、判りずらかったのではと思いますので、何か不明な点があれば自分の判る範囲でお答えしますのでお問い合わせ下さい。
書込番号:21759753
![]() 0点
0点
マザーボードがちがうのですがb55-cd53のbiosがM-FLASHで更新後に起動しなくなってしまたのでjspi1からromライターで書き込みは正常に終わるがverifyでエラーとなるため、読み込んでみると一致していないことがわかります。ICはmx25L3205Dですが、何故書き込みができていないのかご教授ください。取り外し可能なICには書き込みができているのは確認できたのですが、このタイプのICには書き込めません。WHR-G301無線ルーターにもこのmx25l3205dが使われているので試してみましたがだめでした。
書込番号:22049793 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
>MSI2さん
> romライターで書き込みは正常に終わるがverifyでエラーとなるため、読み込んでみると一致していないことがわかります。
ROMライターにて Write操作でデータを書き込む前に Erase操作を行ってチップ全体の消去を行っていますか?
書込番号:22050352
![]() 0点
0点
早速の回答、ありがとうございます。eraseは行っています。自動でも行いましたがverifyでエラーになります。全く、書き込めていないようです。
書込番号:22053058 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
書き忘れましたが、detectができないようです。海外のサイトでも同じような人がいましたが、解決方法まで読みとれませんでした。今使っているromライターは、ch341aです。ezp2010ですとchip errorになって全く動作しません。脱着式のIC chipですと問題なく読み書きできるのですが、JSPI1とクリップは成功したことがありません
書込番号:22053081 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
MSI2さん、
状況、大まかではありますが了解しました。
> detectができないようです。
> ezp2010ですとchip errorになって全く動作しません。
ezp2010の場合には手動にてチップ選択しても Chip Error 状態なのでしょうか?
> 脱着式のIC chipですと問題なく読み書きできるのですが、JSPI1とクリップは成功したことがありません
当初は当該マザーボードのJSPI1が旧タイプ(10P,2x5)でFLASHチップも旧タイプでQuadモードを有していない等の点から、#3ピン(/WP), #7ピン(/HOLD)辺りの接続方法に何らかの問題があるのかもしれないと考えていたのですが、全ピン接続のICクリップでもダメな様なので、これが問題ではなさそうです。
後、どの様な長さのJSPI1接続ケーブル並びにICテストクリップを使用されているのでしょうか? (ケーブルの長さが長い場合には、信号波形劣化により誤動作していることも考えられます)
もう一点考えられるのは、ROMライターからのVCC電圧供給が過大負荷等(SPIマスター機能を持つチップセット側にも流れ込んでいる???)により不安定化している
今のところこれくらいしか思い付きません。
参考までに、市販のGZUt製のJSPI1接続ケーブルの接続図を(画像-1)に添付致します。
書込番号:22055506
![]() 0点
0点
JSPI1ケーブルの長さが影響しているのかもしれません
>ezp2010の場合には手動にてチップ選択しても Chip Error 状態なのでしょうか?
⇒手動でチップを選択していますが、Chip Error になります
>後、どの様な長さのJSPI1接続ケーブル並びにICテストクリップを
>使用されているのでしょうか?
⇒ICテストクリップは30cmです。
⇒JSPI1は2.0mmピッチの5pinと4pinのケーブルを合わせて使用しています。
長さは5pin側が70cmで、4pin側が45cmになっています。
さらに、5cmの配列変換ケーブルを使用してROMライターに接続しています。
もう一点考えられるのは、ROMライターからのVCC電圧供給が過大負荷等(SPIマスター機能を持つチップセット側にも流れ込んでいる???)により不安定化している
>参考までに、市販のGZUt製のJSPI1接続ケーブルの接続図を(画像-1)に添付致します。
⇒現在接続は下記の5pinのみ接続しています。
JSPI1 ROM Writer
3 ---- DO ---- 2
4 ---- DI ---- 5
5 ---- /CS ---- 1
6 ---- CLK ---- 6
8 ---- GND ---- 4
書込番号:22055787
![]() 1点
1点
MSI2さん、
> ⇒ICテストクリップは30cmです。
> ⇒JSPI1は2.0mmピッチの5pinと4pinのケーブルを合わせて使用しています。
> 長さは5pin側が70cmで、4pin側が45cmになっています。
> さらに、5cmの配列変換ケーブルを使用してROMライターに接続しています。
どうやら全ての問題の根源はこれらのケーブルの長さに起因するものと思われます。取扱う信号周波数成分は数10MHzオーダーの高周波信号ですので、短ければ短い程良好な結果が得られます。思い切って短くして(必要最小限程度まで)みて試して下さい。 (ICテストクリップのフラットリボンケーブルでは、一説に寄ると長さ20cmでもエラーを起こす場合もあるらしいとか)
> ⇒現在接続は下記の5pinのみ接続しています。
>
> JSPI1 ROM Writer
> 3 ---- DO ---- 2
> 4 ---- DI ---- 5
> 5 ---- /CS ---- 1
> 6 ---- CLK ---- 6
> 8 ---- GND ---- 4
FLASH ROMチップへのVCC電圧(3.3V)供給はどうするのでしょうか?
マザーボード側から供給するつもりなのでしょうか? もし、そのつもりなら止めて置いた方が良いでしょう。下手をするとマザーボード、ROMライター等を壊し兼ねません。このスレの前の方で紹介している ICP に於ける手法は MSIのAM4マザーボードの新JSPI1ピン・ヘッダーでのみ有効なものと推測されますので。
書込番号:22056677
![]() 1点
1点
自分の手元にある B350M MORTARのROMは「MX25U12873F M2I-10G」というMXICのROMのようです。
手元にあるルーペでなんとか見えました(カメラじゃ映らなかった)
TR4マザーのx399 taichiにも使われてる物ですね。
「1.65 to 2.0 volt for read, erase, and program operations」
とあるので1.8vの低電圧のものだと思います。
書き込みができてないというコメントがありますけど
「Low Vcc write inhibit is from 1.0V to 1.4V」
これじゃないですかね?
自分はパラレル(D-sub25pin)でやってみますが、電圧・電流
どこまで流していいのか、駄目なのか、ちょっとずつ調べながらやっていきます
(パラレルからの4.3vをvccの1.8v以下にしなければならないというのは勘で理解しました
実際もっと低くしなきゃいけないのでしょうけど、勉強します・・。
vccは700mA程度の電池で昇圧回路使ってやろうかと)
ど田舎なのに電子部品ショップがあるんで助かってます。500〜1000円ちょっとでBIOS書き換え修理ができるのは嬉しい。
書込番号:22152671
![]() 0点
0点
kitoukunさん、
> 自分の手元にある B350M MORTARのROMは「MX25U12873F M2I-10G」というMXICのROMのようです。
MACRONIX(MXIC) MX25U12873F ですが、1.8V品では最近台頭してきている様ですね。特に ASRock 製のAM4マザーボードではよく使われているみたいです。
> 手元にあるルーペでなんとか見えました
最近のチップのマーキングは本当に読み難いです。自分もコンデジのマクロモードで撮影したものを拡大してみたり、20xの携帯型双眼実体顕微鏡まで使用したりで結構難儀です。(照明の加減、手ぶれ防止が特に難しい)
> 自分はパラレル(D-sub25pin)でやってみますが、電圧・電流
> どこまで流していいのか、駄目なのか、ちょっとずつ調べながらやっていきます
もう既に MX25U12873F のデータシートをご覧になっている様ですので一言だけ、”ROMチップを飛ばさないようにくれぐれもご注意下さい。”
最後に、JSPI1ピン・ヘッダー 〜 ROMチップ 〜 CPU(APU)ソケット間の内部接続を更に調査しましたので改訂版の内部結線図をご参考までに(画像-1)に示します。尚、この改訂版ではICP関連のことは回路を追えなかった為敢えて触れていませんが、この機能が有効なのは最近のマザーボードの B450 GAMING PLUS でも確認出来ております。
書込番号:22163023
![]() 0点
0点
一応マザーボードに乗っかっているROMのダンプは成功しました。Springbokさんが書かれてる通りのアドレスに
同じような内容がありました。ただ、2回目やろっかなーと /i 実行したら Parity error!の文字と明らかに異常値の000000h
1回目では MX25U12835F (16MB) でした。のっかっているのが12873Fで、同じようなものなので大丈夫かなとは思ってますが
それ以降は全然反応ありません(一度も;;)
この状態だと書き込みは無理ですね・・
回路は抵抗で分圧したものを電解コンデンサと極性のないセラミックコンデンサーでつなぎ、そこから1.8vを取り
レベル変換には2SC1815を2個用いたものです(高周波数用です)
ダイオードはvcc(1.8v)を超えないためにするためのものだそうで、そこらにあるシリコンダイオードを入れましたが
調べてみると「高周波数対応」のものもあったり、色々特性があるダイオードが書かれてます。
SPIPGM配布元にある1.8vのやりかたとほぼ変わりありませんが、金属皮膜抵抗は使っておらずカーボンのみの構成です
成功してる人のページを見ると金属を使ってるようなのですが、やっぱり金属を使ったほうがいいのでしょうか?
金属皮膜抵抗器が望ましいのか、そもそもこの回路が間違ってるのか、シリコンダイオードが間違ってるのか
LPTポート側ーーーーJSPI側(ROM側)
(SCK-2kΩ(1.8kΩ)ーCLK)
(MOSI−2kΩ(1.8kΩ)ーDIO)
(AKC(MISO)-2SC1815コレクタ→ベースー2SC1815コレクタ→ベースー2kΩ(1.8kΩ)ーDO)
(CS#-2kΩ(1.8kΩ)--/CS)
(GND-GND)
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
なかなかむつかしいです
奇跡の1回ダンプ成功で何かが壊れてしまったのでしょうか?
Ryzen 3000対応のベータBIOSが出ているので
試してみたかったのですけどね
(線の長さはこれ以上短くするとマザーにつなげられませんw)
成功したらまた書き込みに来ます。UUID等は得られたので(これが正確なものなのかはさておいて)頑張ってみます
書込番号:23275355
![]() 0点
0点
MX25U12873F
他のデバイスと違い、データ保護やら書き込み保護の機能があるようです。過去初心者の時にどうせ壊れてるならと
勢いで書き込みを行った事があり、後に後悔してましたが、そんな人間を救うための保護機能があるようで一切書き換えられていませんでした。
なので今回無事にデータを再度得ることができました。(過去のデータは無くした)
抵抗は(全て)1kΩ推奨のようで、自分は1.2kΩ(トランジスタのベースとコレクタに接続しているもの)と2kΩ(信号線)ですが、この抵抗はLPTポート側ではなく、SPI側に取り付けるようです。(写真は失敗例 これだとまともに通信できない)
SPI側にすると信じられないくらい良好な状態になりました。(JSPI差込口付近もしくはICクリップ付近に半田付けして追加する)
しかしエラーが一切ない状況は作り出せていません。
上手く行かないのはこの抵抗のせいかもしれないので、近い内にすべて1kΩにします。(確か必要個数は5個。できるだけ金属皮膜で揃えましょう)
ダンプは毎回先頭部分の限られた区域のみ"ベリファイ"で失敗し、失敗箇所をghex バイナリエディタで開くと「FF」が並んでるだけと言う状態です。元々読めない領域なのだろうか。しかし公式のは "ちゃんと見える状態" 。
個別IDだけを抜いたものを公式の正常なBIOSの同じアドレスにペーストし、これをFlashromで書き込むという
準備はできていて、後はエラーがない事と、書き込めるかどうかだけです。
パラレルポート経由のSPIなのでRayer_spiを使います。
flashrom --programmer rayer_spi -L
だーっと出てくるリストの中に「Macronix MX25U12835F PREW 16384 SPI 」が出てきますが
https://www.mxic.com.tw/Lists/Datasheet/Attachments/8393/MX25U12835F,%201.8V,%20128Mb,%20v1.2.pdf
https://www.mxic.com.tw/Lists/Datasheet/Attachments/8681/MX25U12873F,%201.8V,%20128Mb,%20v1.2.pdf
90ページと93ページ… rayer_spiはRayeRさんが作った物です。LPTポートをSPIのデバイスとして使うためのカーネルモードのドライバのようなものだと思います。
LPTポートを触る場合管理者権限が必要になるので以下のようにコマンドを入力
sudo flashrom --programmer rayer_spi
[sudo] Username のパスワード: **********
flashrom v1.2 on Linux 5.15.0-71-generic (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Using clock_gettime for delay loops (clk_id: 1, resolution: 1ns).
Using RayeR SPIPGM pinout.
Found Macronix flash chip "MX25U12835F" (16384 kB, SPI) on rayer_spi.
No operations were specified.
WindowsでのSPIPGMと同じで「MX25U12835F」でした。
ではこちらでも「お試しダンプ」します。
sudo flashrom --programmer rayer_spi -r B350Linuxtest0503.rom
rayer_spiは自動検出なので、チップの指定は必要無いです、多分
Reading flash... done.
doneが出れば完了。パーセント表示なし
保存場所は /home/user
16.8?MB (16,777,216 バイト)
そのままベリファイします。
sudo flashrom --programmer rayer_spi -v B350Linuxtest0503.rom
Verifying flash... FAILED at 0x0001416a! Expected=0x00, Found=0x20, failed byte count from 0x00000000-0x00ffffff: 0xa3
だそうです。凄く大雑把な表示だけど 10進数では「163」12873Fの最初のアドレスから最後のアドレスまでに163個の
エラーが検出されましたと言う意味。失敗の表示アドレスはおそらく最後の失敗のログ
今と同じ長さの1kΩのケーブルを作ってみて、それからかな。この状態だとおそらく書き込みも出来ないと思う
CPUのロックのレバーが上に上がってるのは、下に下げてるとノイズになっちゃわないかなと思ったためです。
1kΩ交換を行い、それでも駄目なら次は電源ですね。本体の電源を入れないと1.8vこない事は確認済なので
チップへの電源供給をマザーボードに任せて、3v〜5vのダーリントントランジスタへの供給は電池か電源5vをケーブルから持ってくる事にします。アースは共通ですが、問題はどこにするか、かな?
使い物にならなくなったLPT(D-sub 25pin)の代わりにステンレス棒を突っ込んでるのですが、これがノイズになったりもするんだろうか。ケーブルのSPI側の先端にテープ貼り付けてますが、あそこに抵抗を半田付してます。
当時ちゃんと理解して「熟読」していればもっと早く解決へ進めそうだったのですが、手探り状態でそれでも
前に進めたことは良かったと思います。 少なくとも半田、ヒューム、吸い込み器等の知識は学べて良かったです
(4年以上かかってるってどうなの)
不思議なのはパソコンのパラレルポートからSPIで1.8vROMに書き込みをする人がいなかった点ですね
皆便利なネットショップで入手した回路使ってましたし
書込番号:25246444
![]() 0点
0点
CH341aで書き換えられない系統の原因は爪と固定する部品の接触ができていない事が大半の原因だそうです。
自分はLPTポート経由のSPIでやってますが、こっちは殆どが自作回路の出来の問題だと思ってます。
ノイズが乗りやすい、作られやすい原因はGNDを広げたり、電流の行き帰りの長さが違うような状況(+の配線や信号線と長さの合わない場所に接続したりすること)を作り出すことが原因のようです。ケーブルの長さは余り関係がなかったですが、+と-の行き帰りのケーブルというか回路の距離は同じにした方がいいです。
ケーブルは全てを入れて20cm超えてますが、15cm以下にした初期に作成した長さの違う、GNDゴチャゴチャ品と比べると
だいぶまともです。初期のやつ(2018年製)はノイズも酷く、そもそもまともにROMチップ読みに行かず(1度成功したきり成功せずレベル)
とても見せられない半田付けの状態で未完成のまま終わりました
今の奴は何度でも読み取って、何度でも同じ結果出してます。これだよ!これを待ってたんだ
GNDラインは一箇所に集約し、他の回路部分の構成だけを変更する事で良い状況の回路が出来ました。
ダーリントントランジスタの電力供給:
電源回路3.3v+ ---- 抵抗1.2kΩ(1.8kΩでも可能らしいがまだ試してない)----2SC1959(Collector) と 2SC1959(Base)の間に入れる。これがダーリントントランジスタによって何倍にも増幅されてLPT PORTの10に信号として送られる模様
マザーボードのFLASHROM等への電源供給のための1.8v?2.0v電源回路:
電源回路3.3v+ ---- 60Ω---|--200Ω---|-----GND ←直列回路に2個の抵抗、60Ωと200Ωの間から負荷のVCCを接続する。
|__負荷__|
GNDは通信側へと接続。
負荷が接続された状態で、理想の電源とならなければ意味がないので、チップを壊さない為にも
代わりとなる負荷を接続し、チップが載った状況と似たような抵抗を選びながら、現在の2v供給回路ができました。
負荷に接続するのが今回のROM(MX25U12873F)
接続するとちょうど2.0v付近にて安定する。 ここの抵抗は炭素皮膜で問題無い(と思います 金属あるならそちら使ってね)
GND:3.3v電源GND--ステンレス棒で橋渡し--2.0v分圧回路のGND
|---ステンレス棒で橋渡し----JSPI(7) GND---2SC1959(Emitter GND)---2SC1959(Emitter GND)---LPT Port(Pin No 18-25の内どれか1つとL字型ステンレス棒で接続。回路組んだ後は22-25辺りが良い位置 必ずしも説明にあるような「18番」である必要はない。18番から25番全て接続しろと書かれてるホームページがあるが、あの通りに従ってはいけない。(多分アレ書いたの学生)GNDの中に回路が出来てしまうし、ノイズも大幅に上昇した。)
やり方次第で2.0v分圧回路のGNDも同じラインに持ってこれて、シンプルに出来ると思います。
DO: ※抵抗はJSPI側によせて付ける。LPT側につけるとまともに動作しない。ROM検出すら失敗します。
JSPI(3)-メスピン-半田----抵抗1.8k?2kΩ----半田====緑色ケーブル====オスピン:ブレッドボード-2SC1959(Base)--2SC1959(Collector)--橋渡し用ステンレス棒---2SC1959(Base)--2SC1959(Collector)--L字型にしたステンレス棒:LPTポートACK(10 MISO)
DI: ※抵抗はJSPI側によせて付ける。
JSPI(4)-メスピン-半田----抵抗1.8k?2kΩ----半田====青色ケーブル====オスピン:ブレッドボード--橋渡し用ステンレス棒-----L字型にしたステンレス棒:LPTポート(9 MOSI)
/CS ※抵抗はJSPI側によせて付ける。
JSPI(5)-メスピン-半田----抵抗1.8k?2kΩ----半田====灰色ケーブル====オスピン:ブレッドボード--橋渡し用ステンレス棒-----L字型にしたステンレス棒:LPTポート(7 CS#)
CLK ※抵抗はJSPI側によせて付ける。
JSPI(5)-メスピン-半田----抵抗1.8k?2kΩ----半田====紫色ケーブル====オスピン:ブレッドボード--橋渡し用ステンレス棒-----L字型にしたステンレス棒:LPTポート(8 SCLK)
2SC1959(npn)は2個で、ダーリントントランジスタ。有名な2SC1815でも出来ると思います
抵抗の値は大事ですが、一番大事なのはGNDです。これがあちこちに分岐させたりすると
エラーが何万個と多発し酷い結果になります。
flashrom v1.2 on Linux 5.15.0-71-generic (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Using clock_gettime for delay loops (clk_id: 1, resolution: 1ns).
Using RayeR SPIPGM pinout.
Found Macronix flash chip "MX25U12835F" (16384 kB, SPI) on rayer_spi.
Verifying flash... FAILED at 0x0001479e! Expected=0x00, Found=0x80, failed byte count from 0x00000000-0x00ffffff: 0x5f
こんな感じになります。
0x5fがもっと小さいと優秀な回路になりますね。ガンバって0を目指します。0でなくても2程度ならマシンは起動するかもです。ちなみに今まで読み込めなかった初期のアドレスの数値、ちゃんと読み込めました。
電源電圧の数値は大事なんだなぁ・・・(あと低ノイズも)
問題は「書き込み」についてですね。Asprogrammerが利用できれば良いんだろうけど行けるかなぁLPT…。
回路の部品や製作した手作りケーブルは書き込みが無事終わってからアップロードします。
とにかくエラー0を目指します。GNDの配線ミスって黒でなく白色にしちゃったのが原因なんだけどなんとかなりそうです。(ちょっと遠い)念には念を入れて、ケーブルはそのままの状態で黒色ケーブルをGNDにします。
書込番号:25259055
![]() 0点
0点
消去に成功。その直後に行ったダンプファイルを見ると全て「FF」で綺麗に埋め尽くされてます。
つまり今まで出来なかった「書き込み」が行えたという事になります
その後書き込みを行ったが、ベリファイでのみ大量のエラー。内容は「アドレス0x00000000-0x00ffffff」で、「0x1804b4」箇所間違ってるという内容。今までのエラーはもっと範囲の小さい、数十件?数千のエラー
しかし今回のエラーは何だこれ?こんなに綺麗に書き込み出来てるのにエラーがこんなにあるだと?
この手のエラーって途中のどこかでFFか00で埋まってる事を示してるんだけど(違うのであれば初期のアドレスからそこら中にちらほら化けが発生する)
0x307a20の数のエラー・・・「3176992」
もう一度やってみると・・・・
0x35d385の数のエラー・・・「3527557」 ふ、増えてる・・・何も外したりもしてないんだぞ
しかし実際のダンプしたファイルは画像のように美しい。書き込み指定したファイルが本番用の「B350M_E7A37AMS.1O6」。これは公式配布のデータに自分のマザーのUUID,シリアル等を書き込んだもの。
sudo flashrom --programmer rayer_spi -w B350M_E7A37AMS.1O6
で、LPTポートに接続されたFLASH BIOS ROMへの書き込みが始まる。ここで失敗をする場合はおそらく書き込みに必要な最低電圧と4.3v <->1.8v レベル変換回路、ケーブルの接触不良をクリアできていない。
Using clock_gettime for delay loops (clk_id: 1, resolution: 1ns).
Using RayeR SPIPGM pinout.
Found Macronix flash chip "MX25U12835F" (16384 kB, SPI) on rayer_spi.
Reading old flash chip contents... done.
Erasing and writing flash chip... Erase/write done.
Verifying flash... FAILED at 0x001cd9cf! Expected=0x46, Found=0x0d, failed byte count from 0x00000000-0x00ffffff: 0x1804b4
Your flash chip is in an unknown state.
Please report this on IRC at chat.freenode.net (channel #flashrom) or
mail flashrom@flashrom.org, thanks!
と出てくる。エラー大杉っすわー。(接触不良だったブリッジは交換したけど、小さな振動で変化するようなものがまだあるのだろうか)
どちらにしろ読み込み、消去、書き込みはできました。
そうです、中国製品を使わず、パソコンだけで他マザーのBIOSを修復したりアップデートしたりできたのです。
LPTポート経由で簡単な分圧回路(負荷接線後に2.0vになるよう調整)ダーリントントランジスタと抵抗を用いた回路による電圧コントロール。
そしてATX電源の3.3v(ここはお任せします。PC本体からの5vでも調整さえすればおそらく可能)
Linux Flashrom RayeR_SPI 開発、この板の皆さん、情報提供者に感謝です。
用いたもの:古いUbuntuパソコン、時間 JSPI側に2kΩ*4(新作ケーブル時に1.8kΩ*4に変更)のついたケーブル20cm-25cm程度 ブレッドボード(試作用ボード) サンハヤトの100円ユニバーサル基板(ハンダまみれ)
ハンダ(犠牲多数) ケーブル(犠牲多数) ステンレス棒(いくつかに分断された) 積層セラミックコンデンサー(いっぱい購入したけど、いらないって?抵抗に並列で使うと反射神経あがるらしいよ) 普通の電解コンデンサー
Panasonic製のスイッチ(電源についてるしあんまり意味無くなった。元々電池でやってたので・・・)
アルミホイル(意味あるか不明だけど、ケーブルに巻き付けた。アンテナになる?ならない?)
どっかのケーブルについてたUSB単子のケーブルのメスピンを剥がしたもの(100円でも売ってますが、JSPIにはスカスカで刺さらないので、ベンチで先をちょっと潰すw)
トランジスター2SC1959 Rank:O 安ものです。 (2SC1815-GR ハイグレードなコレでも多分出来ます。周波数300MHzとは書いてないけど)
ヒートクリップ(めっちゃ役に立った) ハンダゴテ(色々学習できました)
銅のスポンジ(ある意味犠牲者) 非伝導性粘着性のある黒い自己融着テープ(工事用かな?高いやつ)
普通のセロハンテープ(一応非伝導性らしいけど、多少は流れると思う)
お世話になったお店:
パルス電子(東京秋葉原を拠点に国内・海外に幅広く活動してる電子パーツ屋さん)
アヤハディオ(マップやヨドバシ行かなくなった代わりにここへは良く行く)
ヴェリファイは過去に74とかの小さな数値を叩き出した事があるので
どこかしらに接触不良になりかけてる部分があるのかもしれないのだけど、テスターでの導通チェックは完全にできたんですよねぇ。
書込番号:25268247
![]() 0点
0点
BIOSが起動しないとか、FLASH BIOS ボタンがないとか、BIOSの書き換え、BIOSの修理、BIOSの修復等で困ってる人がいたらこのSPIで書き込むチャレンジができるのでまずはこういう方法もあるよと教えてあげたり、試して欲しいと思います。
最初は真っ暗な洞窟や草むらを進むような気分ですが、成功すれば気持ちが良いものです。
通信の部分は金属抵抗を使ってますが、カーボン皮膜抵抗でも可能なのではと思い始めてます。
参考程度に電圧の変化をここに記載しておきます
MX25U12873Fの Vcc 2.0v-1.95v (理由知らないが最初の2.01vより少し下った 何で…分圧回路はカーボン皮膜抵抗。金属推奨 知らんけど)
JSPIのピンの番号(必要な部分のみ)
87 -GND- 内部で1つに接続されてます。2つ繋げる意味無いです、どちらか1方でOK。ATX電源ではCOMMON線
65 :6はCLK.パラレルポートでは8番目 :5は/CS パラレルポートでは7番目
43 :4はDI ,パラレルポートでは9番目 :3はDO パラレルポートでは10番目
21 -Vcc- ここに2.0v 1.95v 等の1.8v用電圧の供給を行う
パラレルポートはマザーボードについてるメスピンを正面に見て右上から13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1と右下に番号がふってあります。 左下からは14,15,16,17,18と番号があり、18から25は全てGNDで共通です。
JSPI(ROM)側の電源供給が停止中の時には
JSPIの3、パラレルポートともに0vを示し
JSPIの4,パラレルポートともに0.08vを示します。
JSPIの5は1.29vを示し、抵抗よりパラレルポート側では3.25vを示しています。
JSPIの6は1.29vを示し、抵抗よりパラレルポート側は0.10vを示します。
JSPIの1と2は分圧回路から2v前後を供給
JSPIの7と8はGNDの役割として電源側のGND、パラレルポート側のGNDと接続してください。(パラレルポート側だけ接続するだけでも最後にコンセントで繋がってるので可能のようですが基準電圧となるので基板上で接線が好ましい。とありますがそれをすると急にエラー吐き出したんですよね・・・謎)
*抵抗は1.8kΩの場合です。
ROM側の電源を入れると5と6はROM側の電圧が1.72vになります。
ケーブルはわかりやすいように
3=緑
4=青
5=灰
6=紫
Vcc=赤もしくは黒もしくは白
GND=赤もしくは黒もしくは白
と分けてます。回路の配置次第でケーブルの使い方(割いて使わない場合)も変わるので固定をする必要はないですが
端子のミスには注意して下さい。ただまともな電源(うちはSeasonicです)ならば+-間違えても即電源がシャットダウンするような構造になってるので、ダメージにはならないと思います。
書込番号:25268260
![]() 0点
0点
いろんなサイトを回ってこちらが一番詳しく記載されていらしたので
書き込みさせていただきました。
CH314Aにて接続を試みているのですが
旧10ピンではうまくいくけど新12ピンではダメなのは何故でしょう?
アリエ〇にてどちらにも互換性があるというハーネスを購入し使用しています。
アサインをたどるとこちらの記載内容と同じでした。
マザーボード側の2mmピッチのコネクターは12ピンです。
古いマザーですが ZH77A-G43 の JSPI1 は10ピンで
1番ピンの位置を合わせて接続し
AsProgrammer_2.1.0 にて認識し書き換えも無事できました。
ですが H81M-P33 は 12ピンで
これを接続するとチップの認識が出来ません。
チップはどちらものマザーも
WINBOND の W25Q64FVSIQ なのですが
認識しません。
何かご存じの方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:25902165
![]() 0点
0点
CPUとメモリを外していることを大前提として
電源も25Q64FVSIQに供給している状態で
SPIを使う時、/WP /HOLD はhigh固定にするとか条件がなければそのまま使えますが
特にQE=1固定という制限もなく
https://youtu.be/nKy57RmuxWM
https://youtu.be/lmYXiE2fQ6E
flashromから試していても無理なら無理という事なのでしょう。
WINBOND の W25Q64FVSIQ は64MBIT = 8MBYTE
E7817IMS.1A0の容量は8192KBであってますし、ピンからうまくいかないのであれば
ピンから25Q64FVSIQへの配線のどこかで事故があったのかもしれません。
自分は最終的にこのマザーのJSPI1による書き換えが成功しましたが、別マザーの
QSPI固定のFLASHはQSPI環境必須(工場出荷時設定)なので無理でした
マザーボードから取り外し直接接触させれば書き換えもできるかもしれませんが
一応念のため確認しますが、 H81M-P33 のマザーは現在も起動可能でしょうか? 起動不可能でしたらそもそもブツが壊れてる可能性が高いです
自分が修理したのは「BIOS書き換えるまで健康だったマザーボード」の修復なので、ROM自体は壊れているとは思ってませんでしたから。
書込番号:25905870
![]() 0点
0点
>きとうくんさん
拾っていただいてありがとうございます。
はい。
このマザー自体は問題なく起動し
USBメモリーから
BIOSアップデートも可能です。
ダウングレードも出来ました。
ピンアサインを疑いさらに
Z390 GAMING PRO でも
試してみたのですが
こちらも一回で認識し
読み出しも問題なく出来ました。
ちなみに苦労して
付属のクリップで挟んでも
H81M-P33のチップは認識せず
機種を手動で設定しても
保護解除や読み込みは
出来ませんでした。
QSPIというモノに
まだ理解が追い付いてませんが
そういったものもあるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
もうちょっと追いかけてみます。
書込番号:25909880
![]() 0点
0点
H81M-P33は手元にないので、ピン配列がどうなっているか調べる事ができません
もしデジタルテスター等をお持ちであれば、ショートしている部分を+-端子で接触させると「ピーーーー」ってなるあの機能で
どのピンがどこの足につながっているのかを調べる事ができます
やり方は簡単で、短絡チェックモードでまず右下にあるピンを固定し、ROMチップの足の部分8か所に1つずつ当てていきます
間に抵抗が何もない所だとそこは「同じ線の上」なので抵抗は0に限りなく近い、つまり同じ線上にあるということです
ブザーがなれば抵抗0ということなので、その当てた場所(ROMの足の部分)とピンの1つが同じ組み合わせということになります
ROMの足の部分がどこに当たるかはROMチップの型番のデータシートに書いてます。(各自調べましょう)
今回当てたピンと照らし合わせて、ノートに絵でも書いておきましょう。
これを順番に1つ1つ8か所で調べていけば、どこがどの役割のピンなのかが判明するはずです。
僕自身はケーブル自作してます。市販のだとピン配列とケーブルが違った場合、どうしようもないので
書込番号:25948698
![]() 0点
0点
半透明扱いになってたので再度投稿
これで調べて、flashromのような便利なツールからCH341Aのハードウェアを利用して書き込み等を行えばうまくいくと思います
flashromはサポートが幅広いので linuxはubuntuで構いません。 sudo apt-get install flashromで普通に入れれたと思います
書込番号:25948739
![]() 0点
0点
今更遅いかもしれませんが
>タヌキと共にさん
「7.1.10 クアッド イネーブル (QE)
クアッド イネーブル (QE) ビットは、ステータス レジスタ (S9) 内の不揮発性の読み取り/書き込みビットで、クアッド SPI および QPI 操作を可能にします。QE ビットが 0 状態 (注文オプション「IG」および「IF」の部品番号の工場出荷時のデフォルト) に設定されている場合、/WP ピンと /HOLD が有効になります。QE ビットが 1 (工場出荷時のデフォルト) に設定されている場合、/WP ピンと /HOLD が有効になります。クアッド対応部品番号(注文オプション「IQ」付き)の場合、クアッド IO2 および IO3 ピンが有効になり、/WP および /HOLD 機能が無効になります。」
とマニュアルにはあるので、Quad Enable bitが工場出荷時で1の場合(25Q64FVSIQ) /WP, /HLODピンの役割は/IO2 /IO3となるはずなので、従来のSPIとの互換性は無くなると思います。
一緒くたの製品にされてはいますが、明確にこの部分だけは区別をしていて、別の製品になってますね。
今まで「SkyProやその類のSPI書き込み」ができた人と、出来なかった人がいるのは
このROM自体の仕様のせいだったと理解しています。
エリート博士号持ちですらその事に気付かず苦労されていたので、僕らのような一般人では頭の中「???」だらけになりますが
マザーボードにくっ付いてるROMの仕様が従来のSPIと互換性があるものと、全く無いものが混在していると言う事です。
QPIやQuadSPI接続をした後からこのQEビットを1から0に変更する事は出来ないようです
要するに、ハズレのROMの場合はQSPI対応のハードウェア(STM32〜FlashPro等)を所有していないと読み書きが出来ないという
事になります。
そういうたぐいのものがなければ「ヒートガン」で互換性のないROMのハンダを溶かして抜き取り、予めデータを書き込んだSingle SPI対応のROMを丸ごと交換するという方法でしか治せないみたいです
同じB350Mでも「SIQ」のWINBOND製品が使われていて、Quad Enable Bitが1の製品だったらそこらにあるSPIの方法では修復不能と言う事になります。
BIOS修理屋さんとかはSTM32を所有しているのかもしれませんね。プログラムとか全部自分で用意する必要ありますけど
書込番号:26053319
![]() 0点
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「MSI > B350M MORTAR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2025/01/28 9:28:32 | |
| 7 | 2024/01/22 18:02:42 | |
| 10 | 2024/01/22 23:36:25 | |
| 5 | 2023/06/21 19:57:38 | |
| 8 | 2019/04/18 10:57:14 | |
| 14 | 2018/07/13 0:46:23 | |
| 13 | 2018/03/19 16:04:35 | |
| 0 | 2017/11/27 19:45:31 | |
| 9 | 2017/11/19 18:41:42 | |
| 34 | 2025/01/28 15:11:49 |
クチコミ掲示板検索
クチコミトピックス
- 2月4日(火)
- 飛行機撮影時のカメラ設定
- ホイールを綺麗に保ちたい
- SIMフリー版の良い点は?
- 1月28日(火)
- サウンドバーのお薦めは?
- 野球撮影用のカメラ選び
- CPU交換にアドバイスを
- 1月21日(火)
- 自作PCのBIOSが起動しない
- eSIM利用時のデータ移行
- カメラの買換えアドバイス
- 1月14日(火)
- スマホの機種変更相談
- 画像編集向きのPC性能は?
- カーオーディオの購入検討
- 1月7日(火)
- SIM差替え後、電波が悪い
- TVの音質を上げる方法は?
- 物撮り用のカメラ選び
価格.comマガジン
注目トピックス
- 血圧が測れるスマートウォッチ登場! そのうえ心電図までチェックできるなんて

スマートウォッチ・ウェアラブル端末
- 花粉シーズン到来で空気清浄機のニーズが変化! 注目は集じん性能にすぐれるダイキンとAirdog

空気清浄機
- スバル「クロストレック」はストロングハイブリッドがベストバイ!試乗でわかった“万能感”

自動車(本体)
(パソコン)
マザーボード
(最近3年以内の発売・登録)