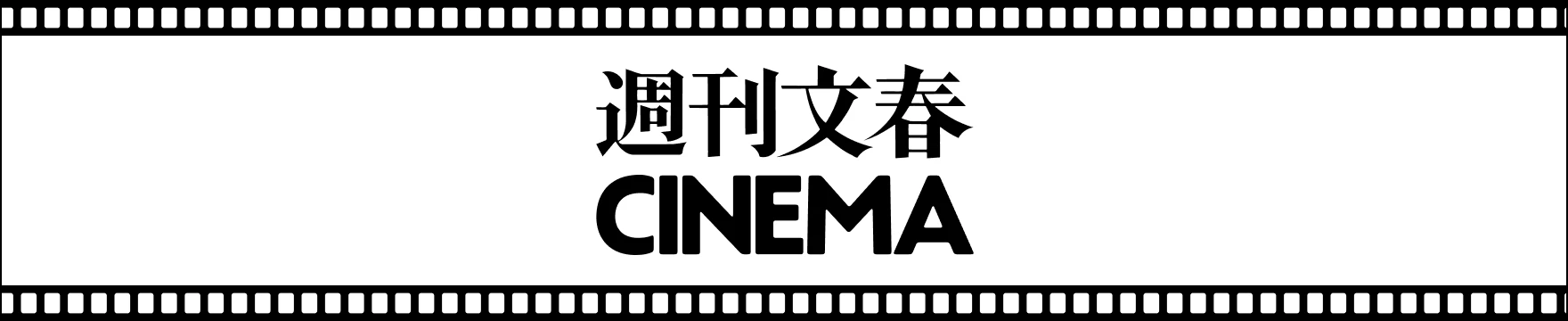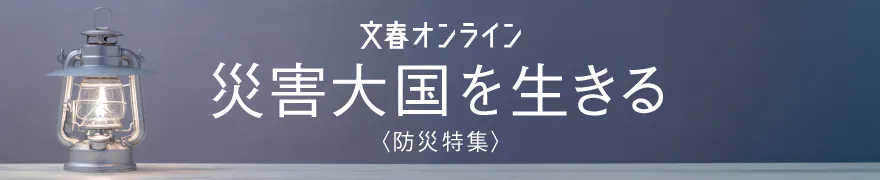宮藤官九郎の書く脚本は、いつも他の誰にも似ていない足跡を残す。例えば朝の連続テレビ小説『あまちゃん』は、ヒロインの幼少期から始まり、成長し結婚して母になる「女の半生記」という朝ドラの黄金律を完全にはみ出している。それは天野アキという1人の少女が16歳から20歳になるまでのたった4年を描いた物語なのだ。
主人公天野アキは物語の中で結婚も出産もしない。だがそのたった4年の青春の1ページの中に、80年代に青春を送り夢破れた彼女の母親、春子の人生が回想として映る。そこには朝ドラの定型である「女の半生記」が主人公の母親の歴史として織り込まれ、同時に80年代に始まるアイドル・サブカルチャー史があり、そして2011年、3・11という同時代の巨大な社会的カタストロフにたどり着く。
海外のティーンネイジフィルム、ガールズムービーを見渡しても、これほど奇妙で定型を外れた、そして同時にこれほど見事な構造を持った作品を僕は寡聞にして知らない。それはアイドルという職業を通した消費社会の中の女性史、女の歴史を描いた物語だったのだ。
大河ドラマのセオリーをはみ出した『いだてん』
『いだてん』もまた、「歴史上の人物の英雄的生涯を1年間追い続ける」という大河ドラマのセオリーをはみ出した作品だった。公式にW主人公とされる金栗四三と田畑政治の2人に加え、物語は明らかに語り手の古今亭志ん生を非公式な3人目の主人公として描いている。
それはまるで落語の三題噺のように、政治と文化とスポーツを3人の敗者を通して語る物語だった。金栗四三は戦争に五輪を奪われ、田畑政治は戦後の五輪を目前に失脚する。そして古今亭志ん生は敗戦の満州でなすすべもなく地を這う。それは僕たちの社会の敗北と失敗の歴史についての物語なのだ。
『いだてん』の準備は2014年末にはもう始まっていたと言われる。TBSのラジオ「ACTION」の中で、宮藤官九郎は2016年にリオ五輪の開会式を見学したことを明かしていた。通常の連ドラでは考えられないほどの長い準備と模索の期間を経て作られている。
この時代を舞台に選べばどう描いても無傷ではすまない、それゆえに誰も描こうとはしないのだ、ということを、宮藤官九郎とスタッフは初期の段階から予期していたはずである。戦前を肯定すれば倫理的な非難を浴びる。否定すれば国民感情の逆鱗に触れる。