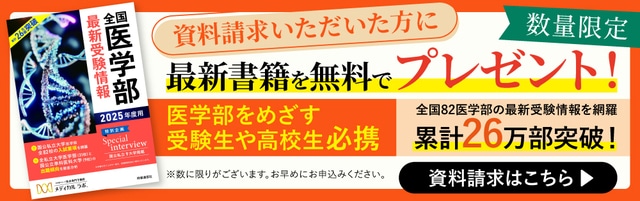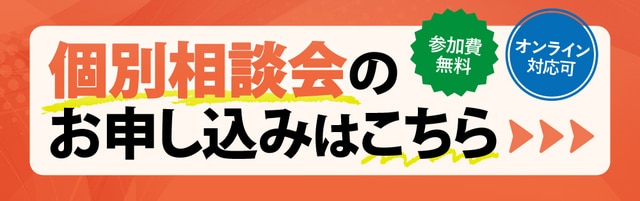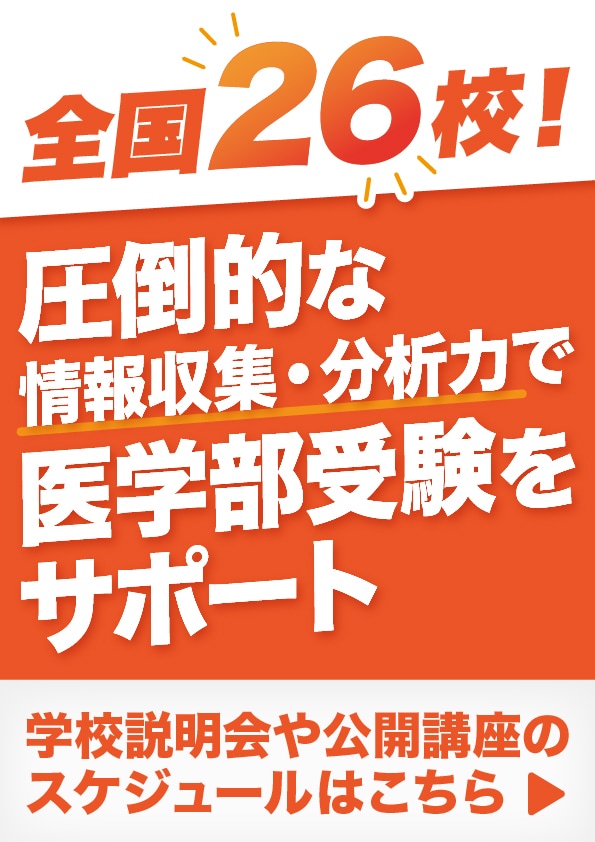テーマ型論文の実例
◆CASE:医師と患者の関係性の中で、特に患者の自己決定権の尊重についての考えを問うもの
【問題】「権利と義務」について、800字程度で論じてください。(800字程度、60分/杏林大学 2022年度・一般選抜・2/2実施)
【解答ポイント】「権利と義務」というキーワードから、患者の主体的に医療を決定する権利(自己決定権)と医師のそれを尊重する義務など、医療現場で重要視されている患者と医師の関係性について論ずる必要がある。
<合格した受験生の小論文>
-----------------------------------------------------------------
医療において①権利と義務は、患者が自ら主体的に医療を決定する権利を有して、医師がそれを尊重する義務を負っていると考えられる。しかし、それは容易なことではない。②インフォームド・コンセントによって全てが可能なわけでもない。
医師は③患者の知る権利を保障するために医療情報を提供して、患者がそれに承認を与えることは、確かに患者主体の医療の実現には必要なプロセスである。しかし、そもそも医師と患者は医療知識において④非対称な関係にある。それ故に、医師は患者に対して優しく教え諭すことになりがちであり、そうなった時に知識面で弱者である患者は医師の意見に疑問を持つことが難しい。そのようなインフォームド・コンセントは、新たな⑤パターナリズムにもなりかねない。
患者主体の医療という本来患者のものである権利を医師はどう尊重すべきか。数日前まで自分は健康で元気であると思っていた患者が定期検査によってがんが発見されたら、酷く混乱するだろう。自分の思い描いていた人生が突然暗転し、自らの権利を行使できる精神状態にはない。医師は、がんという疾患を取り除くために共に闘うのだと、患者をがんと闘う主体に導くことが自身の役割であると思いがちである。しかし、これは医師が考える「医療」という価値観の正しさを患者に押しつけることに他ならない。
患者の人生にとって、がんと闘うことは必要なことだろうか?この患者が80歳代の高齢者であった場合はどうであろう。がんを手術で切除することが「正しい」ことか?と、一度立ち止まって考える必要があるだろう。患者の人生は患者のものである。たとえ「医療」的に正しいと判断される行為であっても、そこに独善的に介入することは許されない。
患者は一人ひとり多様である。手術をすべきかどうか悩み、苦しみの中で人生を生きている患者やその家族に対し、「医療」的な正しさを押しつけるのではなく、まずは寄り添う姿勢を示すことが、患者の権利を尊重するためには大切ではないか。医師に必要なことは「医療」的な正しさが常に絶対だと思い込むのではなく、患者が自らの⑥生(Life)を実現する権利を、尊重する義務を全うすることである。
-----------------------------------------------------------------
(901字)
※編注:Web掲載にあたり、適宜改行を追加しています。
知っておくべきキーワード
①「権利と義務」について、近代以降においては市民が持つ基本的な権利(基本的人権)は何ものにも妨げられないものであり、日本国憲法(第十一条)においてもそれは述べられている。
②「インフォームド・コンセント」とは患者が自らの病気とそれに対する医療行為について医師から十分な説明を受け、それに同意すること。患者は病気の治療にあたり、病気や治療法について詳細に知る権利があるとされ、医師は単に告知するだけでなく正しい理解が得られるように説明する義務があると考えられている。
③「医療における患者の権利」には、他に「受療権」「プライバシー権」「学習権」などがある。インターネットで「患者の権利章典」というワードで調べてみよう。
④「非対称の関係」とは、医師と患者、教師と生徒、健常者と障がい者のように、社会的地位や情報、身体性などに格差があり、対等ではない関係。
⑤「パターナリズム」とは、社会的に強者弱者の関係性があるときに、強い立場にある者がより弱い立場の者のためと称して、その主体性に介入し抑圧すること。医療では、患者主体の医療の対義語として医師主体の医療と考えられている。
⑥「Quality of Life(QOL)」のLifeで生活の質、生命の質のこと。単に生きているだけでなく、人としての尊厳を尊重され、生きる喜びを感じて幸福に生きることを追求すること。医療分野でもQOLの維持、向上を伴う治療が必要だと考えられている。
解説
テーマ型の難しい点は、課題文や図表のように手がかりとなる材料がないことにあります。帝京大学のようにキーワードが提示されていれば、それを繫げることで論述の方向性が得られますが、杏林大学のようにただテーマしか示されていない場合はそうもいきません。
ただし、どのような出題であっても、テーマの言葉の意味を正確に理解し、出題者の意図を推測する、さらにはその言葉から想定される具体的な場面性をイメージする、この3点セットが、テーマ型を考える上では鍵となります。
「権利と義務」というテーマを考えるにあたって、まずは、近代以降の市民社会において市民が持つ権利=基本的人権は条件付きのものではなく、何ものにも妨げられないものであり、義務を果たさないと得られない性質のものではないという前提を確認しておく必要があります。
その上で、医師になろうとする者が書くべきことは何でしょうか。医学部の小論文では、しばしば医師として患者とどのように関わるのか(=医師と患者との関係性)が問われますが、出題者もそれを意図しているはずです。課題文型の小論文が課題文の筆者との対話なら、テーマ型では出題者との対話を心がけてください。
解答では、基本的人権に基づく患者の権利をどのように保障し、その行使をどのようにサポートしていくかが医師に課せられた義務であるという方向性で考えています。
医療は科学に基づいており、より多くその知識を持っている医師と、そうではない患者との関係はもともと対等ではありません。そのため、医師が科学的な知である医学によって患者を支配し、その権威に抵抗しがたいより弱い立場にある患者の自己決定権を侵害しかねません。また、科学的な知は、患者を多数の類型として分析する性質を持っているので、一人ひとり異なる多様な患者をしっかりと見(診)られなくなる危険性も持っています。医師はそのような医学の危うさを常に意識しながら、患者の生き方、生活、人生(Life)を対話によって理解し、患者のあるべき「Life」の実現によってその権利を保障しサポートする義務を果たします。
そうすることで、パターナリズムに陥る危険性を持つ両者の関係に、新たな可能性を作り得るという方向で論述するとよいでしょう。
他の論述の方向性としては、パターナリズム的な要素を持つ関係、例えば、親と子、教師と生徒、上司と部下など、弱い立場の権利をどのように保障するかなどが考えられ、そのような内容で書くこともできるでしょう。
可児 良友
医系専門予備校メディカルラボ 本部教務統括