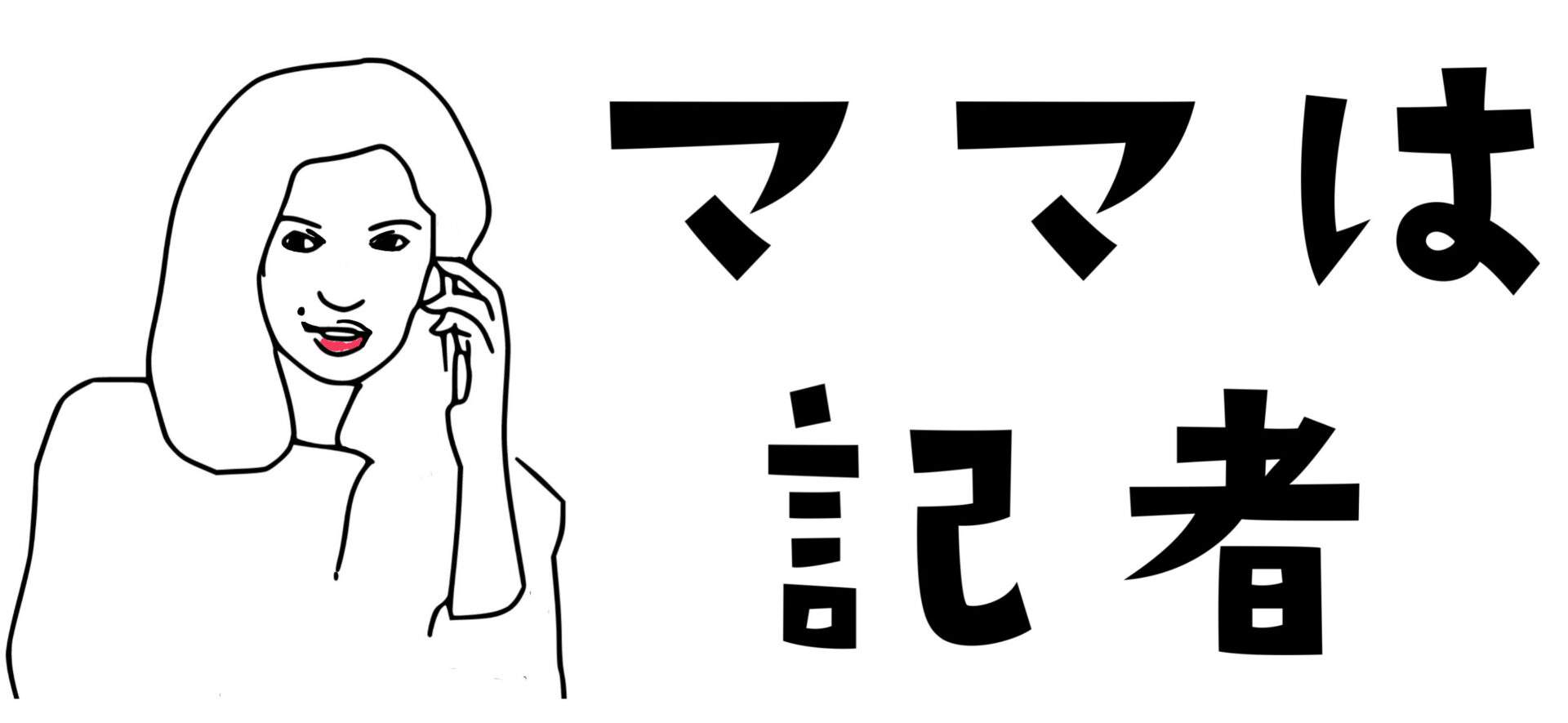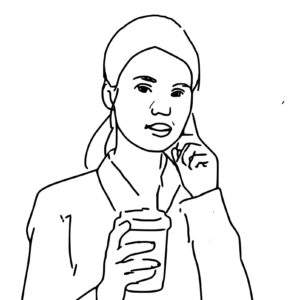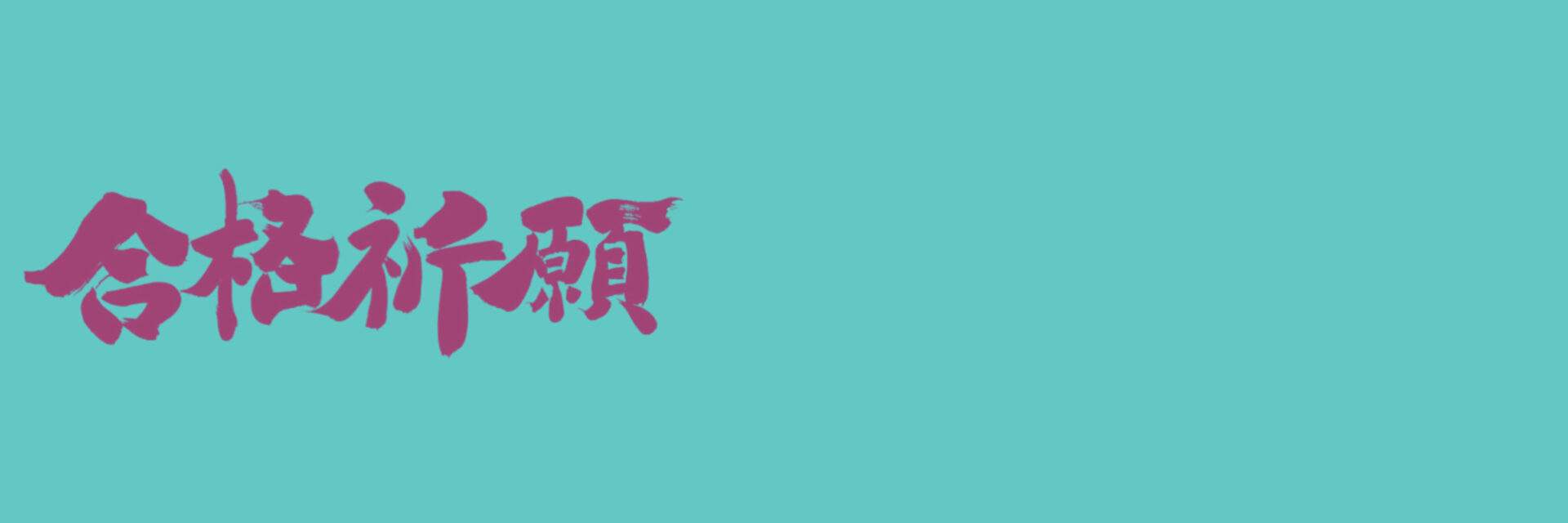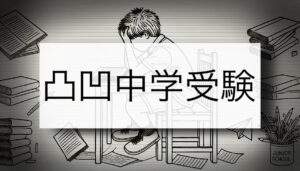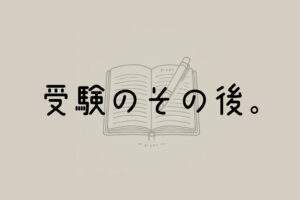凸凹中学受験で起きたこと(続き)
その8 興味のあることばかり掘り下げる
 太郎
太郎凸凹中受、ついに終わった!
白目太郎の中受のこれまで
小4でS入塾。S偏55からスタート。同年、発達特性と高IQが判明。ADHD薬の服薬で落ち着きのなさはおさまり、クラスはαに上昇。
小5秋に大失速、サピックス退塾。転塾、再度の退塾を経て小6の夏前からサピックスに復帰。復帰時のS偏差値は54。11月にS偏68を突破し、志望校を開成中学に変更、合格した。
…と、まあ、凸凹中学受験はなかなか一筋縄ではいかないものだった。しょっちゅう癇癪を起こし、授業には行けず、こじらせて退塾し、戻ってもテストで点が取れないし、ミスも多い。ネガティブな面を先に書いてきたのは、「そんな状況でも、なんとかなった」ということを伝えたかったからだ。
そうでないと、「ギフテッド」という言葉の持つポジティブな響きから、「最初から特別な才能があって、すんなり成功できる子」と誤解されがちだ。
そうではない。
実際には、特性のせいで学校や塾のシステムに適応しにくく、授業についていけないどころか、そもそも出席すらできないこともある。理解はできるのに手を動かすことができず、テストでは凡ミスを量産し、自分の理想と現実のギャップに苦しむ。特に、凸凹のある子は「できるはずなのに、できない」という場面に直面しやすく、そのたびに自信を失い、癇癪や不登校といった形で表れることも少なくない。
「才能があるから大丈夫」ではなく、「才能があるからこそ困難も多い」。だからこそ、うまくいかない部分を先に書いた。
一方で、長男にも得意なことはあった。ただ、それは「計算が爆速」とか「記憶力が異次元」とか、受験に直結しそうな才能ではなかった。
社会を例に説明すると、長男の特異なところは、知識欲の強さだった。社会に関しては頭に情報を流し込むことを好み、「ちょっと疲れたから地図を眺めよう」「気分転換に統計資料でも読むか」となる。迎えに行った電車の帰り道では、社会資料集からクイズを出し合い、疲れた私からギブアップすることも多かった。
教材にとどまらず、旅先などで訪れた博物館の展示や子供新聞、歴史漫画のコラムなどから、どんどん知識のネットワークを構築できるのも特徴だった。苦にならないどころか、「知を構築するゲーム」感覚で楽しみながら、教科書の範囲を余裕で超えていく。
その一方で、年号暗記のような純粋な記憶の反復にはなかなか手が伸びなかった。その結果、試験範囲ギリギリをかすめる知識ばかりが増え、「そこまでは覚えなくていいんだよ!」とツッコむこともしばしばだった。知識量自体は多いものの、受験に必要な「正答する力」とは必ずしも一致しないのが悩ましいところだった。
要するに、長男にとっての受験勉強は、「与えられたものを詰め込む作業」ではなく、「興味のあることをさらに掘り下げる機会」だった。知識を収集すること自体が楽しく、特に歴史や地理の本はいくらでも読んだ。ただ、裏を返せば、「求められていることをやる」のは最後まで苦手だったわけで…。
直前に基本事項をおさらいすると、「後漢書東夷伝」と「魏志倭人伝」の違いもよくわからず、そもそも興味もないといった偏りが次々に発掘され、悲鳴を上げながら「やばい、穴だらけじゃん!」と大慌てで埋めにかかることになった。大事な用語を漢字で書けるようにする、年号を正しく覚えるといった「お勉強」は、最後の1ヶ月で詰め込んだからこそ、文化祭準備のような異常なテンションで乗り切れたのだと思う。
次回は、他の科目での凸の現れ方についても振り返ってみたい。
以下は今後書きたいことのリスト。
今日も授業に行けない!10歳の壁と癇癪と不登校ケアレスミスとの戦い「眠い・疲れている」が分からない授業点が取れない教材以外で学ぶあと伸びを信じる- 5年秋で凸を見極め
- 投薬の効果は
- 記述対策で伸びる
- プロのアドバイスに従え
- 爆伸びは突然に