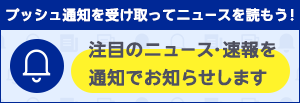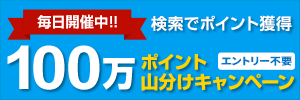「日産解体」が現実味を帯びてきた…「ホンダの子会社」という大チャンスを自ら捨てた日産を襲う最悪のシナリオ
プレジデントオンライン / 2025年2月13日 19時15分
■業界2位の日産が陥った「負のスパイラル」
日産自動車(日産)にとって、今回の本田技研工業(ホンダ)との経営統合は、どのような形であれ、財務破綻寸前の企業が生き残りをかけるという意味で、千載一遇のチャンスでした。しかし、日産は、その好機を自らの手で破談に追いやることになりました。
その要因のすべては、日産という企業文化の根底にある“プライド”を払拭することができなかったことにあります。
ただ、見方を変えると、自力で再生を目指すべく戦略を作り出すことができなければ、たとえ他社による経営改善が図られたとしても、それは一時的な救済に過ぎず、持続的なケイパビリティがつくり出されるわけではないことになります。
日産の経営は、これまでこの繰り返しでした。全社的に常に技術が先行するため、マーケットインによる製品開発や販売戦略が不得手でヒット車種(スカイラインやグロリアなどは1966年に合併したプリンス自動車工業が保有していた車種)を生み出せないことから、業績の悪化を招き、たとえリストラ策が打ち出されたとしても、強固な労働組合組織が足枷となり、抜本的な改善を図るには至らず、財務状況はさらに悪化の一途を辿るという「負のスパイラル」が作り出されてきました。
■「2度のチャンス」をものにできなかった経営陣
極度の販売不振から2兆円あまりの有利子負債を抱え倒産寸前の経営状態に陥った1999年にも、自力での再生に目処が立たず、ルノーとの資本提携により、50億ユーロ(約6430億円)のキャッシュインジェクションに加え、経営者をルノーから招聘し、懸案だったリストラ策を断行することで業績改善が図られています。
業績が悪化するたびに自力での再生が果たせず、他社の力を借りて一時的に業績を改善するという、こうした他力本願に依存する経営体質を日産はもはや払拭することができないのでしょうか。
日産は、2025年2月に、ホンダとの経営統合を断念する決定を下しましたが、ホンダとの提携により活路を見出すチャンスは2度ありました。
両社の統合協議は、2024年12月に開始され、当初は、新たな持ち株会社を設立し、傘下にそれぞれの会社が入り、持ち株会社のトップはホンダが指名し、取締役会もホンダが過半数を握り主導する形での統合が示されました。
この形であれば、二者間でホンダの戦略を優先させ経営の主導権をとることは可能でしたが、日産の業績が芳しくなかったことから、ホンダとしては日産の経営を健全な状態に戻すことが必須でした。
■ホンダ社長は日産の“甘さ”を見抜いていた
そのため、ホンダの三部敏宏社長は、「(統合は)ターンアラウンド(事業再生)が絶対条件だ」として、日産に事業再生計画の取りまとめとリストラの断行を突きつけることになります。
しかし、日産による事業再生計画の策定は遅々として進まず、当初は、2025年1月末までに明らかにし、経営統合の方向性も決めるとされていましたが、具体的な計画は明らかにならず、方向性を決める期限も先延ばしとなりました。
もしこの時、日産が本腰を入れて、工場閉鎖の断行など思い切ったリストラ策を策定してその実行に強い意志があることをホンダに示していれば、持ち株会社による経営統合の道を辿る余地は十分に残されていました。
しかし、日産からホンダに示された事業再生計画に具体策はなく、スケジュールも不明であったことから、ホンダは日産に対して子会社化を打診することになります。三部社長は、この打診が両社の溝を決定的にするものであることを十分に理解していました。
つまり三部社長は、日産が具体策を明確にしない、もしくはできないということは、自力で経営を立て直す意思がないことの表れであると捉え、このような状態でたとえ経営統合しても規模の経済を生かすどころか、共倒れになることを見抜いていたと考えられます。
それゆえ、あえて子会社化を打診することで、日産自らが経営統合を断念する方向へと舵を切ったのです。

■高いプライドを捨てることができなかった
案の定、日産にとって子会社化は受け入れられる選択肢ではなく、招集された取締役会では多くの経営幹部がこれに反発し、あくまでも対等との意識を強く示し、ホンダとの経営統合を打ち切り白紙撤回する決定が下されています。
もしこの時、日産が子会社化に同意できていれば、たとえ日産という社名が残らなくても経営資源の存続は可能でしたが、日産はその高いプライドを捨てることができませんでした。
そもそもホンダと日産が統合への協議入りに至った背景には、「電動化」と「知能化」という大きな構造転換が存在し、これら2つは、自動車業界における新たな競争軸となりつつあります。
2つの競争軸を牽引するのは、紛れもなくテスラですが、BYDなどの中国メーカーが台頭し、ASEAN諸国では販売数を増やし日本の自動車メーカーの市場シェアを奪いつつあります。
ホンダと日産が、三菱自動車工業(三菱自工)も視野に入れて統合することになれば、年間の販売台数が800万台を超えることから、規模の経済による利益が期待できると同時に、ASEAN諸国に強い三菱自工の販売戦略を生かせることができたわけです。
■「資金の確保」という難題が重くのしかかる
また、3社による統合は、バリューチェーンの上流に位置する研究開発機能の統合に始まり、プラットフォーム(車台)の共通化、生産拠点の適正化、販売代理店の拡充に至るまで、さまざまな領域で範囲の経済による統合効果を生み出すことが期待できるものでした。
経営統合が白紙撤回となった今後、両社は単独で生き残りを模索することになりますが、特に日産は資金の確保が焦点です。
日産の2024年9月末における自動車事業の手元資金は1兆4384億円となっており、同年3月末と比べ約6000億円減少しています。そのうえ、2026年3月期には、自動車事業の社債として約5800億円の償還が迫っています。
こうした状況下で、今後、電動化と知能化に向けた投資が数十兆円規模でかかることを考慮すると多大な資金調達が必要となるのは明白です。そのための原資として日産が取り組むべきは、製品開発領域に経営資源やケイパビリティを集中させて、売れるクルマを開発することになります。
しかし、これまで技術ありきで開発を進めてきた日産が、プロダクトアウトからマーケットインへと開発の視点を変更して、売れるクルマを新たに市場に投入できるかどうかは未知数であるといえます。
それゆえ、現実的なのは、工場閉鎖や人員削減によるリストラ策を断行して固定費を大幅に削減し財務体質の健全化を図りながら、売れるクルマも同時に開発していくという経営を着実に実行していくことが求められることになります。
■ついに「解体」も現実味を帯びてきた
特に工場閉鎖については、トランプ政権の政策次第では、テネシー州の北米日産スマーナ工場やミシシッピ州の北米日産キャントン工場を高く売り抜くことも視野に入れて、北米の生産拠点を整備する必要があります。
他方、日産単独での生き残りがいよいよ難しい場合には、新たに経営統合が可能なパートナー企業を見つけることも、ひとつのシナリオとして考えられます。
ただ、今回のホンダとのケースのように、日産のプライドを守ってくれるようなパートナー企業が必ずしも見つかるとは限らないことから、投資ファンドによる再生や被買収の道も視野に入ってくるでしょう。
投資ファンドや被買収企業の下では、市場価値の高い事業部や生産効率の高い工場などは切り売りされることになるため、最終的には日産が実質的に解体され上場廃止になる可能性も否定できません。
したがって、日産は、このような道を辿る前に、単独で生き残るための戦略を描きそれを愚直に遂行することが求められるわけですが、今のプライドの高い日産ではそれが難しいことから、まずは経営陣を刷新して、できるだけ速い段階で新たな成長戦略を打ち出し、“新生”日産としての第一歩を踏み出すことが急務であるといえるでしょう。
----------
淑徳大学経営学部教授
淑徳大学経営学部教授。ハーバード大学留学時代に情報通信の技術革新に刺激を受けたことから、長年、イノベーションやICTビジネスの競争戦略に関わる研究に携わり、企業のイノベーション研修や講演、記事連載、TVコメンテーターなどを務める。日本電信電話株式会社に入社後、中曽根康弘世界平和研究所などを経て現職。単著に『世界のDXはどこまで進んでいるか』(新潮社)、『2020年代の最重要マーケティングトピックを1冊にまとめてみた』『サブスクリプション』(いずれもKADOKAWA)など多数。新著に『経営戦略論 戦略マネジメントの要諦』(勁草書房)がある。
----------
(淑徳大学経営学部教授 雨宮 寛二)
外部リンク
この記事に関連するニュース
ランキング
-
1ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」が規格外すぎ...スイーツもサンドイッチもお弁当も盛りまくり!第2弾の対象商品を見逃すな~。
東京バーゲンマニア / 2025年2月13日 15時49分
-
2通販大手の千趣会、3年連続赤字 本社ビル売却、社長交代へ
共同通信 / 2025年2月13日 21時9分
-
3「日産解体」が現実味を帯びてきた…「ホンダの子会社」という大チャンスを自ら捨てた日産を襲う最悪のシナリオ
プレジデントオンライン / 2025年2月13日 19時15分
-
4為替相場 14日(日本時間 8時)
共同通信 / 2025年2月14日 8時0分
-
5なぜ「セブンの一人負け」が起きているのか…客数減でも好調なファミマとローソンとの明暗を分けた本当の原因
プレジデントオンライン / 2025年2月13日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください