穏便に済ませたいこと
わたしの大切にしていたことを思い出させてくれる人たちすべてに捧げる
1 いきさつ
いくつかの仮説を、初めて主張したのはわたしであることを、ここに書いておきたいと思いました
中学生のころから話してるから、その人についてはやたらいろいろな思い出と紐づいています わたしはその人とフォロワー1000 とかの頃から喋っていて、古い友人たちとの思い出とたくさん紐づいているから、ただ漠然と好きです 変なやつだし、とても悪いことを言うし、自己顕示欲がとっても高いし、少なくともうちの分野の常識が抜けてるけど、人間関係においてそこまで悪いやつではないし、話せば通じるし、プライドは高くないし、面白いやつでした、いまでもそう思っています
十四歳の春から、そろそろ七年の歳月が経とうとしています そうだ、近況を話しましょう、わたしはいま、どこでもないところにいるようです 面白い研究会に参加させてもらいました、褒められ、また、詰められる経験は、かけがえのないものでした 査読コメントが、いきなり優しくなりました 何人目かわからない恋人とは、先月別れました、貴い人でした、ほんとうの意味で万華鏡のような人でした 相変わらず歌を詠んでいます、お菓子作りをしています、交流会で出会った人たちの話は、どれも面白いです
十代のころのわたしは、いろいろな人に喧嘩を売ったものでした 自分を顧みるということを知らず、ただ直観と激情にそそのかされるままに生きていました 他者の苦しみに共感する術を知ろうともがくなかで、思想は極右から極左に揺れ動き、リベラリズムに落ち着きました 恋というものを知っても、人間の愛を知らず、醜さというものを知っても、本当の美しさというものを知らず、構造と慣習をさきに理解し習得するばかりで、ただそこにいる人それ自体を受け入れるすべを知らない自分を憎み、高すぎる理想と自己像の乖離に苦しみました 自らに割り当てられた性別や、両性愛との距離感をつかむこともできませんでした
そういう、十代のわたしのかけらを保存しているのが、Twitter にある,「rmnscnt」というアカウントです なんどかログインしていましたが、十代という奇妙でかけがえのない時間を完全に終えてしまったわたしは、もう、このアカウントを使うべきではないのだと、最近は思うようになりました このアカウントは、わたしにとっては、もはやこの世にいない友人たちとの会話の記録とともに、それじたいが大切な思い出の品となっています そのような場で荒っぽいことはしたくありません
これから話すことは、そのほとんどが、おそらく、完全な発展形として、そのうちどこかの誰かさんが著者の論文になります 内緒ですが、すでに学会発表されたものもあります OA で公開されるものが多いと思いますが、読めないようなら、メールしてください 縁のある人たちに、PDF を渡します
2 穏便に済ませたいこと
高校一年生(2019年)から、高校二年生の終り(2020年)にかけての約二年間、わたしはこの note のアカウント(その前は Academia.edu)で、日琉諸語とアイヌ諸語の音韻史に関するのべ50本の研究ノートを発表しました そしてまた、研究ノート未満の思いつきを、rmnscnt とその前のアカウントで投稿していました
論文誌の投稿規定に差し障る可能性と、だいぶ見解が変わってしまったり、方法論的に危うかったりするものを自説として扱われても害が大きいことから、50本の研究ノートの中身を公開するつもりは現時点でないのですが、どういうわけか、わたしが高校生のころに書いていた記事中で主張されていた仮説の一部が、その人、つまりすーちゃんが原因となって、提唱者が伏せられたまま独り歩きしたり、孫引きに孫引きが重ねられて品質が落ちたりしてしまっているようなのをときどき耳にしたり、目にしたりします これは、無視するわけにはゆかない気がするのです
提唱者が伏せられたまま仮説が独り歩きすることによって、すーちゃんの承認欲求の ROI が狂ってしまっている様子には、見ていて心苦しさを覚えますし、また、わたしの文章に奇妙な解釈が加えられているありさまは、あまり気分の良いものではありません このような現状は、どうにも望ましくないことのように感じたのです そこで、いくつかの仮説を、初めて主張したのはわたしであることをここに書いておいたほうが世の中のためになるのではないかと思いました それが、この記事の執筆の直接の経緯と動機です
2.1 有坂池上生成
YouTube の動画で出典を明記せずに使用されてしまったため、ご存じない方も増えていると思いますが、有坂池上生成というのは、高校2年生のときにわたしが思弁していた一連の仮説の総称です
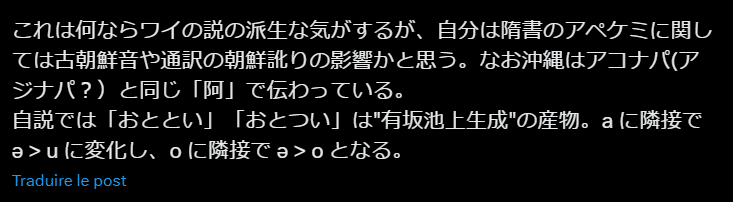
当時のわたしが直観し、「有坂・池上生成」と呼んでいた仮説群は、現在のわたしの解釈では、本質的にはある制約が古代ジャポニック諸語の音韻論にめいめいに作用するドリフトだったといえるのですが、以下に示すように、当時のわたしはしばしば、個別の音韻規則そのものを指して使っていました
*ə> *i /_$a> *e /_$o
詞例:*rəNtaj > pRyk *joda, OKin yeda, OAdm yade【枝】*kəkəNta > OKin ko₂ko₂da ~ ko₂ki₁da【こんなにもたくさんに】*mə-ra > OKin *mo₂r-, (> Adm *marap- > ) 愛知・鳥取 maraw-【面倒を見る】*pə(l)so > pRyk *poso, OKin *poso₁ ~ *poNso₁, Adm *peso【臍】(借訓で甲乙が無視されるのはしばしばであり,⟨細⟩ を「臍」としてもソは甲類として解釈できる)
わたしこの note のアカウントで公開していた研究ノートでは、「有坂・池上生成」というものは、厳密な音韻規則として扱われていました わたしは研究ノートのなかで厳格に定義し、棄却と改訂を繰り返していたのですが、現在 Twitter や YouTube でこの用語を使っている人は、あまり厳格に仮説を運用していないようです これはさらなる仮説発見の芽を自ら潰す行為であり、言語学的によくないのですが、わたしと同じ水準で議論できる人というのもあまりいないので、そもそもアカデミアの外ですし、言い立てても仕方ないことではあるのかなと思っています
2.1 狗古智比狗
倭人語〈狗古智比狗〉の前部要素が一般名詞「東風」である可能性をはじめに指摘したのは、このスクリーンショットの主ではなく、わたしでした

これは研究ノート未満の思いつきであり、ツイートした形跡じたいはあります しかし、わたしは定期的にツイートをすべて削除する習慣があったため、会話の痕跡じたいは残念ながら見つけられません 当時のわたしはいまとは違ってこの固有名詞の解釈に音韻体系の解明のうえで重要な情報があると感じなかったため、研究ノートにはしなかったのです 我ながら当時のわたしの歴史言語学への向き合い方はあまりにストイックすぎて怖いです Hypothesis.org のノリだったら毎日記事を公開してたんじゃないだろうか…
コチは恐らくココチという形(これは静岡県だか愛知だかに残っている)に重音脱落が起きたもので,後部要素は *-te【風】(cf. ハヤテ)なんじゃないかな。前部要素はクランベリー。
— Ize Kawai (@rmnscnt) September 14, 2021
2.2 バマ相通
たとえばすきえんてぃあ氏は *Nm > m ~ b が自分の再建だと主張しているが、*Cm によってバマ相通を説明するという発想は禾本一郎さんが2019年に初めて言及したもので、某氏の unpublished (2021)、わたしの note (2020),如木花さん (2022) なども各々の視点から論じている。
— Ize Kawai (@rmnscnt) June 2, 2024
バマ相通というのは興味のつきない問題ですが、そもそも問題の全貌が見えていないことには始まらない問題でもあります
*‾karəp > CJnc *karə-【軽い】 → *karəp-m<a>-【軽くなる】> EMKin karom- ~ karob-*‾marəp > CJnc *marə-【丸い】 → *marəp-m<a>-【動作が円状をなす】> EMKin marob- ~ marom「転がる」*‾təp<a>-【訪ねる】 → *‾təp-məra-p<a>-【訪ねる-見守る-[複数形]】> EMKin tomurap- ~ toburap-

2.3 魏志倭人伝を読めているのかということ
すーちゃんは本当に「魏志倭人伝」を読めているのだろうか、特定の単語がどの固有名詞に対応するかを推測することは、亀井孝のいう「読める」状態に過ぎません かりそめにも歴史言語学を研究する者ならば、「ヨメる」状態、つまり、当時の漢字音と日琉語の古い段階の音韻論的な対応を説明できる状態を目指す必要があります すーちゃんはこのことをいうとき、そういった常識がわかっているのでしょうか
言語学めちゃくちゃ詳しい人でも文献史学と考古学と神話学を知らないと魏志倭人伝を読めないというのは最近数年で思い知らされたことで、人類の限界を感じる
— すきえんてぃあ@書け (@cicada3301_kig) March 20, 2024
わたしは時折友人たちを通じてすーちゃんの考察を目にする機会がありましたが、「魏志倭人伝」の音韻論的な対応を説明できる段階に達していると思ったことは一度もありません
たしかにわたしは、2020年に書いた28番目の研究ノートにおいて、傍国の音価が示唆する歴史音韻論的仮説を論ずるにとどめ、官名や人名には触れませんでした この理由としては、わたしの歴史学的な知識の不足も多少はあるのですが、それ以上に、邪馬台国の言語の大部分が、まだ「ヨメる」状態に達していないということがわかっただけで十分だったからです
むろん,これらに関しても更に考察をすすめる必要があるから,現在のところきちんとした結論を与えることはできないが,恐らく『魏書』地名は日琉祖語程度の共時態か,それ以前のものであることは間違いがないという結論を,Bentley (2007) と同様に描いたところで筆を擱く。
(ちなみに、喜ばしいことなので書いておくと、わたしはいま、「魏志倭人伝」に現れる母音対応の問題は,ほぼ理解できているつもりでいます)
先ほども言ったことですが、当時のわたしの歴史言語学への向き合い方は非常にストイックかつ先鋭的であり、音韻法則を定立できていないのならばその歴史研究には何の価値もないと考えていました それゆえに、今となっては若気の至りそのものですが、本邦で出版されたほとんどの歴史言語学の論文を無意味なものとして嘲っていたものでした そんなわたしには、音韻法則の定立にとって何の役にも立たない比定の作業を進めるよりも先にすべきことがたくさん見えていたのです
ところでわたしは、すーちゃんに、科学哲学における常識である、最良の説明のための推論(Inference to the Best Explanation)に関する知識を前提としたお話をしたことがあります。学際的歴史研究が最良の説明のための推論を行うとき、個別分野のなかでは意味を持つ理論的価値が役に立たなくなります。そのさいに、どのような理論的価値を残し、仮説を採択していくべきか、という問題に向き合うことには、どんなに不毛な議論のなかであっても意味があります。
おそらく、こうした問題について真面目に考えたことのない方には難しすぎる話だったのだとは思いますが、当時のわたしは、すーちゃんが多少なりとも学際的研究に向き合う態度を持っていると期待してしまっていたため、このような返信をうけたことに、深く悲しみ、失望したものでした。ここでいう実在性というのは所与の前提ではなく、仮説を採択するか判断するうえでの理論的価値のことなのです。言うまでもなく、そのような理論的価値の存在を認める認識論は、筋が悪いです。
まず実在性を仮定した上で論じているので、議論全体が仮定に乗っている。仮定のうえで論じたらどうなるか、という方法論に対して仮定を問うても意味がない。 https://t.co/SuEi9KXior
— すきえんてぃあ@書け (@cicada3301_kig) March 21, 2024
不毛なレスバトルから学際研究にとって有意義な論点を抽出したのに、こんな的はずれなことを言われてしまったのも悲しかった記憶があります。
こんだけ言うてて吉備の比定すらできてなかったじゃん https://t.co/5HemhzFqvP
— すきえんてぃあ@書け (@cicada3301_kig) March 20, 2024
ちなみに、2020年のわたしも、吉備の比定くらいならしています
3.19.支惟
吉備。LHC *kie-wi.OKin kibi₂ < PJ₀ *kiNp{u, o, ǝ}i.*Np > *w のやうな変化が発生した方言は当該地域で未発見であり,闡明が待たれる。あるいは *kilpVi のやうな詞形でハ行転呼が発生しているのかもしれない。
せっかくだしほかの話もしたいのですが、わたしは自分の思いついたことを見せびらかすのは論文と学会でだけにしたいと思っています
2.4 「上代東国方言」の系統的位置
わたしには、重母音の改新のみに基づいて「上代東国方言」の分岐が日琉分岐よりも古いと推定する仮説をすーちゃんに広めてしまった責任があるのではないかと思います その仮説はなぜかまるっきりそのままの話を引き写されて動画になってしまっていますが、この系統仮説は(その積極的な証拠はまだ提出されていないのですが)誤りだと考えています

すーちゃんが「上代東国方言」の分岐が日琉分岐よりも古いと考えている論拠は、わたしの2019年の6番目の研究ノートが「八洲」という特徴的な呼称を付して提唱した系統分岐モデルとまったく同じです
八洲祖語は,通説上の日琉祖語(proto-Japanese-Ryûkyûanであり,proto-Japonicではない)における*ui, *oi, *iaという母音連続(もしくは二重母音,学派によって解釈が異なる)が琉球祖語においても,上代近畿諸方言においても狭母音に融合する形で合流する改新を受けているため内的再構以外の手段によって得ることができないのに対して,上代東国諸語においてはu, o, iという風に,二番目の母音が脱落する改新を受けているため比較再構によって得ることができるという事実(vid. Kupchik 2011, Vovin 2013)は,比較言語学の経済性という観点から考えれば改新を共有していないのだからより古い時代の分岐に起因するものであると考えるべきであるという主張にもとづいて提案せられる。
依然として議論の余地のある問題ではありますが、すくなくともわたしは、日琉諸語の歴史のなかで東日本の諸言語の分岐が相対的に新しいことは、ほぼ確実であると考えるのが普通だと思います もしかしたらこれについては Igarashi (2025) がさわりだけ言及するかもしれない気がする、しかしいずれにしても、そう考えるしかないような材料とフレームワークはすでに五十嵐 (2018) で示されています それが読めていないと指摘しても、すーちゃんは理解してくれませんでした、言語学的な素養が欠けていて理解できなかったのかもしれません
2.5 木簡
この投稿は、わたしの投稿を引用していますが、わたしの投稿の文脈を理解していないために自己弁護としてまったく的はずれになっています
例えば木簡からわかる中央に分布した非中央語について知識がなくて上から目線で嘲笑していたのは当初からそっちじゃないか pic.twitter.com/Z0AOZBBgQu
— すきえんてぃあ@書け (@cicada3301_kig) January 18, 2025
ここでどこからともなく取り出され、なぜか引用されているわたしの2021年のツイートで挙げられている①を、「木簡からわかる中央に分布した非中央語」の話だと思って読んでしまうのは、わたしの引用した文献を読んでいないし、わたしの投稿の意図も読めていないがために生じた、まったくの誤読だといえます

この投稿の作成者だからこそ言えるのですが、この投稿で引用されているのは、犬飼隆の『木簡から探る和歌の起源』(2008)で、ページ数も間違っています わたしは奏さんに別の文献情報を誤って教えてしまって、当時在野だった奏さんが自腹で『木簡による日本語書記史』(2005)を買いまでしてしまったので、とても申し訳ないことをしてしまったと思います
そもそもその本のなかで、木簡における上代特殊仮名遣いがどう扱われているのかみてみましょう 「はるくさ」木簡の〈刀〉の違例をこのように説明するのは軽部利恵や毛利正守などが立つ、通説的な立場です
また、上代特殊仮名遣いの区別もずさんである。(中略)このように、字画の少ない万葉仮名を用い、音韻の清濁と上代特殊仮名遣いにこだわらないのが(引用者注:木簡に特有の)「褻」の様相である。
そして、引用されている犬飼隆の文献には、通説とは異なり、「はるくさ」木簡の〈刀斯〉が、年代的位置および歴史的地位から、特殊な位置にあることを認めている点に意義があります これを明示するために、わたしは犬飼(2008)を引用しました しかし犬飼隆も、これが中央における非中央方言である、という解釈を下しているわけではありません その代わりに犬飼は、独自の上代日本語の母音体系の成立論の観点から分析すべきだという持論に言及しているのです
次の「刀斯」は今のところ解釈が困難である。「年」に解釈しようとすると、そのトは上代特殊仮名遣いで乙類なので七世紀なら「止」があてられていなくてはならない。「刀」は上代特殊仮名遣いで甲類のトをあらわすが、その「とし」または「とじ」に相当する適当な語が比定できない。形容詞の「利し」や女性の「刀自」などでは文意がつながらない。(中略)おそらく、オ段音の上代特殊仮名遣いの本質そのものについて、今まで考えられていたのとは別の見方が必要になるだろう。すでに筆者はその見解の一端を前著『木簡による日本語書記史』第六章で述べている。
「はるくさ」木簡の〈刀斯〉が非中央方言だ、と解釈するのは、そのときわたしがほんのすこし言及した独自見解にすぎないはずです そうしたハイコンテクストな文脈を理解したうえでわたしの投稿を記憶することができていなかったのは、すーちゃんがそもそも犬飼隆の当該の文献や、その周辺の文献を読んでいないからでしょう 犬飼隆の文献を読むために本を購入しまでした奏さんの学問的誠実さと、ひどく残酷な対照をなしているこの出来事を、わたしは深い悲しみなしに受け入れることができません
わたしにとってすーちゃんは、インターネットの楽しい話し相手だったのですが、わたしたちが読んでいるような文献をぜんぜん読まないから、しだいにわたしたちから教わるばかりになっていって、話してもつまらなくなってしまっていきました 大変に、大変に、残念なことでした
2.6 アイヌ祖語の再建
すーちゃんが動画のなかでしていたアイヌ語関連の問題設定の多くは、実は、わたしによるものです
さいきん気づいたのですけど、不遜なので、あまり言わないようにしていることがあります それは、歴史言語学的に筋の良い、つまり生産的な仮説を生み出せるような問題設定をするのには、なにか容易に言葉にすることのできない才能が要るようだということです どうやら、わたしが苦もなく直観できてしまう道筋が、大半の友人には見えていないらしいのです すーちゃんは2020年以来検討に値するアイヌ語に関する仮説を発表できていないようですが、これは、わたしが Twitter で問題提起をしなくなったことが一因です
それ以外の要因には、すーちゃんがアイヌ語の基本文献を一冊も持っていないことが挙げられるように思います たとえば、すーちゃんは動画のなかで Vovin (1993) に触れますが、実際に引用するのはそれよりも包括性において劣る Vovin (1992) です これは、すーちゃんが Vovin (1993) を Google Books の断片からしか閲覧できず、sealang.net にある後者をもっぱら参照していたことを意味します
すーちゃんは、ある動画で、宗谷・樺太における raising の非対称性を「母音の動きが不自然」だと批判して Vovin のアイヌ祖語体系を修正し、アイヌ祖語に *a, *e, *ɨ, *u, *o, *ʌ の7母音を再建することを提案しています ちなみに宗谷や樺太のこの母音の動きはべつにそんなに不自然なわけではないです、わたしの良き友人であり良き読者であったすーちゃんは、当時のわたしが「不自然」だと言ったのを、引き写しているというわけなのです


じつは、宗谷・樺太における raising の非対称性を問題であると提起したのは、わたしが2020年に友人たちの間で行った発表資料の B 案が初出でした この発表資料の10枚目のこのスライドはかなり出来がよかったので、当時、ツイートして見せびらかしたのを覚えています(ちなみにいまのわたしは、Alonso de la Fuente さんよりも出来のいい母音体系を思いつけています)

ちなみに、アイヌ祖語に子音クラスタを再建すべきでない、という指摘は、2019年あたりに禾本一郎さん、わたしの2019年の19番目の研究ノートなどによってすでに指摘されていました でも、こうした問題は、わたしたちが読めなかった Alonso de la Fuente さんの博士学位論文がすでに言及していたことでしたので、わたしたちに新規性はありません
緒言
本研究ノートでは,Vovin(1993)のアイヌ祖語*hr, *pr, *H[ɦ?], *h, *trが,それぞれ*hr, *pj, *h, *x, *tr[r̥?]に改められるべきであることを指摘する。
ああそうそう、ちなみに、すーちゃんはこの動画のなかで、「古シベリア諸語には無声の共鳴音がある」という趣旨の発言をしていますが、これも、当時まだ未熟だったわたしに由来する勘違いです ニヴフ語などにもそれはありますが、実際には無声の共鳴音が豊富にあるのは、Alonso de la Fuente さんが予想するようにトランスヒマラヤ諸語です
すくなくともアイヌ語に関して、すーちゃんはかつては良き読者であり、話の合う友人でした だからどうか、たとえわたしたちに由来する部分があったとしても、この動画を非公開にしないでほしいと思います この動画は、おそらく世界で唯一のアイヌ語史の入門書であり、未解決問題の紹介になっているのです その内容に政治的な偏向があったとしても、すくなくとも現在の人々にとって、また、もしかしたら後世の人々にとっても、大切なものです
そういえば次の動画で「利根川」のネをアイヌ語の nay と比較していますが、これはわたしがはじめて言及したものでした すーちゃん(2020)「1000年前のアイヌ語を再現する」が一瞬触れるのは、わたしの思弁です これについては似たような水名がそんなにたくさんなかったので検討をやめた記憶があります
それから、アテルイが aca + ruwe もしくは aca + ruy と比較できるし、比較すべきであることについても、わたしは2020年あたりに述べています わたしは残念ながら、すーちゃんとは違って、Kupchik さんのするのようなたった一例をつかって歴史音韻論的な思弁を繰り広げる危うい議論に価値を感じられないので、研究ノートにはしなかったのですが
2.7 閑話休題
この動画の「私の上代日本語を監修して下さっている人」というのは、ほかでもなくわたし、remi. のことです 本当に本当に、苦しかったけど、楽しい青春時代でした 書いていると涙が出てくるので、いったん、休みます
2.8 その他
以前は、わたしたちの(主にわたしの?)していた懐かしい議論をクレジットなしに引き写した動画たちがたくさんあったのですが、だいぶたくさん非公開になってしまっているようです 残念なことではありますが、仕方のないことなのかなとも思います
すーちゃんが自分が発見したと思い込んでいる仮説のなかには、すでに提唱されているものがいくつかあります 目についたものを書いておきましょう
2.8.1 わたしの仮説ではないが…声調発生
この動画で「世界で初めて再現」されている声調発生(tonogenesis)の仮説とまったく同じものは、Alexander Vovin が1997年に提唱しています この論文は open access であり、すーちゃんがなぜ読んでいないのか、わたしにはわかりません すーちゃんは他にも open access であるにもかかわらずなぜか読んでいない論文がたくさんあり、それも、わたしがすーちゃんにリプライしなくなった理由の一つでした
2.8.2 わたしの仮説ではないが…韓日比較
この動画で「学者たちが見落としてきた関係」とされている朝鮮語 *t と日本語 k の対応は、すでに、Martin (1966) によって指摘されています
Martin (1966) は英語圏の韓日の語彙比較における基本文献であり、これを参照していないことは極めて残念です しかもこのような語中のみに見られる対応にたいして primary な子音である *kʷ を再建するのは、歴史音韻論的な素養の欠如といわざるを得ません 算数でたとえるなら、最初の小問が誘導だと気付かないのと同じです また *kʷ > t はたしかにヘレニック諸語にみられますが、これは後舌狭母音の前母音化が起きていることと無関係ではないでしょう わたしも中学生や高校生のはじめのうちは印欧諸語にみられる音韻法則を端から当てはめて日琉諸語の音変化を考えていたものですが、それは右も左もわからない初心者のすることです すーちゃんは他にも基本中の基本の文献であるにもかかわらずなぜか読んでいない論文がたくさんあり、また、歴史音韻論的なレベルが驚くほど低く、それも、わたしがすーちゃんにリプライしなくなった理由の一つでした
2.8.3 わたしの仮説ではないが…係り結び
音声を聴いてみたが主張しているというより解説動画が趣旨っぽい
この動画では係り結びが疑似分裂文の倒置に由来すると主張しますが、これは大野(1956a, b, c, d, 1964)がすでに提唱しています
大野晋は係り結びの起源論における基本中の基本文献であり、これを参照していないことは極めて残念です、というか、この話を本気でしたいのなら、言語道断なのです 記述が国語学者に遠く及んでいないのはもちろん、行われている議論もまた極めて素朴であり、一般言語学的な視座を完全に欠いています ナロック(2023)や Roberts (2022) あたりを読んで反省してほしいと思います
2.8.5 わたしの仮説ではないが…韓日比較②
この動画では、日本語 m と朝鮮語 k が比較されていますが、これは cppig1995 さんが高校時代に(たしか本人曰く「頭がおかしくなって」)提唱した音対応であって、従来の研究文献はなにも指摘していないはずです わたしは韓日比較は素人なのですが、すーちゃんは素人のわたし以上に韓日比較について何も知らないから、区別がついていないのではないかと感じます
そしてこの動画は cppig1995 さんの再建体系よりも遥かに bizarre であり、*gw という、自然性原理に反した再建音が示されています このような音素を再建してしまうのは、歴史音韻論的な素養の欠如といわざるを得ず、大変に残念です 算数でたとえるなら、複雑な文章題を解かなければならないのに四則演算すらままならない、というのが良い比喩だと思います また趣旨である歴史言語学の教育動画として相応しくありません すーちゃんは歴史音韻論的なレベルが驚くほど低く、それも、わたしがすーちゃんにリプライしなくなった理由の一つでした
2.8.5 逆に歴史言語学に貢献している動画はあるのか?
この動画は新規性があって面白いです
この動画で再建されている *ni-ap という AOJ nap- の前段階は多少は面白いかもしれません しかしそれ以外は、基本中の基本の文献すら押さえずに行われており、学術的に異様です せめて講座国語史の文法史くらい読みましょう
4 最後に
最後に、わたしの旧い友人の動画を見て歴史言語学に興味をもち、ゆくゆくは研究する仲間になろうと思ってくれた人たちへ
ありがとう 本当にありがとうございます
本気で本当のことを知りたいときは、まずは教科書を眺めて、誠実に議論するところから始めるとよいと思います
本気で本当のことを知りたくなったとき、よかったら、わたしに言ってください、協力します 喜びます わたしでなくてもいいです、いえ、わたしなんてではなく、どうか、本当の専門家と話してください そして、どうかぜひ、ともに大いなる謎に立ち向かう仲間になってください、わたしが願うのは、ただそれだけです 一人ひとりの力は弱くて当たり前です 学問というのは、一人の天才が切り拓くこともありますが、大多数の普通の人によって回っているのです
ずっと rmnscnt として言おうか言うまいか迷っていたことは、だいたいすべてがこの旧い友人の動画と、わたしの文章の関係に関することでした それらについて、わだかまりなく、おおよそすべて話すことができたので、わたしがこのアカウントにログインすることは、もうないと思います
歴史言語学を学びたい人のための読書案内
わたしが高校生だったころとはちがって、いまはこんな素晴らしい教科書が出ています
標準的な教科書の中身を読むと、一部のもぐりの歴史言語学者よりも歴史言語学に詳しくなれる可能性があります
言語考古学の何たるかを知れば、インターネットで行われている議論がいかに些末な問題に関するものなのかわかるでしょう
そして、系統樹を扱うリテラシーは、歴史言語学者にとって不可欠です
一章が重めの新書一章くらいなのでスナック感覚で読めます
加筆情報
2025年1月20日 2.4 節「東国語派の系統的地位」2.5節「木簡」を追記
2025年1月21日 2.6節「アイヌ祖語」2.7節「閑話休題」2.8節「その他」を追記
昔のことを思い出しすぎて疲れてしまったので、おそらく以降加筆しません
追伸
rmnscnt は email が紐づいていないので、DM の通知を受け取ることができません わたしに連絡したいときは、友人を通してください
すーちゃんは歴史言語学がぜんぜんできないのですが、言語学をつかって古代史みたいなことはやりたかったんだろうなと思っています だから、すーちゃんがやりたかったことを叶えてくれたっぽい(?)みんなには感謝しています しばらくのあいだ(明日21日か明後日22日くらいまで)ツイッターにて「新年歴史言語学相談室」を開いています
ということで新年歴史言語学相談室をやっていますhttps://t.co/Vz0i4pbpSC
— Ize Kawai@新年歴史言語学相談室 (@rmnscnt) January 20, 2025
