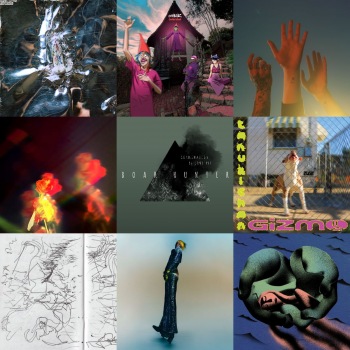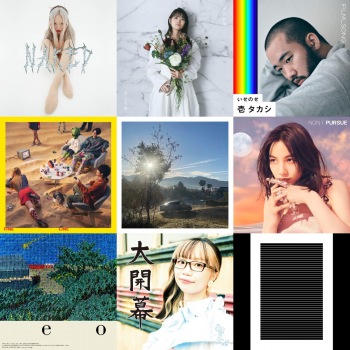REVIEWS : 004 エレクトロニック(2020年5・6月)──八木皓平

毎回それぞれのジャンルに特化したライターがこの数ヶ月で「コレ」と思った9作品+αを紹介するコーナー。今回はエレクトロニック・ミュージックを中心としたセレクトで八木皓平が担当。
Lorenzo Senni『Scacco Matto』
ドラム・ビートはほぼなく、ベースラインも強調されず、ほとんどの楽曲はダンサブルというよりかなりイビツなリズムが基盤となっているエレクトロニック・ミュージック。ここに色鮮やかで、煌びやかなシンセの音色を足すのが、イタリアのミラノを拠点に活動を展開するロレンツォ・センニのセンス。トランスを研究し、辿り着いた彼の境地がここにある。キャッチ―で反復的なメロディーが、リズムと一体になってミニマルな構造を作り上げる。ダンスをさせるという制約を設けないことがロレンツォのルールだからこそ、彼はこのサウンドを作れたのだろう。踊れないが快楽的なのではない。踊れないからこそ快楽的なのだ。エクスペリメンタルにもダンス・ミュージックにも落ち着かない、彼のスタイルは〈Warp〉からの初のフルアルバムとなる本作でひとつの完成を見せた。
Elysia Crampton『ORCORARA 2010』
アンデス地域に住む先住民族、アイマラ族の子孫であり、クィアであること。エリシア・クランプトンの音楽が紡ぐ物語の根底には常にそれらのテーマが貫かれている。精巧に練り上げられたアンビエント・ミュージックは、フィールド・レコーディング、フォークロア、クラシック、ロック、ポエトリー・リーディング等々、様々な要素をコラージュした圧倒的なサウンド。楽曲から現代性と神秘性を同時に感じるのは、彼女の歴史的なルーツが音楽と深くリンクしているからだろう。ラビットやチノ・アモービなどともコラボレーションを展開する、新世代のエレクトロニック・ミュージック・シーンを牽引する希有な才能が産み出した今年トップ級であろう傑作は、私的であることが政治的であり、そして歴史的であることと矛盾しないことの凄みを世界に突きつける。
Nicolas Jaar『Cenizas』
FKAトゥイグス『Magdalene』をプロデュースすることで彼女の作家性をネクスト・レベルへ押し上げ、今年の2月に別名義アゲインスト・オール・ロジックの新作『2017 – 2019』における自由奔放なトラック・メイキングで改めてその才能を世界に痛感させたニコラス・ジャー。続いて届けられたのが、この不穏で美しく、荘厳な魅力をたたえたエクスペリメンタル・サウンドだ。ジョン・コルトレーンに影響を受けたらしく、たしかにサックスやウッドベースらしき音も聴こえはするが、どちらかといえば本作の肝は全体を通しての宗教的な雰囲気だろう。彼のヴォーカルは時に教会で歌われるクワイアのようだし、ガムランやパイプオルガンのようなサウンドも響いてくる。ジェームズ・ブレイクやボン・イヴェールとはまた異なった、テクノロジーを通した宗教性へのアプローチをとっており、この音楽家の懐の深さを実感できる。
Charli XCX『How I'm Feeling Now』
本作を聴くと、チャーリー XCXに必要だったのはなんらかの制限を制作過程に介入させることだったんじゃないかと思わずにはいられない。単発のシングルは素晴らしい、しかしアルバムとなるとどうにもトゥーマッチになり焦点がブレがち。それが彼女の印象だった。しかし本作はCOVID-19のパンデミックによってロックダウンになってしまった状況下で作られたせいか、いつもよりもどことなくラフで、しかしだからこそ研ぎ澄まされた印象がある。参加プロデューサーはBJ バートン、〈PC Music〉のA. G. クックとダニー L ハール、そして100 gecsなど、大衆性と実験性を高いレベルで極めて同居させる逸材ばかりが集められており、これで心が躍らないわけがない。世界中に暗澹たる空気が立ち込めているときに、その状況をクリエイティヴな魅力に反転させ、世界に解き放つ。稀代のポップスターの最高傑作がここに産まれた。
Gabber Eleganza&HDMIRROR『The Real Life』
本稿で取り上げたロレンツォ・センニ、クラップ!クラップ!、そしてこのGabber Eleganza。全員イタリア人プロデューサーだ。イタリアには独自のテクノ文化が連綿と受け継がれていることの一片がここに示されている。特にGabber EleganzaはEPをロレンツォ・センニのレーベル〈Presto!?〉からリリースしていることからもそのつながりは明らかだ。彼が南アフリカの俊英プロデューサーであるHDMIRRORと組んで作り上げたサウンドはガバ、トランス、ハードコアといったアグレッシヴなダンス・ミュージックがベースとなり、それらをアップデートさせるような内容になっている。凡庸な作り手ならひたすら高揚感溢れるダンス・ミュージックの機能性に終始してしまいそうだが、エレクトロニカのクールなセンスが細部で眩いきらめきを放ち、至る所からインテリジェンスの香りが立ち上がる。