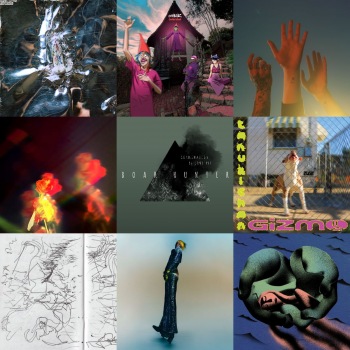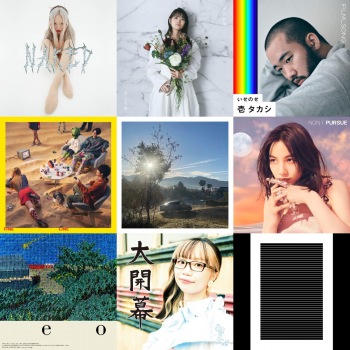REVIEWS : 071 ポップ・ミュージック(2023年12月)──高岡洋詞

"REVIEWS"は「ココに来ればなにかしらおもしろい新譜に出会える」をモットーに、さまざまな書き手がここ数ヶ月の新譜から9枚(+α)の作品を厳選し、紹介するコーナーです(ときに旧譜も)。2023年の最後を締めくくるのは高岡洋詞による“ポップ・ミュージック”と題して、10月から12月までの、SSW、バンドなどなど、国内のここ3ヶ月ほどのエッセンシャルな12作品をお届けします。
OTOTOY REVIEWS 071
『ポップ・ミュージック(2023年12月)』
文 : 高岡洋詞
みらん 『WATASHIBOSHI』
2022年からリリースしてきたシングル6曲を収録した1年9か月ぶりの3作め……だそうだが僕が聴いたのは初めて。メロディも歌詞も歌声もポップな魅力いっぱいで、特に色艶と柔らかさと強さを併せ持った声のよさと歌のうまさが印象に残る。トロピカルな “好きなように” からギターの弾き語りをベースにした “レモンの木” まで、ヴァリエーション豊かでキャッチーな編曲はプロデューサー久米雄介の手腕だろう。 “恋をして” “夏の僕にも” のキラキラぶり、 “海になる” の全行パンチラインなど、1年後にはバカ売れしていても不思議でないポテンシャルの塊。「きみが描いたかわいい怪獣たちを/雑に消すのが大好きだったわ」( “もっとふたり” )の一節がとりわけグッとくる。年寄りには若さが眩しく映るものだが、20代は20代で大変なのだ。
パスピエ 『印象万象有象無象』
2011年に『わたし開花したわ』を聴いたとき、当時の最前線ともいうべき情報処理能力の高さと知性、人を食ったユーモアに仰天したものだ。それから12年、クラシック、ジャズ、ニュー・ウェイヴ、J-POPといったルーツに忠実なのは従来通りだが、地に足の着いた真摯さというか腹の据わり具合というか、「これしかできないから全力でやる」的ないい意味での不器用さにも近い切実さを感じるのは、アルバムも9作めを数えれば自然なことなのかも。 “化石のうた” “選択詩” “バジリコ” などのひねくれたポップさ、 “ならすならせば” や “嬉しいことも悲しいことも” “GOKKO” のメロディと言葉の有機的な関係はパスピエにしか求め得ないものだ。けたたましいのに癒され、ムズムズするのに落ち着く。変わらずワンダーが詰まった11曲。
King Gnu 『THE GREATEST UNKNOWN』
21曲59分50秒をシームレスにつないだ大作だが、まったくそうは感じさせない構成力に舌を巻く。古今のロックはもちろん、ポップからR&B、クラシカルな映画音楽など、バンド・サウンドの限界に挑んだ広大なサウンドスケープのなかに、実に11曲(!)のシングル曲がリアレンジを経てスムーズに収まっている。ポール・サイモンやデヴィッド・ボウイやゴリラズ、日本でいえば細野晴臣、ムーンライダーズ、それこそパスピエなど、隣接するスタイルを次々に飲み込んで拡張してきたエクレクティック・ロックの系譜にあり、しかも大量の情報を高速処理するセンスと能力はその最新版といった趣。ヒップホップのアルバムを聴いているような感興があるのは、インタールード的な小品が配されているだけが理由ではない。