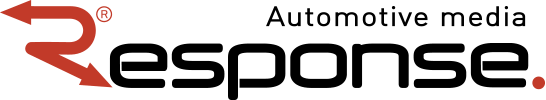EVとは?主な4種類(BEV・HEV・PHEV・FCEV)と特徴、メリット・デメリット
電気を動力とするEV(Electric Vehicle)には、電気のみで走るBEV(バッテリー式電気自動車)、モーターとエンジンを組み合わせるHEV(ハイブリッド車)、外部充電も可能なPHEV(プラグインハイブリッド車)、水素で発電するFCEV(燃料電池車)の4種類がある。
充電時間や航続距離はEVの種類によって大きく異なり、たとえばBEVは充電に数時間かかる一方、FCEVは数分で水素の充填が完了する。PHEVなら、電気とガソリンの併用で航続距離を伸ばせるメリットがある。
充電時間や航続距離は、実用性に大きな影響を与えるため、利用目的にあったEVを選ぶことが重要だ。本記事では、EVの種類ごとの違いや特徴、メリット・デメリットを詳しく解説する。
電気自動車(EV)とは
EVとは「Electric Vehicle(エレクトリックビークル)」の略で、動力はガソリンエンジンなどの内燃機関ではなく、バッテリーに蓄えられた電気を使ってモーターを駆動する。走行中にCO2を排出しないので、クリーンで環境負荷がない。
 「日産アリア」 B6(66kWh、2WD)
「日産アリア」 B6(66kWh、2WD)
バッテリーは主にリチウムイオン電池が使われ、その容量によって走れる距離(=航続距離)が変わる。EVは、一般的に航続距離が短く長距離運転に向かないことや、充電施設の数が少ないなどの課題がある。
EVの課題を補完してくれるクルマがプラグインハイブリッド車(PHEV)だ。PHEVはモーターのほかにジェネレーター(発電機)となるエンジンを搭載しており、基本の走行はEVとして走り、バッテリーの充電量が少なくなると組み合わせた発電用(一部駆動用)のエンジンでジェネレーターを回して発電し、ハイブリッド走行をおこなうことで航続距離を伸ばすことができる。
また、充電スタンドなど外部電源を利用して充電できるのが特長で、電気とガソリンを二刀流で使うことができるのが強みだ。
EVの種類(BEV・HEV・PHEV・FCEV)と特徴
 「Honda e」
「Honda e」
一般に普及しているEVは、主に4種類(BEV・HEV・PHEV・FCEV)に分けられる。4つのEVの基本的な違いを、動力源や充電方法、後続距離などの観点から解説する。

まず各EVの基本的な違いは、走行時の動力源にある。BEVは電気のみ、HEVとPHEVはガソリンと電気の組み合わせ、FCEVは水素から作る電気を動力源とする。
| 種類 | 動力源と仕組み | 主な用途 |
|---|---|---|
| BEV(バッテリー式電気自動車) | 電気のみでモーターを動かして走行 | 都市部での移動、配送業務、通勤・買物など |
| PHEV(プラグインハイブリッド自動車) | 電気とガソリンを併用。外部充電も可能 | 遠距離通勤、営業車、レジャーなど |
| HEV(ハイブリッド自動車) | ガソリンと電気を併用(エンジンで発電) | 一般的な用途全般 |
| FCEV(燃料電池自動車) | 水素から発電した電気で走行 | 長距離トラック、路線バスなど |
長距離トラック輸送ではFCEVが、都市部の配送車両ではBEVが、遠距離通勤や営業車にはPHEVが、一般的な用途にはHEVが適するなど、使用目的によって最適なEVは異なる。
EVの充電・補給時間
走行のための「充電・補給時間」は、EV選びの重要なポイントの一つ。ガソリン給油のように数分で済むものから、充電に数時間かかるものまで、EVの種類によって大きく異なる。
EVの種類ごとの充電・補給時間と走行距離
充電・補給時間は、EV選びの重要なポイントの一つで。ガソリン給油のように数分で済むものから、充電に数十分から数時間かかるものまで、EVの種類や搭載するバッテリーの容量によっても大きく異なる。
| 種類 | 充電・補給時間 | 補給方法 | 一回の補給での走行距離 |
|---|---|---|---|
| BEV |
普通充電:8~12時間程度 急速充電:30分程度(80%充電) |
自宅や公共の充電設備で充電 | 300~500km程度 |
| PHEV |
普通充電:2~4時間程度 ガソリン給油:5分程度 |
充電とガソリン給油の併用が可能 |
EV走行:50~80km程度 ガソリン含む:500~1000km |
| HEV | 給油のみ:5分程度 | ガソリンスタンドで給油 | 700~1000km程度 |
| FCEV | 水素充填:5分程度 | 水素ステーションで水素を充填 | 500km以上 |
BEV(バッテリー式電気自動車)の航続距離はガソリン車などと比べると短いが、一般的な通勤や買い物利用には十分だ。バッテリーが空の状態からフル充電には半日以上かかるものの、継ぎ足し充電や夜間に自宅で充電すればよい。ただし、長距離移動では計画的な充電が必要だ。
PHEV(プラグインハイブリッド自動車)は、日常的な移動はEVモードで、長距離移動はガソリン車として使えるハイブリッドな特性を持つ。HEV(ハイブリッド自動車)は、従来のガソリン車と同様の使い方ができ、頻繁な給油なしで長距離移動も可能だ。
FCEV(燃料電池自動車)は短時間の水素充填で長距離走行ができるため、バスやトラックなどの業務用途に適している。乗用FCEVも登場しているが、水素ステーションはガソリンスタンドや充電スタンドと比べ少ないため、水素ステーションの整備状況を考慮する必要がある。
| 種類 | 走行時のCO2排出 | エネルギー源 | 環境性能の特徴 |
|---|---|---|---|
| BEV | 排出なし | 電気 |
・走行時のCO2排出ゼロ ・電力の製造方法により環境負荷は変動 ・バッテリー製造時の環境負荷に課題 |
| PHEV | 走行モードにより変動 | 電気とガソリン |
・EV走行時はCO2排出ゼロ ・エンジン走行時は少量排出 ・日常的な短距離移動ではBEVと同等の環境性能 |
| HEV | ガソリン車より少ない | ガソリン |
・エンジンとモーターの併用で燃費を改善 ・同クラスのガソリン車と比べCO2排出量を30~50%削減 ・外部充電が不要 |
| FCEV | 排出なし(水のみ) | 水素 |
・走行時のCO2排出ゼロ ・水素の製造方法により環境負荷は変動 ・将来的な再生可能エネルギーとの親和性が高い |
BEV(バッテリー式電気自動車)とFCEVは、走行時のCO2排出がないため、環境性能は高い。ただし環境負荷としては、燃料の電気や水素の製造過程でのCO2排出を考慮する必要がある。
PHEV(プラグインハイブリッド自動車)は、短距離のEV走行では環境性能が高く、HEVは従来のガソリン車と比べて大幅なCO2削減を実現する。特にHEV(ハイブリッド自動車)は外部充電のインフラに依存せず、すぐに環境負荷を低減できる選択肢として普及が進んでいる。
現時点では、電力や水素の製造、バッテリーの製造過程など、走行時以外での環境負荷も重要な課題となっている。今後、製造技術の発展や再生可能エネルギーの普及により、さらなる環境性能の向上が期待される。
EVの種類ごとの車両構造の違い
EVは、動力源の違いによって車両構造が大きく異なる。構造の違いは、整備性や製造コスト、車両価格にも影響を与える。
たとえば、ハイブリッド自動車では、モーターとエンジン両方の仕組みが必要な分、BEV(バッテリー式電気自動車)より複雑な構造になる。
| 種類 | 構造の特徴 | 主な部品 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|
| BEV | もっともシンプル |
・モーター ・大容量バッテリー |
○部品が少なく整備性が高い △大容量バッテリーで価格が高い |
| PHEV | もっとも複雑 |
・エンジン ・モーター ・バッテリー |
○2つの動力源で用途が広い △部品が多く製造コストが高い |
| HEV | やや複雑 |
・エンジン ・モーター ・小型バッテリー |
○技術が確立され信頼性が高い △エンジン整備はガソリン車と同様必要 |
| FCEV | 特殊な構造 |
・燃料電池 ・水素タンク ・モーター |
○高効率な発電システム △専門的な整備技術が必要 |
BEV(バッテリー式電気自動車)は、もっともシンプルな構造を持ち、従来のエンジン関連部品が不要となるため、オイル交換が不要となるなどメンテナンス面のメリットもある。整備性が高い。一方で、航続距離を確保するための大容量バッテリーが、車両重量や車両価格に大きく影響する。
PHEV(プラグインハイブリッド自動車)は、モーターとエンジン両方を搭載するため、もっとも複雑な構造を持つ。2つの動力系統を効率的に制御する必要があり、高度な制御技術と多くの部品を必要とする。このため、製造コストは比較的高くなる。
HEV(ハイブリッド自動車)は、エンジンを主力としながらモーターでアシストする構造。モーターやバッテリーの大きさによってアシストの範囲や出力が変わり、フルハイブリッド(ストロングハイブリッド)や、マイルドハイブリッドなど様々な種類があるのが特徴。長年の開発により完成度が高く、燃費も含めてコストパフォーマンスにすぐれている。
FCEV(燃料電池自動車)は高圧の水素を扱うため、特殊な構造と高度な安全システムが必要。燃料電池という特殊な装置を使用するため、現時点では製造コストが高く、専門的な整備技術も必要となる。
EVの種類ごとのインフラ整備状況
充電や燃料補給のためのインフラ整備状況は、EVの利便性を左右する重要な要素。EVの種類によって必要なインフラは異なり、整備状況にも大きな差がある。
| 種類 | 必要なインフラ | 整備状況 | 利用時の特徴 |
|---|---|---|---|
| BEV |
・急速充電器 ・普通充電器 |
・充電スポット:全国約2万カ所 ・自宅充電が可能 |
○自宅充電で日常的な走行に対応 △長距離移動では充電計画が必要 |
| PHEV | ・充電設備 | ・全国約2.7万カ所のガソリンスタンドが利用可 | ○インフラ面での制約が少ない |
| HEV | ・ガソリンスタンド | ・充電設備も利用可能 |
○従来通りの給油で対応可能 ○新たなインフラ不要 |
| FCEV | ・水素ステーション |
・全国約160カ所 ・都市部中心の整備 |
△水素ステーションが限定的 △整備拡大に時間が必要 |
既存のインフラを活用できるHEV(ハイブリッド自動車)や、ガソリンスタンドと充電設備の両方が使えるPHEV(プラグインハイブリッド自動車)は、インフラ面での制約が少ない。
BEV(バッテリー式電気自動車)は、充電設備の整備が進んでいるものの、長距離移動時には充電スポットの確認が必要だ。FCEV(燃料電池自動車)は水素ステーションの整備がまだ発展途上で、利用可能エリアが限定される。
今後は、BEVの充電設備のさらなる拡充や、FCEVの水素ステーション網の整備が進むことで、利便性の向上が期待される。
EVのメリット
 「日産リーフ」
「日産リーフ」
EVの主なメリット
01EVは排出ガスが出ない(少ない)
EVはバッテリーにためられた電気を使ってモーターを駆動してクルマを動かしているため、ガソリン車のようにガソリンを燃やして排気ガスやCO2を出さない。車両単体で見れば環境に対しクリーンでエコな乗り物といえる。
また、PHEVはバッテリーの充電状態が良いときには電気を使ってモーターのみで走行する。バッテリーがなくなってからも、ハイブリッド車としてエンジンとモーターを併用して走ることができるので、トータルとして燃費が良く環境性能に優れている。
ただし、EVが環境に与える影響として重要なのは、車両単体で見ればクリーンでエコでも、EVに供給する電気を石油や石炭による火力発電などでまかなっていては本末転倒になってしまうということ。国のエネルギー政策を太陽光発電などの再生可能エネルギーにシフトしていくこともセットで考えていく必要がある。
02EVは加速がスムーズで気持ちいい
EVはモーターの特性によって、アクセルを踏みこんだ瞬間にトルクが立ち上がるために、加速性能に優れているメリットがある。ガソリン車は回転数が上がるにつれてパワーを増していく特性のため、その運転感覚は大きく異なる。また、ガソリン車に比べてアクセルの踏み込みに対する応答遅れも少ないので、ドライバーは思い通りの加速を得ることができる。
03EVは振動が少なく、静粛性が高い
ガソリン車、ディーゼル車はエンジンの振動や騒音が少なからず発生するが、EV/PHEVはモーターの特性で振動や騒音が少ない。そのためむしろタイヤが発するロードノイズや風切り音の方が気になるほど。最新のEV/PHEVには、このあたりの遮音性にもこだわったモデルが登場してきている。
04EVは重心高が低く、操縦性に好影響を与える
EV/PHEVはバッテリーを車体の中央床下に搭載する場合がほとんど。このクルマを構成する部品の中でも重量があるバッテリーを車両の中心近くの下の方に収めることで、ガソリン車と比べると重心高が低くなり、高速走行時やコーナリング走行時にも安定して走行することができる。
05ガソリン代より電気代の方が安い
EVなら、同じ距離を走らせたときに電気代が安いメリットがある。たとえば、同じ車種にガソリン車とEVを設定するプジョーの208とe-208を走らせたときのコストを比べてみることにしよう。話をわかりやすくするために、e-208の一充電走行距離(WLTCモード)である380kmを走ることとする。
<条件>
ガソリンは1リットルで170円、ガソリン車のWLTCモード燃費は17.9km/リットル、電気は1kWhで30円、EVの一充電走行距離(WLTCモード燃費)は380km、総電力量は50kWhとする。
| 208(ガソリン車) | 380÷17.9×170=3609円 |
|---|---|
| e-208 | 30×50=1500円 |
380km走ったときの、208のガソリン代が3609円、e-208の電気代が1500円ということで、EVの方が半額以下で走れる試算になった。つまりEVの方が、経済性が高い(=おサイフにやさしい)ことになる。
06EVなら減税、補助金が受けられる
EVを購入するときには、エコカー減税や自動車税の減税を受けられるほか、国や自治体から補助金をもらうことができる。
例)日産リーフe+ G(車両価格499万8400円)を東京都で購入する場合
- エコカー減税3万円+自動車税減税1万8500円=4万8500円
- 国の補助金:42万円 ※令和3年度CEV補助⾦
- 自治体の補助金:45万円 ※東京都の場合
- 合計:87万円
車両価格は499万8400円と同クラスのモデルに比べて比較的高価格だが、減税と補助金の合計が87万円ということで、優遇措置を生かせばリーフe+ Gは412万8400円で購入することができる。
07EVは災害時やアウトドアでの蓄電池として利用できる
EVは大容量のバッテリーを搭載しているため、災害時だけでなく平常時も蓄電池として利用することができる。
たとえば日産リーフe+(64kWh)なら、一般家庭で4日間の電気をまかなうことができる。
※一般家庭での一日あたりの使用電力量を約12kWh/日とした試算値。
また、キャンプなどのアウトドアでの電力使用が可能で、これまでには思いつかなかった場所でEVを蓄電池として利用することができる。
08PHEVは航続距離が長い
PHEVはバッテリーの電気がなくなってもガソリンで走ることができる。たとえば三菱アウトランダーPHEV Mグレードの場合で見てみると、バッテリー容量は20kWhで電気だけで走れる距離は87kmだが、ガソリンではWLTCモード燃費16.6km/リットル×燃費タンク容量56リットル=929.6kmも走ることができ、トータルの航続距離は87+929.6=1016.6kmと圧倒的に長いのだ。
EVのデメリット
EVのデメリット
01航続距離がガソリン車に比べて短い(EV)
「航続距離」とは無給油(無給電)で走ることのできる距離のこと。EVの場合は「一充電走行距離」と同じ意味となる。EVはガソリン車に比べて航続距離が短い。
これも先ほどのプジョー208とe-208を例に見てみることにしよう。
| 208(ガソリン車)の航続距離 | 17.9×44=787.6km WLTCモード燃費:17.9km/リットル 燃料タンク容量:44リットル |
|---|---|
| e-208(EV)の航続距離 (WLTCモード一充電走行距離) |
380km |
この例を見てもわかるように、ガソリン車の方がEVより2倍以上走れることになる。最近ではテスラのモデルSのように、652kmの航続距離(推定)というロングランができるクルマも出てきているが、まだまだ高価格だ。
02EVは充電に時間がかかる
ガソリン車ならタンクが空の状態からでも数分で満タンまで給油することができるが、EVではそうはいかない。このあと説明する急速充電器を使っても、充電器の性能にもよるが30分間で80%を充電するのが精一杯で(リミッターがかかる)、それなりの待ち時間が発生する。
道の駅やサービスエリアなどでは、カフェでお茶したり買い物をしながら時間を潰すということができるが、長距離を走る場合はしっかりと計画してから出かけないと、時間どおりに目的地に着けないことがあるので注意が必要だ。
また、普通充電器の場合は満充電にするまでに一般的に8〜12時間とより時間がかかるため、自宅や宿泊先、勤務先などで長時間駐車する際の充電に適している。
03EV用の充電スタンドが少ない
EV用の充電スタンドの登録拠点数は、急速充電器で8933普通充電器で1万15447(GoGoEV調べ、2024年11月29日時点)と、ここ数年で拡大してきた。しかし、まだまだガソリンスタンド(給油所)の2万7414(経済産業省 資源エネルギー庁調べ、2023年3月31日時点)には及んでいない。
自宅での充電ができるのがEVのメリットだが、遠出した際の充電や万が一の電欠のことを考えると不安に感じる人がいるのは事実だ。また、【02】のように充電に時間がかかるということは、充電スタンドでの充電渋滞が起こる可能性も高いということで、まだ利便性が高いとは言えない。
04EVは車両価格が高い
EVのメリットについては「減税、補助金が受けられる」と書いたが、それでもEVはガソリン車に比べて車両価格が高い。
これもプジョー208(ガソリン車)とe-208(EV)を例に見てみることにしよう。
| プジョー 208 GT車両価格 | 316万1000円 |
|---|---|
| プジョー e-208 GT 車両価格 | 450万3000円 |
| e-208の補助金 | 78万6000円(国からの補助金33万6000円+地方自治体からの補助金45万円 ※東京都の場合) |
| e-208の車両価格から補助金を引いた金額 | 450万3000円―78万6000円=371万7000円 |
ということで、プジョー208とe-208の場合、EVの方がガソリン車より補助金を差し引いても55万6000円高いことになる。減税を考慮すればその差はもう少し縮まるが、ガソリン車と比べると現状では高価格であることは否めない。
また、PHEVもガソリン車より複雑なメカニズムと高価なバッテリーを搭載しているために、どうしても車両価格が割高になってしまう。
05EVは自宅に充電設備が必要
自宅の駐車場に充電設備を設置することでEVの利便性は大きく向上するが、設置には製品代と工事費を合わせて10万円前後かかるので、初期コストが発生する。また、マンションなどでは充電設備が設置できないこともあるので、近所や生活圏内に充電スタンドがあるかを確認しておく必要がある。
EVの充電
 マツダ「MX-30 EV MODEL」 EV Highest set(ハイエスト セット) 2WD
マツダ「MX-30 EV MODEL」 EV Highest set(ハイエスト セット) 2WD
EVの充電スタンド
EVの充電スタンドには、普通充電器と急速充電器の2つのタイプがある。設備の費用負担が少ないために普通充電器の数が多いが、急速充電器は移動の途中での充電に適しており、今後、EVを普及させていくためには、急速充電器の拡充が必要となる。
日本では急速充電器の規格はCHAdeMOが一般的に使われているが、ポルシェのターボチャージャー、テスラのスーパーチャージャーなど、より最大出力の大きな独自の充電規格も登場している。ちなみに一部のPHEVには、普通充電器のみ対応するモデルもあるので注意が必要。
EVの充電時間
普通充電器は単相の交流100Vもしくは200Vのコンセントを使用する。一般的に満充電までにする時間は8〜12時間ほどかかるので、時間の余裕が必須。ちなみに充電量は出力×時間なので、200Vの方が100Vとくらべておよそ半分の時間で済むことになる。
一方、急速充電器は電源に3相の交流200Vを使用する。普通充電器の出力は一般的に3〜6kW、急速充電器は古いものでは20kW程度だが、今では50kWが主流になっている。ちなみにテスラ専用のスーパーチャージャーは250kWという超大容量となる。急速充電器の充電時間は1回30分が基本となり、およそバッテリーの80%までの充電をおこなうことができる。80%に達しない場合はいわゆる「追い充電」も可能だが、混雑時は1回充電がマナーだ。
EVの料金/電気代(出先/自宅)
出先で公共のEV用充電器を利用するには、多くの場合「充電カード」による認証が必要となる。充電カードはEVを販売する自動車メーカーが発行するものもあるが、現在では「e-Mobility Power(以下、eMP)カード」の利便性が高い。eMPは充電インフラを整備・拡充する会社で、公共の充電器のほとんどをネットワークしている。
利用料金はカードによってまちまちだが、月会費が500〜6000円前後、これに都度利用した分だけ、事前に登録したクレジットカードから引き落とされる。
では、EVを自宅で充電する場合の電気代はいくらぐらいなのだろうか?
電気代は基本料金+電力量料金が基本だが、会社や契約プランによってまちまち。さらに充電を日中にするか夜間にするかでも違ってくるが、わかりやすく言うと、1kWhで日中※なら30円前後、夜間※ならだいたい20円前後が一般的な相場となる。
※電力会社によって日中と夜間の時間帯が異なるので要注意。また、新電力は夜間料金の設定がないことが多いので注意が必要。
たとえば日産サクラ(総電力量20kWh)とトヨタbZ4X(総電力量71.4kWh)を満充電にするといくらかかるのか試算してみた。
| 日産サクラ | 日中:30円×20kWh=600円 | 夜間:20円×20 kWh=400円 |
|---|---|---|
| トヨタbZ4X | 日中:30円×71.4 kWh =2142円 | 夜間:20円×71.4 kWh=1428円 |
夜間電力をうまく利用しながら充電すれば、車両価格の高さをカバーすることもできそうだ。
EVの航続距離
 TOYOTA「RAV4 PHV BLACK TONE」
TOYOTA「RAV4 PHV BLACK TONE」
すでにEVでは「デメリット」、PHEVでは「メリット」のところでも紹介したが、ここではもう少し具体的にどの車種がどのぐらいの航続距離(WLTCモード)なのかを見てみることにしよう。
EVの航続距離
EV各車の航続距離の例は以下の通り。
| 日産 | サクラ:180km(20kWh) |
|---|---|
| マツダ | MX-30:256km(35.5kWh) |
| レクサス | UX300e:367km(54.4kWh) |
| プジョー | e-208:380km(50kWh) |
| ポルシェ | タイカン:354km(79.2kWh) |
EVでは搭載されるバッテリーの容量(総電力量)によって航続距離が大きく変わる。また、バッテリーは重く車重に大きく影響する。そのため、容量が同じでも車両重量が重い車種の方が、航続距離が短くなる傾向がある。
また、ポルシェ タイカンは79.2kWhと大容量のバッテリーを搭載しているが、最高出力が240kW(326ps)とハイパワーなため、航続距離は354kmと意外にも短い。これはポルシェに求められるスポーティな走りを実現するため、出力を優先させた結果と見ていいだろう。このように航続距離は、総電力量、車両重量、出力などで決まってくるのだ。
PHEVの航続距離
PHEVのメリットの項で紹介したが、EVと違い、ガソリンエンジンでも走ることができるPHEVは航続距離が長い。PHEVの場合、ハイブリッド走行を含めた航続距離を公表しているメーカーは少ないが、便宜的に以下の計算式で航続距離を出してみた。
EV走行換算距離(等価EVレンジ・km)+ハイブリッド燃費(WLTCモード・km/リットル)×燃料タンク容量(リットル)
| RAV4 PHV | 95+22.2×55=1316km |
|---|---|
| メルセデスベンツ A 250 e セダン | 72.1+16.3×35=642.6km |
| ボルボ XC40 リチャージ | 41+14.0×48=713km |
EVに関する補助金
 ボルボ「C40」
ボルボ「C40」
EVは車両価格が一般的に高めだが、国と自治体から補助金(令和3年度CEV補助金)が受けられるというメリットがある。車種ごと、グレードごとに、「次世代自動車振興センター」のホームページに掲載されているので、EVの購入を考えている人はチェックしてほしい。
次世代自動車振興センターEVの車種ラインアップ
 「The BMW iX xDrive40.」
「The BMW iX xDrive40.」
EVの車種ラインアップ
| 日産 リーフ | 関連記事はこちら |
|---|---|
| ホンダ Honda e | 関連記事はこちら |
| プジョー e-208 | 関連記事はこちら |
コンパクトクラスのEVとしては、国産モデルのホンダeと日産リーフ、輸入モデルのプジョーe-208が代表的だ。
ホンダeはモダンで親しみやすいシンプルなデザインの都市型コミューターで4人乗りとなる。最大の特徴はリアにモーターを搭載したRR(リアモーター・リア駆動)であること。また、インテリアでは5スクリーンを水平配置した世界初のワイドビジョンインストルメントパネルを採用し、先進性をアピールしている。バッテリーの総電力量は35.5kWhで航続距離は283kmとなる。
日産リーフは初代が量販世界初のEVとして2010年に登場しており、現行型は2017年にフルモデルチェンジした2代目。5人乗りの5ドアハッチバックで、標準モデルは40kWhで322kmの航続距離だが、62kWhバッテリー搭載モデルは458kmと、このクラスでは最長のロングドライブが可能だ。
プジョーのe-208はガソリン車の208とボディ、シャシーを共用しているのが特徴。ガソリン車と比較しても居住空間など室内スペースが変わらず、使い勝手に優れている。50kWhのバッテリーを搭載しており、航続距離は380kmとなる。
| マツダ MX-30 | 関連記事はこちら |
|---|---|
| レクサス UX300e | 関連記事はこちら |
SUVは車高の高さからパッケージングの自由度が広く、EVとの親和性が高いため、多くのモデルをラインナップしている。
コンパクトクラスでは、マツダ初の量産EVとなるMX-30が代表選手。マツダとしてはRX-8以来となる観音開きタイプのフリースタイルドアを採用し、スタイリッシュなデザインと使い勝手をうまく融合させている。バッテリーは35.5kWhで、航続距離は256kmとなる。
もう1台はレクサスのUX300eで、こちらもレクサス初の量産EVとなる。UXが持ち味とする個性的なデザインや、高い利便性、取り回しやすさはそのままに、レクサスならではの上質な走りと優れた静粛性を追求している。54.4kWhのバッテリー容量を持ち、367kmの航続距離を実現している。
| アウディ e-tronシリーズ | 関連記事はこちら |
|---|---|
| ポルシェ タイカン | 関連記事はこちら |
| テスラ モデル3 | 関連記事はこちら |
アウディは2026年以降に発売する新型車をEVのみにすると発表しており、EVで覇権を取りに行く構えだ。同車はEVモデルに「e-tron(イートロン)」というブランド名を付けており、日本ではコンパクトSUVのQ4 e-tron & Q4 スポーツバック e-tron(発売は2022年秋以降の予定)、ラージSUVのe-tron & e-tron スポーツバック、ラージセダンのe-tron GT & RS e-tron GTと3車系6モデルをラインナップする。いずれも高出力モーター&大容量バッテリーを搭載しており、アウディらしいダイナミックな走りを実現している。
そしてアウディと同じフォルクスワーゲングループに属するポルシェは、2020年からe-tron GTの兄弟モデルとなるタイカンを日本で発売している。タイカンの最上級グレードのターボSは最高出力750hp(約760ps)、総電力量93.4kWhというハイスペックを誇る。e-tron GTよりもさらに高性能に振っており、タイカンがスポーツカー、e-tron GTはグランツーリスモというように性格を分けている。
テスラはEVのみに特化した自動車メーカーで、なかでもコンパクトセダンのモデル3が世界的に売れている。その人気の秘密は、0-100km/h加速3.3秒という圧倒的なパフォーマンスと565kmという長い航続距離、そして479万円〜というリーズナブルな価格設定だ。
| BMW iX | 関連記事はこちら |
|---|---|
| メルセデスベンツ(EQ) EQC | 関連記事はこちら |
| ジャガー I-PACE | 関連記事はこちら |
そのほかにも輸入ブランドのSUVは群雄割拠の状態で、2018年にいち早く日本に導入したメルセデスベンツ(EQ) EQCとジャガー I-PACE(アイペイス)は全長がそれぞれ4770/4695mmということで、どちらもアッパーミドルクラスに属する。どちらも400psを超える高出力モーターを搭載し、航続距離も430km以上としており、パフォーマンスは互角と言える。
そして2021年11月には、BMWから満を持してiXとiX3という2台のEVのSUVが同時に日本発売された。iX3は全長が4740mmでEQCとI-PACEと同じアッパーミドルクラスに属するが、iXは全長が4955mmとe-tronと同じラージクラスとなる。車名のとおりX3をベースにした1モーターのEVで、FR(フロントモーター・リア駆動)となるが、iXは専用のプラットフォームを採用した2モーターの4WDとなる。
 PEUGEOT「NEW 3008」
PEUGEOT「NEW 3008」
PHEVの車種ラインアップ
| トヨタ RAV4 PHV | 関連記事はこちら |
|---|---|
| 三菱 アウトランダーPHEV | 関連記事はこちら |
| レクサス NX450h+ | 関連記事はこちら |
PHEVも車種カテゴリーとしては、EVと同様にバッテリーを搭載する必要性からパッケージングの自由度が高いSUVが圧倒的に多い。
RAV4 PHVとアウトランダーPHEVは、どちらもアッパーミドルクラスのSUVでまさにガチンコのライバル関係にある。アウトランダーPHEVは急速充電に対応しているが、RAV4 PHVは普通充電のみとなる。最高出力ではシステム出力306psのRAV4 PHVに軍配が上がるが、アウトランダーPHEVは三菱が誇る電動4WD技術による高い走破性、そして3列シート7人乗りという武器を持っている。
この2台とサイズ的にはほぼ互角ながら、レクサスと独自のプレミアム性を打ち出したSUVがNX450h+だ。RAV4 PHVと共通のメカニズムを搭載するが、NX450h+の方がレクサスらしい質感の高さを演出している。
| ジープ レネゲード 4xe | 関連記事はこちら |
|---|---|
| プジョー 3008 HYBRID4 | 関連記事はこちら |
| ボルボ XC40 Recharge | 関連記事はこちら |
輸入ブランドでは、前の3車よりもサイズがひと回り小さいコンパクトからミディアムクラスのSUVが揃っている。
ジープ初のPHEVレネゲードは、ジープならではのアイコニックなデザインと、全長4255mmという手頃なサイズ感が特徴。
洗練されたデザインが人気のプジョー3008にも、GT ハイブリッド4というPHEVモデルを設定。こちらはシステム出力が300psと、その見た目からは想像できないほどのパワーを秘めている。
ボルボは、XC40、XC60、XC90という3モデルにリチャージ プラグインハイブリッドというPHEVを設定。全長4425mmと最もコンパクトなXC40は、FFのみの設定で、41kmのEV走行が可能となる。
| ポルシェ カイエンE-ハイブリッド | 関連記事はこちら |
|---|---|
| ランドローバー レンジローバー | 関連記事はこちら |
ラージSUVのポルシェ カイエンはシステム出力462psを発生するEハイブリッドと、同680psを発生するターボS E-ハイブリッドを設定。そしてこのどちらにもクーペタイプもラインナップしている。とくにターボS E-ハイブリッドの走りはSUVでもポルシェらしさを感じさせる躍動的で刺激的なものだ。
ランドローバーのレンジローバーにもPHEVモデルを設定する。3リットル直6+モーターを搭載し410psのP410eと510psのP510eという2モデルをラインアップ。その優れたオフロード性能がもたらす機動性の高さは折り紙付きで、オフロードも安心感のある走りを披露する。
| トヨタ プリウスPHV | 関連記事はこちら |
|---|---|
| メルセデスベンツ A 250 e | 関連記事はこちら |
| BMW 330e | 関連記事はこちら |
トヨタのプリウスPHVは、現行型が2代目。プリウスとは異なるデザインを採用し、先進的なイメージを醸し出している。60kmのEV走行が可能で、急速充電にも対応しているので、ガソリンを使わずよりアクティブに行動することができる。
メルセデスベンツはコンパクトカーのAクラスに、A250eとA250セダンというPHEVを受注生産モデルとして設定している。1.3リットルターボエンジンは160ps/250Nmだが、これにモーターの72kW(102ps)/300Nmを掛け合わせ、見た目の印象からは想像出来ない加速を見せる。
BMWもPHEVのラインナップを拡大しているが、ミディアムクラスセダンの3シリーズには330eというPHEVを設定している。2リットル直4ターボにモーターを組み合わせ、最高出力は215kW(約292ps)というハイスペックを誇る。その走りは爽快で、BMWが提唱する駆け抜ける歓びを感じられるPHEVに仕上がっている。
最新ニュース
-

フォードのEV新型2車種、コンチネンタルタイヤ純正装着…効率と快適性を向上
-

BMW『iX』最上位モデルが「M70」へ進化! 659馬力にパワーアップ、100km/hまでわずか3.8秒
-

フィアット『グランデ・パンダ』、EVとハイブリッド設定…3月欧州発売へ
-

トヨタ プリウスPHEV、ジオフェンシング技術で「リッター200km」に燃費向上…欧州2025年モデル
-

EV向け800Vシステム対応、インフィニオンが高効率な新パワー半導体発表
-

東京オートサロン2025出展車を制して、トヨタの新型EVが注目度トップに!…1月の詳細画像記事ランキング
-

マンション・アパートの機械式駐車場でもEV充電可能に、ユビ電とファムが業務提携
-

「集大成感ある」「めっちゃお得」SNSで反響の新型テスラ『モデルY』、ボディサイズ拡大には賛否両論?
-

ENEOS、エネチェンジのEV充電器とローミング連携へ 2月3日から
-

ポルシェ『タイカン』、氷上EV連続ドリフトでギネス世界新記録…17.5kmを走破
最新レビュー記事

【メルセデスベンツ EQB 新型試乗】コンサバ一家も違和感なく乗り換えOK!BEV初の7人乗りSUV…南陽一浩

買うなら急いだほうがいい? 読んで決める、EV試乗記ランキング 2022年上期

【日産 サクラ 新型試乗】補助金なしでも180kmの航続距離に納得できれば…丸山誠

【三菱 ekクロスEV 新型試乗】ふつうに走れてふつうに乗れるEV、という価値…岩貞るみこ

【BYD ATTO3 新型試乗】日本のEV市場の台風の目となるか?その実力は…丸山誠

【三菱 eKクロスEV 新型試乗】軽自動車とBEVの相性は、間違いなく良い…中村孝仁

【日産 アリア 新型試乗】第一印象は、洗練、上質、そして知的なBEV…中村孝仁

【BMW iX 新型試乗】約1400万円でも納得、新鮮さを味わえるEVだ…中村孝仁
人気記事ランキング
-

【日産 エクストレイル 新型】最高出力は同じ、FWDとe-4ORCE…違いは過渡特性
-

メルセデスベンツのフルサイズ電動SUV『EQS SUV』、生産開始[詳細写真]
-

ハマー EV、まずは最強1000馬力仕様がラインオフ…GMの「ファクトリーゼロ」から
-

VWのEVミニバン、『ID.Buzz』…今秋から納車を欧州で開始
-

ジープ『リーコン』、新世代電動SUV…2024年から生産へ[詳細写真]
-

わんこ2匹と一緒に乗れる、電動バイク『ポニー』先行販売開始
-

ルノー『5』復活? 50周年記念コンセプトはEV
-

ジープの新型車、EVの可能性も…9月8日発表予定
-

テスラのEVトラック『セミ』、新写真を公開…内外装をアップデート
-

【日産 サクラ 新型試乗】軽ユーザーの一日の走行距離は50km以下って言うけれど…岩貞るみこ