大岩優輝さんの行った(口コミ)お店一覧
行ったお店
検索条件が指定されていません。
1~20 件を表示 / 全 151 件
令和三年三月五日、巧まずして啓蟄の雨疎らなるみぎり、鮨党の畏友とともに名古屋市名東区本郷の『おけい鮨』さんを初めて訪ねました。 こちらの橋本博親方は、御齢十七の若さから、六本木(当時は芋洗坂を少し下った場所だったそうな)の銘店『福鮨』さんの亡き先々代・福澤重雄翁の下で修行を積まれたとの由。また、十数年前に中野坂上より銀座五丁目に移転された超有名店『さわ田』さんの澤田幸治親方が、嘗てこの『おけい鮨』さんでも学ばれたとも仄聞しましたが、今回お伺いし、実に合点がいった次第です。 故・福澤重雄翁曰く、「うちは企業じゃないよ、家業だよ」「家族の顔が見えないお店はダメ。必ず家族の者がお客様をお迎えしなきゃいけないよ。人任せにして支店なんかは作っちゃいけない」と。橋本親方はこの教えを確りと守られており、こちら本郷店では二番手を御子息が、給仕は女将さんが務められています。 なお、本店に当たる『石川橋店』はこちらの御令兄である橋本武夫親方が、『本山分店』は本店の二番手さんが、那古野の『鮨橋本』さんは本店の御子息の橋本達也親方が、それぞれ営んでいらっしゃいます。更に或る方のブログを拝見し、堀田の『春勢』さんや、大曽根の『鮨Diningおぐら』さんも、おけいさんの門下であると知り、改めて其の脈々たる系譜に瞠目いたしました。因みにおけい鮨さんの先代は、二親方御兄弟の御母堂だとか。 扨て、橋本博親方は、輓近は稀覯な〝捻り鉢巻〟をされた、如何にも粋な鮨職人を思わせるお見附です。然り乍ら全く居丈高で寡黙に非ずして、寧ろ然許り柔和で能弁な御仁。お鮨や一品料理を供される折りにも、含蓄に富んだ御高説を賜り、其れで居て全く嫌味が御座いません。其れも其の筈、塩の研究家としても御高名な親方は、今年で御齢七十五歳を迎えられ、数年前に体調を崩されるまでは、全国各地を廻り講演をされていたとか。 入店と共に「いらっしゃいませ!」と親方から意気軒昂たる御挨拶を賜り、思わず背筋が伸びます。店内は宛ら街場鮨を思わせる設え。決して悪い意味に非ずして、正に千客万来、雲勢万勢の活気に満ちており、御常連の足繁く通われる理由が疾うに伝わってきます。錦や丸の内の華やかな雰囲気や、一見お断りの凛とした空気感とは一線を画する世界感で、語弊を恐れずに申さば、矢張り街場鮨と形容するのが最も適うているのではないでしょうか。カウンターは十二名程が掛けられる堀込になっており、小上がりには二卓程のテーブル席が御座いました。 先ず以て、畏友が酒類を嗜まれないとの事なので、今回は大人しく(笑)、温かいお茶をいただき、早速お鮨がメインの『璃寛』コースを注文。因みにこちらのコース名は何れも特徴的なのですが、寡聞にして存じなかったため、〝困った時のGoogle先生〟を恃みに調べましたところ(汗顔)、総て日本の伝統色、尚且つ江戸時代に於ける歌舞伎役者の俳名に準えた、当時の流行色であることを識りました。いやはや、何ともあはれなり、いとをかし、当今はエモいと申すべきか(笑)、実に趣がありますね。而して勉強になります。おっと、直ぐに話が横道に逸れるのは御愛嬌として御寛恕賜りたく存じます(汗顔)。やっとかめに頗る肌に合うお鮨屋さんに寄せていただいたので、如何しても筆が進んで仕舞うのです。何分御容赦を。 閑話休題、先ず親方はお通しとして、『白魚の卵綴じ』を供されました。我らが木曽三川のシラウオです。春の味覚ですね。素朴な味わいが何とも言えず、白魚の上品な風味に思わず食指が動きます。白魚は蛤が漁れる河口や汽水湖なら何処でも漁れるのですが(※塩害に伴う常陸川水門の建設で、淡水湖となった常州は北浦でも今なお漁れ、帆曳き網漁で有名ですが)、如何せん桑名の白魚は小さく、天麩羅の種などでは敬遠されがちで、宍道湖などのものを供されるお店が多い印象ですが、其の実、汽水域たる揖斐川河口の白魚は、塩分濃度がよく、抜群の塩加減であると評判です。本稿を記している数日前に伺った、地元の星『平和寿司』さんでもかなり推しており、生・煮・揚の三段活用で供されました。 扨て、やおら握っていただきました。こちらは赤酢を使われています。程良く甘めで酸味は控えめ。硬さも含め優しめの印象ですが、粘りなんざ皆無です。また、生姜は甘味がなく、ピリッとした辛さの立ったもの。 以下、いただいたお鮨と其の印象を列記して参ります。 ・真鯛 昆布〆 親方は塩昆布を乗せ、ほんの少し檸檬を合わせられました。之れが出色。少しばかり寝かせたと思しきややしっとりとした真鯛は、秀逸な旨味と香り。昆布〆に塩昆布まで配されたとは思えない程、イノシン酸とグルタミン酸のバランスが素晴らしく、飽くまで昆布は脇役として出しゃ張りすぎていません。檸檬を白身か烏賊に配されたのは東桜の『鮨処成田』さんもそうだったか、敢えて酢橘ではなく檸檬を使われるのは、確たる理由があってのことでしょう。柑橘類を強か搾ったり、〆しすぎた白身に是れ復た多すぎる塩と香りの強い酢橘を配したりして、繊細な風味を殺してしまう凡百の握り手さんが散見されるなか、他の追随を許さざる腕と技であると拝察します。 ・甘海老 海老味噌のソースと小口切りにした浅葱を添えて。とりわけ女性からこちらのスペシャリテとも評される握りです。何とも濃厚な味噌と、甘海老のねっとりした食感と甘みが官能的。このソース…海老の頭をミンチ状にして海老味噌と混ぜてあるのでしょうか。違ったら恥ずかしいですが(汗顔)。臭みは皆無。最近は紹興酒漬けなどされるお鮨屋さんもありますが、こちらは以為らく立て塩もしっかりされているのではないかと。 ・ばふん雲丹 軍艦巻き 根室は花咲港の明礬不使用のものだとか。皆さんの投稿を拝見すると、如何やら日高昆布の名産地としても知られる前浜産のようです。濃厚な甘みとコクは固より雲丹らしい豊潤な香りが素晴らしい。海苔と雲丹の風味が見事にマッチしており、なかなかでした。 ・寄せ豆腐 お豆腐屋さんに特注している、おけい鮨さんでしかいただけない逸品。濃厚な大豆の風味と滑らかで蕩めくような食感。この円やかさを引き立てているのが、奥能登は見附島を臨む、珠洲の揚げ浜塩田の塩とにがり。その歴史は実に四百年以上前、後陽成天皇の御代にまで遡ります。当時の加賀藩二代藩主・前田利常公は「改作法」の一環として「塩手米制度」を敷き、土地を持たない貧農に対し、米を貸し付ける代わりに塩硝を納めさせるなど、製塩を奨励しました。土地柄、大きな川がないため海水の塩分濃度が高く、且つ内浦で砂浜の多い能登は、製塩には最適の地だったのでしょう。また専売権を敷くことにより、嘗て豊臣家の旗下にありお取り潰しが恐れられた加賀藩にとって、無言の武力を持つことにもなりました。 なお、揚げ浜式製塩は今なお奥能登・珠洲の地に受け継がれ、国の重要無形民俗文化財にも指定されていますが、珠洲以外でも塩田による伝統的な製法で塩を作っている場所がただ一つあります。そう、それこそが伊勢の神宮。内宮の御料地である、五十鈴川沿いの御塩浜で汲んだ海水により、御塩殿鎮守神の鎮座まします、同地の御塩田並びに御塩殿神社で謹製された御塩が、神饌として奉納されているそうです。 今回いただいた能登の揚げ浜塩田の塩は、ジッパー付きのビニル袋でお持ち帰り。塩味が強すぎず、仄かに甘味を感じます。塩むすびに最適だとか。 ・本鮪の中とろ&大とろ 千葉勝浦のもの。此処から親方が握られました。僅かながら親方の方が、二番手である御子息よりも強めに握られていると感じました。 こちらは煮切りが塗られておらず、直接醤油皿からつけるよう促されましたが、已んぬる哉、前述の塩を掛ければ良かったと、いただいた後でハッとしました。 厚めの切り付けで脂の乗りも勿論良かったのですが、これを塩でいただいたら…と思うと一寸後悔です。中とろはしっかりとした脂の旨味に、後味として仄かな酸味の余韻を残し、大とろは脂の旨味が強いですがくどさはありません。 ・虎河豚 天然もの。紅葉おろしと浅葱を合わせ、タネと酢飯の間に鉄皮をかましています。しっかりとした歯応えで且つ切り付けも酢飯とのバランスが素晴らしい。若干水っぽさを感じないでもなかったですが、薬味でカバーできていました。最近有難いことに河豚をいただく機会に恵まれているので、此処らで炙りも食べてみたいなぁと思ってみたりもしました。 ・浅利の味噌汁 茶碗蒸しか味噌汁かを選べます。椎茸が苦手なのと、季節的にもこちらを選びました。因みに畏友は茶碗蒸しを。 赤だしではなく合わせ味噌のようです。しっかりとした浅利の旨味と香りが出汁になっており、ほっこりします。浅利は恐らく地物と思われますが、なかなか身も大きく食べ応えがあります。 ・真鰺 3枚づけ。伊良湖水道のものにおろし生姜と浅葱を合わせて。如何せん食感は柔らかかったですが、香りと旨味は良く美味しかったです。薬味がいいアクセントになっていました。新井白石が『東雅』で「鰺とは味なり、その美なるをいう」と述べた話は何処かでしたかと思います。 ・喉黒 焼き 炙りというより焼きに近い喉黒です。カボスと塩で。これがまたお見事。爽やかなカボスの香り。滴るばかりの脂ながら、全く拗さを感じさせません。皮目の香ばしさが更に強いと尚良。 ・煮蛤 木の芽を合わせて。少し香りが気になりましたが、この絶妙な柔らかさは、火入れ、漬け込みも含め、抜かりなく手当てをされた証左でしょう。噛むほどにコハク酸が口腔内に広がります。ツメはサラッとして濃すぎず甘め。ただ、無粋ながら蛤がもう少し良質なものなら…と思ってしまいました(汗顔)。なお、穴子の項目で後述しますが、こちらは極めてクラシカルな仕事をされているようです。 因みに国産の蛤は巷間には稀有。桑名の蛤なんて豪語しながら、実際は支那蛤を桑名で蓄養したもの、なんて話が彼方此方で散見されます。言うならばバッタモンですね。これはこれで美味しいんですが、矢張り桑名の本地蛤しか勝たんです(笑)。いやはや長良川河口堰の問題然り、旧建設省と土建屋連中の薄汚い癒着には甚だ忿懣やる方なし。彼奴らの大罪は万死に値するでしょう。 ・車海老 出ました、県魚。三河湾の車サイズ。生きたものをしっかり拝見していないので断言はできませんが、この歌舞伎の隈取を彷彿とさせるくっきりと華やかな縞模様は、まさしく天然ものではないでしょうか。香りも甘みも食感も素晴らしい。個人的には茹でたての温かいものも好きですが、茹でてすぐ氷水に漬けて粗熱を取り、発色を更に強めた、江戸前の仕事が為されています。 ・青柳 地物。しっかりと紐付きでピンとそそり立った斧足が何とも粋。臭みがなく、独特の風味と甘味、ほんのりした苦味がなかなかです。いやはや春ですね。歯応えがあり、水っぽさもなし。こちらも仕事が活きています。一度、本場江戸前・市原産のものや、摘みに最高な干し姫貝の炙りも食べてみたいですね。 ・蛍烏賊 軍艦巻き 茹でたものに酢味噌と浅葱を合わせて。絶妙な張りと噛んだときに溢れるワタの濃厚な甘味がよき。ただ、酢飯とのバランスは矢張りあまりよくないのか、一体感がいま一つです。摘みとしていただきたいですね。もう少しすると沖漬けも出回るそうなので、そちらも楽しみ。 ・焼き穴子 柚子塩&ツメ 名古屋では珍しい焼き穴子。時折り江戸前ならば煮穴子、関西の押し鮨ならば焼き穴子、と宣う朴念仁がいますが、酢飯の塩梅で幾らでも応用が利くかと。柔らかすぎない絶妙なふんわり感がまた一興。 さて、煮蛤の項目で少しばかり俎上に載せましたが、こちらは何と言っても〝トモヅメ〟の仕事をされています。多くのお鮨屋さんでは、こんな時間と労力のかかることは致しません。ツメ(=煮詰め)とは要するに甘ダレのことで、昔はその種の煮汁に醤油や味醂を合わせて煮詰めていましたが、今は何処も同じツメを使われているところが殆どです。穴子だけでも骨の下処理から裏漉し、気の遠くなるような煮詰め、種の漬け込みと逐一手間がかかるのに、おけいさんは蛤でもしっかりと蛤詰め(某氏の投稿を拝読し、斯様に称される旨知りました)を如才なくされており、こうした仕事をされているだけで既にこちらに伺う価値があると愚考します。 柚子塩に関しては流石塩の巨匠、穴子の甘みが際立っており、柚子もいい塩梅。ツメについても、その濃度や甘さ、とろみに至るまで素晴らしい。唸らされます。 ・桜鱒(追加) 旬の走りの本鱒。早咲き桜は咲いていますから、もう盛りなのでしょうか。浅葱がかましてあります。若干水っぽさが気になりました。おけいさんはアニサキスの懸念から鯖も一度冷凍されているとの由。桜鱒も当然そうでしょうが、たまたまかも知れませんが、手当てが少々甘かったのかも知れません…多謝。とは言え名古屋で桜鱒も珍しいですし、季節を味わうものですからね。 ・鰹 藁燻し 無農薬有機米(!)の藁二種類(岐阜は郡上八幡の上野さんのものと、愛知は新城の浅井さんのものだったか)を二度に分けて燻したものに、塩を合わせて。これは出色でした。先ず嫌みのない藁の香りが何とも堪りません。昨今はバーナーで炙られるお鮨屋さんが多いですが、この燻した藁の芳しい薫香は明らかに一線を画しています。もちろん鰹自体の香りと酸味も上品且つ豊かで、この爽やかさが申し分ありません。是非ともこちらで初鰹がいただきたいなと切望する次第です。 ・玉子焼き しっかりと空気を抜いて焼き上げた、江戸前伝統のカステラ系玉子焼きです。最近流行りのスフレのようなデザート風の玉子焼きも好きですが、矢張りこうしたお店では本流がいただけてオツですね。芝海老の風味と甘みが何とも粋。硬すぎず柔らかすぎないふんわりとした食感は、まさしく大和芋を使われている何よりの証拠です。 ・小鰭(追加) バシッと〆られ酸味が立った、実にクラシカルな小鰭。親方が「鮨は小鰭に始まり、小鰭に終わる」と嬉しそうに仰っていました。「鮨は小鰭に止め刺す」という言葉が指すように、小鰭ほど職人さんの手当てによって味や食感の変わるタネはないでしょう。みっちりとしていながら、パサつきなど皆無。水っぽさも生臭さも全くありません。迸る香りが最高。塩加減も丁度良いです。 ・小柱 軍艦巻き(追加) こちらはなかなかの大星です。シャキッとした食感、香りと甘みが出色。海苔と合わせることで最高の磯の風味が堪能でき、何とも官能的です。酢飯との相性もバッチリ。小柱と呼ばれるのは、平貝や帆立などと比べて貝柱が小振りなため。 ・干瓢巻き 巻物は五種類(干瓢、山牛蒡、梅しそ胡瓜、ひろっことおかか、とろたく)から二つ撰ぶのですが、どうしても干瓢は外せないし、今しかいただけない人ひろっこが食べたかったので、畏友のご所望されたとろたくと合わせ、無理を申し上げて三種類巻いていただきました。親方の粋な計らいに頭が下がります。 さて、こちらの干瓢巻きは山葵をかましています。醤油は穏やかで甘みが立っており、濃すぎず優しい印象。バッチリ歯応えがあり、総じて好みです。 ・とろたく巻き 良質なとろに生姜と大葉を合わせて。これが可成りの好印象。これまで、あちらこちらでいただいてきた中でも、一、二を争うほどです。細切りにした沢庵を幾らかかまし、秀逸な食感と甘みを演出。また大葉の香りが何とも爽やかで、正にとろとの三位一体。海苔は何方のものか訊き忘れましたが、風味も食感もなかなかでした。 ・ひろっことおかか巻き 秋田をはじめとした東北の一部地域で栽培される、浅葱の若い芽であるひろっこ。『あま木』さんでもいただきましたが、こちらは雪融け後の天然ものでしょうか。おかかは枕崎は『まるけい』さんの本枯節をその場で削って。いやはや、感服いたしました。ひろっこのシャキッとした食感、最高品質たるおかかの秀逸な香り、甚だ無粋ながら正直何本でも食べたいです。 ・苺 東郷町は『コンドウ農園』さんの「かなみ姫」。栃乙女と章姫の自然交雑種ですが、何とも巨大で面喰らいました(汗顔)。非常に瑞々しく、酸味がなく際立った甘みです。これをジャムにしたら至高ではないでしょうか。改めて親方の生産者さんとの繋がりの広さを実感します。 初見の今回はこれにてお納めです。 扨て扨て、何時にも増して長文となって仕舞いました(笑)。何とも久方振りに驚嘆させられるお鮨屋さんに伺い、張り切ってしまい…至り穿鑿は寧ろ野暮で無粋でしょうか(汗顔)、否、学究の人たる橋本親方に相対した以上、それ相応の知識を身に付けたいと思うのが、通人気取りの性。筆者のような生半通、もとい生四半通はまだまだ青いですが、倦まず撓まずなお研鑽に努めてまいりたいと思う次第です。 おけい鮨本郷店さん、名古屋を代表する素晴らしいお鮨屋さんです。蓋し種の質に関して囂しく宣う無粋者が彼方此方にいますが、こちらのような老舗の極めて真っ当なお鮨屋さんと高級鮨店さんを比べる方が野暮でしょう。今後、初鰹、春子、新烏賊、新子、厚岸のまるえもん、秋刀魚の押し鮨、『浅草やげん堀』さんの七味を合わせた鱈の白子、氷見の鰤大根、白板昆布を合わせた鯖、梅しそ胡瓜巻きなどなど、いただきたいものが山積みです。 なお、親方はここ数年、体調の優れないことが増えてきていらっしゃると仄聞。名古屋の至宝である橋本親方には、いつまでもお元気でいていただきたいと、深く深く乞い願うて已みません。当然、今後ずっと通わせていただきます。 本当に色んな意味で味わい深く、感動させられました。是非皆さんにお訪ねいただきたい超名店です。 ご馳走さまでした。 百拝
2021/03訪問
1回

2023/11訪問
1回
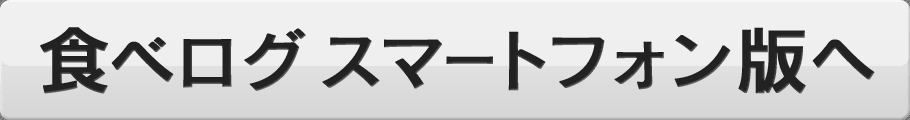





















新橋の親方とニアミス!