熊本の「交通系IC全部廃止」は東京でも起こるのか 「きょうからSuica、使えないモン!」な事態に
2016年に約8億円をかけて全国共通の交通系ICを導入し、「我が街の鉄道・バスで、SuicaやICOCAが使えます!」と大々的に宣伝していたが、それから10年も経たないうちにあっさり使えなくなり、愛用していたカードで乗車できなくなってしまった。
クレジットカードをかざして乗車する「タッチ決済」は、首都圏だと東急電鉄・東京BRTなどが対応しており、キャッシュレス乗車の手段としてじわじわ普及している。ただ、これまで2億枚が発行されてきた交通系ICの知名度には遠く及ばず、「クレジットカードで電車・バスに乗れる」事実すら知らない人も多いだろう。
ましてや熊本県では、乗客の1/4(24%)が交通系ICを利用しており、使えなくなった旨を乗車の段階で知らされ、愕然とする人々も見受けられたという。
9年前に少なからぬ費用を負担して導入した交通系ICを、なぜわざわざ「全撤去」する必要があったのだろうか?
交通系IC「維持or撤退」で7.7億円の差


熊本県で交通系ICの全撤退が起きた最大の理由は、「おおよそ7.7億円の差がつく」費用負担の問題だ。
(国の補助なし)
☆タッチ決済を含めたシステム(採用)=導入費用6.7億円
(負担割合:国1/3、鉄道・バス会社1/3 、県1/6、市1/6)
熊本県の鉄道・バス5社は、交通系ICの保守契約満了が、2025年3月に迫っていた。今後の更新には12.1億円を要するものの、導入時に政府から行われる補助(「地域交通キャッシュレス決済導入支援事業」など)はあくまでも「導入支援」であり、更新への補助はない。
国交省の資料にも「代替更新のみに要する経費は補助対象外」とご丁寧にも明記されており、鉄道・バス5社と熊本県・熊本市が12.1億円すべてを被らなければ、交通系ICを存続できない状況だった。










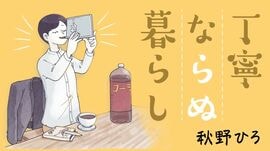









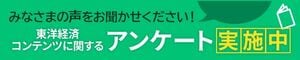









無料会員登録はこちら
ログインはこちら