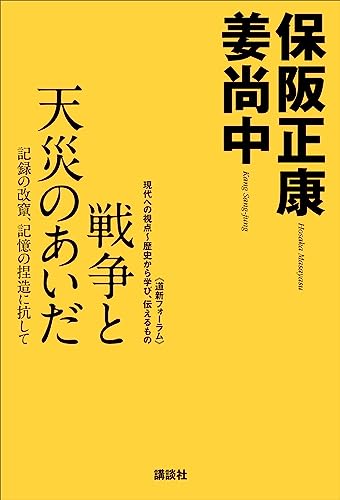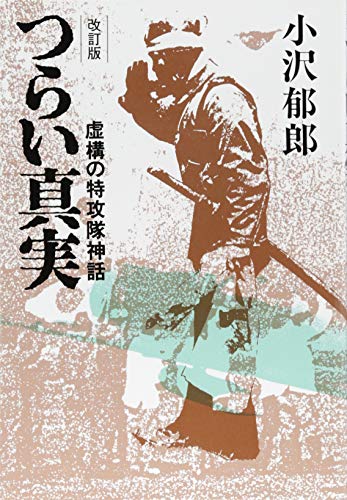特攻隊がテーマといえば、『永遠の0』とかしょーもない話が目白押しだが、それにしてもこれは一線を越えてしまった感がすごい。
公式サイト掲載のあらすじが以下。
親や学校、すべてにイライラして不満ばかりの高校生の百合(福原遥)。
ある日、進路をめぐって母親の幸恵(中嶋朋子)とぶつかり家出をし、近所の防空壕跡に逃げ込むが、朝目が覚めるとそこは1945年の6月…戦時中の日本だった。
偶然通りかかった彰(水上恒司)に助けられ、軍の指定食堂に連れていかれる百合。
そこで女将のツル(松坂慶子)や勤労学生の千代(出口夏希)、石丸(伊藤健太郎)、板倉(嶋﨑斗亜)、寺岡(上川周作)、加藤(小野塚勇人)たちと出会い、日々を過ごす中で、彰に何度も助けられ、その誠実さや優しさにどんどん惹かれていく百合。
だが彰は特攻隊員で、程なく命がけで戦地に飛ぶ運命だった−−− 。
時代設定がなんと1945年6月。敗戦のたった2ヶ月前である。この時代の日本社会の雰囲気を知っていたら、いくらタイムスリップ設定のファンタジーといってもこんなアホな話は作れないだろう。
だいたい、周囲と明らかに服装も違う身元不明の若い女がふらふら歩いてたら、まず真っ先にスパイと疑われる。たちまち特高か憲兵隊に捕まってアウト。たかが一特攻隊員に助けることなどできはしない。
女子高校生がタイムスリップして特攻隊員と恋に落ちるだ?
— ゴクラクトンボ (@takayukiigokura) December 7, 2023
隣組で相互監視が凄まじい時代に
素性不明な人間が自由にできるワケないだろよ。
憲兵に突き出されて物語は終わりだ。
特攻隊も戦争の悲劇ですが、相互監視の時代の閉塞感、絶望感も忘れてはいけないのです。
— ゴクラクトンボ ???? (@takayukiigokura) December 7, 2023
ところで特攻隊といえば、日本では純粋な若者たちが家族や愛する者を守るために笑って散っていったというような美しい物語が広く流布しているが、これは戦後になって作られたファンタジーでしかない。
中にはそんな隊員もいたかもしれないが、大半の現実は次のように過酷なものだった。[1][2]
特攻隊員の本心はどこにあったか。ある調査が存在するのだが、陸軍航空本部は昭和二十年五月末に知覧基地で「特攻隊員の心理調査」を密かに行っている。その結論には最終段階となっても「益々決心ヲナスニ甚大ノ努カを要スル」隊員は「約三分ノ一アリ」と記載されていたという(生田惇『陸軍航空特別攻撃隊史』)。
生田は、特攻隊員の三分の一は「最初から希望していなかった」としたうえで、「戦隊長以下全員が特攻となるなら喜んでいくが、特定人員だけというのは納得できないとする心情もあったようである」と書いている。
この調査結果は当時の建て前の中での調査にすぎないが、それでも三分の一は不本意に思っているとするなら、実は大多数の特攻隊員が納得していなかったと思える。志願を挙手で募ったとか 「一歩前へ」などとその意志を尊重したかのような論が、戦後は主に指揮官や軍事指導者から弁解気味に語られているのだが、「個人の人格」など寸分も考慮しない日本軍にあって、特攻志願だけにそれが行われたなどというのはまさに笑止である。
保阪 記憶をもった人はほんとうにいなくなりますが、自分なりに仕事を進めていますと、一般に言われている事実や記憶を修正するかっこうになることもあります。
たとえば二年ほど前、千葉で講演したあと、杖をついたおじいさんが、
「どうしても保阪さんと話をしたい」
と、お嬢さん ―― といっても五十代ぐらいになっておられましたが ―― といっしょにやってこられた。そして娘さんに、
「ちょっと出てろ」
と言って別室に下げてから、私と二人で向き合って、
「自分はがんで余命もかぎられている。あなたに話を聞いてほしい」
と前置きして話しはじめた。「私は学徒兵で整備兵でした。私たちは昭和二十年の四月に何人もの特攻の飛行機の整備をしました。知覧からは特攻で何人も飛んでいきました。彼らは飛び立つ日に失神する、失禁する、泣きわめく。きれいなことを言って飛んでいった人もなかにはいるけれども、ほとんどは茫然自失です。それを私たち整備兵が抱えて乗せたんです」
「私は罪の意識をずっともっています。それをだれかに言わないと死ねない。書く、書かないはあなたの自由だけれども、どうかこの話を憶えておいてください」
調べてみると多くの特攻隊員は鹿児島湾の入り口、あるいは知覧の近くの山中で落ちちゃっているんですが、しかしみごとに ―― というべきなのでしょうか ―― 米艦に体当たりしたことになっていたりするんです。
こういう老人たちの、死ぬ間際になってこれを言わずには死ねないという記憶がある。
しかも、美しい特攻隊神話は、特攻を命令した者たち自身が、自らの責任から逃れるために作り上げてきたものなのだ。死んでいった隊員たちを美化すればするほど、死を命じた自分たちの責任は問われなくなるからだ。[3]
4「美談」の形成
昭和二十年八月十五日、日本は降伏した。一航艦長宇垣纏は「最後の特攻機」として沖縄に突入した。特攻生みの親たる大西滝治郎は自刃した。神雷隊司令だった岡村基春も自決した。かれらを軍事能力において高く評価はできない。軍事能力の評価は苛酷なまでの結果論しかありえないのである。が、かれらは詫びて殉じた。(略)(略)
しかし、なにものにであろうと、詫びも殉じもしない生き方の方が圧倒的に多かった。
フィリピン四航軍司令官富永恭次、九州六航軍司令官菅原道大、ともに「お前たちだけを死なせはしない、わしも最後の特攻機で突入する」と若者たちに言いつづけ、戻ってきた特攻隊員には理由もきかず、「お前は命がほしいのか」「死なぬのは精神が悪い」と叱咤した二人は、まるで双生児のように生き残った。敗勢のフィリピンから敵前逃亡して、地上部隊兵士までの嘲罵を浴びても台湾で中央復帰を策した富永。八月十五日に、海軍の宇垣長官突入の報に応じた高級参謀鈴木京大佐から、「閣下も御決心を」と言われるや、当惑げに、ねちねちと、「あと始末が大事、死ぬばかりが責任をはたすことにはならない。それよりはあとの始末を」と言った菅原。
若者たちには言い訳を一切許さず、「死ぬばかり」を強要した四、六航軍の参謀たちも見事に死なぬ理由を見つけだした。
敗軍の将と参謀たちの「あと始末」とは「兵を語る」ことであった。旧軍教育の最大の柱が「言い訳をせぬこと」であったのにである。正当なる説明さえも「言い訳」とし、卑怯とした人たちがである。
まず田中耕二。知覧基地で鬼の作戦参謀として特攻隊員を叱咤し怖れられたかれは、終戦時は大本営参謀となり、敗戦後は第一復員局で「後始末」に打ちこんだ。第一復員局資料整理部の報告書『航空特攻作戦の概要』はかれの筆である。(略)
(略)
用語・文体・発想のすべてが、戦中「大本営発表」に酷似する。あれだけの敗戦から「なにものも学ばず、なにものも忘れぬ」元参謀の文章は、負け犬の傷のなめあいの一環としてなされたものではない。自分たちのかつての愚行の正当化を、「美談」を実像とすることを通じて達成しょうとしている。よわよわしい詫びや「免罪」の意図をはるかにこえた、居なおりの偽証である。
(略)
昭和五十一年、防衛庁防衛研修所戦史室『大東亜戦争公刊戦史』全一〇二巻が完結した。その中でも、特攻隊神話は固守されている。『比島捷号陸軍航空作戦』(昭和四十五年)に言う、「特攻隊員は志願者をもって充当することを根本方針とされた……若武者たちの……民族の伝統的精神が爆発し(たもの)」と。
(略)
多額の税金を消費して、防衛庁がかくまで戦中「皇国史観」そのままの太平洋戦争史の「正史」ともいうべきものの作成に努めたのは一見不思議のようでもある。が、それがどのような人的構成と雰囲気でものされたかを知れば、疑問は氷解する。
昭和三十九年二月、陸軍特攻の真相の探求者高木俊朗は、航空自衛隊防衛部長空将補田中耕二を訪れた。先客の元六航軍司令官菅原道大が田中のセンパイ顔で同席した。まず菅原が命令口調で高木に要求した。
「特攻のことを書くのもよいが、(わしが慰霊している)特攻観音のことも、大いに書いてもらいたい」
志願か否かの質問への、田中の答は、
「行きたくない者を、むりにださせたことはない」
である。元大本営参謀の虚像固守の姿勢は一貫している。
(略)
死者に対する遺族・関係者のかなしみは深い。若者たちが、みずから進んで、満足裡に死んだとは、遺族のほとんどが思いたいであろう。その遺族らのかなしさに乗じて、多くの若者にムダ死を強いた者が、強制の事実なしとし、虚像の美化を自己の正当化の根拠とし、はては自分の慰霊の姿のPRまでを要望する。ここには、絶望的なまでの腐臭がただよっている。
若者たちの献身が純粋で美しくあればあるほど、その若者たちの生も死も利用しつくす者の醜悪さはきわだつ。特攻隊は、その実施時の実態においてとともに、その「神話化」の過程において、昭和期天皇制軍隊の恥部 ― 指揮官・参謀クラスの醜悪さをかくすイチジクの葉として利用されつくしている。
特攻隊をテーマにした映画を作るなとは言わないが、作るべきものがあるとしたらそれはまず第一に、こんな外道な作戦を立案し、また部隊を指揮して何千人もの若者を自爆攻撃に追い込んだ者たちが、責任も取らずに戦後をどのようにのうのうと生きてきたかを描く作品だろう。
[1] 保阪正康・姜尚中 『戦争と天災のあいだ ーー 記録の改竄、記憶の捏造に抗して』 講談社 2012年 P.140-142
[2] 保阪正康 『「特攻」と日本人』 講談社現代新書 2005年 P.56-57
[3] 小沢郁郎 『改訂版 つらい真実・虚構の特攻隊神話』 同成社 2018年 P.156-161