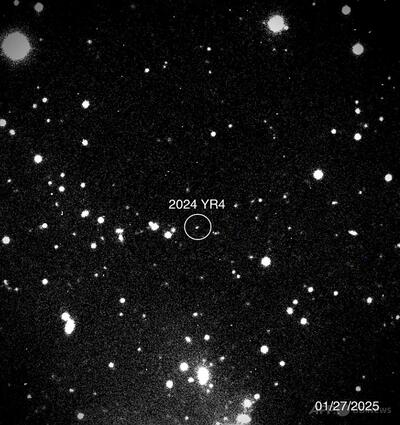よみがえる「チョルノービリ」の悪夢 戦下のウクライナ原発周辺住民
このニュースをシェア
【8月19日 AFP】アナスタシヤ・ルデンコさん(63)は、1986年のチョルノービリ(チェルノブイリ、Chernobyl)原発事故の処理作業に従事した亡き夫ビクトルさんに授けられた金メダルを握り締めた。
ウクライナ南東部を流れるドニエプル(Dnipro)川を挟んでザポリージャ(Zaporizhzhia)原発の対岸に位置するビシチェタラシウカ(Vyschetarasivka)村。ここに住むアナスタシヤさんは、夫の死を悼む。2014年に膀胱(ぼうこう)がんで亡くなったのは、放射線被ばくが原因だったのではないかと思っている。
ロシア、ウクライナ両政府は、ザポリージャ原発周辺を砲撃したと非難し合っている。放射性廃棄物貯蔵施設にもロケット弾が着弾した。監視機関は、壊滅的な結果につながりかねない深刻な事案だと警告している。
「私たちもチョルノービリの人々と同じ運命をたどっていたかもしれない」と、アナスタシヤさんはAFPに語った。「今の状況には何もいいことがない。どのような結末になるのかも分からない」
■過酷な任務
旧ソ連時代の原子炉が爆発して北部一帯に放射能をまき散らしたチョルノービリ原発事故がもたらした深い傷跡は、今もウクライナに刻まれている。ロシア軍は2月に侵攻を開始すると、同原発を占拠。しかし、首都キーウ制圧に失敗し、数週間後には同原発からも撤退した。
ロシア軍はザポリージャ原発も侵攻開始早々に占拠。今なお掌握し続けている。ウクライナ側は、ロシア軍が原発を拠点に攻撃を仕掛けてくる一方、自国軍は応戦できていないとしている。
チョルノービリ原発事故に深く関わった人々にとって、状況が悪化の一途をたどるザポリージャ原発をめぐる動きは、いや応なく過去を思い起こさせるものとなっている。
ビクトルさんは、60万人ともいわれる事故処理作業員の一人だった。住民が強制的に立ち退きを迫られた「立ち入り禁止区域」での除染作業という、困難な任務に就いた。
原発事故による死者数は公式にはわずか31人だ。しかし、数千人の作業員が致死量の放射線を浴びたとの推計もあり、算定の仕方には懐疑的な見方もある。
ビクトルさんは立ち入り禁止区域で延べ18日間、トラックの運転手を務めた。金メダルは、その功績に対し、労働組合から授けられたものだ。ウクライナ国防省の公文書には、ビクトルさんの職務内容とともに、被ばく量24.80レントゲン(照射線量の旧単位)と記されている。
アナスタシヤさんは「夫に関する書類を見るとつらくなる」と語る。「大勢の人が亡くなるか、癒えることのない傷を負った」
「ザポリージャの施設が砲撃にさらされている様子が、私たちが住む場所からよく見える」と言うアナスタシヤさん。「何かが漏れているのではないかと人々はうわさしているが、当局はそれを公式には認めていない」と話した。
■感覚がまひ
バシル・ダビドウさん(65)によると、ビシチェタラシウカ村には自身も含め、チョルノービリで事故処理作業に従事した元作業員3人が暮らしている。
ダビドウさんは、チョルノービリで3か月半にわたって除染作業に従事した。立ち入り禁止区域には102回入り、線量計で放射線量を測定したり、汚染された家屋を重機で解体したりした。
ロシア軍がザポリージャ原発を占拠した数日後、緊急時に備えて被ばくを軽減するヨウ素剤が配布された。
しかしダビドウさんは、チョルノービリ立ち入り禁止区域で作業をした経験があるだけに、危機にさらされているザポリージャ原発の対岸に住んでいることへの恐怖に対しても、感覚的にまひしているようだ。
「もし現実をそのまま受け止めれば気が変になってしまうだろう」「だから過去の経験を通じて現実をふるいにかけている」と、ダビドウさんは語った。
「怖がってどうする。怖がっても救われはしない」 (c)AFP/Joe STENSON