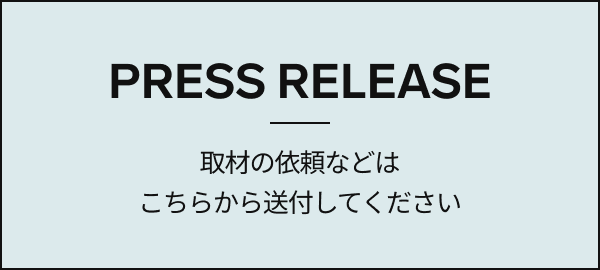「テストの結果よりも、取り組む過程を重視する」「学校運営は、各学校や先生に委ねられている」これらはオランダで行われている教育の特徴だ。
2020年のユニセフの報告書によると、オランダは38先進国のうち“子どもの幸福度がもっとも高い国”だとされていて、教育先進国のイメージも強い。
なぜオランダの子どもたちは幸福度が高いのか? 一人ひとりの個性や能力を重視するオランダの教育の実態、日本との違いは……?
4年前に家族4人でオランダ・アムステルダムへ移住し、ソフトウェアの研究開発を行う会社を起業した川崎文武さん(38)に、オランダのリアルな教育、子育て事情を聞いた。
どの学校も同じ学び方ではない

「イエナプラン」を知っているだろうか。
モンテッソーリ教育やシュタイナー教育に並ぶ世界的に有名な教育モデルの一つで、“一人ひとりを尊重しながら自律と共生を学ぶ”ことを重視する教育モデルだ。
ドイツで始まりオランダで広がったイエナプランでは、「8つのミニマム」「20の原則」などのベースとなる考え方を元にカリキュラムが作られる。
これらの原則が軸にあれば、具体的な取り組み方や方針は各学校や先生に委ねられていて、どの学校もまったく同じ学び方ではないのが特徴だ。
「基本的にオランダでは、小学校は決められたところに行くのではなく、各家庭で選びます。
私が住む場所の近くにイエナプランの考え方を取り入れている小学校があったので、現在はそこに(長女を)通わせています」(川崎さん)

オランダでは公立・私立問わず多くの学校がイエナプランを採用しており、川崎さんの7歳の娘さんもその現地校に通っている。
「イエナプランでは、教室を『リビングルーム』として捉えます。
日本では黒板や先生に向かって着席するスタイルが一般的ですが、イエナプランではグループ・リーダーと呼ばれる教員とクラスの子どもたちが、自分たちで教室内の環境を整えていきます。学校やクラスによってさまざまなカラーがあり、決められた席もありません。
日本の一般的な小学校と比べると、自由でのびのびとした雰囲気を感じます」(川崎さん)
実際に、現地の学校に通わせてみて驚いたという授業やルールにはこんなものがある。
1. “その子のペース”に合わせて入学・進級する
オランダでは5歳からが義務教育だが、1年前の4歳から小学校に入学することができる。
入学は日本のように“決められた月の一斉入学”ではなく、4歳の誕生日の翌日から順次入学可能。入るタイミングは各家庭や子どもの状況に合わせて決める。
「入学後も教員の判断で飛び級もあれば留年もあり、年齢だけで学年に当てはめられることがありません。子どもの成長度合いはさまざまなので、その子のペースを重視しているなと感じます」(川崎さん)
2. 授業中に質問がある人は、赤いカードを机の端に置く
みんなの前で質問がしにくい生徒の声をスルーせず、うまくすくい上げる。
「日本では“手を挙げた方がいい”という雰囲気もありますが、娘の通っている学校では無理矢理手を挙げさせようとはしません。だからといって、放置もしない。
子どもの声を逃さない進め方に関心しました」(川崎さん)
3. テストの点数よりも、その後のアプローチに重点をおく
テスト終了後、生徒は「簡単だった/普通だった/難しかった」と書かれた箱に感想を投票。感想と結果に乖離がないかを確かめる。
もし「“簡単”に投票し、結果が悪かった」場合に教員が着目するのは、勉強ができない事実ではない。今回の学習は向いていなかったという気づきであり、それ以上に向いているものがあるかもしれないという可能性として捉える。つまり勉強ができない=悪というレッテルは貼られない。
「日本は100点に向かおうとするけれど、オランダの場合は“自分の能力はどのくらいなのか”自己認識と合っているかが大事。
オランダでは幼い頃から“強みは人によって違う”ことを教えられます。そういった教育の思想が、社会に出た時にも自分らしさを理解し、人の良さを認められる大人に育っていくのかなと感じます」(川崎さん)
オランダは「教育コスパのいい国」だった

会社員時代から、「いつかは海外暮らしがしたい」と考えていたと話す川崎さん。
日本で独立して事業が軌道に乗ってきたタイミングで、3カ月間、米・カリフォルニアに住まいを移した。しかし、ビザ取得のハードルの高さや治安への不安から家族で暮らすイメージが持てず、一時は帰国も視野に。
そんな時、学生時代に訪れたオランダの素晴らしさを思い出し、起業面、教育面について調べたところ、あらゆる面でマッチしていることに気がつく。
「まず、移住にともなう手続きがオンラインで完結することに驚きました。
家の契約、会社の登記など、アメリカからリモートで手続きを終え、引っ越したその日から住まいがある状態でスタートできました」(川崎さん)
さらには、諸外国からの移住者であっても、高校生までの教育費はほぼ無料だと知った。
「日本ではまだ取り入れている学校が少なく、場合によっては高額な学費を払って受けることができるイエナプラン教育が、オランダでは多くの学校に備わっています。
また、日本でネイティブ並の英語力を身につけようと思ったらインターナショナルスクールを考えますが、日本で高額な費用を払うよりもオランダに暮らして現地の学校に行く方が、教育コストはかからないかもしれません」(川崎さん)
川崎さんが生活拠点をオランダに決めたもう一つの理由、それはスタートアップ援助金があることだった。税金控除や研究費を含め、年間あたり500万円ほどの額が支払われる。とにかくあらゆる面で最善だった。
パパの送迎は「当たり前」

オランダでは、「何においても“平等”という意識がある」と川崎さんは話す。
性別や国籍、職業、母と父の子育てにおける役割など、あらゆる事象においてステレオタイプをなくそうという意識が強い。保育園の送迎で見かけるのは、多くがパパの姿だそうだ。
「“イケてる”男性の概念が日本とオランダではちょっと違うなと感じます。
バリバリ仕事をこなすビジネスパーソンだけがかっこいいとされるのではなく、ゆったり暮らして育児にも向き合っているお父さんがイケてる、という感覚なんです。
自分たちらしく生活するという、堂々とした姿が素敵だなと思いますね」(川崎さん)
また、多くの移民を受け入れているオランダは、言語の違いで社会的な優劣がつかないことも暮らしやすさの一つだという。
娘さんが通う小学校のクラスメイトも、ベルギーとオランダのMIXの子、ギリシャの子など国籍はさまざま。アジア人は少ないけれど、学校側もそれを特殊とはしない。
「異文化への理解やリスペクトが個々人に根付いていて、例え言葉がカタコトだとしても、街全体に受け入れられている感じがします。
海外志向をあまり持っていなかった妻も、オランダでの暮らしに慣れるのが早かったですね」(川崎さん)
「日本とオランダ、どちらが良いか」より大切なこと

「オランダの教育を知ったからこそ、日本の教育の良さを改めて感じることもある」と川崎さん。
例えば、日本では四則計算を必ず学び、全員がある程度できるようになるまで教師が見守るが、どこまでやるかが各個人に委ねられているオランダでは、全員ができるわけではない。
「日本の教育の基礎レベルは高いなと感じます。みんな一定の知識や学力を持てる仕組みがあるのはすごいこと。
また、タスク達成型の日本の教育のメリットもたくさんあると思います」(川崎さん)
さらに「整理整頓や礼儀を重視するのも日本の教育の素晴らしいところ」と川崎さん。実際に暮らしてみて、日本とオランダ、どちらの教育が良いと明言はできないと話す。
「大事なのは、その子に合う場所や環境に身を置くことだと思います。
娘は今、オランダの学校に楽しみながら通っています。
親としては、“自由と調和”がベースにあるオランダの環境でどんな成長をしていくのかが純粋に楽しみです。
“できないこと”ではなく“できること”にフォーカスを当てる教育方針は、きっと子どもたちに生きる自信を与えてくれるはずです。
自分を認めて、ひいては他人を認められる心が育ってくれたらいいなと思っています」(川崎さん)