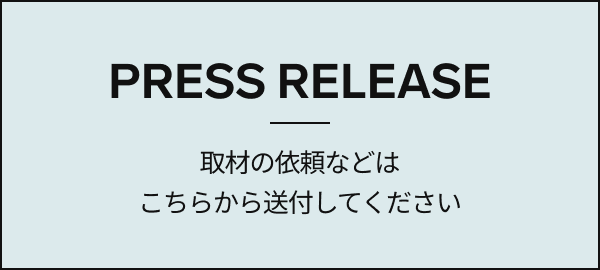コロナ禍で話題になった産直ECの「食べチョク」。
「7年運営してきて、ポジティブな面も、一方で課題も出てきた。今日は私たちにとってすごく重要な一日です。生産者から消費者に直販する食べチョクから、一気にサービスのラインナップを拡充します」
運営元であるビビッドガーデンの秋元里奈代表は、11月7日に都内で開かれた事業説明会の場で、そう宣言した。ビビッドガーデンは、創業以来初めて物流拠点を持ち、新たなビジネスモデルにも挑戦する。
月2500万円稼ぐ農家も

食べチョクのサービス開始は2017年。コロナ禍での急成長を経て、2021年には年間流通金額が数十億円規模にまで成長した。7年目を迎えたいま、登録生産者数は1万人、ユーザー数は100万人を超えた。
ビビッドガーデンは、実家が農家だった秋元代表が、産者のこだわりが正当に評価される世界の実現を目指し設立した。食べチョクも、低所得になりやすい中小規模の農家に新たな販路を提供することで、所得における課題を解決することを狙ったサービスだった。
コロナ禍では、野菜などを卸していた飲食店などが営業停止になったことで販路を失った生産者をサポートした。在宅需要も追い風に、販売数が増えていった。
「生産者さんにとって新たな販売の選択肢になっているのかなと思います」
と、秋元代表はこれまでの歩みを振り返る。
実際、食べチョクに登録している生産者の中では、月間最高収益で2500万円近く稼げるようになった農家もあったという。
ただ、7年運営してきた中では、課題も見えてきた。
産直ECの課題解決へ、3つの新サービス

産直ECによって生産者の収益の向上に少なからず寄与できたとはいえ、なかには産直スタイルがフィットしない産品を扱っている生産者もいる。例えば、白菜のような大きな葉物野菜は大量購入されることは少なく、産直ECで数を売ることは難しかった。
できるだけ手間をかけずに販売したいという声も根強い。いくら販路が広がったとしても、一度に大量に販売できるような大きいロットでの販路を求める生産者からの声は、当初から多かったという。
生産者側だけではなく、消費者側でもライフスタイルが多様化していくにつれて、ニーズはどんどん広がっていった。
食べチョクという一つのプラットフォームの中で、日常使い用の野菜を購入するユーザーや贈答品を買うユーザー、規格外商品を購入してコストを抑えているユーザーなど、多様なユーザーが入り乱れ、「ユーザーからすると探しづらい」(秋元代表)状況も発生してしまっていた。

そこで今回ビビッドガーデンが発表したのが、次の3つの新サービスだ。
共働き世帯や子育て世帯のニーズに答える冷凍食品サブスクサービスの「Vibid TABLE(ビビットテーブル)」。
贈るシーンや相手に合わせてギフトを選ぶ独自のコンシェルジュ機能を活用し、隠れた銘菓を選定してくれるギフト特化サービスの「コレダギフト」。
そして、ユーザーが好みに応じて商品をまとめて購入できるネットスーパー「食べチョク ドットミィ」。
秋元代表は、「3年後にこの3サービスで(食べチョクの現ユーザー数の)100万人を超えていくというところを目指しております」と意気込みを語った。
今回発表された3つのサービスは、どれもこの7年のビジネスで直面した課題にアプローチしたものだ。ただ、冷凍食品のサブスクやネットスーパー事業などは競合も多い。
秋元代表としては、「顔の見える生産者」「国産であること」「マイナーな食品まで取り扱う多様なラインナップ」といったこれまで培ってきた食べチョクの良さが、差別化要因になるのではと期待する。しかし競合環境を考えると、どうしてもサービスの独自性は感じにくい面もある。

ただ、新たに「物流拠点」を整備したビジネスモデルを作り始めたことは、ビビッドガーデンというスタートアップ企業の成長曲線を考える上で注目の要素だと言える。
実際、秋元代表は記者会見の中で
「生産者1万件、消費者100万人のこの食べチョクで培った顧客基盤を基に、より多くの販路を生産者さんに提供できるような総合流通企業を目指して事業を展開していきます」
と、企業としてこれまでとは異なるフェーズに入ったことを強調していた。
創業以来初の物流拠点。toBで飛躍も

ビビッドガーデンは今回のサービスローンチに合わせて、関東近郊に1カ所物流拠点を確保したことを発表している。ここに農家から送られていた産品や加工品を集積することで、ユーザーの希望に合わせた発送を一挙に進める。新サービスのネットスーパー「食べチョク ドットミィ」の運用にも欠かせない拠点だ。
実は事業説明会の中で、秋元代表は物流拠点を整備したことで、「より買いやすくなるので、いち消費者だけではなく、小売店や飲食店といった販路にも広げることができる」とtoB向けビジネスへの展開可能性を語っており、すでに一部の小売店などとは取り扱いに関する議論を進めている段階だとBusiness Insider Japanの取材に答えている。
ビビッドガーデンでは、過去にも小売店や飲食店向けのtoBビジネスに挑戦したことはあった。ただ、当時は生産者からの直送ではコストが大きく、取扱量も少なかったため安定的な供給も難しかった。その反省を踏まえ、
「もしBtoBtoCをやるなら、物流拠点は必須だなと。それができてから展開しようと考えていました」(秋元代表)
という。
一つ一つは小さな農家でも、産地をリレーしながら拠点に集約できれば、どの季節でも食材を安定的に供給できる。7年間の成長によって実現が可能になったサービスだ。
高単価商品である加工食品もこのスキームに取り入れることで、中小農家のさらなる販路拡大に寄与できる。これまで培ってきたtoCビジネスに加えて、toBビジネスも軌道に乗れば、ビビッドガーデンとしてもさらに大きな成長曲線を描ける可能性が見えてくる。
秋元代表の野望は果てしない。
「流通を攻めていくという話をさせていただきましたが、実はもっと長期の展望もあります。生産者さんが抱える課題は販売だけではなく、多岐にわたります。流通をまずしっかり広げていくことに加えて、将来的には様々なソリューションを提供できる生産者さんにとってのソリューションプラットフォームになっていきたいと思っています」
将来のIPOに向けて、自分たちが何者かを伝え続けていく姿勢も明確だ。
「IPOについては、具体的に言えるものはありません。ただ、私たちは流通企業としてだけではなく、農業業界を変えていく企業として今後も成長していきたいと思ってます。市場に対してのメッセージも一次産業を変えていく企業として認知をされるように、事業展開をしていきたいなと思っています」