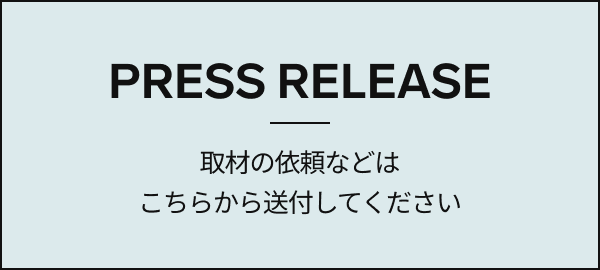2023年の夏、NTTは京都大学大学院文学研究科の出口康夫教授と一般社団法人京都哲学研究所を設立。趣旨に賛同した日立製作所、博報堂、読売新聞といった企業も同研究所の研究活動に参画している。
なぜ総合ICT事業を標榜する通信企業のNTTが先頭に立って京都哲学研究所を始めたのか。
二人いる共同代表理事のうちの一人、NTT会長の澤田純にインタビューした。
もう一人の共同代表理事の出口康夫は、設立の趣旨について「哲学はいま再び、社会に向き合い、社会にエンゲージしなければなりません」と言っている。
※インタビューは4回にわたって掲載する。第1回となる今回は、研究所の設立に至った背景について。
コロナ禍以前に始めていた哲学の研究

——なぜ、京都哲学研究所をつくったのですか。何かきっかけがあったのでしょうか。
澤田会長(以下、澤田):2019年の夏のことでした。コロナ禍の前ですね。当時、京都大学の総長だった山極(壽一。現京都大学名誉教授)さんに話して、「西田幾多郎の哲学の概念を継承している」出口(康夫)教授を紹介していただいたのです。
そして、お目にかかった出口先生に「NTTはIOWN(アイオン)という新しい情報通信基盤を整備します。電気から光に通信インフラを変えていこうと思います」と伝えたら、こんなことを言われました。
(注・IOWN……電子技術から光技術へシフトすることで、「低遅延」「低消費電力」「大容量・高品質」のネットワークを実現する通信インフラ)
「澤田さん、新しい社会インフラには新しい哲学が必要です」
その頃、私はユヴァル・ノア・ハラリが書いた『ホモ・デウス』(注・ヒトは不死と幸福、神性を目指し、ホモ・デウス(神のヒト)へと自らをアップグレードするといった内容の本)に触発されていました。新しい技術と未来についての本ですね。また、他にもさまざまな本を読んで刺激を受けていたのです。新しい技術と人間の関係について常に考えていました。
私は出口先生の意見に賛成し「では、一緒に哲学の研究を始めましょう」となり、2023年、京都哲学研究所を設立しました。
—— 数年前から計画されていたのですね。
澤田:はい、そうです。出口先生と出会ってから5年が経ちました。生成AIや新情報通信基盤により、社会や人々の生活が大きく変化する可能性はますます高まってきています。そういう時代になってきたということでしょう。
そして、最先端の技術、自然科学を突き詰めていくと、結局、自分の存在とは何だろうと、改めて人間に対する問いが生まれてくる。生成AIがいくつも出てくる社会になれば、人間の価値観に影響してしまうでしょう。そうしたことを突っ込んで議論するためにつくったのが京都哲学研究所です。
—— 新しい技術が普及すると、「研究開発者は倫理や自戒が必要になってくる」ということでしょうか?
澤田:ある程度、技術者にはそういった倫理性というものが要るとは思います。一方で、知識、新技術の研究については自由であることが前提です。
何者にも影響されずに研究してもらわないといけない。ただ、社会の側が新技術をどのように利用するか、どういうルールで臨むかは議論しないといけない。これは両輪だと思っています。
—— コロナ禍の時期、NTTは会食問題があり、澤田さんは事態を収拾して、NTTの社内制度などをガラッと変えました。
澤田:はい。会食問題への対処がありました。歴代の幹部も会食はしていたのですが、私は社長として、たとえ自分がいなかった時期であっても責任を持って対応するべきだと思いました。そんなある種の達観もあり、問題を解決してほぼ1年後に社長を降りました。
あの時、会社の規定を変えました。会食などのルールもかなり厳しめにしました。人事制度も変えて年功序列を崩していくモデルにしました。女性の視点を経営に取り込むことも推進しました。リモートワークにより在宅を基点にする働き方も導入することにしました。
NTTが持っていた、長い年月によって培われたシステムをかなり変更しました。変革の時期だったのです。

—— それもまた新しい技術とそれに対応する社会、人間を考えてのことですか。
澤田:それはあります。出口先生がおっしゃったように「新しい社会インフラには新しい哲学が必要」ということを体験したようなものでした。
私たちは技術という面で次の社会を開いていける可能性が出てきたわけです。そこにはみんなが受容できる新しい概念が必要だと思っています。
また、2015年くらいからはデカップリングの議論も盛んになってきました。これも考えなくてはならない。
(注・デカップリング……「分離」「切り離し」を意味する。現在ではアメリカ経済と中国経済の緊密な関係の解消・希薄化を指す語として用いられている)
単純な二元論では答えは出ない

澤田:京都哲学研究所は新しい技術の登場で変わっていく社会と個人、そして分断が進む世界のなかで日本発の営みをしたいと設立したものです。
これから価値多層社会になっていくと考えていますが、それを実現するためには世界の哲学や産業に携わる人たちがディスカッションする、京都哲学研究所はそういうモメンタムを作ろうという組織なんです。
西洋哲学と東洋哲学をどうつないで、どういう思想を作るか。言い方を変えると、世界中の人がAかBかではなくて、「AもBもあるね」という認識を持てる構造にできるかが私たちの命題です。
——澤田さんが著書(『パラコンシステント・ワールド』)で述べているパラコンシステントということでしょうか。
澤田:パラコンシステントは、みなさんにはまだ耳慣れない言葉ですね。パラコンシステントとは同時実現を目指す第三の道のことです。かつて私が京都大学で学んだ土木工学はトレードオフの思想が基本。「選択と集中型の経営」もAかBかを決めることです。しかしAとBの同時実現を目指す第三の道もあって、これをパラコンシステントと言うのです。
デジタルかアナログか、ビジネスとしての事業性か公共性か、現場力か経営力か、中央集権か自律分散かなど、単純な二元論では答えが出せません。パラコンシステントな思想をどう作っていくかだと思っています。
—— 今のお話で社会と哲学の関係はよく分かりました。ですが、なぜNTTが手を挙げたのでしょうか。そこはどうお考えでしょうか。
澤田:冒頭に言いましたが、NTTが開発しているIOWNは世界のコミュニケーションをゲームチェンジする研究です。これはほぼ全世界を対象にした研究で、普及のためのIOWNグローバル・フォーラムを作りました。現在、世界から155社、5機関が参加しています。
(注・IOWNグローバル・フォーラム……NTT、インテル、ソニーの3社が中心となって設立した国際的な非営利団体)
澤田:IOWNグローバル・フォーラムの最終的な目標は標準化です。IOWNを標準化させて、利用法、技術アーキテクチャ(仕様等)を考えていく。同フォーラムは日本発のコミュニケーション技術を標準化するための組織です。IOWNを世界で使ってもらえるものにするためにはデファクトを目指すわけですが、往々にしてデジュールで負けてしまう傾向があります。
(注・デジュール標準……公的な機関、政府が決める標準。対義がデファクト標準であり、事実上の標準。市場で多くの人に受け入れられたもの)
アメリカは良い技術は市場が決めると考えています。日本はデファクトでやっていこうとしていますが、社会的なエンゲージの力、つまり、思想力がないと、自ら開発した技術をデジュールに推すことができない。
——なるほど。EVへの圧力がそうですね。欧州が環境規制のためにEV導入を先んじて決めて、デジュール標準にしてしまった。
澤田:日本は思想力が弱い。例えばSDGsや環境問題を標準にしようと決めたのは欧米です。欧米が決めた枠がありますから、それに乗っても日本が欧米を凌駕することはできない。
技術が社会を作るのか社会が技術をリードするのか。前者がデファクトで、後者がデジュールとすれば日本は後者の競争には弱い。しかし、私たちは新しい技術には両方とも必要だと思うのです。
そして、同じことを言ったのが西田幾多郎です(注・西田幾多郎の哲学は近代西洋哲学の二元論・対象論理的な思惟様式とは異なっている)。西田は両方だと。技術が社会を作り、社会が技術をリードするとしている。それが「絶対矛盾的自己同一」(注・矛盾しているように見える2つの要素が、より高いレベルで統一されている状態)につながるのですが、この概念は世界にはないんです。
——哲学というとアカデミズムの世界の話だと思っていましたが、お話を伺っていると、新しい技術を開発しただけでは世界では戦えない。思想的な裏付けがなければいけない。哲学は日本企業の世界戦略にとっては重要なものだと理解しました。
(文中敬称略。第2回に続く)
野地秩嘉(のじ・つねよし): 1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』『高倉健インタヴューズ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ビートルズを呼んだ男』『トヨタ物語』『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』など著書多数。