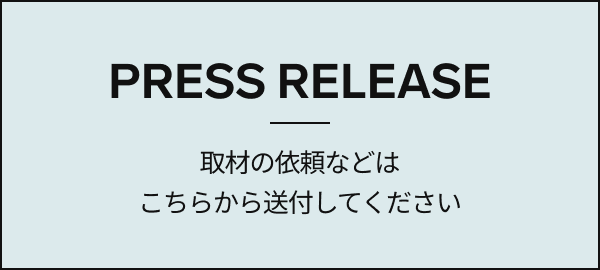2024年1月1日に発生した能登半島地震から1年が経過しようとしている。
Business Insider Japanでも何度か被災地の様子を伝えているが、内閣府の非常災害対策本部によると1月1日の地震による死者は489人、全壊した住宅の数は6445戸、半壊は2万3225戸にものぼっている(2024年12月24日14時時点)。
今も能登半島を中心に復旧・復興が進められているが、それと同時に「次の災害を見据えた準備」も着実に積み重ねられている。
準備の1つとして注目されているのが「ドローン」の活用だ。石川県と石川県警察、KDDI、ローソンは12月23日、「コンビニ」を拠点にしたドローンの実証実験を実施。実験で見えてきたドローンの利点と課題を解説しよう。
ドローンが飛び立ち、行方不明者捜索や現場確認

実証実験が行われたのは、能登半島中央部に位置する七尾市。金沢駅から車で1時間10分程度の場所に位置する「ローソン七尾小島町店」だ。すぐ側には七尾警察署がある。
実証実験は2つのシナリオに基づいて実施された。1つは「行方不明者捜索」、もう1つは「交通事故時の初動対応」だ。
いずれもシナリオでも司令部からの入電から指示を受けた七尾警察署の署員が、KDDIのドローン操縦者と連携。現場にドローンを向かわせ、行方不明者を探したり、交通事故現場の確認をしたりするというものだ。

ドローンはアメリカ・Skydio製AIドローン「Skydio X10」を使用。今回の実証実験は、同機体として国内初となる「レベル3.5飛行」となった。
レベル3.5飛行とは、2023年12月の航空法改正により新設され、レベル3飛行(無人地帯における目視外飛行)に必要だった「補助者・看板等の配置」や「道路横断前の一時停止」などを条件付きで緩和する措置になる。
また通常、一定重量以上のドローンを含む無人航空機の飛行には、事前に国土交通省に飛行申請を行い、承認を得る必要がある。
今回は実証実験のため、レベル3.5(一部エリアはレベル2)の飛行を、KDDIスマートドローンが事前に国土交通省へ申請し、許可を得ていた。
しかし、KDDIスマートドローンによると、今回のような交通事故を含む事故や災害等の発生時に、国や自治体からの依頼があった場合において、「捜索又は救助のための特例」(航空法第132条の92)の適用を受け、飛行申請なく運用することが可能だと国土交通省にも確認をしているという。

23日の実験では、ローソン七尾小島町店の屋上に設置されたポートから、約1km先の小丸山城址公園、約5.1km先の能登島大橋まで、それぞれの目的地までの操縦および作業のためのドローン操作を、七尾警察署にいるKDDI子会社・KDDIスマートドローンの職員が担当した。
Skydio X10は、スムーズで安定した飛行だけではなく、点検・監視・災害に特化した機能を持つ。
今回の実験ではX10に搭載されたサーマルカメラでの行方不明者捜索や、高精細なズーム機能や3Dスキャン機能を用いた事故現場確認が実施され、実証実験は大きな問題はなく完了した。
新生ローソンによる「地域防災コンビニ」

今回の実証実験の背景には、能登半島地震での行方不明者の捜索や道路などの被害状況の調査にドローンが活躍したという実績があった。
ただ、自治体や警察が災害対応のためだけにドローンを導入するのは予算的に現状困難だ(例えばSkydio X10は1台あたり約250万円)。
そのため、今回の実験では日常と災害発生などの非常時を区別しない「フェーズフリー(Phase Free)」をテーマに掲げ、ドローンの活用の幅を広げられないか模索した。
また、KDDIは2024年2月にローソンの公開買い付け(TOB)実施を発表。現在、ローソンは三菱商事とKDDIがそれぞれ半分ずつローソンの株式を持ち共同運営をしている。
その一環でローソン、三菱商事、KDDIの3社はコンビニの未来の活用例として「地域防災コンビニ」をコンセプトとして掲げており、「ローソンの屋上をドローンの拠点として使う」という今回の実験は同コンセプトの象徴的なものとなった。
社会実装のために克服すべき3つの課題

一方で、実験を通して早くも課題も見えてきた。現場の取材から分かったことは大きく分けて3つになる。
1つ目は「ドローン操縦の運用」だ。
今回は実証実験ということで、七尾署の署員が隣にいるKDDIスマートドローンの職員に逐次指示したり、相談を受けたりしながら捜索や現場確認を進めた。
しかし、石川県警察本部の大嶌正洋本部長は「災害時でもドローンを使うことになると警察職員が運行していることがほとんど」と語るなど、一般的な警察業務を民間企業に依頼することはないという。
「企業の方で運行をしていただいて(ドローンを)警察が使うのであれば、それなりに整備しないといけないところがある」(大嶌本部長)
そのため、今回の実証実験の目的としても、仮にKDDIスマートドローンのような民間企業に委託するならどのような運用方法が考えられ、整備すべき法律は何かなど、問題点の洗い出しが目的となっていた。

2つ目は「ネットワーク」の問題だ。
今回の実証実験の2つのケースそれぞれは特に問題なく実施されたが、実は1つ目の行方不明者捜索から2つ目の事故現場の確認に移る際、予定にない中断時間が発生した。

KDDIスマートドローンの博野雅文社長は中断の原因を「(電波の弱いエリアが)遠隔運行の操作に影響をもたらした」と説明し、「いかに早急に解決していくのかが重要な課題」とした。
なお、Skydio X10にとってレベル3.5飛行は今回が国内初事例となるが、モバイル回線(LTE)を活用して遠隔飛行をしたのも初めて。
今後、KDDIスマートドローンは衛星通信「Starlink」をドローンの機体に搭載していく計画もあり、KDDIの事業創造本部 LX基盤推進部部長の鶴田悟史氏は搭載時期について「そんなに遠くない未来には」と言及した。
3つ目は「ドローンの導入計画」だ。
今回はあくまで実証実験となり、石川県警察でドローンが捜査にすぐ使われるわけでも、災害用に県が導入を決めたわけでもない。
大嶌本部長も「直ちにやるわけではない」と、現時点で公表できるロードマップはないと説明した。

こうした温度感はKDDIスマートドローン側も同じだ。
同社は「どこでも10分以内にドローンが駆けつけられる」ように「全国1000カ所にドローンポートを設置する」ことを目標としているが、その具体的な目標達成時期は「いつというのはまだ」(いずれも鶴田氏)と留めている。
鶴田氏も現実的に「日常的にドローンが飛び回るようになるのはまだ先」としつつも、Skydio X10の性能や今回の実証実験の結果を見て「(これまで)社会実装されない(理由となる)部分は超えたと感じている」とコメント。
今後も石川県だけでなく全国でこうした実験を重ねることで、ドローンによる災害対策やビジネスの活性化につなげていきたい考えだ。
(取材協力:KDDI)