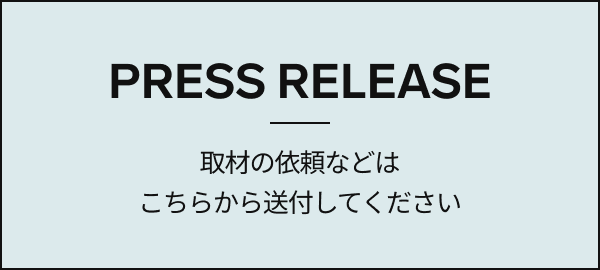アマゾン(Amazon)のオフィス復帰(RTO)命令厳格化、すなわち週5日出社義務化の初月は波乱の幕開けとなった。
Business Insiderの取材に応じた複数の従業員の証言によれば、年初の同社各拠点では、デスクや会議室、駐車場の不足、オフィス内での盗難など、従業員が一斉に出社したことによる混乱が相次いだ模様だ。
出社により同僚と対面で交流する機会が増え、質の高い協業が期待できそうだといった前向きな発言が聞かれた一方で、わざわざ出社したにも関わらずビデオ会議に費やす時間が長くてさほど変化が感じられないといった声も聞かれた。
Business Insiderはこの年始、アマゾンの現役従業員7人に週5日出社義務化後の社内の様子について話を聞いた。スラック(Slack)の社内チャンネルや従業員同士のメッセージやり取りの内容が分かるスクリーンショットも複数入手した。
スラック投稿では早くもこんな嘆き節が確認された。
「お願いだから、RTO3(週3日出社すなわち週2日の在宅勤務が可能な勤務形態)に戻してほしい。そうでなければ、適切な環境を整備できてなおかつ業務成績の優秀な従業員にだけでも在宅勤務の選択肢を与えてほしい」
この投稿には、他の従業員からの同意や支持を示すリアクション(絵文字)が22件付いていた。
完全に雇用する側が優位
アマゾンの従業員総数は150万人、うちコーポレート部門の従業員数は35万人ほど。したがって、社内スラックなどで週5日出社に不平不満をぶちまけている従業員は、全体から見ればほんのひと握りにすぎない。
とは言え、パンデミックの最中で徐々に在宅勤務に慣れてきたところだったのに、またしても新たな(ポストパンデミックの)現実に適応しなければならなくなった従業員たちにとって、日常生活の劇的すぎる変化に不平や不満を抱く方がむしろ自然な反応ではないか。
ペンシルベニア大学ウォートンスクール教授で同大学ヒューマンリソース研究センターのディレクターを兼務するピーター・キャペリ氏は、オフィス出社の強制は従業員の反感を招く可能性があるだけでなく、経営陣が在宅勤務などからの移行を円滑に実現できなかった場合に従業員の側で(改善や緩和など)できることがあまりないので、苦痛に満ちたものになりがちだと指摘する。
また、近頃はリモートワーク可の企業も減っており、退職してよりフレキシブルな勤務形態の企業を選ぶ選択肢も現実的ではなくなっている。
「選択権は完全に雇用主側にあるのです」(キャペリ氏)
「対面交流は不可欠」派の意見
もちろん、アマゾンのあらゆる従業員が週5日出社に不満を抱いているわけではない。
同社に今回の厳格なオフィス復帰命令の適用を支持している従業員はいるのか尋ねたところ、広報担当を通じて実名の従業員2人のコメントを得られた。
アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)のレナ・パルンボ氏は、(在宅勤務が常態化する中で)同僚たちとの人間的なつながりを再構築することの重要性を常々感じてきたので、オフィスで一緒に仕事をする時間が増えることの喜びもひとしおだと言う。
同じくAWSに勤務するキャッシュ・アシュリー氏は、仕事上の関係構築や教育機会の創出の観点から、対面での交流が不可欠だと指摘する。また、週5日フル出社することで仕事と家庭生活との間に明確な線引きが可能になるため、ワークライフバランスの実現にも役立つと言う。
「オンラインではこうしたつながりを再現できません」(アシュリー氏)
アマゾンの広報担当はBusiness Insiderの取材に対し、できる限りスムーズな移行を実現できるよう全力で取り組んでいるとした上で、次のように強調した。
「当社としては比較的少数派と言える(不満や問題を感じている)従業員たちから話を聞いて改善に取り組んでいますが、貴編集部が匿名の従業員に取材して集めたという意見やエピソードは、当社が従業員から直接聞いて得ている大多数の感覚や認識と合致しないものです」
「いまオフィスには素晴らしいエネルギーが満ちあふれています。皆が顔を合わせて一緒に仕事をすることで生まれるイノベーション、コラボレーション、コネクションを目の当たりにして、従業員の誰もが興奮を感じているのです」
同様の見解は、週5日出社義務化前の昨年10月上旬時点で、AWSを率いるマット・ガーマン最高経営責任者(CEO)も示している。
Business Insider編集部が入手した当時の社内ミーティングの文字起こしによれば、ガーマン氏は自分が直接話した従業員の「10人中9人」から、フルタイムのオフィス復帰を楽しみにしているとの声が聞かれたと発言していた。
デスクとチェア、会議室が足りない
アマゾン従業員のほとんどは1月初旬から週5日出社を開始したものの、オフィス復帰計画の実施に当たって事前に想定された課題を解決できないままの見切り発車だったことが、複数の従業員の証言から窺(うかが)われる。
一部の従業員は出社してから使えるデスクがないことに気づき、カフェテリアやロビーで仕事スペースを探さなくてはならなかったという。また、問題はデスクだけでなく、オフィスも会議室も椅子が足りなくて困ったようだ。
会議室も足りていない。内密の話題でも気兼ねなく話せる在宅勤務に慣れきった従業員たちも、いまやオフィスで同僚たちに四方八方取り囲まれて仕事せざるを得ず、その手の会話を周囲に聞かれたくない時は会議室や電話ブースにしれっと滑り込むのだという。
そういう予約なしのイレギュラーな利用のために会議室が塞(ふさ)がっている時間も増え、中には周囲にダダ漏れでも気にせずオープンスペースで内輪の話題を議論する管理職もいるそうだ。
駐車場もシャトルバスも満車満員
マイカーで出社したもののオフィスの専用駐車場が満車で停められずに困るケースも多発している。
Business Insiderが確認したスラック(Slack)の社内チャンネルの投稿によれば、近所の路上駐車スペースが空いていてそこに停めたケースもあれば、やむを得ず自宅に引き返したケースもあるようだ。
米テネシー州ナッシュビルの拠点オフィスに勤務する従業員の投稿によれば、同拠点では駐車許可証の発行待ち期間が(満車のために)数カ月という。その穴埋めのためか通勤定期券が無料支給されており、その対応は「非常に気前が良い」という。
また、別の従業員の証言によると、これまで在宅勤務だった従業員がオフィスに殺到したことで渋滞が発生し、早朝のミーティングに通勤中の社内からリモート参加せざるを得ない従業員もいるようだ。
スラックの社内チャンネルには、(オフィスと最寄り駅などを結ぶ)専用シャトルバスが満員で乗車を拒否されたという従業員の投稿も見られた。
私物の盗難事案相次ぐ
週5日出社が始まった最初の週には、オフィスにおける基本的なルールまで忘れ去られてしまったかのような事件も発生していたようだ。
スラックの社内チャンネル投稿によれば、カナダ・トロントオフィスの複数の従業員がデスクからそれぞれの私物が消えたと訴えている。
ある従業員は自分に割り当てられたデスクに置いたキーボードとマウスがなくなったと投稿。別の従業員はそれに反応して、私物は安全な場所に保管するよう促した。
別の従業員は率直な感情をこう書き込んでいる。
「比較的恵まれた報酬を受け取っている大人だけが働くオフィスで、安心して私物を置いておくことすらできないというのは恥ずべき事態だ」
この盗難と思われる事案についてアマゾンにコメントを求めたが、広報は回答を控えるとした。
共有された「サバイバルガイド」
クローズド型コミュニティSNS「ブラインド(Blind)」上のアマゾン従業員向けチャンネルには、複数の従業員が作成もしくは編集に関与したと見られる「エッセンシャル・サバイバル・ガイド(生き抜く上で不可欠の手引き)」が投稿されている。
オフィス復帰する同僚たちへのアドバイスを(一種のウケ狙いで)まとめたファイルだ。
「オフィスの厄介者にならないために」の項には、同僚と同じ職場で勤務する際にやるべきこと、やってはいけないことがリストアップされている。
「ローンチパッド(つまり自宅)を出発する『前に』個人の衛生管理、清潔度に関するプロトコルをデプロイしよう。そう、在宅勤務が始まってからサボりがちになっているシャワーをしっかり浴びることだ」
「トイレの個室は『サーバーレス』環境ではない。使用後は水を流そう。ガベージコレクション(不要なメモリ領域の解放、ここでは排泄物をイメージした比喩)という言葉があるくらいだ」
「靴の着用はオプションではない。(リモートワークで)仕事の合間にビーチを走れた時期はもう過去の話なのだ。足指は適切なコンテナ(もちろん靴だ)に格納すべし」
出社しても結局ビデオ会議だらけ
オフィス出社をめぐってはここ数年激しい議論が繰り返されてきた。社内に最も深刻な対立をもたらした問題の一つだったと言っていいだろう。
2023年2月に週3日出社義務化が発表された際には、数万人の従業員がスラックの社内チャンネル「リモートアドボカシー」に集結し、ポリシー変更に反対する嘆願書に署名した。
アンディ・ジャシーCEOは社内ミーティングで繰り返し出社義務化の意義を強調したものの、従業員からは根拠となるデータを示すよう迫られるなど議論は平行線をたどってきた。
ついに週5日出社が義務化されたこの年明け以降も、従業員からは依然として反対の声が上がっている。実際にフル出社してみたが実際の業務にほとんど影響はなく、生産性の特段の向上は確認できないというのが彼ら彼女らの主張だ。
Business Insiderの取材に応じた複数の従業員が、週5日出社義務化後もオフィスにおける業務時間の相当部分を顧客とのビデオ会議が占め、社内ミーティングも別拠点に勤務する従業員とのものが多く、対面のミーティング頻度が高まったということもないと証言した。
スラックの社内チャンネルではこんな投稿も確認できた。
「オフィスにいてもチーム内での議論はほとんどないです」