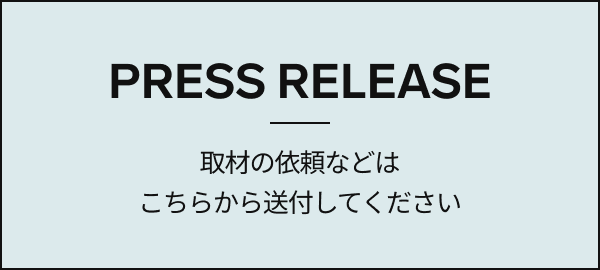米マイクロソフト(以下マイクロソフト)と半導体メーカーのクアルコム(Qualcomm)は、プライベートイベント「Snapdragon Tech Summit」の基調講演で、両社が共同で開発を進めてきたArm版Windows 10を搭載した「Always Connected PC」を発表した。
Arm版Windows 10とは、スマートフォン向けの省電力なプロセッサで動くWindows 10だ。発表に合わせてHPがENVY x2というタブレットPCを発表した他、ASUSがNovaGoという360度回転型2-in-1デバイスを発表した。
現在タブレット市場では、依然としてタブレットのトップシェアを誇るアップルのiPad Pro、マイクロソフトのSurfaceシリーズなど、いわゆる“プロシューマー”向けの製品が好調で、多くのタブレットメーカーがプロシューマー向けへのシフトを進めている。今回発表されたArm版Windows 10は、そうしたプロシューマー向けタブレット市場に大きな影響を与えることになりそうだ。
というのも、Arm版Windows 10を搭載した機器は、iPad Proの特徴である長時間バッテリー駆動・常時ネット接続と、Windowsタブレットの特徴である高い生産性という両方を兼ね備えている製品だからだ。
縮少を続けるタブレット市場、各社の狙いは「プロシューマー」ユーザー
タブレット市場は年々縮少しており、今後成長する可能性が少ない —— これがデバイス業界関係者の共通認識だ。このため、タブレットのメーカーは、最大の市場シェアを誇るアップルを先頭に、プロシューマーと呼ばれる「自分の予算で生産性を向上させるハード製品を購入するビジネスパーソン」や自営業者などにターゲットを移しつつある。
その先頭を切ったのが、マイクロソフトのSurfaceシリーズだった。今や多くのPCメーカーが「Surfaceライク」な2-in-1ノートを発売したほか、アップルもSurfaceシリーズの特徴だった画面のカバーがわりになる「フォリオキーボード」とスタイラスペンをオプションで用意したiPad Proを主力製品に据えている。Androidはこの市場からは事実上脱落し、Apple vs Windowsというのが基本的な構図だ。
しかし、現状iPad Proも、Windowsタブレットもそれぞれ弱点を抱えている。軽量で長時間バッテリー駆動を実現しているiPad Proだが、最新のiOS11でもローカルのファイル管理にはまだまだ制約が多い。
一方、Windowsタブレットではそうした制限はないが、PCと同じCPUで設計されるため、バッテリー駆動時間が短いという弱点を抱えている。
Arm版Windows 10は「フル機能、長時間バッテリー駆動、LTE常時接続」
そうしたタブレット市場に一石を投じることになるのが、今回マイクロソフトとクアルコムが発表したArm版Windows 10だ。その発表に合わせて、ASUSとHPが搭載製品を発表している。


このArm版Windows 10は、大きく3つの特徴を備えている。
1つめは、PC向けのWindows 10の全機能が使えること。Arm版(といっても現時点で対応しているのはクアルコムのSnapdragon 835のみだが)Windows 10は、これまでのインテル/AMDのCPU向けとなるx86版Windows 10と全く同等の機能を備えている。しかも、CPUの命令セットが変わると生じるアプリの互換性の問題を、「バイナリートランスレーション」と呼ばれる特殊な仕組みによって回避している。これによって、ユーザーは現在Windows 10で利用しているアプリがそのまま使える。

2つめは、長時間バッテリー駆動が可能なことだ。新発表のHPの「ENVY x2」は20時間、ASUSの「NovaGo」は22時間という連続動画再生をうたう。例えば、従来のインテルのプロセッサを搭載したSurface Proは13.5時間のビデオ再生だ。さらに、スタンバイ状態では、約30日間の待ち受けができるなど、スマートフォンと同じような使い勝手を狙っている。


3つめは、すべての製品がLTEモデム内蔵であること。Arm版Windows 10を搭載したデバイスは、「Always Connected PC」と呼ばれている。ユーザーがタブレットをカバンから取り出して、スリープを解除すれば、スマートフォンと同じようにインターネットに接続された状態から使い始めることができる。
平たく言えば、バッテリー駆動時間の制限をあまり気にする必要が無いiPad Proの特徴と、PCと同じレベルの生産性を実現しているWinodwsタブレット、その両方の良いところ取りをしたのが、Arm版Windows 10ということになる。これをパラダイムシフトと言わずして何をパラダイムシフトと呼ぶのか。
Arm版Windows10マシンはどんな用途に使えるか?
ただし、課題もある。最大の課題は「処理性能」だ。今回のArm版Windows 10搭載機器が採用するSnapdragon 835は、最新のiPad Proに搭載されているA10などと同等、または上回る性能を発揮する。しかし、PC向けのプロセッサであるIntelのCoreプロセッサや、AMDのRyzenと比較すると、性能面で見劣りするのは事実だ。
会見の席上でも、クアルコム幹部も、マイクロソフトの幹部も、「Arm版Windows 10でユーザー体験が変わる」とバッテリー駆動時間やLTE常時接続については何度も強調したが、性能には誰も何も触れなかった。つまり両社ともに、そこが十分だとは思っていないのだ。
では実際にどのような性能なのか?
会場にあったデバイスをテストした限りでは、マイクロソフト Officeなど今となってはCPUやGPUの性能にあまり依存しないようなアプリでは、特に不満を感じることはなさそうだった。一方で、CPUやGPUの性能が重視されるゲームや、写真や動画の編集などといった用途に関しては、やや不満を感じる可能性は高い。
そこはマイクロソフトも住み分ける戦略だ。Arm版Windows 10を発表したイベント「WinHEC 2016」の会場で、マイクロソフト Windows & Devices担当上級副社長 テリー・マイヤーソン氏は、「今後もゲームやコンテンツ作成などに利用するハイパフォーマンス製品はインテル/AMDベース、長時間バッテリー駆動/常時接続の製品はクアルコムベースと住み分けることになるだろう」と述べている。
つまり、依然として性能を必要とする用途には、従来通りインテル/AMDベースの製品でカバーし、常時接続や長時間バッテリー駆動時間を必要とするユースケースではArm版Windows 10でカバーする計画だ。従って、市場では今後もインテル/AMDベースの製品と、クアルコムベースの製品が共存していくことになると思われる。
(文、撮影・笠原一輝)
笠原 一輝:フリーランスのテクニカルライター。CPU、GPU、SoCなどのコンピューティング系の半導体を取材して世界各地を回っている。PCやスマートフォン、ADAS/自動運転などの半導体を利用したアプリケーションもプラットフォームの観点から見る。