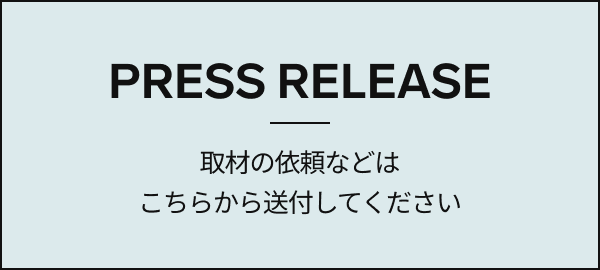4月上旬のある日、渋谷駅構内。ひとつの広告の前で私は思わず足を止めた。
「どうして女子はバリカンを入れてはいけないのですか?」

やっと時代が追いついてきたのか —— 。そこに踊る文字をみて、私は胸のすく思いがしていた。
10年ぶりに髪の毛をバリカンで刈った私

2017年の11月、私は自分の髪の毛をバリカンで刈った(左写真がその時のもの)。
理由はもちろん、日本で女性が押し付けられる画一的な「女性らしさ」に抵抗したかったからだ。
と言えたらカッコいいのだが、本当は「目立つにはどうしたらいいですか?」と知人でジャーナリストの津田大介さんに相談したところ、「見た目を変えると認知してもらいやすいよ」とアドバイスをもらったからだ(後日「まさか本当にやるとは」と言われたが)。
実は私は高校1年生のときにも一度坊主にしたことがある。部活の同期で、親友だった子が髪の抜ける病気にかかってしまい、「じゃあ私も」と髪を刈った。
当時も周囲からは驚かれ、学校の先生からは叱られたが、それが逆に「自分らしい髪型とは?」を考えるきっかけにもなった。
あれから10年。世間も変わっているだろう —— と坊主に踏み切ったが、大きな誤解だった。
髪を坊主にしたらお説教

私の坊主は会社で波紋を呼んだ。
まず腰を抜かすほど驚いていたのが、編集長(バブル世代)。ひとしきり驚いたあとには、お説教がはじまった。
「そんな髪型にしたら取材を受けてもらえなくなるよ。自由な髪型・服装にしていいのは、ちゃんと実績を残し、一人前になってから。新人なのに服装で個性を出そうとしても、その前に警戒されて取材を受けてもらえなくなるだけだよ」
一方、30〜40代の先輩社員は「あぁ〜……」と意外に薄い反応だった。認められていたのか、「見て見ぬフリ」をされていたのかはわからない。
逆に支持を受けたのは、20代の同年代からだ。坊主の何がいけないのか、男性が坊主にしても何も言われないのに、なぜ私が坊主にするとダメなのか、と問うと「私(僕)もそう思う」と力強い意見が寄せられた。
動画は500万回再生

この広告に大いに勇気付けられた私は、早速「パンテーン」ブランドを展開するP&Gの広報に、この広告の意図を尋ねてみた。
そもそもこの広告は「#HairWeGo さあ、この髪でいこう。」というメッセージのもとで展開してきた広告キャンペーンの第3弾だ。
きっかけは、生徒が髪の毛を染めておらずパーマもかけていない、つまり生まれつきの髪かどうかを証明するために「地毛証明書」を学校に提出しなければならないというニュースだった。「髪型校則について、社会全体で対話するきっかけをつくれれば」と、3月下旬からTwitter・新聞・ラジオと多方面で広告を仕掛けてきた。
4月8日からは「#この髪どうしてダメですか」と題されたYouTube動画を公開。公開から2日ほどで約500万回再生を記録。さらにTwitterでも、「#この髪どうしてダメですか」のハッシュタグで7万5000以上のツイートが広がっているという。
同じ4月8日からは、東京・渋谷と大阪・梅田で交通広告を実施。書かれているのはすべて、実際にアンケートに書かれた髪型校則に対する疑問だという。
「学生らしい髪型って具体的にどういった髪型ですか?」「茶色く染めちゃダメなのに、黒染めはいいんですか?」「どうして女子はバリカンを入れてはいけないのですか?」
「あるべき」に疑問を投げかける、ストレートな言葉たち。ここに書かれたメッセージは、あの日の私が発したものだ —— そう感じて胸が熱くなった。
炎上広告との違いは「状況に物申しているか」

「#この髪どうしてダメですか」の広告が大きな反響を呼んでいる理由について、ジャーナリストの治部れんげさんは「(社会から押し付けられる)“らしさ”についてみんながモヤモヤしているところを、うまく言語化しているからでは」と分析する。
女性やジェンダーがテーマの広告は、近年強い批判を浴びたり「炎上」したりするものも多い。そういうものと今回の広告の違いについて、治部さんは「おかしな規範に物申しているかの違い」だ、という。
「(炎上する広告は)今ある規範やバイアスを受け入れろ、と押し付けてくるもの。大変な目にあっている人たちに対して、その状況に疑問を呈するのではなく、二次被害を与えている」
今回の動画広告には「地毛証明書」の存在自体は受け入れている先生の姿も映されている一方で、「バリカン」のようなラディカルなメッセージも込めているなど、「消費者のダイバーシティに配慮した広告」だと治部さんは評価する。
なお、この広告に登場するのは女性が多いが、動画には男性も出演している。
「パンテーンはもともと女性向けのヘアブランドなので、出演者に女性が多いという傾向はあるが、 女性だけの問題だけではないと考えている」(P&G広報担当者)
画一化された“らしさ”や“あるべき”への問いかけを —— そう思い、部屋にあるバリカンへと再び手が伸びたが、そういえば来週は評価査定だと思い出した。
くだらない規範にはNOと言いたいが、やはり上司の目は気になる。そんな自分も、「自分らしい」と認めてあげることから、まずは始めよう。
(文・写真、西山里緒)