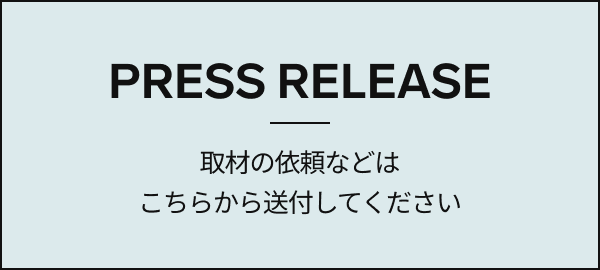日本のイチゴが、ニューヨークで旋風を巻き起こしている。
アメリカを代表するフレンチ界の巨匠、ダニエル・ブリュー氏のミシュラン二つ星レストラン「ダニエル」をはじめ、味に惚れた有名レストランのパティシエから注文が殺到。ソースや飾りといった素材の一部ではなく、デザートの“主役”として、加工せずそのまま提供している店がほとんどだという。
レストランだけではない。高級スーパー・ホールフーズをはじめとする100店舗以上のスーパーでも販売。店頭に並ぶそばから飛ぶように売れている。
食通をうならせるこのイチゴ、生産しているのは日本人CEO率いるオイシイファーム(Oishii Farm)だ。
2016年にアメリカで創業した同社は、畑やビニールハウスではなく屋内の「植物工場」で、完全無農薬のイチゴの量産化に成功。欧米の植物工場スタートアップが破綻・撤退に追い込まれる中、一人勝ちの状況となっている。2024年2月には、シリーズBで日本円にして総額200億円超の資金調達を実施したことでも話題となった。
共同創業者兼CEOの古賀大貴氏は、CNBCなどアメリカのメディアでも引っ張りだこで、4月には国際カンファレンス「TED 2024」に史上4人目の日本人として登壇。一躍時の人として脚光を浴びている。
「植物工場は、日本が勝つべくして勝てる領域」
そう断言する古賀氏に、一人勝ちの理由と戦略について聞いた。
競合他社はなぜ「レタスしか作れない」のか

──TEDのライセンスを受けた「TEDx」ではなく、本家のTEDに登壇する日本人はそう多くありません。反響は?
TEDの舞台に立つことは非常に光栄であると同時に、大きな不安もありました。ただ、最後にステージ上からスタンディングオベーションを見た時は、(2017年の発売から)これまでの僕らの6年間の取り組みに対して世界が反応をしてくれたように感じ、不思議と緊張も吹き飛び、グッと熱いものが込み上げてきました。
──植物工場に対する期待の現れでしょうか。
植物工場は2015年前後から世界的に注目され、スタートアップへの投資も相次いでいました。ところが最近になって全く利益が出ないことに失望感が広がり、ここ1年間でトップを争っていた欧米の競合他社がバタバタと潰れていった。業界全体としては、植物工場はもうダメだという雰囲気になっています。
──しかし、オイシイファームは2024年2月、シリーズBラウンドで1億3400万ドル(約206億円)もの資金を調達しています。
すでに“儲かる”ビジネスモデルを確立しているからです。投資家もそこを評価してくれた。我々の思いとしては、オイシイファームが完全に勝馬に乗ったことを決めに行くのが今回のラウンドでした。
──競合他社はなぜ脱落したのでしょうか。
競合他社はレタスしか生産できなかったからです。レタスは単価が安いので、どんなに美味しいものを作っても結局は価格勝負になってしまう。結果、利益を出せないまま投資家が手を引いていった。
ただ、それは予想できたことでした。競合他社のほとんどがおそらく5年後には潰れてしまうだろうと。というのも、僕はそのサイクルを1回見ていたからです。
植物工場ではハチが飛ばない“常識”の壁

──1回見ていたとは?
実は2000年代前半に、日本で第一次植物工場ブームが起きていたんです。海外からは全く注目されませんでしたが、日本ではシャープやパナソニック、東芝をはじめ名だたる企業が参入し、国内には数百カ所もの工場がありました。僕は当時所属していたコンサルティングファームでコンサルタントとして携わっていたんです。
この時のブームは完全にプロダクトアウトの発想で、LEDや空調といった既にある技術の使いみちとして始まりました。しかし、やはり技術的にレタスなどの葉物しか作れず、利益が出ずに下火になっていったんです。
──なぜ葉物しか作れなかったのでしょうか。
実の成る作物は、花を咲かせて受粉させる必要があります。つまり、ハチを飛ばさないといけない。でも、ハチは非常に繊細な生き物で、人工の光のもとでは巣から出てこなかったり、飛んでもフラフラしながらすぐ戻ってきてしまったりする。植物工場ではハチが飛ばないというのが業界の常識になっていて、そこを突き崩せなかったのです。
「40日後の出荷量」も分かる独自システム

──オイシイファームはその常識を覆したと。技術的なハードルをどう乗り越えたのですか。
まずは、ハチに自然の中にいると感じさせる環境を作ることが重要だったので、そこをクリアすることから始めました。自然環境と植物工場の違いを丁寧に因数分解して原因を突き止め、そこを徹底的に詰めていけば生産できるだろうと仮説を立てたんです。
創業当初はとにかくそこに集中し、2〜3年目に何とかハチを飛ばすことに成功しました。
──次のハードルは?
生産性です。ハチが飛ぶようになったとしても、どれだけ受粉してくれるかで効率が全く変わってきます。通常のビニールハウスのイチゴは受粉の成功率が6〜7割。でも、オイシイファームでは独自の技術を導入し、受粉成功率95%を実現しています。
──独自の技術とは。
一つひとつの苗の健康状態や収穫量を把握し、環境管理を完璧にコントロールできるシステムを自分たちで構築しました。工場内をロボットが24時間巡回して苗単位で画像解析し、光や風、温度といった環境データもすべて記録。さらに、そのデータをもとにAIで計算し、今日はハチを飛ばすか飛ばさないか、また液肥や水やりといったコントロールまでできるシステムを内製化したんです。
40日後に何キロ出荷できるかも分かるので、季節を問わず、計画的に生産・販売できるようになっています。
なぜ「イチゴ」に着目したのか

──イチゴを選んだ理由は。
真っ先に考えたのが収益性です。レタスの失敗を見ていたので、味に差をつけやすく、高い値段で売れるものは何か。たどり着いたのがイチゴでした。超高級品種のイチゴを生産できれば、初期段階から収益化ができるだろうと。
次に、技術的なハードルが高いこと。競合他社がレタスを作っている間に量産化に成功すれば、彼らがイチゴに挑戦する頃には5年先、10年先を行く状況に持っていける。誰も参入できない期間が長ければ長いほど、価格崩壊を食い止めることもできます。
──早期に勝ち逃げパターンを作れると。
個人的に一番重視しているのは、長期的な戦略としてのブランド力です。20年後、30年後に業界No.1のポジションを確立し、「野菜と果物といえばオイシイファーム」と言われる存在になる。そのためにはブランドで差別化できる作物でなければなりません。
その点、イチゴは「あまおう」「とちおとめ」など、ブランドを確立できるほど味に差をつけやすい数少ない作物の一つなので、ブランド化するのに最適だったんです。
──イチゴの次にトマトも発売しました。
2023年12月に発売し、一部のホールフーズで販売しています。イチゴは2017年から販売している「Omakase Berry(オマカセ・ベリー)」と、第二弾の「Koyo Berry(コウヨウ・ベリー)」があります。オマカセ・ベリーのほうが甘みが強く、レストラン需要が高いのですが、このトマトはそれよりも糖度が高い。おそらく世界一甘いトマトだと思います。
目指すは「世界最大の農業生産者」

──トマトの次も考えているのでしょうか。
まだ言えませんが、さまざまな作物の栽培に取り組んでいます。そもそも僕たちのゴールは、高級イチゴをニューヨークで売って儲けようという話ではなく、世界最大の農業生産者になること。それが創業当初から掲げている目標です。
──なぜ植物工場に着目したのですか。
農業が危機に瀕しているからです。農業には安定した気候、安い土地、潤沢な水、安く安定した労働力、農薬という5つのファクターが不可欠で、1つでも不足するとコストが指数関数的に高くなります。
日本はまだ5つとも兼ね備えていますが、海外はすでに脅威にさらされている。山火事や洪水など大規模な異常気象が毎年起きていますし、アメリカではかつて500円程度だった農業従事者の時給が3000円に跳ね上がっています。
一方、植物工場には天候リスクが一切ありません。水はリサイクルして使えるので少ない量で事足りる。土地は農地である必要がないので、僕たちも元プラスチック工場を居抜きで買ってリノベーションしてイチゴを作っています。農薬も必要ありませんし、自動化も圧倒的に進めやすいので人手も少なくて済みます。
──屋外の農業におけるリスクが、植物工場ではゼロになる。
そうです。2015年頃には、このままいくと植物工場で作った農作物のほうが安くなるという世界的なコンセンサスが形成され、植物工場への投資が一気に進んだ。これがサステナビリティの観点で始まった第二次植物工場ブームです。
現状はまだ僕たちだけしかレタス以外の農作物を量産できないので、ブームがしぼんだように見えますが、植物工場のニーズ自体が衰えているわけではありません。土地も劣化しますし、人口も爆発的に増えていくなかで、水も農地も絶対的に不足することは明らかですから。
植物工場は「日本が勝てる」領域

──だからこそ200億円もの資金を調達できたと。これまでのラウンドと反応の違いは。
一番の違いは、日本の政府や企業の反応です。日本では長らく、植物工場は儲からないというレッテルが貼られていましたが、実はものすごいチャンスだと気づき始めたんだと思います。
──日本企業にとってのメリットは。
世界に先駆けて植物工場を手掛けていた経験もありますし、グリーンハウス(ビニールハウス)など屋内で農作物を栽培する施設園芸の技術や高品質な種苗を持っている国は、日本とオランダだけというベースもあります。
何より、植物工場に必要な空調やLED、自動化といった技術は日本のお家芸で、世界トップの企業が日本に集まっている。植物工場は、日本が勝つべくして勝てる領域なんです。
──植物工場の世界の市場規模はどの程度拡大していくのでしょうか。
今後大半の生鮮野菜・果物が植物工場で生産できるようになると仮定すると、現在の野菜・果物市場規模ですら100兆円を超えていますから、 価格さえ低減できれば長期的にはそれ以上の規模になるかもしれません。
重要なのは、植物工場によって農業の構造自体が完全に変わっていくということです。
──農業の構造がどう変わるのでしょうか。
農業はこれまで、地域分断的にしか行えないものでした。国や地域で気候も土壌も違うので、グローバルに同じものを作ることができません。
でも植物工場なら、東京でも北極でもアフリカでも全く同じものを生産できます。つまり、自動車のような産業と全く同じ構造になって、将来的にはトップ5社、10社が世界のシェア95%を占める時代に変わっていきます。その一時代を、日本の企業や農家の方も含めて一緒に築き上げていきたい。
──200億円の使い道は。
とにかく生産が追いつかない状況なので、よりサステナブルな量産体制の構築を目指しています。
研究開発面では、自動化・省人化をさらに進めてコスト削減につなげたいですし、育種にも力を入れる予定です。植物工場なら環境を自在にコントロールできるので、気候に合わず戦力外とされていた種を発掘したり、工場育ちの種をかけ合わせたりすることで、これまで達成できなかったような収量や糖度を、遺伝子組換えなしで実現していきたいと思います。