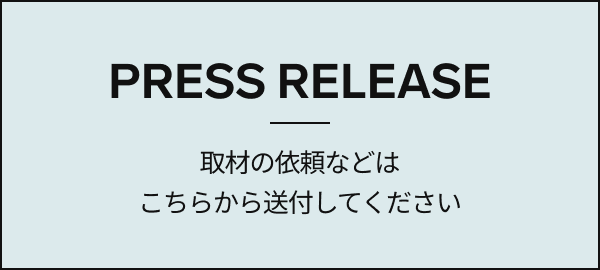民主党の大統領候補の指名を確実にしたカマラ・ハリス副大統領(59)。 8月19日~22日にイリノイ州シカゴで行われる民主党の全国大会で、両者共に指名受諾演説を行う。
ハリス氏は8月6日、副大統領候補としてミネソタ州のティム・ウォルズ知事を選び、選挙戦を本格化させている。
前評判では「ハリスは人気がない」と言われていた。しかし蓋を開けてみれば、バイデン大統領の選挙戦撤退発表から1週間で集まった献金は、記録破りの金額・2億ドルにも達し、ボランティアも1週間で17万人が殺到する人気ぶりだ。
アメリカのメディアでは今、「若者たちがハリスに『恋している』」という表現が使われるようになっており、オバマが登場した時の熱狂を思い出すものがある。
カマラ・ハリスとは、一体何者なのか? その熱狂の理由を7つのキーワードをあげながら解説したい。
キーワード1:ガラスの天井
ハリスは1964年、カリフォルニア州オークランドで生まれたアフリカ系、南アジア系のアメリカ人だ。
父はジャマイカ出身の経済学者のドナルド・ハリス(スタンフォード大学名誉教授)、母はインド出身の内分泌学研究者シャマラ・ゴパラン=ハリス(乳がんの研究者。2009年に他界)。両親は、カリフォルニア大学バークレー校で出会った。
ハリスの自伝「The Truths We Hold: An American Journey」には、幼いころから両親に連れられて市民権運動に参加していたこと、それが彼女のその後の人生の原点になっていると書かれている。
7歳の時に両親が離婚、その後は、妹と共にシングルマザーに育てられた。HBCU(歴史的黒人大学)の名門、ハワード大学を卒業し、カリフォルニアで法科大学院を出た後、1990年からカリフォルニア州の検事としてキャリアを積み始める。
そこで頭角を現した彼女は、2003年にサンフランシスコの地方検事に(有色人種女性としては初めて)、2010年にはカリフォルニア州検事総長に選出された(黒人として、また女性としては初めて)。
彼女が全国的に注目を集めるようになったのは、2016年、連邦上院議員に当選した頃からだ。上院は、女性やマイノリティが増えてきているとはいえ、白人男性の世界だ。黒人女性として上院議員に選出されたのは、ハリスで史上2人目であり、インド系としては初めてだった。
このように、「女性初の」「黒人初の」「アジア系初の」がついて回る人生を送ってきたハリスは、2020年、米国史上初の女性、かつ初の黒人の副大統領となった。米国史上もっとも高い地位に就いたアジア系アメリカ人でもある。
米国独立から244年間、副大統領は全員が白人男性だったということだ(副大統領候補になった女性は、ハリスを入れてもわずか3人しかいない)。ガラスの天井を破った、歴史的快挙だった。
2020年の大統領選の勝利演説でハリスがこう述べたのを覚えている人も多いだろう。
「私は米国史上最初の女性副大統領かもしれませんが、最後ではありません。なぜなら、今夜この瞬間、すべての小さな女の子たちは、この国が可能性に満ちた国であることを見ているからです」
キーワード2:米国初のセカンド・ジェントルマン

カマラ・ハリスが結婚したのは、50歳の時。
彼女は初婚、夫ダグ・エムホフは再婚で、連れ子が2人いる。エムホフは、米国史上初の「セカンド・ジェントルマン(副大統領の夫)」であり、大統領・副大統領の配偶者としては初のジューイッシュ(ユダヤ系)でもある。
弁護士だった彼は、ハリスが副大統領に当選した後、勤めていた大手法律事務所を辞めた。妻をサポートし、セカンド・ジェントルマンとしての仕事に専念するということだった。
歴代大統領・副大統領の妻たちのほとんどは、夫のキャリアのために仕事を辞めてきた。特に憲法などで定められいるわけではないが、ヒラリー・クリントンやミシェル・オバマのように素晴らしいキャリアを持つ女性でもそうしてきたし、それは大して話題にならなかった。当たり前と思われていたからだろう(ジル・バイデンが、ファースト・レディになった後も大学教員の仕事を続けると宣言した時には、驚きをもって受け止められた)。
でも、エムホフが仕事を辞めることは話題になった。地位の高い仕事についている男性が、妻のキャリアを優先するために仕事を辞めるというケースは米国ですらいまだに珍しい。
エムホフは2021年、カマラ・ハリスの言葉をもじった題の寄稿「I Might Be the First Second Gentleman, But I Don't Want to Be the Last(私は、最初のセカンド・ジェントルマンかもしれませんが、最後にはなりたくありません)」をGQに掲載している。
この寄稿で彼は、選挙戦を通じてハリスとともに各地を回り、ごく普通の人々の抱えているさまざまな問題、社会の不正義や歪みを目の当たりにするうちに、視野が開かれ世界の見方が変わったのだと述べている。
また、自分の息子や娘には、パートナーを全面的にサポートするということが、男であれ女であれ、ちっとも特異なことではない世界に生きてほしいとしている。
キーワード3:一番大事な呼称は「ママラ」
ハリスの義理の娘・息子は、彼女を「ママラ」と呼ぶ(MomとKamala の合成語)。血のつながった母親とは違う、もう一人の愛する母親として。
2020年、民主党大会での演説で、ハリスはこう述べた。
「私はこれまでいろいろな役職名で呼ばれてきました。そこに副大統領というタイトルが加わることを願っていますが、私にとって一番大事な呼称は『ママラ』です」
彼女は、夫の前妻ともいい関係を築いている。妹の子どもたちのことも非常にかわいがっておりよく話に登場する。
カマラ・ハリスが女性に支持される理由、ヒラリー・クリントンとの違いは何なのかと、考えた時、この「理想のおば」的な親しみやすさ、人間味のある温かみ、共感力などが合わさった「Likability」(好感度)の高さが一つの鍵ではないかと感じる。
ハリスの、飾らなさや、化粧っ気もなくエリートぶらない雰囲気は、「庶民のことを親身になって考えてくれそう」と思わせるものがある。
よく大統領選の候補について「一緒にビールを飲みたいと思えるような人か」ということが話題になる。たとえば、ジョージ・W・ブッシュは、その意味においてジョン・ケリーよりも人気があった。ハリスも、一緒にビールを飲んだら楽しそうだ。
キーワード4:Joyous(楽しそう)

私がハリスの魅力だと思うのは、ユーモアのセンスだ。
彼女は、さすが元検事らしく、直球でズバっと核心を突くし、明らかに厳しい。でもそれと同時にユーモアのセンスがある。
腹の底からゲラゲラと豪快に笑う姿や、音楽がかかるとつい踊ってしまうノリノリなところも、「joyous(生き生きしていて楽しそう)」と描写される。
これらの愉快な側面がトランプ側の攻撃の的になってもいるが(まったく意味不明な攻撃だろう)、アメリカ人は、四六時中ひたすらマジメな人よりも、ユーモアのセンスがある人が好きだ。
ハリスの場合も、それで女性や若者の好感度が上がっているところが少なくないと感じる。
キーワード5:「イエスかノーか答えてください」
ハリスを一躍「国民的スター」にしたのは、上院議員時代(2017年~2020年)の司法委員会での数々の名場面だ。
彼女が、トランプ政権の高官や、最高裁判事候補を容赦なく問い詰める姿は大反響を呼び、毎回SNSで拡散され、「よく言ってくれた」と称賛された。
なかでも、ブレット・カバノー(現最高裁判事)の承認公聴会(2018年)は、「Must-see TV」(絶対に見逃すことのできないテレビ番組)と言われるほど、世間から広く注目を集めた。
名場面はいくつもあるが、特に彼女がカバノーに「政府が、男性の身体について決定権を持つような法律を思いつきますか?」とたずねた時は印象的だった。
カバノーはしどろもどろになり、ハリスに「イエスですか、ノーなんですか」と詰められ、最終的にしぶしぶ「ノー」と答えた。
これは、女性が中絶できるかできないかを政府が決めることのおかしさ、男女の不平等をあぶり出すための、非常に効果的なやりとりだった。
相手が誰であろうと遠慮せずに厳しい質問を浴びせ、「Please answer, sir. Yes or no」と問い詰め、嘘を暴こうとするハリスの姿に、多くの人たちが胸のすく思いを感じたと思う。
キーワード6:「いまは私が話しています」

2020年10月、ハリスが副大統領候補として前副大統領のペンスと対峙した討論会も、彼女に対する女性たちの共感と支持を高める出来事だった。
この討論会で、ペンス副大統領は、ハリスの話を10回にもわたってさえぎった。
ハリスは、「I’m speaking (今、私がしゃべっているのです)」と何度も言った。それも、感情的にはならず、極めて落ち着いた様子で、あくまでも礼儀正しく。
黒人の女性に対して、アメリカでは「angry black woman」というステレオタイプがある。ハリスは、まったくそうではなかった。 声を荒げることはなく、時に笑顔を見せるほどだった(努めて怒りを抑えているのであろうことは想像がついたが)。
この討論会が終わるや否や、SNS上で、ハリスへの共感、賞賛の声が爆発的に拡散した。
「かっこよかった!」「男性の割り込みに屈せず、笑顔で毅然と押し戻したのは素晴らしかった」「娘にも見せたい」といったコメントを多数目にした。そして、翌日にはさっそく「I’m speaking」と書かれたさまざまなTシャツがオンライン・ショップで売られるようになり、私もいくつか購入し、クリスマスに友達にプレゼントしたりした。

ハリスが男性に話をさえぎられる姿を見るのは、これが初めてではなかった。
上院議員時代、さまざまな公聴会において、同様のことが起き、それらの映像は女性たちを怒らせた。ニューヨーク・タイムスは2017年、二度にわたってそれを記事にしたくらいだ(「男が女の話を遮るという普遍的な現象」、「カマラ・ハリスが(また)上院公聴会での質問中に話を遮られた」)。
「I’m speaking」という言葉は、つい最近もハリスによって効果的に使われた。
2024年8月7日、ミシガン州での演説中、イスラエル批判のグループが「ジェノサイド!」と声を上げ始めたときのことだ。ハリスは、まずこう語りかけた。
「今ここに集まっている人たちはみんな、民主主義が大事だと分かっているから来ているんですよね。民主主義では、全ての人の声が聞かれるべきです。でも、今は私が話しているんです」
それでも相手が止めないのを見てとると、今度ははるかに強い口調で「あなたたち、トランプに当選してほしいなら、今ここでそう言いなさい。そうでないなら、今は私が話します」と言って会場の大喝采を浴びた。
キーワード7:人工中絶問題

ヒラリー・クリントンがトランプに負けたのは8年前。今回が、アメリカで女性が最も厚いガラスの天井を破る二度目の挑戦になるわけだが、8年前と比較したとき、いくつかの違いがあると感じる。
まず一つに、女性大統領の誕生を願う人々からすると、ヒラリーの時にいよいよと思っていたのに叶わなかったという無念さが根底にある。
「二度とあんな悔しい思いはしたくない」という、敗者復活戦のような空気感があり、今度こそガラスの天井を割りたいという感じだ。
加えて今回は、すでに一度トランプ政権を経験しているので、あのトラウマを繰り返したくないという切実さ、危機感もある。2016年の選挙の時点では、トランプが大統領としてどうかは未知数だった。今回はそこが全く違う。
政策面でも女性たちの期待を背負っている。
2022年、最高裁が、1973年の「ロー対ウェイド判決」を覆し、州の妊娠中絶禁止措置を認める「ドブス判決」は、アメリカの司法にとって歴史的な出来事だった。
50年近く続いた判例が覆り、しかも女性の人権を「拡大」ではなく「制限」する方向にシフトしたのだ。
この判決の直後から、保守州では、人工中絶を規制する動きが急速に強まり、市民たちが住民投票でそれに抵抗するという事例が続いている。極端な州では、強姦や近親相姦の場合ですら中絶を認めない。中絶手術を施した医師に最長99年までの禁錮を求める州法などもある。
ハリスは、「ドブス判決」以来、先頭に立って、女性の自己決定権を守るべきだと強く主張してきた。これは超党派で女性たちの共感を集めやすい問題だ。
共和党支持の女性でも、「妊娠したらもれなく産めという方針には賛成できない」「女性の身体に関する自己決定権に政府が介入するのはおかしい」という人たちは決して少なくない。ここは、民主党がどんどん攻めていくべきところだし、ハリスが得意とするトピックでもある。
この8年で、アメリカは変わった。
アメリカ国内外の環境もだが、トランプ政権を経験したということが、アメリカ人の求めるリーダー像を変えたという気がしてならない。
ハリス自身も変わった。バイデン大統領から後継指名されてからのハリスには、2020年の彼女にはなかった迫力を感じる。
私は4年前の大統領選の時もハリスを応援していた一人だが、あの頃の彼女には、「何が何でも大統領になりたい」「私がなるのだ」という気合いが今一つ感じられなかった。今回はそれを感じる。
ホワイトハウスに4年間いたことで成長し、自信をつけたのかもしれないし、トランプの再選を許せば、前回どころではないカオスが待っていると分かっているから、それを何としても自分が止めるのだと決意しているからかもしれない。
これからの選挙戦に注目したい。