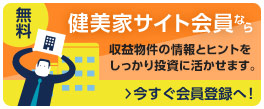クラウドファンディングの一種として、投資収益の獲得を主目的に資金を拠出する「投資型クラウドファンディング」がある。
投資型クラウドファンディングにもさまざまな種類があり「投資型クラウドファンディングとは?Vol1. 種類ごとの特徴を紹介」においては、次の4つのファンドについて、それぞれの特徴を紹介した。
■ 不動産投資クラウドファンディング
■ ソーシャルレンディング
■ 株式投資型クラウドファンディング
■ 事業投資型クラウドファンディング
今回はその続編として、各クラウドファンディングをいくつかの観点から比較した。
投資型クラウドファンディングの比較と選び方

今回紹介した4つのクラウドファンディングの特徴を一覧化すると、上の図の通りとなる。自分が投資するファンドのタイプを選ぶときには
①収益・リスク
②投資期間
③ファンド事業自体のリスク
に着目するとよいだろう。
まず、いずれの観点においても事業投資型クラウドファンディングは不透明性が強いことに留意しておきたい。2025年時点で投資可能なファンドが限られているため、平均的なリスクや収益性の想定が困難だ。
①収益・リスク
収益・リスクでみると、株式投資型クラウドファンディング(以下、株式型)が最も高く、次いで不動産投資>ソーシャルレンディングとなる。株式型は、うまくいけば数倍以上のリターンを生むケースもある。実際にFUNDINNOが公表する過去事例では、すでに340%のリターンを達成した事例もある。
不動産投資クラウドファンディング(以下、不動産型)とソーシャルレンディング(以下、ソーシャル型)の差は、実情としては小さい。
不動産型の本質的な仕組みから言えば、不動産売買によって得る価格差益(キャピタルゲイン)も投資家に還元されうる。
不動産市況が悪化すれば、投資家に損失が及ぶリスクもある。しかし、実情として利回り分配の確実性を優先し、さらにキャピタルゲインの分配を積極的に行わないファンドが散見される。
たとえばCREALでは「当初の想定利回り以上の分配を行わない」と明記している。例外としては、たとえばCOZUCHIは売買益などをキャピタルゲインを投資家に還元して、想定利回り以上の分配を多くのファンドで実現させている。
②投資期間
投資期間については、株式投資型が「不明確」、不動産型とソーシャル型は数ヶ月~数年で「明確」といえる。投じた資金が必要になる時期がある程度明確な場合には、不動産型かソーシャル型がよいだろう。
一方で、株式投資型は、FINDINNOのプラットフォームを活用して、自分が売りたいタイミングで売却希望を出せるというメリットがある。一方で、不動産型やソーシャル型の大部分は、途中換金ができない点に留意が必要だ。
③ファンド事業自体のリスク
ファンドのタイプごとのファンド事業者や事業の安定性にも着目しておきたい。不動産型は不特法によって規制が整備されていて、さらに複数の大手事業者がサービスを運営していて、実績が積み上がっている点において安心感がある。
ただし、 現行の多くの不動産型は、機関投資家の不動産ファンドではよく見られる倒産隔離の仕組みが取られていない点に注意が必要である。この点は詳しくは「不動産クラウドファンディングはどのような仕組み?【不動産投資家のクラファン基礎講座2】」を参照してほしい。
ソーシャル型については、投資スキームがわかりにくい点が留意点だ。最終的に投資家の資金は特定企業の融資に充てられるのだが、その間に複数の企業への出資・融資が行われるケースがしばしば散見される。
たとえば、オルタナバンクの「【毎月分配】国内分散短期運用型ファンドID808」では、ファンド自体は営業者への出資という形態を採っている。営業者は一度、グループ企業に集めた資金を融資し、さらにそのグループ企業が融資先に貸し付ける仕組みだ。
間に入る関係者が多く、その分事業継続のリスクも内在すると考えられる。一方で、ファンドによっては担保や保証付与によりリスクを抑える仕組みのものも見られる。
担保や保証付与ができるのは、「負債」を投資対象とするレンディングならではの特性といえるだろう。
株式型は、FUNDINNOの場合は信託保全が図られているため、FUNDINNOに万が一のことがあった時にも、顧客資産への影響が限定される可能性が高い。
ただし、株式型で活発にファンドを組成する事業者自体が限られているため、FUNDINNOにもしものことがあれば株式型のクラウドファンディングの普及自体が滞る恐れがあるだろう。
事業投資型はさらに深刻で、すでに継続的にファンドを組成する事業者がきわめて限られた状況になっている。継続的な投資を考えているなら、それぞれのファンドビジネスの安定性にも着目すると良いだろう。
まとめ
今回の記事では前回の「投資型クラウドファンディングとは?Vol1. 種類ごとの特徴を紹介」に続いて、投資型クラウドファンディングの比較や選び方を整理した。
近年は、不動産市況が活況であることもあり、特に不動産投資クラウドファンディングにおいて多くのファンドが組成されている。
一方で、ソーシャルレンディングや株式投資型クラウドファンディングも継続的にファンドが組成されていて、豊富な投資機会が存在する。自身の投資先を不動産に偏らせないためにも、これらのファンドにも着目してみるとよいだろう。
投資型クラウドファンディングの普及によって、かつては個人では投資が難しかった先に対して、小口で気軽に投資ができるようになった。
一方で、思うようにファンドの組成や資金募集が進まずに、事業の継続性が危ぶまれるサービスも散見される。ファンド選びにおいては、投資先だけでなく事業者やファンド自体の継続性にも着目して、信頼できるサービス・銘柄に投資をするとよいだろう。
執筆:(いとう けいすけ)