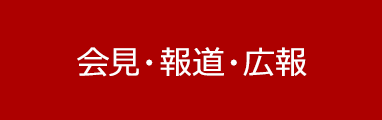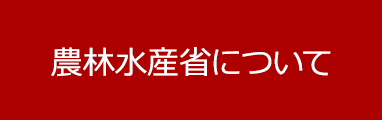小里農林水産大臣記者会見概要
| 日時 | 令和6年10月25日(金曜日)9時56分~10時05分 於: 本省会見室 |
|---|---|
| 主な質疑事項 |
|
質疑応答
記者
北海道に続いて、一昨日、千葉でも鳥インフルエンザの発生が確認されましたが、対応を改めて教えてください。
大臣
10月17日に北海道厚真町、23日に千葉県香取市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。どちらも、迅速な防疫措置が実施され、既に防疫措置は完了しています。
これらの事例については、過去と比べても早い時期の発生であり、また、既に野鳥での感染も見られています。繰り返し申し上げていますが、今後、全国どこで発生してもおかしくない状況です。引き続き緊張感を持って取り組んでまいります。特に、全国の養鶏業者の皆様におかれては、改めて飼養衛生管理を徹底していただくよう確認をお願いします。
また、今般の発生事例を踏まえ、10月17日に改めて都道府県に対し通知し、関係機関と連携して、過去の発生から得られた知見を活かした発生予防対策及び異状の早期発見・通報の徹底、農場周辺における野鳥及び野生動物対策の強化、円滑な防疫措置の実施に必要な体制整備を行うよう依頼しました。
引き続き、農水省では、全国の養鶏業者や関係事業者の皆様と危機感を共有して、発生予防やまん延防止に緊張感をもって取り組んでまいります。
記者
千葉では採卵用の鶏が殺処分されたと思うのですけれども、このまま拡大が続いた際の卵の価格への影響と、卵の価格が高騰してしまった際の対策があれば教えてください。
大臣
一昨年の大発生で大変なご心配をおかけした経験があります。一昨日、今シーズン2例目となる高病原性鳥インフルエンザが確認されました。今回の発生農場の国内全体に占める割合(飼養羽数)は、0.03%であることから、現段階では国内の鶏卵の需給や価格に大きな影響を与える状況は生じておりません。
今後の鶏卵の需給や価格の見通しについて予断をもって申し上げることは困難ですが、例年、鶏卵価格は鍋物需要やクリスマスの製菓需要により、年末に向けて上昇する傾向にあります。鶏卵は国民生活に欠かせないものであることから、引き続き、需給や価格の動向を注視してまいります。
記者
農業分野の経済対策の検討状況について聞かせてください。
大臣
経済対策については、石破総理からの指示で、3つの柱のうちの一つである日本経済・地方経済の成長の施策として、食料安全保障の観点を踏まえた農林水産業の支援等が明示されたところです。現在、総理指示を踏まえた具体的な内容について検討しています。
農水省としては、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえ、食料安全保障の抜本的な強化等を図る観点から、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進めていくものとしています。具体的には、農林水産業・食品分野の所得向上や、中山間地域をはじめとする農山漁村の活性化に資する取組等が経済対策に盛り込まれるよう、取り組んでまいります。
記者
米の価格について、坂本前大臣は9月6日の記者会見で、今後新米が順次供給され円滑な米の流通が進めば、需給バランスの中で一定の価格水準に落ち着いてくると考えているとの見解を示されました。現状、店頭に並ぶ米の価格は高止まりしており、消費者から先行きに不安な声も聞かれますが、今後の見通しについて見解を聞かせてください。
大臣
小売価格の現状を見ると、小売物価統計では、9月のコシヒカリは前年同月より+42.2%高の5キロ当たり3,285円となっています。米の価格は、需給バランスなど民間の取引環境の中で決まっていくものと認識しています。農水省として価格の見通しなどについてコメントすることは差し控えさせていただきますが、引き続き、関係団体とも連携し、米の出荷、在庫、価格等の状況を把握するとともに、丁寧な情報発信を行ってまいります。
記者
北海道のホタテについて、稚貝になる前段階のホタテの幼生の採取数が大幅に減少し、成貝として出荷する2年から5年後の漁獲量を心配する声が上がっています。減少理由は特定できていませんが、調査や対策等は考えていますか。
大臣
全国のホタテガイ生産量の約9割を占める北海道において、ホタテガイの放流や養殖に必要な幼生の採取に不振が生じていることは承知しています。このため、各漁協においては、通常利用しない小さいサイズの稚貝を活用するなどの取組が行われていると聞いています。今回の不振の原因については、現在、北海道立総合研究機構が主体となって分析を行っています。
今後のホタテガイ生産への影響については、稚貝の生育状況を見極める必要があり、引き続き北海道庁と連携し、状況を注視してまいります。
報道官
よろしいでしょうか。それでは、これで大臣会見を終わります。
以上